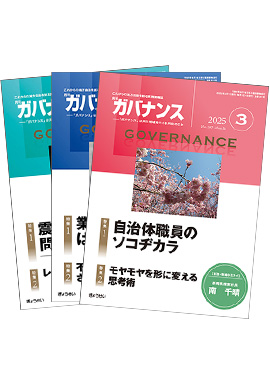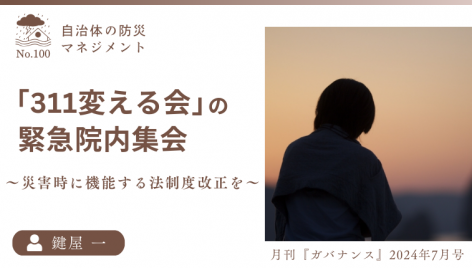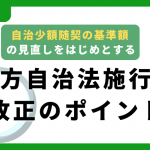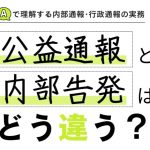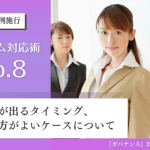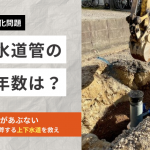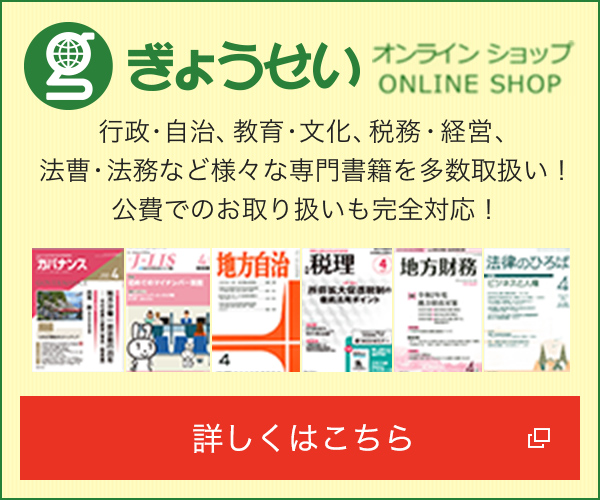自治体の防災マネジメント
自治体の防災マネジメント[103]国土強靭化事例セミナー ~民の力で災害を乗り越える
地方自治
2025.05.14
※写真はイメージであり、実際の土地とは関係ありません。
本記事は、月刊『ガバナンス』2024年10月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
9月10日、内閣官房国土強靭化推進室が主催する国土強靭化事例セミナーが東京で開催された。「国土強靭化 民間の取組事例集」の中から選ばれた6団体に出演いただいた。私はこの事例集の審査委員長を務めているので、同じく審査委員の磯打千雅子香川大学特命准教授、岡本正弁護士と一緒にコメンテーターを務めた。

事例集発表会場の様子
せたがや防災NPOアクション
発表者は代表の宮崎猛志さん。平時には、子育て支援、外国人支援や環境問題への取組みをしている多様なNPOが、日常から顔の見える関係づくりを行い、災害時の避難生活支援、お困りごとのつなぎ役を担う緩やかなネットワーク組織である。2013年に発足した。
分科会活動は、普段取り組んでいるテーマに防災の観点を加えたコミュニティづくりや発災時にはテーマ別支援ユニットとしての受け皿を担っていく。
素晴らしいと感じたのは、この活動を世田谷区が委託料を支払うなどしっかりと後押ししていることだ。そして、世田谷区地域防災計画に基づき、世田谷区、社会福祉協議会、世田谷ボランティア協会と4者連携をして、定例会議を行っている。
多くのNPOは、平時にそれぞれの専門領域で活動するが、災害時に何をどうすれば良いのか、ほとんど考えられていない。世田谷区の4者連携は、ボランティアセンターを設置している自治体のモデルとなるだろう。
川辺復興プロジェクトあるく
発表者は代表の槙原聡美さん。あるくは2018年の西日本豪雨災害を契機に岡山県倉敷市真備町川辺地区の住民が結成した団体だ。被災経験をもとに、未災地の方が同じ後悔をしないように願いを込めた様々な活動を実施している。
「防災おやこ手帳」は、忙しい子育て世帯が手に取りやすく、わかりやすいようにイラストを使い、大切な部分を凝縮して作成している。災害によって亡くなった方や浸水した建物に取り残された方が多く、避難時の声掛けの大切さを強く感じたことから「黄色いタスキ大作戦」を発案して、タスキの出ていない家族に避難の呼びかけをすることとしている。
これらの活動は、有識者を入れながらも自分たちで何度も何度も話し合って工夫を重ねている。地区防災計画は昨年完成したが、なんと50回の会議を経たという。実用的で、とてもわかりやすい計画となっている。あるくのLINEグループへの参加は600人を超えた。そして、災害後に新住民が100世帯も増えたそうだ。まさに災いを転じて福となす。より良い地域の復興活動が新しい住民を迎え入れる好事例だ。
あけぼの会(女将さん会)
この会は、静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合の女性部で宿泊業の中核・女性パワーの結集を目的に1995年に結成された。発表者は組合専務理事の小川英雄さん。
地震発生後に宿泊客を安全にお帰しするためには、宿泊施設で「おもてなし」の中核となっている女将が的確な対応をすることが重要であるということで『女将の地震初動マニュアル』を作成してその周知に取り組んだ。特に写真のアクションカードは実に良くできている。

女将の地震初動マニュアル
観光客は楽しむために来ているので、ハザードマップを把握したり、防災グッズを用意したりすることはなく、災害に極めて脆弱である。国は自治体に観光危機管理計画の作成を呼び掛けているが、その動きは非常に弱々しい。女将さんが自ら立ち上がってこのレベルのマニュアルを作成したことは、全国の観光地のモデルとなる事例である。
ぶどうの家
ぶどうの家は、様々な形態の福祉事業所を運営している。発表者は代表の津田由起子さん。その理念が素晴らしい。
・とことん在宅にこだわる
・自分たちの都合で投げ出さない
・目の前のその人を支える
平時も災害時も共通する深い意味が込められている。ここも2018年の西日本豪雨災害で被災した倉敷市真備町の事業所である。そこで住民が安全に安心して暮らすために避難機能付き共同住宅を作ろうと計画した。サツキPROJECTと名付けられ、スマートウェルネス事業とクラウドファンディングを活用して、被災したアパートをリフォームすることで2020年6月に完成した。2階のコミュニティルームに車イスで直接行ける大きなスロープが目印である。そして、このアパートに入居する条件は、災害時に自室に避難者を受け入れる可能性があることを了承していることである。
素晴らしいと感じたのは、どんな場所に誰が住んでいるのか、皆がわかっていることだ。津田さんは、「助けてと言い合えるまち」が目標と話されていた。
株式会社Resilire(レジリア)
グローバルレベルのサプライチェーンの強靭化を目指す企業である。発表者は津田裕大社長。なんと28歳。2021年5月創業で小林製薬、積水化学、大日本印刷など名だたる大企業のサプライチェーンのリスク管理をサポートしている。
事業の概要は次のとおりである。企業がモノを作るとき、様々な企業から材料を調達するが、一次下請けは直接の取引があるが、二次、三次以下になると把握できていないことがほとんどである。特に調達先が海外だと難しい。それを調達先にIDを渡して必要事項を入力してもらうことで、サプライチェーンの全体像を把握、可視化した。これで、国内外で感染症、災害、大事故などが発生したときに迅速に対応することを可能にする。まさに「コロンブスの卵」だ。やはり2018年の西日本豪雨災害をきっかけに、「面倒だけど重要な社会課題を解決したい」と考えたのがきっかけという。その志と急成長する姿が眩しく感じられる。
WOTA株式会社
発表者は前田瑶介社長。生活排水の再生循環利用を可能にして、災害時に水循環型シャワーや手洗いを提供している企業である。2014年の創業以来、地球上の水資源の偏在・枯渇・汚染によって生じる諸問題を解決するため、「小規模分散型水循環システム」及び「水処理自立制御技術」を開発している。
2018年の西日本豪雨災害の被災地で水循環型シャワー「WOTABOX」のプロトタイプで断水対応を行ったが、1台だけだったので、その悔しさをばねに量産し2019年の東日本台風では長野県全地域で、今年の能登半島地震ではすでに購入している自治体からも支援を得て、全避難所の84%に提供したという。
自衛隊のお風呂も大事だが、たとえば毎日、生理中の女性は9%程度いたり、異性介助が必要な障がい児がいたりするので、個別対応のシャワーが必要になる。
前田社長は「災害時にも水に困らない」「そもそも断水が起きない仕組み」を目指すという。そして全国で1万人に1台程度まで普及すれば、分散備蓄・集中運用により被災地で水に困らないというビジョンを示した。
6組の話を伺って感じたのは英語の「Muddle Through」だ。泥沼を苦労して切り抜けるという意味で、誰かの後を付いて行くのではなく困難を泥まみれになりながらも自力で克服する人を称賛する言葉だ。まさに日本の「民の力」を存分に聞かせていただいた。
Profile
跡見学園女子大学教授
鍵屋 一(かぎや・はじめ)
1956年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、東京・板橋区役所入区。法政大学大学院政治学専攻修士課程修了、京都大学博士(情報学)。防災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長、危機管理担当部長、議会事務局長などを歴任し、2015年4月から現職。災害時要援護者の避難支援に関する検討会委員、(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事、(一社)防災教育普及協会理事なども務める。著書に『図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ』(学陽書房、19年6月改訂)など。