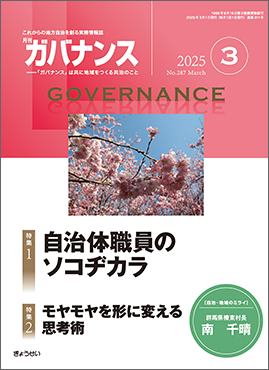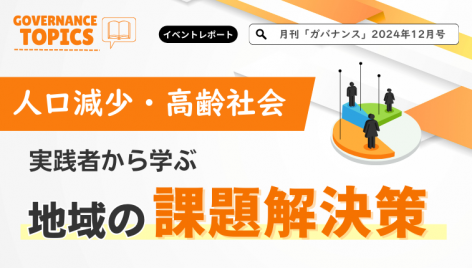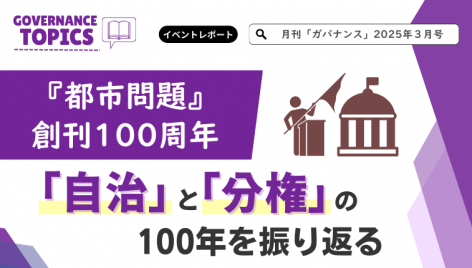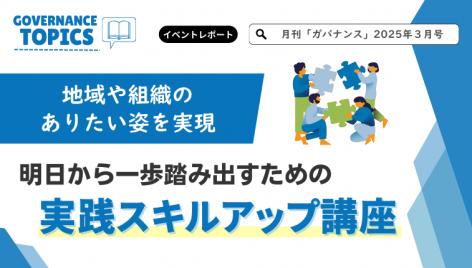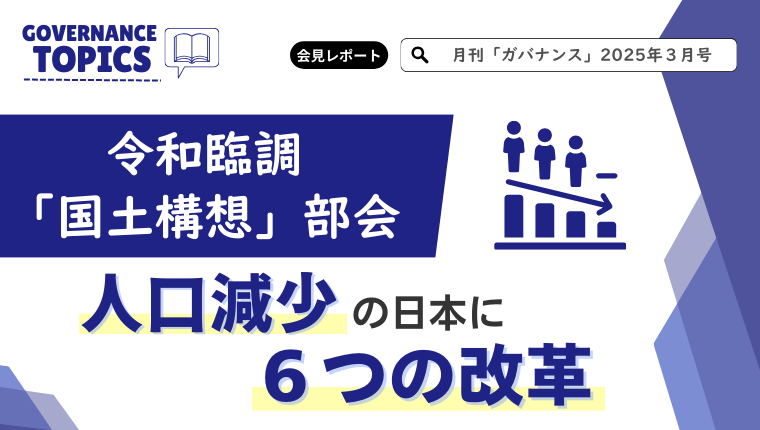
ガバナンスTOPICS【イベントレポート】
【令和臨調「国土構想」部会】人口減少の日本に6つの改革/会見レポート
地方自治
2025.03.14
(『月刊ガバナンス』2025年3月号)
【連載一覧はこちら】
【ガバナンス・トピックス】
人口減少の進む日本に6つの改革を提言
──令和臨調「国土構想」部会による提言
経済、労働、学識など民間有志による政策提言組織「令和国民会議」(令和臨調)は、2月5日に、人口減少に適応した社会に移行するための、多様な働き方や地方自治、国土利用など6つの改革提言を公表した。
パラダイムチェンジを
令和臨調は、2022年6月に発足。今回提言を行ったのは、第3部会「国土構想」部会。同部会は、2023年7月に、呼びかけ第一弾として出された「人口減少危機を直視せよ」において、人口減少という現実を正面から受け止めて日本社会のあり方を大きく変革し、「人が成長し、産業がかけ合わさり、地域がつながる社会」を目指すことを提案。今回は、それに続き、より踏み込む形で提言が行われました。


人口減少に適応する社会への提言が行われた。
パラダイムチェンジを通じて人口減少と自然災害を乗り切る
2月5日に行われた記者会見には、同部会の永野毅(東京海上ホールディングス取締役会長)、山田啓二(京都産業大学理事長・教授、元全国知事会長)、板東久美子(元消費者庁長官)の3人の共同座長のほか、主査の宇野重規(東京大学教授)、伊藤正次(東京都立大学教授)が出席した。
今回の提言では、人口増加を前提として機能不全に陥りつつある日本の社会・組織のあり方や制度を抜本的に見直し、「日本を解き放ち、組み替える─多様な生き方・働き方へのパラダイムチェンジを通じて人口減少と自然災害を乗り切る─」と題した。
3つの基本的な考え方
基本的な考え方を以下3点とした。
人口半減と激甚化・頻発化する自然災害という現実に対し、社会のあり方、価値観を時代に合った形に変えなければ、人々の暮らしや国土、文化を守れない
国民全員で、この国の将来のあり方を根本的に考え直すべき。機能不全に陥った人口増加前提の社会から、人口減少を前提にした持続可能な社会へのパラダイムチェンジを
多様性を活かし、心豊かな生き方・働き方の文化創造こそが、これからの日本社会の駆動力になる。政府や国会を巻き込んで国民運動の展開が必要
永野共同座長は、「新たな時代に重要なのは、個人の自律性と多様性だ。人口減少や激甚化・頻発化する災害などの『逃れられない現実』を悲観するのではなく、チェンジをするチャンスなのではないか」と提言に込めた思いを述べた。
具体的な方向性は
会見では、具体的な改革を実現するための方向性も示された。
人の潜在能力を解き放つ:
一人ひとりの生き方、働き方の自由度を高め、より能力を発揮できる社会へ
①女性の潜在能力の解放
②環境・意識・情報のバリアの解消
③一人の人間が多様な社会的役割を果たすことを可能にする環境の実現
④住む場所を選べる複数居住地制度
⑤多様な選択を可能にする教育への転換
⑥多様な主体の協働・共創の拠点となる大学
所有から利用へ「国土」の活用方法を変える:
国土の多様性・可能性を活かし、危機に強い国土構造に転換する
①地域資源の活用と地域の活性化
②自然資本の価値の再定義と適切な維持
③社会資本ストックの持続可能な維持管理
④自然と社会の資源循環による課題への取り組み
⑤平時・非常時のリスクに対応する地域と住まいの形─分散と集住
⑥東京の集積リスクの低減
⑦地域の特性を活かした業種なき産業構造の実現
新しい「国と地方のあり方」を考える:
基礎自治体の権限強化から、「基盤の集権化と機能の分権化」
①住民サービスの「作り込み」から「組み合わせ」へ
②デジタル技術の活用による地域行政の強化
③オープンで自律的な組織
6つの具体的な改革提言
先述の方向性を踏まえて、2100年人口6000万人を見据え、2050年をターゲットにした具体的な改革についても提言された。6つの提言は次のとおり。
生き方・働き方の改革
マルチタスク・マルチハビテーションの実現。複数住所制度への変更
所有権・利用権の改革
空き家・空き地や放置山林における所有権と利用の分離による利用優先制度の確立、豊かな自然資本の保全と利用の両立
地方自治改革
広域化や官民の協業化、ローカルマネジメント法人、DX(メタバース市役所、Maasお出かけ市役所)による行政革命
国土の「分散と集約」
東京をはじめ大都市のダウンサイジング化、孤立的分権から広域的連携への転換、地方の集約化の推進
教育の多様化改革
教育の複線化。子どもの個性や特徴に基づくオーダーメイドの教育への転換、自治体や企業と共に地域を支えるプラットフォームとしての大学へ
実行機関の設立
政府にも受け皿を作り国民運動と連携
また、各論についてもいくつか触れ、宇野主査は、「空家特措法や所有者不明土地法の改正などで、所有者不明土地の問題の解消は進んでいるものの、個別の改革にとどまっている」と指摘し、「『所有から利用へ』の視点で、全体として法制度の再構築が必要だ」と訴えた。
さらに、老朽化した社会資本の問題が表面化していることについても、持続可能な維持管理の必要性を指摘した。官民が一体となって国のあり方を議論し、長期的視点から国土政策を推進・チェックするための国土構想委員会(仮称)の国への設置も提案した。
山田共同座長は、「今ある制度や考え方を、未来に向けて変えていかなければならない」と提言に力を込めた。

山田啓二共同座長は、限られた資源と財源の重要性を訴えた。
(本誌/浦谷 收)