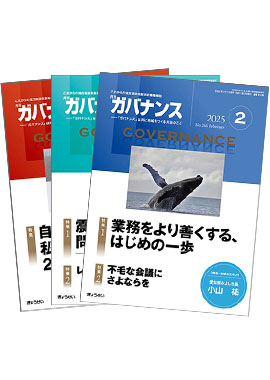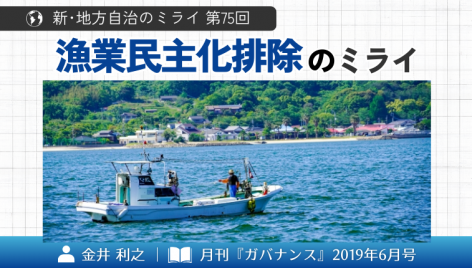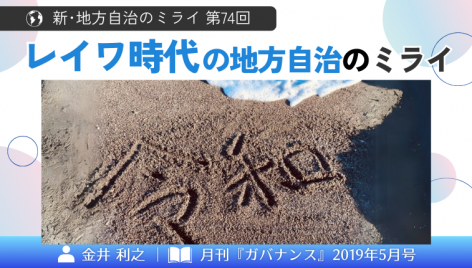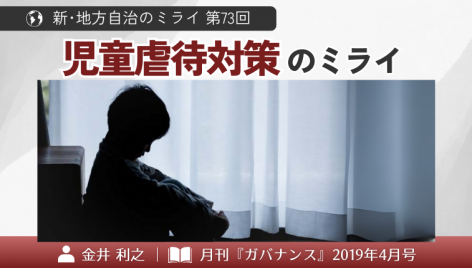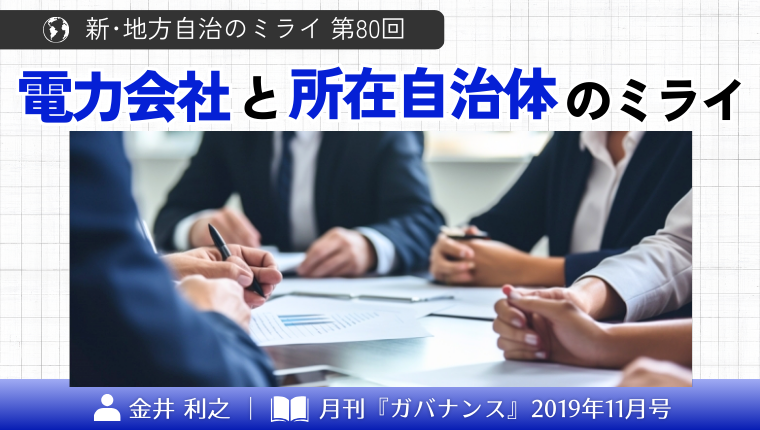
新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第80回 電力会社と所在自治体のミライ
地方自治
2025.04.03
本記事は、月刊『ガバナンス』2019年11月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに
吉田開発株式会社への国税当局の査察を端緒として、森山栄治・福井県高浜町元助役が関西電力の八木誠・会長、岩根茂樹・社長などを始めとする幹部に対して、多額の金品を渡している実態が明らかになった。そのため、豊松秀己・副社長、森中郁雄・常務、鈴木聡・副事業本部長、大塚茂樹・副事業本部長は、所得税の対象に該当するとの指摘を受け、金沢国税局に修正申告・納税をするに至った。
こうした事態を受けて、関西電力は内部調査委員会を組織した(注1)。その報告書は、2018年9月11日付でとりまとめられていたが、公表することなく本年9月27日に発覚するまで内々に済まされていた(注2)。発覚して記者会見に追い込まれ、センセーショナルで時代劇のような報告書の記載内容もあって、属人的な問題として面白おかしく報道されている。しかし、個人的な問題に矮小化することなく、自治の構造的観点から検討してみよう。
注1 委員長は小林敬弁護士、委員は千森秀郎弁護士、種村泰一弁護士、井上富夫・副社長執行役員、月山將・常務執行役員、廣田禎秀・常務執行役員である。
注2 産経新聞電子版2019年10月2日0時57分配信。
資金直流という現象

原子力発電所に限らないが、負担・危険・受苦などを伴い忌避されるような施設・事業を地方圏に立地することは、簡単なことではない。国などの事業主体は、当該施設・事業が必要であることを主張するが、「何故、当該地域でなければならないのか」という問いに答えることは、容易ではないからである。
そこで、正面からの立地の妥当性についての論証は断念し、しばしば、施設・事業に経済便益を付随させることによって、地元の懐柔を謀る。忌避施設には様々な負担・危険などが想定されるが、それを上回る経済便益を提供すれば、地元自治体・地元住民の合利的な一定範囲の了解が得られるかもしれない。「最後は金目」(石原伸晃・元環境相)という「金言」があるように、同意をカネで買う。そのため、資金の流れは、基本的に国や事業者から、地元自治体・地元企業・地域住民に一方的に向かう直流である。
原子力発電所でいえば、所在自治体等に交付される、いわゆる「(旧)三法交付金」が有名であるし、また、地元住民への電気料金軽減措置という恩恵もある。しかし、金額的により重要なのは、発電所施設に伴う所在自治体への固定資産税や、電力会社から直接または間接に地元事業者に発注される様々な事業である。その裾野は広く、受注事業者が地元企業ではなくても、その事業者が雇う作業員への宿舎・食事の提供なども地元への経済便益になる。
資金交流という現象

今回の報告書で明らかになったのは、国・電力会社から地元に一方的に直流するだけではなく、地元事業者(吉田開発など)・所在自治体関係者(森山・元助役)から、電力会社側に逆流していることである。「常識」に照らせば、電力会社等から地元にカネが流れるからこそ忌避施設を受入れる理由になるのであって、地元から電力会社にカネを流してまで、忌避施設を受入れる理由はないはずである。
もっとも、金額的には圧倒的に電力会社等から地元に流れる金額が大きい。その意味では、相殺すれば大局的には電力会社等から地元への資金の直流である。
吉田開発・森山氏側からの金品提供は、より大きな経済便宜を関西電力から引き出すための、「ポンプの呼び水」である。(電力会社から得られる便益に比べれば)「わずか」ではあるが、個々の幹部にとっては「大枚」ならば、こうした「工作」は合利的である。
自治体が国の役人を接待した「官官接待」も、国から多額の補助金・公共事業を獲得するための「初期投資」という意味で、合利的である。そして、「官官接待」に必要な資金源も、結局は、補助金等で回収できる。つまり、「官官接待」をする自治体側も、受ける官僚側も、「ウィン・ウィン(もちつもたれつ)」である。関西電力は民間企業ではあるが、構図としては「官官接待」と同じである。
不適切な関係の「是正」は可能か
上記のような資金交流関係は、通常は不適切であると考えられる。実際、官邸も経済産業省も、原子力規制委員会も言語道断として批判している。政権・経済産業省は、原子力発電所の再稼働を目指しており、こうした資金交流事件が、原子力事業への信頼を毀損することを危惧するからである。電力会社幹部と地元企業との「ウィン・ウィン(もちつもたれつ)」は、資金が無から生じない限り、誰かのマイナスで支えられる。端的には、電力料金から生み出されているから、電力利用者の負担になっている。
国の立場を忖度すれば、是正方向は明白である。原子力発電事業の展開のために、所在自治体が大きな力を持ちすぎたことが、こうした不適切な資金交流を生じた原因である、と考えるだろう。本来は、圧倒的な電力会社の札束の前に、一方的に地元関係者は「頬を叩かれ」て静かに平伏すべき存在である。それが、地元関係者の「分際」で電力会社幹部の「頬を札束で叩く」などは、「言語道断」である、と。
従って、電力会社の権力を回復し、地元関係者から「頬を札束で叩」かれる存在から脱しなければならない。それができないならば、国が厳しく電力会社を管理しなければならない。地元関係者が電力会社に対して発言力を持たないようにするためである。そして、国は自治体に提供する経済便益を、できるだけ小さく抑えられる。うまくいけば、国の為政者は地元と電力会社の双方から利得を得られる。これまでの電力会社による微温的な「地域共生」ではなく、場合によっては、地元自治体の反対を押し切っても、再稼働等を押し付けるべき、と。
自治体の対応の難しさ

不適切な関係が暴露されれば、是正措置が取られることは、充分に有り得る。それは、自治体側関係者の発言力を低下させる方向に向かう可能性が高い。確かに、所在自治体関係者が、「恫喝」をする「M」(注3)になったのは、適切とは言えない。しかし、所在自治体側の発言力が封じ込められれば、忌避施設・事業に伴う負担・危険は簡単に地元に押し付けられる。あるいは、地元同意が「買い叩かれる」ことになる。
注3 森山氏のイニシャルのMとして、関西電力や役所での陰語となっていた。産経WEST2019年9月29日21時51分配信。
所在自治体は、地域住民に不当な負担・危険が押し付けられないように、国や電力業界などに対して、充分な交渉力を持つべきである。その先人の努力の結晶が、安全協定に盛り込まれた「地元自治体同意」である。所在自治体の同意なくして、原子力発電所の稼働は有り得ないという仕組である。それゆえ、地元有力者に大きな交渉力を与える。しかし、この交渉力を、これまで、地元側が「金目」を電力会社から引き出すためにしか使ってこなかった。
国は立地地域に提供する経済便宜を下げるために、本事件を理由に介入をするだろう。自治体としても、不適切な関係を維持することはできない。しかし、それは自治体側の発言力を清算する方向に作用しやすい。地元住民の利益を代弁するために、自治体は交渉力を付けなければならない。しかし、今回の「不祥事」に対して、所在自治体側が積極的に対処する動きは見えない。再稼働への不同意をタテに、電力会社に対する「真相解明」と「信頼回復」と「金目」を求めるだけである。明確な路線が描けていない。
さらに言えば、地元には人材がいない。助役退任後久しい森山氏がミイラ(M)のように隠然とした権力を持ち続けたことは、同氏に代わる次世代の育成に失敗したことを意味する。立地紛争などで形成された同氏を引き継ぐ自治体関係者はいない。次世代は、同氏が形成した経済便益を受け取るだけだった。所在自治体の後継者たちは、「金目」ではない方向で交渉力を正しく行使することも、交渉力を再生産することも、できなかった。本件が森山氏の死去とともに表面化し、国(国税・原子力当局)が攻勢を強めるなかで、所在自治体は発言力なき負担・危険の引受に転落するミライ(M)が展望されつつある。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。