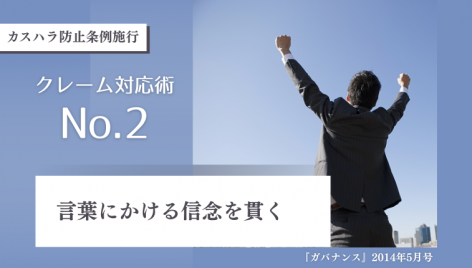新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第72回 自衛官募集協力のミライ
地方自治
2025.01.22
本記事は、月刊『ガバナンス』2019年3月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

現自民党総裁は、「立党以来の悲願である憲法改正に取り組むときがきた。自衛隊は今や、最も信頼される組織だ。残念ながら、新規隊員募集に対し、都道府県の6割以上が協力を拒否しているという悲しい実態がある。地方自治体から要請されれば自衛隊は直ちに駆けつけ、命をかけて災害に立ち向かうにもかかわらず、だ。この状況を変えよう。憲法にしっかりと『自衛隊』と明記して、違憲論争に終止符を打とう」という趣旨を述べた(注1)。その後も、前記自民党総裁と同一人物である首相は予算委員会でも「6割の自治体」と発言を訂正しつつ、同趣旨を繰り返している(注2)。
注1 産経新聞デジタル版2019年2月10日配信。
注2 岩屋毅防衛相の2019年2月15日衆議院予算委員会の答弁では、自衛官募集に協力しているのは全市区町村の36%(632団体)という。「協力」の意味は「紙か電子媒体での資料提供」である。なお、63%(931団体)は住民基本台帳から情報を取得し、10%(178団体)からは情報を得ていないという。産経新聞デジタル版2019年2月15日配信。完全非協力は0.3%(5団体)という。東京新聞デジタル版2019年2月16日配信。
さらに、状況を防衛省がすでに確認しているにもかかわらず、与党の自民党は、2月14日付で、防衛相から聞くことができないのか、所属国会議員に、選挙区内の自治体の自衛官募集に対する協力状況を確認するよう、文書で求めた。
これまでも、憲法96条先行改正による「お試し改憲」、憲法改正国民投票権の享受、教育無償化、参議院合区解消など、場当たり的な改憲の「理由」が存在してきた。ある政党(party) の「悲願」という部分(part)的目的のために、適当に「理由」が持ち出されているようであるが、これらは必ずしも地方自治保障を阻害することに直結するものではなかった。しかし、今回の「理由」は、自治体を国に協力させることが「理由」となっており、地方自治保障の観点からは看過できないものである。そこで、今回は本件を採り上げてみよう。
立法政策としての協力・執行義務
一般的に言えば、国が国の政策実施のために自治体に協力・執行を法律で義務付けることは、有り得ないわけではない。ただし、法律を制定すると何でも強制可能となるのであれば自治は抑圧されるので、憲法上の地方自治保障という限界が立法にも課されている。また、国の政策の実施であっても、自治体の事務になるのであって、自治体の政策裁量はある。とはいえ、実態的には立法裁量は広く、多くの法律によって自治体に義務付け・枠付けがされてきた。例えば、介護保険は、憲法に明記されているはずのない新しい政策であるが、介護保険法で市区町村に実施が義務付けられている。
もちろん、違憲の政策は、法律で自治体に義務付けることはできないから、自衛隊法が違憲であるならば、憲法改正をした上で自衛隊法を合憲化する必要がある。とはいえ、現行憲法解釈では自衛隊自体は違憲ではないので、改憲は必要ない。むしろ、重要なことは、立法政策として、どの程度の協力を自治体に法律で求めるかである。自衛隊法第97条①は「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」とし、同法施行令120条は、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」としている。実態としては、防衛省は各市区町村に、住民基本台帳をもとに18歳・22歳という「適齢」者名簿の提供を求め、得られた場合は自衛官募集のダイレクトメールを発送しているという。
自治体による政策判断

現行法制では、国は自治体に経費負担を前提に事務委託できるが、その内容は募集に関する報告・資料提出である。ただし、自治体側に明示的な義務を課してはいない。防衛省が自治体に提出を求めても違法ではないというだけであり、あとは自治体の任意の政策判断である。
自衛官は、徴兵制(注3)ではなく志願制である以上、個々人の任意の応募への発意が必要である。要するに、単なる採用・就職活動である。その際に、防衛省にだけ、市区町村が名簿を作成して対象者を絞る便宜供与をして、ダイレクトメールなどをはじめとした「リクルート活動」を認めるべきか、大いに疑問もあろう。自衛官といえども公務員でしかなく、公務員募集に行政側が持っている名簿情報を優先的に使うのは、行き過ぎであろう。結局、民間企業の就職活動に対して、市区町村がわざわざ名簿を提供すべきか、と同じ問題である。
注3 なお、政府見解では自衛官の徴兵制は違憲とされている。現行憲法では徴兵制を導入できないから改憲をする、というのであれば為政者の動機としては成立する。現在のダイレクトメールが将来の「赤紙」となるわけである。
このように考えれば、住民基本台帳の情報(例えば、氏名、年齢、性別、住所)を自衛官募集に提供するのは、相当に慎重になるのも当然である。とはいえ、自衛官募集も重要であると考える市区町村も多かろう。その意味で、名簿は提出しないが閲覧は認める、という運用を多くの市区町村がしていよう。市区町村ごとの個人情報保護に関する政策感度は、住民世論などにも左右されるので、国が一律に決めるのも適切ではないので、報告・資料提出にどのような協力をすべきかは、自治体が判断すべきであろう。
一般に、個人情報保護の要請から、あるいは、DV・ストーカーや勧誘・ダイレクトメール対策などから、住民基本台帳には閲覧制限が課され、あるいは、大量開示請求には消極的になってきた。とはいえ、災害弱者・乳幼児健診・小中学校就学・独居老人などの要支援者・対象者の把握のためには、個人情報保護と生命・安全などの衡量もある。若者本人の知らないところで、市区町村の一方的判断で情報提供されるべきほど、自衛官の「なり手不足」問題(注4)が、個人の生命・安全に匹敵するくらいの価値があるのかが、問われよう(注5)。まさに、自治体が政策判断するのが、2000年改革で目指した分権型社会である。
注4 現実には、格差社会と若者就職難のもとでは、低所得層高校生等への進路指導において自衛隊は「優良勤務先」であり、民間就職を諦めて自衛官に志願せざるを得ない構造(「経済的徴兵制」)が生じるともいう。むしろ「人手不足」は他職種で著しい。
注5 上記の情報提供は、提供される本人の生命・安全に資する。「適齢」期若者の情報提供は、提供される若者本人の生命・安全に資するかどうかは不明である。むしろ、他人の生命・安全のために提供されるかもしれない。
事実上の影響力の行使

法制上の義務付けをしない場合でも、政権・府省官僚・与党などの国政為政者は様々な影響力を自治体に行使できる。典型的には、補助金などによる財政的誘導がある。また、国の事業を特定の自治体の地域に実施する/しない選別という「箇所付け」も影響力となる。
明示的な助言・批判や行政指導という情報による影響力もある(注6)。さらに、「実態調査」という名目で、特定の自治体の行動を炙りだし、社会的・政治的な圧力を掛けようとする手法もある。法制的な分権改革がされても、国政は様々な集権的手法を有している。
注6 例えば、ふるさと納税を巡る総務相による泉佐野市への批判は、このタイプである。なお、この件に関しては、総務省は、批判に留まらず、法的制限を課すべく地方税法改正を2019年に行い、指定団体制度が導入された。
その意味で、今回の自民党の所属議員への協力情報の確認作業は、新手の「圧力」手法といえよう。すでに防衛省は実態を把握しており、自治体の行動は明確である。その上で、小選挙区ゆえに、選挙区の代表回路を独占している自民党議員を介して確認をさせることで、国の意向に反する特定の自治体を、何らかの国の政策/事業上の不利益があるかもしれないと萎縮させる効果が生じ得る(注7)。もちろん、明示的な指示や圧力ではないという弁解も、自民党側は可能である。「月夜の晩ばかりではない」と言われるのと同じで、あくまで、自治体側の危険回避への指向に基づく忖度を前提としている。
注7 国政与党から自治体への圧力だけでなく、与党幹部から党総裁に従うことを求める各議員に対する圧力ともいえる。
おわりに
冒頭に紹介した自民党総裁発言は、自衛隊の災害救助派遣という「箇所付け」と、自衛官募集への名簿提出という協力とを、リンケージすることを示唆する。つまり、自治体が名簿提供で協力すれば災害救助派遣がされ、協力しなければ災害救助から見放される、かのごとき印象操作をする。言うなれば、国の政策に自治体が賛成しなければ、住民は国の事業やサービスを享受できない状態である。住民を人質にとって、自治体の政策判断を国に従わせようとするものである。
地方自治保障がなされ、自治体の政策判断の自由が認められるには、自治体の政策判断がいかなるものでも、当該地域あるいは当該自治体に対する国の政策的取扱が無差別であることが不可欠である。2001年以降、すっかり干涸らびてミイラ化してしまった分権理念ではあるが、改めて、基本原則の復活を図ることが必要であろう。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。