
自治体最新情報にアクセス DATABANK
自治体最新情報にアクセス|DATABANK2023 月刊「ガバナンス」2023年8月号
地方自治
2023.08.21
目次
自治体最新情報にアクセス DATABANK
(月刊「ガバナンス」2023年8月号)
●市の強みや戦略をまとめた「統合報告書」を作成
岡山県瀬戸内市(3万6700人)は、統合思考によってまちづくりを進めるため、「瀬戸内市統合報告書2022」を作成した。統合報告書とは、財務データと非財務データ(ガバナンス、CSR、知的財産等)の両方の観点から、組織の独自の強みや戦略、ガバナンス、今後の事業展開や見通しなどをまとめたもの。組織の短期・中期・長期にわたる価値の創造について理解でき、組織内外とのコミュニケーションツールとなることから、企業や大学を中心に作成されている。
同市では、市の戦略や事業実績などを分かりやすく説明し、またリスクも含めた公正で中立的な情報を市民と共有するとともに、内外に瀬戸内市をアピールすることを目的として、国際統合報告評議会(IIRC)のフレームワークに沿って作成した。自治体がIIRCのフレームワークに沿って統合報告書を作成したのは全国で初めて。
統合報告書は、48P・オールカラー。市の概要とあゆみ、将来像とその実現に向けた価値創造のプロセス及びリスクと機会、未来の姿(ゼロカーボン、歴史・文化・芸術活動、ダイバーシティ、子育て)、取組実績、ガバナンスなどを、写真や図表、データを入れて分かりやすく紹介している。
統合報告書の作成プロセスを通じて庁内各部署の有機的なつながりが生まれ、統合思考による意思決定ができる職員の育成につながっているのも大きな成果で、統合報告書を活用して市民や市内外の関係者とともに持続可能なまちづくりに取り組んでいく。
(月刊「ガバナンス」2023年8月号・DATA BANK 2023より抜粋)

●災害時要配慮者対策の推進に向けて大学と共同研究
東京都豊島区(28万3300人)は、災害時要配慮者対策の推進に向けて大正大学と「災害時要配慮者対策の推進に係る共同研究に関する覚書」を締結。防災や福祉に関して幅広い知見を有する大正大学と連携して、高齢者や障害者等の災害時要配慮者が抱える課題解決のための共同研究を進めている。
区は21年8月に庁内プロジェクトチームを立ち上げて災害時要配慮者に必要な支援策や体制を検討し、4000人を超える避難行動要支援者の「個別避難計画」の作成を計画している。だが、その作成プロセスや体制が確立されていなかったことから、大正大学と共同で研究していくことにした。まずは優先度の高い要支援者の計画作成を着実に進めていくため、モデル地区を選定して個別避難計画を作成・検証する。8月5日には大学との共催で防災講習会を開催した。
(月刊「ガバナンス」2023年8月号・DATA BANK 2023より抜粋)

高際みゆき区長(右)と大正大学の髙橋秀裕学長。
●NFTを活用しデジタル住民票を発行
山形県西川町(4900人)は、NFT(非代替性トークン)を活用した「デジタル住民票NFT」を発行した。自治体発行のものとしては全国初。
デジタル住民票の保有者は、町のデジタル住民として、町内の水沢温泉館・大井沢温泉館の入浴無料(町内在住者を除く)や、保有者限定オンラインコミュニティ・メタバース空間での交流など、さまざまな特典を受けることができる。
同町は、23年4月、NFTマーケット「HEXA(ヘキサ)」を運営するメディアエクイティ社と包括連携協定を締結。双方の資源や人材を有効活用し、協働によるまちづくりを推進することにより、町の活性化と町民サービスの向上に向けた取組みを進めている。今回のデジタル住民票の発行もその一環であり、新たな関係人口の創出を目指している。さらに町では、ふるさと納税額2億5000万円達成を目指し、寄付者限定のNFTを返礼品として発行するとしている。
(月刊「ガバナンス」2023年8月号・DATA BANK 2023より抜粋)
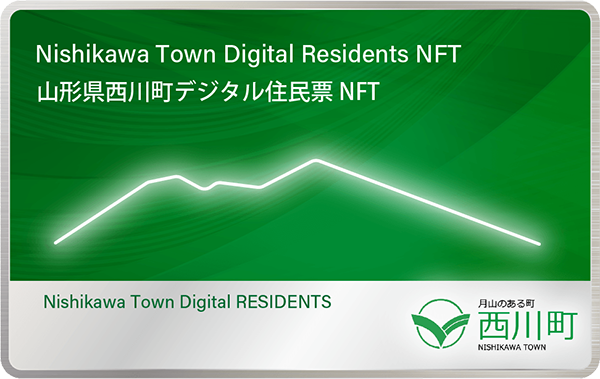
●市バスの平均乗車人数と停留所別の乗降人数データを公開
神戸市(151万7600人)は、23年4月、市バス利用状況データサイト「mieruka(ミエルカ)」を公開した。市バスのICカードの“ 2タッチ化” により得られた乗降データを活用し、市バス1便ごとの各停留所間における利用客の乗車状況(一定区間の平均車内人数)や停留所別の乗降客数が分かるもの。この規模のデータ公開は全国で初めてという。
神戸市バスでは、21年3月より、ICカードを利用して乗車する際に、利用客に乗車時と降車時の2回、ICカードみ取り機にタッチしてもらうことにより、停留所別の乗降客数が正確に把握できるようになった。mierukaでは、それにより得られた乗降データが活用されている。
市では、mierukaを活用することで、市バスの混み具合が分かるため、フレックス勤務など時差出勤の目安になり、より快適に市バスを利用できるようになるとしている。また、妊婦やベビーカーを利用している人も、市バスの混雑の目安を確認することが可能になる。さらに、停留所ごとの乗降人数を市場調査や街の活性化に役立てることもできるという。
YouTubeでmierukaの操作方法の解説動画を公開しており、市のWebサイトよりアクセスが可能となっている。
(月刊「ガバナンス」2023年8月号・DATA BANK 2023より抜粋)
●自治体で利用できるChatGPTのシステムを共同開発
宮崎県都城市(16万2600人)は、生成AIのChatGPTに関する行政利用調査研究事業を進めている。市は地域課題をAIやIoTなどの先端技術で解決することなどを目的に企業から提案を募集する「都城市DXチャレンジプロジェクト」を進めており、そのプロジェクトとして採択したもの。システム開発会社のシフトプラス㈱とChatGPTを自治体環境で活用できるプラットフォーム「zevo」の共同開発を23年5月から開始した。自治体が企業と共同でChatGPTのシステム開発を行うのは全国初となる。
ChatGPTの活用に対しては、行政の効率化や市民サービス向上の観点から大きな期待が寄せられているものの、自治体はセキュリティの関係上、インターネットに接続していない自治体専用ネットワーク(LGWAN)を利用しているため、基本的に庁内業務ではインターネットシステムであるChatGPTが利用できない。また、ChatGPTの活用では個人情報などについてのルール整備の必要性が指摘されている。そのため市は、ChatGPTをLGWANで安全に使うことができるサービスとして「zevo」をシフトプラスと共同開発し、活用に当たっては個人情報と機密情報の入力を禁止するとともに、万が一入力してしまった場合でも情報の流出に繋がらないようシステム面での安全措置を確保することとした。6月に「zevo」の利用テストが行える環境が整ったことから、想定される行政利用のデモンストレーションを実施。その後、庁内への展開を図っており、7月からはシフトプラスによる他自治体での無償トライアルも開始した。市は引き続き、行政分野におけるChatGPT活用の可能性について調査研究を進め、また、他自治体への横展開についても全面的に協力していく。
(月刊「ガバナンス」2023年8月号・DATA BANK 2023より抜粋)
●県内ローカル線の維持・活性化に向けて「ローカル線応援団」の募集を開始
山口県(134万500人)は、県内ローカル線の維持・活性化に向けて取り組む意欲のある事業所、店舗及び各種団体、個人を登録する「やまぐちローカル線応援団」の募集を開始した。
応援団は、従業員の通勤・出張でのローカル線利用促進、駅舎・車窓からの風景や沿線名所・名店などの魅力の発信などを通して、登録者自身や従業員、家族が積極的に鉄道を利用し、鉄道の利用促進に向けた取組に協力・参画する。
登録企業・団体は、県のWEBサイトに企業・団体名、サービス提供内容、取組みの内容等を掲載しPRを行うことができ、地域貢献に取り組む企業・団体としてイメージの向上が期待できる。県では、オリジナルロゴ入りの登録ステッカーやのぼり旗、PR用動画データ等を提供するとともに、優秀な取組みに対し、表彰状と報奨金を授与するとしている。
また、個人の応援団についても、情報発信回数や内容が優秀な活動者に対し、表彰状と商品(宿泊券等)が授与される。
登録を希望する企業・団体は申込書を県交通政策課まで提出する。一方、個人の希望者はやまぐちローカル線応援団公式Instagramをフォローするか、専用フォームに入力して登録する。
(月刊「ガバナンス」2023年8月号・DATA BANK 2023より抜粋)
●水稲生育予測システム「でるた」の運用を開始
千葉県(631万900人)は、23年4月、水稲の生育を予測し、病害虫防除など稲の生育状況に応じた適切な作業時期の目安が分かる水稲生育予測システム「でるた」の運用を開始した。スマート農業推進の一環として県が開発したもので、「穂が『出る田』んぼが予測できる」ことから、「でるた」と命名された。「でるた」は、WEBアプリであるため、パソコン、スマートフォンいずれの端末でも利用が可能であり、利用に際しての登録は不要。利用料も無料となっている。
対象となる稲の品種は、県が育成した「粒すけ」をはじめ、県内で生産されている主要6 品種。「アメダス地点(県内10か所)」「移植日(苗を植えた日)」「品種」の3項目を選択するだけで、誰でも簡単に生育状況を予測することができる。
22年4月より実際の運用を想定した運用試験を実施したところ1万3000件を超えるアクセスがあり、県ではシステムの実用性や運用方法などが確認できたとしている。
また、職員による現地確認では、調査した約80%の水田において、予測された出穂期は実測値の前後3日以内に収まり、アンケート結果でも「予測の精度に問題がない」「使いやすい」「継続利用したい」など肯定的な意見が多数を占めているという。
近年、水稲の生産については、気候変動の影響から、追肥や斑点米カメムシ類の防除対策などの作業の適期の判断が難しくなってきたことに加え、経営の大規模化により管理する水田が増えている。こうした背景を踏まえて県では、簡単かつ正確に生育状況を予測できるシステムの開発に取り組むこととなった。
こうした経緯を経て運用フェーズへと至ることのできた「でるた」は、県の独自開発のため、開発や運用にかかるコストが低く抑えられている。
(月刊「ガバナンス」2023年8月号・DATA BANK 2023より抜粋)






















