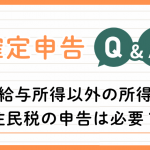巻頭言 税制鳥瞰図 国税・森林環境税・譲与税の争論
地方自治
2021.09.10
巻頭言 税制鳥瞰図
国税・森林環境税・譲与税の争論
東京経済大学経済学部准教授 佐藤 一光
森林環境税及び森林環境譲与税の3つの問題

森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、令和元年度から同譲与税の譲与が始まっている(課税は令和6年度開始)。同税が創設された背景にはいくつもの問題が横たわっている。第一に、日本の林業の衰退である。国土の3分の1を森林に覆われた日本は、特に戦後の住宅不足を背景として木材生産と将来の生産に向けた植林が盛んであった。ところが、安価な外国産の木材に押されて素材(建材)生産は徐々に減少してきた。1990年台後半には、市場で出回る木材価格では、植林から伐採までの費用を賄うことができなくなった。そこで、森林整備における政府の役割、林業政策の重要性が高まってきたのである。第二に、環境問題の深刻化や、環境意識の高まりによって、いわゆる森林の公益的機能・多面的機能が強調されるようになった。気候変動問題に対する二酸化炭素の吸収源としての森林や、生物多様性の源泉としての自然、そして国土の保全や水源の涵養といった機能が重要視されている。第三に、地方分権の推進によって、地方独自課税の必要性が認識されるようになった。そこで、森林の公益的機能に着目して多くの地方森林環境税が導入されてきた。地方森林環境税は、いわば地方自治と環境政策とを重視する地方政府の象徴と呼べる存在となった。
もっとも、採算性の悪化による国有林事業の縮小、都道府県における林務官の減少など、林政全体としては徐々に撤退戦を強いられてきた。そこで林政の切り札として創設されたのが同税である。森林経営管理において市町村がより重要な役割を担うようになってきたため、林業費の財源を保障する必要があったのである。マンパワーの少ない市町村では、地方森林環境税のような独自課税を課すことが難しかったからでもある。
同税の導入は、財政需要を満たす税制改正として社会保障の充実以外では近年稀に見る思い切った改革である。ところが同税には、財政学者からも、林業の現場からも多くの批判が寄せられている。例えば月刊『自治総研』では、「国税・森林環境税の問題点」と題した連載が行われた(2019年2月から8月号まで)。同税の問題点としてこの連載の中では、①国税に適用してはならない地方税の論理を国税に適用した「人頭税」であること、②国民に対する説明責任を果たしていないこと、③必ずしも林業費の多い自治体に多く譲与されるわけではないこと、④森林保全を訴えてきたアクター達の意見が反映されていないこと、⑤同税が森林保全に繫がるのか不透明であることなどがあげられた。
「森林環境税バブル」を喜ぶ声もあるが…

他方で、林業の現場では、降って沸いた財源によって「森林環境税バブル」とも呼べる状況が生まれている。不在山主の調査、不明瞭な境界線、劣化した林道、木材蓄積量の調査や野生生物による食害への対応など、林業の現場では対応すべき多すぎる課題に直面していたため、一息ついた感も強い。しかし、財源ができたと喜んでばかりもいられない。現場からも、同税の謳う目的である「パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等」が実現できるかどうか疑問の声が上がっている。その理由として、①林業従事者の減少によって森林整備の予算が消化できない状況が既に生まれていること、②近年の木材高騰によって伐採量が増加しているが再造林(植林)率が低くなっていること、③予算の大部分が林業従事者・山林所有者に届かない使われ方がなされていることなどがある。
目的税が目的とする政策目標を達成できなければ、後に残るのは不公平な負担の人頭税と林業への憎悪である。国税・森林環境税・譲与税を世紀の悪税にしないためには、森林と林業の再生に資する使い道と公平な負担のあり方について、今一度真摯に考える必要があろう。
Profile
佐藤 一光 さとう・かずあき
東京経済大学経済学部准教授
1979年、滋賀県生まれ。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士後期課程修了、博士(経済学)。慶應義塾大学経済学部助教、内閣府計量分析室、岩手大学人文社会科学部准教授を経て、2021年4月より現職。著書に『環境税の日独比較』。論考に「保育士の給与が低い理由」(『都市問題』vol.112)、「現代的貨幣理論の構造と租税論・予算論からの検討」(『財政研究』Vol.16)「エネルギー課税の長期的な国際比較」(『エコノミア』Vol.69 No.2)など。