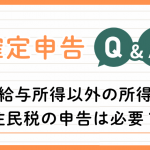自治体の防災マネジメント
自治体の防災マネジメント[3]熊本地震に学ぶ小規模自治体の災害対応課題
地方自治
2020.03.26
自治体の防災マネジメント―地域の魅力増進と防災力向上の両立をめざして
[3]熊本地震に学ぶ小規模自治体の災害対応課題 鍵屋 一(かぎや・はじめ)
(月刊『ガバナンス』2016年6月号)
2016年4月14日、16日に熊本県益城(ましき)町は震度7の烈震に襲われ、それ以降も大規模余震が継続した。本連載では、魅力増進型防災について取り上げているが、今回はこの熊本地震に関する内容とする。
益城町は人口約3万4000人、1万4000世帯に対し、全壊住宅が約1000、半壊・一部損壊が約4300。全壊世帯は全員、半壊・一部損壊世帯の半分が避難しているとすれば、避難者は8500人に上ると見積もられる。事実、4月22日には町全体で1万1000人の避難者がいた。4月30日現在で、避難所にいたのは5366人、そのうち車中泊が749人である。その他の方は、壊れた自宅に残ったり、近隣自治体の避難所や親族を頼って移動したと考えられる。
自治体は、被災者でありながら支える側でもある。4割の住宅が損壊し、3割を超える住民が避難するという過酷な状況に襲われた、小規模自治体における発災直後の災害対応の課題について検討する。
安易な批判をしてはならない

益城町は、まず避難所の設置、運営に全力を挙げて取り組んだ。残念なことに、避難所として予定されていた県立と町立の大型体育館2か所が甚大な地震により損傷を受けて使用不能となった。このため、残った公共施設、福祉施設、民間ホテルなどに避難者が殺到し、入れなかった人は車中泊、テント泊を余儀なくされた。
こういう状況で、どの自治体がきちんとした災害対応ができるだろうか。たとえば、「避難所で高齢者、障がい者が厳しい状況に置かれている。町はしっかりと対応すべきだ」なの非難が寄せられる。しかし、要配慮者にきちんとした対応をするためには、福祉施設などに避難している一般避難者に別の場所に動いてもらわなくてはならない。しかし、どの施設も満杯で動かせないのが現状だ。そこで、一部壊れた施設を補修して避難所として使えるようにしたり、テントを張って誘導したりして、少しずつ動かしながらより良い環境づくりを目指している。
現場を見ているからと言って、ものごとを表面的に捉え、問題点を指摘するだけの批判をしてはならないと強く思う。まして現場から離れた遠くの場所から、安易な批判をすることは避けなければならない。これは、私自身の自戒でもある。
自治体への批判は自治体の評価を落とし職員を意気消沈させるだけでなく、住民に自治体への不信感を募らせる。それは、災害に慣れていない報道機関が、往々にして「かわいそうな被災者と役に立たない行政」という行政批判のニュースを流すからだ。このため、行政の些細なミスがさも重大な失敗であるかのように報道され、住民の行政不信の思いが増幅される。
それよりも、被災者に心を寄せる応援メッセージ、地域単位での生活支援情報など、被災者支援や次の災害を防ぐ啓発に力を入れるのが、災害時の報道機関の重要な役割だと信じている。
庁舎は倒してはならない
益城町庁舎は一部損壊し、診断が終わらないと使えない状況だ。そこで保健福祉センターにある児童館の1フロアーを災害対策本部にしている。ざっと100m²程度に、町職員、警察、消防、自衛隊、応援職員、防災関係機関など60人から100人がいる。机とイスが所狭しと並べられ、避難所よりも狭いくらいだ。その結果、災害対策本部や記者会見を開くこともままならない。町長室は児童図書室で、そこで要人を迎えたり重要な打ち合わせをしている。職員の勤務環境も苛酷だ。秘書は、町長室入口で、イスに座ってメモをとりながらの仕事で、机もPCもない。
庁舎被災による空白時間の課題は、阪神・淡路大震災の大きな教訓の一つだ。首長も職員も執務場所がなくなり、不慣れで不便な場所で苛烈な災害対応をせざるを得なくなる。東日本大震災でも、庁舎が被災した自治体は全く同じ困難に直面した。
自治体の業務継続の観点からも、本庁舎が被災した際の代替庁舎を考えておくことは重要だ。たとえば消防事務組合の防災庁舎を安全な場所に建て、本庁舎被災時に首長室・幹部室・災害対策本部執務室・会見室を用意する。または、多くの職員が参集できる場所(体育館・公民館など)に仮執務スペースを設けるなどが考えられる。
職員を避難所に長く張り付かせてはならない
4月22日現在、本部に詰めている職員は町長以下31人、16箇所の避難所に161人だ。そもそも、自治体規模に対して職員数が少ないうえに、緊急対応的に町職員が避難所を運営しているので、本来の災害対応業務に戻れない。それは、余震がひどくて応援職員やボランティアがなかなか入れなかったり、あるいは宿舎不足などで受け入れられない状況だったからでもある。もっとも、臨時役場が狭いので、戻る場所はないのだが。
そこで、町役場を応急補修して使えるようにしたり、徐々に入ってきた応援職員やボランティアに避難所運営の一部を任せたり、避難者による自主運営に移行することによって、職員を戻そうと努めている。
孤独にしてはならない

被災すると、実に多くの関係機関、マスコミがどっと押し寄せる。それぞれに支援の熱意、ミッションを持っているが、受け止めるほうは一つなのだから大変だ。重要な判断、要人やマスコミ対応は首長の仕事だが、非常に孤独である。たとえば、今後、仮設住宅用地を確保する時期が来るが、学校の校庭に建てるか否か、などはどちらに決断しても厳しい批判が待っている。
このとき経験ある首長や補佐役がサポートしてくれれば、どれほど心強いだろうか。また、実務では、役所内部、関係機関相互の情報共有、連携の調整作業が非常に多数発生する。これが小規模自治体では総務課長に集中する。もちろん、集中することで情報の一元化ができるが、膨大な量で、かつ不慣れな業務であるため、課長をサポートする人材、課長の相談役になる人材が必要だ。
現場でも、たとえば私は福祉避難所の調整に従事したが、要配慮者一人を動かすために本人、家族、ケアマネージャー、施設幹部、担当職員と多くの調整が必要だ。これを何十人と繰り返す。そして、今後、もっともっと増えていく。
東日本大震災、そして熊本地震の応急対策の現場では、消防、警察、自衛隊、国交省、水道、ガス、電気など組織的広域連携体制の力が光った。このシステムを市町村に持ち込むのはどうか。たとえば、被災地で幹部職員として経験のある市町村職員の登録システムを作り、平時から内閣府兼務辞令を出しておく。発災時には、直ちに内閣府防災の一員として被災地自治体に派遣し、それぞれの災害対策本部で首長、幹部職員を市町村の立場で支援する。さらに、現場で動ける一定の経験を持った市町村職員を登録しておき、災害時には要請を待たずに市町村に業務別に数十人規模で派遣する。このような行政版支援チームを制度化することが、小規模自治体を支援するには極めて有効と考えている。
Profile
跡見学園女子大学教授 鍵屋 一(かぎや・はじめ)
1956年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、東京・板橋区役所入区。法政大学大学院政治学専攻修士課程修了、京都大学博士(情報学)。防災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長、危機管理担当部長、議会事務局長などを歴任し、2015年4月から現職。避難所役割検討委員会(座長)、(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事、(一社)防災教育普及協会理事 なども務める。 著書に『図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ』 (学陽書房、19年6月改訂)など。