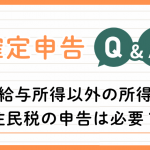徴収の智慧
徴収の智慧 第22話 取立責任
地方自治
2019.08.13
徴収の智慧
第22話 取立責任
景気と徴税

いわゆるバブル経済の崩壊やリーマンショックによる経済へのダメージなど、平成の時代に入ってから、あたかも打ち寄せる波のごとくうち続く試練に晒されたわが国の経済(とりわけ地方の経済)は、残念ながら、その後も回復基調にあるとは言えない状況である。経済は、非常にデリケートで、決してひとつだけの要因で大きく変動するものではない。複数の要因が重層的に、あるいは相互に作用しあって変動するものである。こうした中にあって言うまでもなく税は、経済活動の成果物を主たる課税対象としているから、もちろん経済と無縁ではあり得ないし、それゆえ税収は、景気の動向をもろに反映することとなる。
もとより、景気の動向がどうであろうとも、賦課や徴収といった税務行政は、税法の定めるところに則り、粛々と進めていかなければならないものである。つまり、景気が悪く税収の伸びが期待できないからと言って、厳しい徴税をしたり、その逆に、好景気の影響で税収が順調だからと言って、徴税の手綱を緩めるなどといった「あってはならない配慮」をしたりしてはならないのである。税務行政の最大のメルクマールは、公平であることであり、それが法律に基づいて適正に行われることである(租税法律主義)。そのことが担保されていればこそ、納税者は税務行政に信頼を寄せるのである。このことについて、ひとつの例を見てみよう。
滞納処分の対象財産

最近は地方団体の徴税力も大いに向上しつつあり、不動産公売は言うに及ばず、捜索や動産公売に着手するところも少なくなく、滞納処分の対象財産は、かつてに比べたら非常にバラエティに富んだものとなっている。生命保険もそのひとつである。生命保険には生活保障的な機能があるとも言われるが、別の側面としては、単なる預貯金と違って、万一の場合の給付という付加価値のついた貯蓄商品としての性格もある。その意味で滞納整理においては、効果的な財産ではあるのだが、滞納処分によって取り立てられて保険契約が消滅してしまうと、再度同一の給付水準で加入しようとする場合は、掛け金が増えてしまったり、あるいは高齢者だと再加入することができなくなってしまうなどという問題があった。そうした懸念もあったことから、先ごろ保険法が改正され、介入権という新たな制度が導入され、一定期間内に介入権者(保険金受取人)が解約返戻金相当額を支払うことで、保険契約を存続させることができるようになったのである。
納税誓約の問題性

ところが、差し押さえた生命保険について、介入権行使期間を経過しても保険会社に解約申込みをせずに、滞納者と「納税誓約」をしてしまう実務取扱いをしているところがあるというのである。すなわち、こうである。生命保険の差押えを執行したところ、滞納者から「取り立てられたら万一の場合に困る」といって懇願されたとか、あるいは「役所は人の一生を台無しにするのか!」などと脅されたりした挙句、そうした滞納者の勢いに押されて、勝手に取立てを留保して、分納という任意納付に期待する約束をしてしまうというのである。そもそも、分納も含めた任意納付が期待できない滞納者だからこそ財産調査をして、差押えをしたはずであるのに、口頭で苦境を訴えられたとか、ましてや脅されたなどといった理由にもならない理由で強制執行を留保して、履行の確証のない分納を認めてしまうのは、滞納整理の道を外れているし、徴収職員として何とも情けないことである。
国税徴収法第67条第3項は、「徴収職員が第1項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。」としているが、この規定は、「金銭を取り立てたときは、その金額の限度において、滞納者の国税の納税義務を消滅させることをいう。」(同法基本通達第67条関係13)のである。したがって、取り立てるまでは延滞金が生じるのであって、徴収職員が速やかに取立てをしないことによって、滞納者に過大な延滞金の負担を強いることにもなるのである。徴収職員の一存で勝手な解釈をし、運用するような牽強付会は許されない。取立責任を果たすべきである。