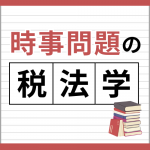時事問題の税法学
時事問題の税法学 第27回 サラリーマン受難時代
地方自治
2019.08.19
時事問題の税法学 第27回
サラリーマン受難時代
(『月刊 税』2018年1月号)
徴税強化

以前、NHKテレビで毎週火曜日の夜、「平成世の中研究所」という情報バラエティ番組があった。平成6年3月1日放送のテーマは、「所得税は不公平か」だった。番組では、東京に住む年収827万円のサラリーマンが登場し、仕事に必要な衣類の購入代、自転車通勤の費用、新聞購読、散髪、クリーニング代、冠婚葬祭費、同僚と一杯やる交際費など、日頃、必要経費と感じている支出を家計簿から目一杯抽出した金額は、年収の9.5%。一方年収827万円に対する給与所得控除額の比率は約23%で、サラリーマンはトクしているというオチがついた。
この番組をいまここに紹介ができるのは、税制上、自営業者が優遇されているという世間の批判に対抗するために、個人事業主の全国組織である全国青色申告会総連合が、その機関誌で、この番組の内容を取り上げたからだ(「青色申告」496号・平成6年5月1日)。
給与所得控除のありがたさは税務の常識ではあったが、収入=所得と思っているサラリーマンが多いことから、番組内容は新鮮だったかもしれない。それから約10年後の平成17年6月、政府税調は、給与所得控除額の縮小という増税案と自営業者の徴税強化を提起した。これをうけ、毎日新聞は、「サラリーマンも申告の時代に」という社説を掲載した(平成17年6月22日)。論旨は、給与所得者と事業所得者との所得捕捉率などの不公平感を骨子に、特定支出控除の拡大や自己啓発費用の経費化など、給与所得者への申告納税制度を提唱していた。
その頃、源泉徴収から年末調整の下にあるサラリーマンに納税意識と痛税感を持たせようという気運もあり、サラリーマンにも申告納税を導入するという論議もあった。かつてこのサラリーマンの申告制度が争点となった最高裁昭和60年3月27日判決、いわゆる大嶋訴訟では、給与所得への申告制度の導入は、税務執行の混乱を招くと指摘していたが、電子申告は、技術的には後押していたといっていい。
サラリーマンの申告納税
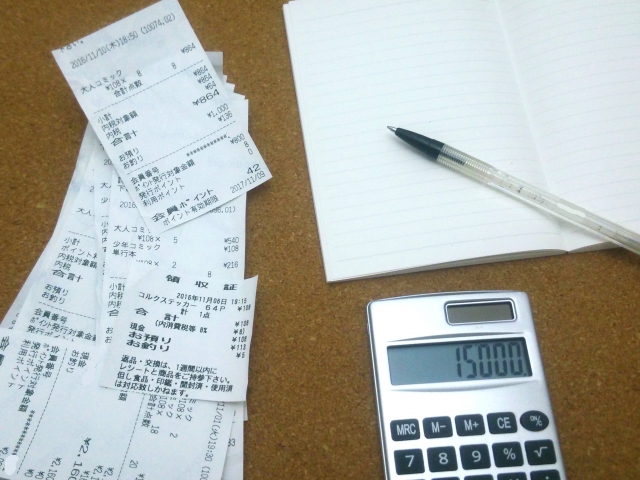
もっとも業務関連性や費用対効果などの必要経費の論理は、所得の種類に応じて変化することもなく、サラリーマンが勤務や通勤に必要な衣類の購入費や社内の冠婚葬祭や飲食にかかる費用の経費性が容認されることはない。自己啓発に励み知識を習得しても昇給する保証はない、つまり給与所得の計算には、必要経費の概念は存在しない。
仮に申告制度が導入したとしても、内容は年末調整の程度になり、源泉徴収義務者は年末の給与計算が緩和され、該当者が全員、申告手続をするはずもないので国庫が潤う、というような話も囁かれていた。
時を経て平成24年度税制改正で、給与所得控除の控除額が変更され、年収1500万円を超えるときには、控除額は245万円を上限すると改正された。こういうランク別の改正は、段階的に対象ランクが下がる可能性が高いが、案の定、平成25年12月には政府与党は、平成28年分には年収1200万円を超えるときには控除額の上限を230万円、同29年分には年収1000万円を超えるときには控除を220万円を上限とする検討すると報道されたが(朝日新聞平成25年12月10日)、それは予定通り実施されている。
ところがこのところ報道される来年度の税制改正では、さらに給与所得の見直しを行い、対象を年収800万円から900万円とする方向だという。消費税税率アップに比べて大きな増税であるが、当事者であるサラリーマンはその実情を理解しているか疑問である。
一方、20数年前に示された事業所得者への徴税強化は進展しただろうか。例えば、最高裁平成26年1月17日判決では、弁護士会役員として活動費用が必要経費として容認されたが、これは業務関連性における業務を拡大させた。業界団体の活動に資金を投じても収入は増えないが、業界人としての活動は業務の一環という論理である。やはり自営業者は税制上、恵まれているといえるだろうか。