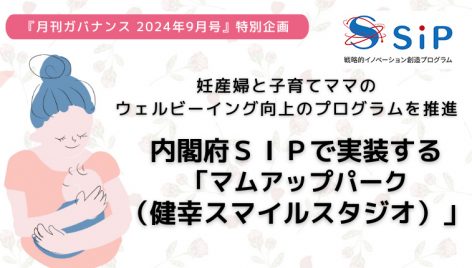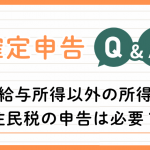新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第30回 辺野古移設のミライ
時事ニュース
2023.06.26
本記事は、月刊『ガバナンス』2015年9月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
はじめに

在日米軍の普天間飛行場の基地被害を「軽減」するという目的で、同飛行場の返還が日米合意された。そのための代替施設が必要であるとして、結果的には沖縄県名護市辺野古という「県内移設」が一体不可分として付いていた。しかし、本土での負担分任なき県内移設には、沖縄県及び名護市はほぼ継続的に反対をしており、基地移設は小泉政権のような強力な長期安定政権のもとでも進まずミイラ化していた。
米軍基地は、それが所在する自治体にとっては極めて深刻な問題であり続けた。しかし、分権論議や役割分担論でも、外交・防衛は国の専管事務とされやすい。特に日米安全保障条約に起因する米軍基地問題は、「条約誠実遵守」(憲法98条②)からも、同条約を締結している以上、国の政権自体にも当事者能力が十全に備わっているわけでもない。
同時に、米軍基地被害は、地域住民の生活に極めて密着した問題であり、自治体が最優先に取り組むべき課題で有り続けてきた。外交・防衛に自治体が容喙(ようかい)するのは越権であるという批判は、原始的には存在していたが、広く地域における事務を推定される日本の自治体において、基地被害への対策をとるのは自治体の基本的な事務であるという了解が成立している。特に、国の政権に当事者能力がなく、米軍自体が「戦勝国の占領軍」という意識が抜けないため、通常の迷惑施設以上に、米軍基地は周辺被害が大きい傾向があるのである。
そこで、今回は辺野古基地移設問題のミライについて検討しよう。
「この道しかない」という思考停止
米軍基地被害を甘受せざるを得ない膠着状態は、従米主義の戦後自民党政権の限界によるものとすれば、政権交代で変わるかもしれない。こうして、2009年8月30日の総選挙で政権交代を果たした小(しょう)鳩山政権は、「最低でも県外」を掲げ、沖縄県内の期待は高まった。
しかしながら、小鳩山政権は、日米関係を優先する外務官僚・防衛官僚などに阻まれ、「抑止力に対する不勉強」を方便として、県外・国外移設を断念しただけでなく、10年6月に鳩山由紀夫首相は辞任に追い込まれた。こうしたトラウマから、その後の民主党政権では、辺野古移設問題はタブー化され、結局は、自民党政権時代の膠着状態に戻った。
さらに、12年12月の総選挙で政権再交代を果たした安倍晋三首相は、辺野古移設を加速化することになった。第2次安倍政権は、仲井眞弘多(なかいまひろかず)・沖縄県知事(当時)を説得し、13年12月に同知事が埋立承認をして、県内移設に大きく進みだした。
とはいえ、仲井眞知事の公約変更に対する沖縄県内の反発は強く、14年11月の同県知事選挙では、普天間基地閉鎖・撤去・県内移設阻止などを掲げた翁長雄志(おながたけし)・前那覇市長が当選した。このため、沖縄県当局は県内移設反対に舵を切った。こうした県民世論は、14年12月の総選挙でも示され、沖縄県内小選挙区で自民党候補は全員落選した。
にもかかわらず、「この道しかない」と考える政権は、「粛々」と移設関連作業を進め、翁長・沖縄県知事との面会も長期に拒絶していた。このため、沖縄県側は、前知事時代に行った埋立承認の法的瑕疵を調査し、取消をも視野に入れて、事態は泥沼化の様相を見せ始めた。
「この道しかない」なかでの作業停止

こうしたなか、15年8月4日に、菅義偉・官房長官が記者会見で、1か月間の作業停止と集中協議を表明した。すなわち、8月10日から9月9日までの1か月間、政権側は、辺野古沿岸部での海底ボーリング調査、米軍キャンプシュワブへの工事資材の搬入、埋立に向けた県との協議を中断する。沖縄県側も、上記の埋立承認取消に関する判断を留保する。その間、政権と沖縄県とで集中的協議を行う、というものである。
とはいえ、集中的協議とは、どのように何を行うのか、難しいものである。この間の水面下の調整をしていた安慶田(あげだ)光男・沖縄県副知事によれば、「最低1週間に1回」というイメージである。しかし、協議の形態を巡って、入口から紛糾することは、外交交渉でよくみられる。また、政権は集団的自衛権法案などで国会が多忙であり、協議できる時間があるのか、疑問である。
さらに、何を協議するのかが最大の問題である。政権側は辺野古移設以外の方策を考えておらず、辺野古移設という「なぜこの道しかない」のかを説明して、沖縄県側の理解を求めるということになる。「対米公約であり、他の方策はあり得ない」というのが、政権・外務官僚・防衛官僚の基本的スタンスである。しかし、結論が決まっている内容をいくら説明しても、「結論ありき」と受け取られ、説得力を持たないのは当然である。
単に「国は聞く耳を持っている」という世論アピールを狙うだけであるならば、かえって期待を持たせただけ、作業再開後の沖縄県側の反発は強くなりかねない。
「道がない」なら進行停止するのが自然
同じことは、沖縄県側にも言える。沖縄県側の結論も決まっており、「普天間基地閉鎖・撤去・県内移設阻止」ということである。「対県民公約であり、他の方策はあり得ない」というのが、沖縄県の基本的スタンスである。しかし、結論が決まっている内容をいくら国の為政者に説明しても、「結論ありき」と受け取られ、説得力を持たないのは当然である。このまま、1か月間の集中的協議をしても、出口に向かう道は、容易には見つからない。要は「道がない」のである。
「この道しかない」と進めば、結局、泥沼に至る。対米公約を果たして、冊封国としての辺野古移設という貢物を献上できても、国内(注1)的には大きな禍根を残す。沖縄県民の負担は右から左に移っただけで軽減されず、他方で、アメリカ政府からはそれほどには評価されない。「いつまで掛かっていたのか(Too late)」と言われるのがオチである。
注1 国の為政者が、沖縄県のことを、本心から「国内」と思っているかどうかは定かではないし、この疑念が沖縄県側と「日本政府」側との大きな隔たりになっている可能性もある。
泥沼の紛糾後、新国立競技場建設問題のように、最終段階になって中止に追い込まれれば、アメリカからは統治能力がないと呆れられ、普天間基地に横柄に居座る口実を与えるだけである。「この道」はどう進んでも碌なことはないのである。
そのようなときには、慌てて進まず、その場に停止するしかないであろう。もちろん、日米交渉を再開して、辺野古移設合意を白紙にすることを目指すしかない。当然ながら、統治能力のない日本政府に対して、アメリカ政府は呆れており、再交渉には応じないだろう。しかし、どの道、統治能力がないと覇権国に認識されるのであれば、無理して県内移設を強行する必要もない。所詮は超大国・戦勝国・占領国・覇権国のアメリカに、対等と認めて貰えることなどないのである。これが冷厳とした国際政治の現実である。
おわりに

辺野古移設が進まなければ、普天間基地が固定化される。しかし、辺野古移設が進めば、辺野古基地が固定化される。いや、むしろ、日本側が合意して提供したのだから、より一層固定度が高い。日本政府側・沖縄県側が、内ゲバまでして、苦労して進める案件ではない。本来ならば、他の基地と同様、単純に普天間基地の縮小・返還・閉鎖を要求する努力を進めるしかない。
辺野古移設の日米合意は、いわば、普天間縮小・返還・閉鎖への取組みを停止させる足枷である。しかし、条約でもない日米合意に、自治体が縛られる必要はないのである。
そして、この「不平等合意」を改正することこそ、日本政府が本来はなすべき外交交渉であろう。もちろん、アメリカ政府は呑まないだろうが、主張し続けることが、日本政府の役割なのである。国の専管業務である外交事務を忘却している国の為政者に、本来の役割を思い出させることも自治体の役割である。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)など。