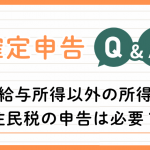新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第14回 国家戦略特区というミイラ
時事ニュース
2023.01.25
本記事は、月刊『ガバナンス』2014年5月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
はじめに

第2次安倍政権は、2014年3月28日に国家戦略特区諮問会議を開催し、東京圏、関西圏、新潟市、兵庫県養父市、福岡市、沖縄県の6地域を国家戦略特区に指定することを決定した。
国家戦略特区とは、13年の成長戦略国会で制定された国家戦略特区法に基づき指定するもので、地域限定で規制緩和を行い、「世界一ビジネスがしやすい環境」を目指すものである。いわゆる、強固な「岩盤規制」を打破するための「ドリル」という位置づけがされている。国家戦略特区では、国・自治体・企業で特区会議を設け、事業計画を立てて、14年夏には具体的な活動に入るという。
いわゆるアベノミクスは、①金融②財政③成長戦略の三本柱で、日本を「バック」させることを目指している。しかしながら、①はカネ余りによる株のバブルによる含み益は生まれたものの、産業空洞化により、思ったほど輸出が伸びていない。②は小泉構造改革路線によって土建業による公共事業の消化力が低下しており、単に資材・労働力不足に陥りつつある。そこで、③への期待がかかっている。そして、四半世紀の不況にあえぐ自治体としても、地域経済を活性化させたいため、それなりの関心を集めている。そこで、今回は国家戦略特区を考えてみたい。
地域指定方式
特定の地域に限定して、税財政・金融上の優遇措置を行うことは、政策手法として古くからあった。戦後復興期の特定地域開発はこのようなものであり、それが各地に拡散した。さらに、「史上最大の陳情合戦」と呼ばれた1960年代の「新産業都市」の指定も同様である。その後も、テクノポリスやらリゾートやら、様々な形で様々な地域指定がなされてきた。
特定の地域に限って選別的に指定されて優遇措置が行われるから、当然、自治体や地域はそうした「優遇」を求めて、水平的に競争することになる。国は、自治体・地域間を競わせて、国の意向を押し付けることができる。したがって、こうした地域指定方式は集権的な効果を持っている。ところが、自治体・地域間の陳情圧力があまりに強く噴出すると、国としても少数を選別して優遇することが困難になる。結果的には、多数の地域が指定され、その結果、財源は限られているから、「広く薄い」優遇措置になる。そのため、こうした地域指定方式は、期待された効果を挙げ得なくなる。
構造改革特区・総合特区・国家戦略特区

これに対して、特定の地域を限定して、法規制を緩和しようというのが、新手の特区方式である。「法の下の平等」という理屈から言えば、規制をするだけの必要があるならば、特定の地域だけで緩和することは、理に適わないとも言える。したがって、特区方式は、特定のまとまった地域(自治体の区域)に限定して、他の地域とは必ずしも性質が明確に異なるとは言えないにもかかわらず、特定の規制を緩和する点で、非常に興味深い手法なのである。
最も積極的に特区方式が取り組まれたのは、小泉政権下での構造改革特区である。これは規制緩和の手法であり、特定の地域に限定して実験的に規制緩和を行い、全国的な規制緩和につなげようというものであった。この点は特区指定を目指す自治体にとっては微妙なものがある。構造改革特区は自分のところだけが規制緩和をすることで、他地域と比べて有利になるのであれば、特区の規制緩和が全国展開されるのは困る。しかし、構造改革特区という考え方自体は、規制緩和の全国展開を狙っている。
ところが、景気低迷は続き、特に、リーマンショック以降はさらなる落ち込みが見られた。とはいえ、全国的に景気対策を打てる力もなく、地域限定の経済対策を目指すようになる。そのための手法として特区方式が注目された。その典型が、11年6月に制定された総合特区法に基づく総合特区である。これも新成長戦略と称するものの一環であり、地域からのオーダーメードによって、特定の地域にのみ、規制、税制、財政、金融の優遇措置をすることで、国際競争力の強化と地域活性化を目指そうとするものであった。
国家戦略特区は、総合特区と、地域選別的な経済成長戦略という意味では、同じである。しかし、自治体発という「分権」「地域主権」的な総合特区に比べて、「国家戦略」というその名の通り、「集権」「国家主権」的なものに180度転換している。国主導の特定の地域で経済改革をすることで産業競争力を向上させ、国際経済活動の拠点として形成しようというものであり、国として一部地域に限定しようという指向を持っている。国家戦略特区という「特権を国から付与」されることを望む「国策自治体」と、国家戦略として特定地域を依怙贔屓したい国との思惑が一致して、国家戦略特区が運用されることになる。
談合体制の地域限定的復権の試み

国家戦略特区ごとに、国家戦略特別区域会議(通称、国家戦略特区統合推進本部)が設置される。その構成員は、①特区担当大臣、②関係自治体の長、③首相が選定した民間事業者である。特区担当大臣と関係自治体の長は協議して、必要に応じて関係行政機関の長や「密接な関係を有する者」も加えることができる。特区会議では、①②③の全員合意によって、国家戦略特別区域計画を策定する。同計画は、関係大臣の同意を得て、必要に応じて国家戦略諮問会議の意見を求めて、首相の認定を受ける。こうして、規制の特例措置が得られることになる。
このように、国家戦略特区とは、①国と②自治体と③民間事業者の地域的な談合体制を、産業競争力向上と規制緩和に関して構築するものである。いわば、「政官業地」の四者間の利益複合体を、地域的に構築しようというものである。
もともと、戦後日本の政治経済体制は、政権党・官僚が業界利益または地元利益と結合する利益共同体を形成してきた。業界利益を確保する「政官業」の「鉄の三角形」と、地元利益を代弁する「政官地」の利益誘導政治とである。公共事業は、土建業の業界利益と、主として地方圏の地元利益とを、同時に満たすものであった。
こうした、戦後日本の政治経済体制は、バブル崩壊後の公共事業抑制や、小泉構造改革で、大いに傷ついた。そこで、「バック」を目指す第2次安倍政権としては、こうした談合体制を再構築しようとするのは自然な流れであろう。とはいえ、すでに公共事業の消化力を喪失している土建業界・地方圏を前提にすると、復興増税・消費増税による潤沢な国家資金を投下しても、単純な再構築は困難である。また、全国規模での談合体制の再構築もすぐにはできない。そこで、規制緩和という特権を軸とした地域限定の「政官業地」談合体制というミイラの蘇生を目指しているのである。
問われる自治体のスタンス
こうした戦略の成否は、いまのところ不明である。戦後体制の「政官業地」の四者利益複合体は、それ自体が産業競争力を生み出したというよりも、利益複合体の外の製造業などで生産された国富を、業界間・地域間・世代間で再分配するものであった。その意味では、産業競争力の原因ではなく、産業競争力の結果として、成立しえたものに過ぎず、1990年代以降の産業競争力の崩壊とともに崩れていった。その逆のメカニズムが作用するかどうかが鍵である。
政治における中央集権主義と経済における放任・市場主義と、比較的に中国のやり方をお手本とする第2次安倍政権ではあるが、改革開放期の中国の経済特区のように、功を奏するかは不明である。自治体としては、こうした国家戦略に「国策自治体」として付き合うのか、一線を引いて冷静に対応するのか、スタンスが問われるのであろう。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)など。