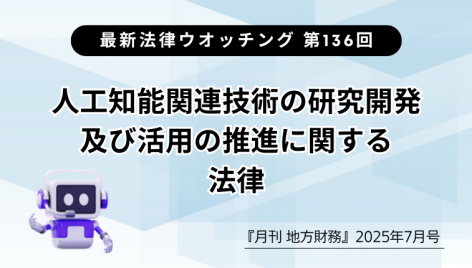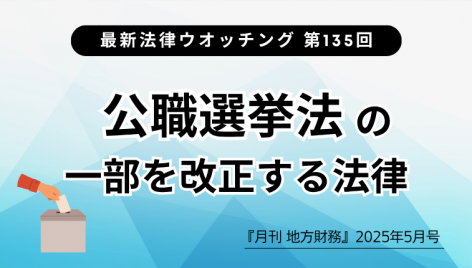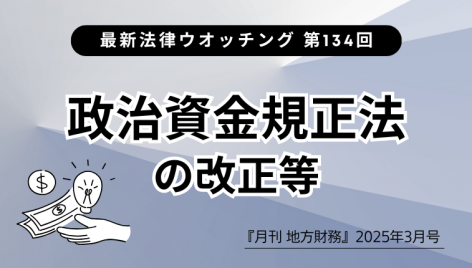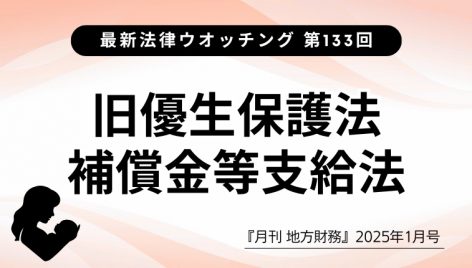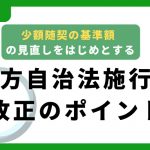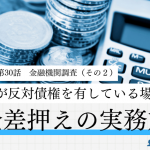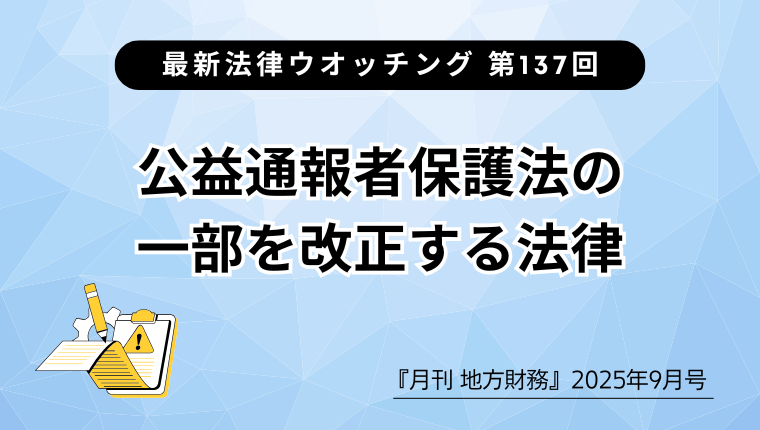
最新法律ウオッチング
公益通報者保護法の一部を改正する法律|最新法律ウオッチング
自治体法務
2025.10.06

この記事は4分くらいで読めます。

出典書籍:『月刊 地方財務』2025年9月号
★「最新法律ウオッチング」は「月刊 地方財務」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 地方財務 2025年9月号
特集:過疎対策のまがり角―計画見直しを見据えて
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,870 円(税込み)
詳細はこちら ≫
最新法律ウオッチング 第137回 公益通報者保護法の改正
※2025年8月時点の内容です。
2025年の通常国会において、公益通報者保護法の一部改正法が成立した。
公益通報者保護法は、2020年に公益通報者の範囲の拡大や保護の強化等のための改正が行われたが、その後も、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められていた。また、国際的な潮流として、公益通報者の保護の強化が進んでいる。
こうした状況を踏まえ、政府は、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲の拡大、公益通報を阻害する要因への対処、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要があるとして、改正法案を国会に提出し、成立した。
公益通報者保護法の改正
●事業者の体制整備の徹底等
公益通報対応業務従事者(公益通報を受け、事実の調査をし、是正に必要な措置をとる業務に従事する者)を定める義務に違反する事業者(常時使用する労働者数が300人超に限る)に対し、従来からの指導・助言、勧告権限に加え、勧告に従わない場合の命令権と命令違反時の刑事罰(30万円以下の罰金、法人等の両罰)を新設した。
また、この事業者に対する従来からの報告徴収権限に加え、立入検査権限を新設するとともに、報告懈怠・虚偽報告、検査拒否に対する刑事罰(30万円以下の罰金、法人等の両罰)を新設した。
さらに、事業者の体制整備義務の例示として、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示した。
●公益通報者の範囲拡大
働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にあるフリーランスと、業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスを追加し、公益通報を理由とする業務委託契約の解除、取引の数量の削減、取引の停止、報酬の減額その他不利益な取扱いを禁止した。
●公益通報を阻害する要因への対処
事業者が、労働者等に対し、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止し、これに違反してされた合意その他の法律行為を無効とした。
また、事業者が、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止した。
●不利益な取扱いの抑止・救済の強化
公益通報後1年以内(事業者が外部通報があったことを知って解雇や懲戒をした場合は、事業者が知った日から1年以内)にされた解雇や懲戒は、公益通報を理由としてされたものと推定する規定を設けることにより、民事訴訟上の立証責任を事業者に転換した。
また、公益通報をしたことを理由として解雇や懲戒をした者に対し、直罰(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、法人等の両罰)を新設し、法人に対する法定刑を3000万円以下の罰金とした。
さらに、公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員・地方公務員等に対する不利益な取扱いを禁止し、これに違反して分限免職や懲戒処分をした者に対し、直罰(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)を新設した。
●施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日(2025年6月11日)から1年6月以内の政令で定める日から施行される。
国会論議
国会では、通報妨害や通報者探索が許容される正当な理由について質問があり、政府からは、例えば、労働者に対し、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先に通報しないよう求めることや、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのかなどを特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、通報者の特定につながる事項を問うこと等があり得るとの説明がされた。
また、公益通報後1年以内の配置転換も立証責任の転換の対象とするとともに、公益通報を理由とする配置転換も罰則の対象とすべきとの指摘があり、政府からは、我が国ではメンバーシップ型雇用が一般的で、配置転換について事業者に広い裁量が認められており、労働法制で権利濫用であることの立証責任は労働者が負っていることを踏まえると、立証責任を事業者に転換することは困難であり、また、配置転換は、必ずしも不利益な取扱いとはいえず、その様態は様々であり、不利益性は個人の主観や事情に依存する部分が大きく、罰則の対象とすることは困難との説明がされた。
★「最新法律ウオッチング」は「月刊 地方財務」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 地方財務 2025年9月号
特集:過疎対策のまがり角―計画見直しを見据えて
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,870 円(税込み)
詳細はこちら ≫