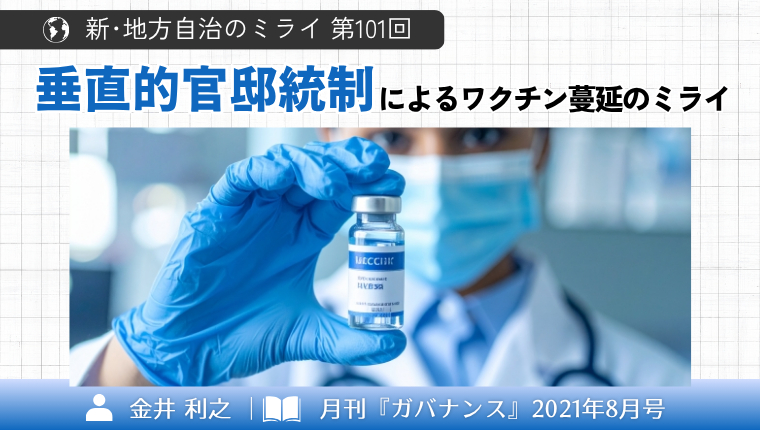
新・地方自治のミライ
垂直的官邸統制によるワクチン蔓延のミライ|新・地方自治のミライ 第101回
地方自治
2025.10.03

出典書籍:『月刊ガバナンス』2021年8月号
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
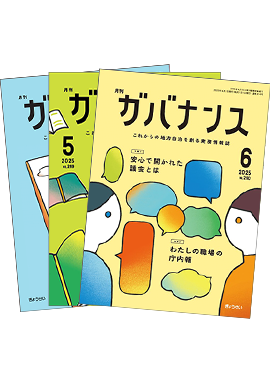
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2021年8月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

ワクチンは、COVID-19を脱却または忘却するための「ゲーム・チェンジャー」として、政治的・「科学」的に構築されつつある。
そのワクチンが「後進国」・日本にもようやくおこぼれ(トリクル・ダウン)する。そこで、菅義偉政権は、2021年5月になって、「1日100万回接種」「7月末までの高齢者へのワクチン接種完了」を打ち出した(注1)。官邸は明確にワクチン大作戦に舵を切った。ワクチン問題は、すでに6月号で触れたが、自治体にさらに与えた影響を論じてみよう。
注1 時事ドットコム2021年5月9日7時22分配信。
国の統制と自治体の競争

戦後自治体制は、〈垂直的行政統制と水平的政治競争の複合体〉である(注2)。各省官僚が自治体に対して行政ルートを通じて統制を及ぼすが、自治体側は様々な政治的競争を行うことで、垂直的行政統制を打破しうる。ただし、佐藤誠三郎が指摘したように、両者は論理的には、相互排他的ではない。自治体の水平的政治競争により、国は自治体を分割統治できる。21世紀に政治主導・内閣政治・官邸支配が強化され、〈垂直的官邸統制と水平的政治競争の構造〉に遷移した。このなかで、COVID-19は発生した。
注2 村松岐夫『地方自治』東京大学出版会、1988年。
垂直的官邸統制のもとで、自治体は官邸への忖度に基づき、寵愛競争を繰り広げる。しかし、2020年5月頃から様々なコロナ対策禍の閉塞に直面し、第2次安倍晋三政権は次第に主導性を失い、自治体は暴走を始めた。〈垂直的官邸統制と水平的政治競争の構造〉に順応した自治体は、忖度すべき存在がないと、自ら方向性を決める能力はない。
政権は、外出自粛とGoToの反復横跳び政策で、感染流行の「波乗り」をした。「政府」の英語版である「government」は、もともと「船の操舵」を淵源とする。従って、景気波動や感染流行への「波乗り」こそが、本来の為政なのかもしれない。しかし、〈垂直的官邸統制と水平的政治競争の構造〉は、垂直的統制指向であるため、「波乗り」対応は、リーダーシップの欠如であり、司令塔の不在であり、施策の失敗と受け取られてしまう。こうして、官邸、各大臣、官邸官僚・各省官僚、専門家集団(コロナさんぼうほんぶ)、自治体、医師会、五輪組織委員会などが、それぞれに独断専行の迷走をする。
ワクチン大作戦
2021年になってワクチン調達の目処が付いたことで、菅政権はワクチン接種推進(まんえん)による官邸統制回復に乗り出した。
ワクチン蔓延を掲げるならば、もっと早期からワクチン調達を実現しなければならなかったので、「遅い」「不手際」「段取りの悪さ」という批判は不可避である。
逆に、イスラエル・イギリスなどのワクチン「専心国」の「実証」結果を見て判断するという、「後発優位」の利点を主張する機会も失う。そもそも、日本は「さざ波」(注3)程度と認定すれば、ワクチン蔓延をするまでもなく、「波乗り」を仕切れたかもしれない。
注3 NHKデジタル版2021年5月24日17時49分配信。
ともあれ、官邸が断固としてワクチン蔓延という方針を決めてくれれば、〈垂直的官邸統制と水平的政治競争の構造〉にある自治体は対処しやすい。政権を忖度して、政権の寵愛を期待して、ワクチン蔓延に向けて「全集中」できる。つまり、それ以外は思考停止できる。忖度・寵愛自治体に求められるのは、接種を早期に蔓延させる意思と能力だけである。国が「1日100万人接種」や「7月末までに終わらせる」という号令を打ち出し、それに向けて「調査(あつりょく)」をかけてくれば、自治体は「できます」と回答し、また、数値目標に向けて、公平性とのバランスを欠いても邁進する(注4)。戦時日本の物動国家における「員数主義」であり、共産主義国家で蔓延した「ノルマ主義」である。要するに、配給統制経済である。
注4 このため、自治体発行の接種券によって制御されてきた医療従事者・高齢者・基礎疾患者という順位付けは崩壊し、誰でもよいから、接種券なしでもよいから、居住自治体とは無関係でよいから、できるだけ多くの人に接種すること自体が自己目的化した。その結果、どこで誰が接種しているかの把握に手間取り、「余剰」ワクチンの有無や「必要」ワクチン量の配給先も、6月後半から制御不能になった。
水平的政治競争の逆流

ワクチン蔓延という官邸の方針が固まり、国・自治体関係は「小康」を迎えたかに見えた。しかし、ワクチン蔓延加速化にこだわるあまり、官邸統制は過剰になっていく。
第1に、自治体を通じたワクチン蔓延だけでは1日の接種回数が増えないとして、自衛隊を徴用した国直轄接種や(注5)、企業・大学などの職域接種の回路を併設した(注6)。ワクチン配給の総量は決まっているので、結局はワクチン「不足」に陥って、各地で新規受付中止や予約キャンセルになる。
注5 菅義偉首相は岸信夫防衛相に4月27日に指示を出し、5月24日から東京と大阪にコロナワクチン大規模接種センターが開設された。NHKデジタル版政治マガジン2021年6月2日配信。
注6 政権は5月末には職域接種に向けて調整を進め、6月21日から本格的に開始された。産経新聞デジタル版2021年5月31日23時17分配信。時事ドットコムニュース2021年6月21日19時24分配信。
第2に、総量が机上で確保できたことは、現場に適切に配送できることを、必ずしも意味しない。しかし、政権の「作戦参謀」や一部マスコミ関係者たちは、「総量は確保できているはずなので、どこかに余っているはずだ」と、自治体や医療機関に責任転嫁する。いわゆる「目詰まり」論である。
しかし、そもそも、一定程度の「無駄」や「在庫」がない配送システムはあり得ない。また、無駄があってもそれは逐次、実践のなかで改善していくしかなく、調節にある程度の時間は掛かる。さらに言えば、配給体制が信用できない場合には、少なくともトラブルを避けるための「予備」を抱えようと努力し、あるいは、多めに配給を要請する。配給統制経済とは、そういうシステムなのである。
こうして、国からの配給が滞り、あるいは、自治体・医療機関の「在庫」や「目詰まり」への責任転嫁が生じるなかで、自治体から国への不満が逆流する。官邸がワクチン蔓延を指令したから、全力で忖度・寵愛競争したにもかかわらず、それに対応できない国に「梯子を外された」という不平不満である。水平的政治競争が垂直的行政統制を破壊し得るように、水平的政治競争が垂直的官邸統制を阻害する(注7)。
注7 なお、垂直的官邸統制と水平的政治競争との両立が、官邸や寵愛自治体の期待であろう。ワクチン不足を陳情した泉房穂・兵庫県明石市長に対して、西村康稔・経済再生担当相は、県か他の市町村に相談せよと回答して、自治体間の取り合いの問題に転嫁した。AERAdot2021年6月30日19時50分配信。また、吉村洋文・大阪府知事や1都3県知事は、7月2日に大都市部への優先配付を菅首相に陳情した。日本経済新聞デジタル版2021年7月3日0時40分配信。同2021年7月2日19時54分配信。自治体間で陳情競争または相互協調できれば、官邸に不満が逆流することはない。
ただし、これは自治体が自ら住民のために適切な政策判断をするという、第1次分権改革が目指した「分権型社会」ではない。20世紀後半の集権体制と相似である。単に、官邸の方針を丸呑みした「居直り」でしかない。また、時が経てば徐々にワクチンは(デルタ株に効きが悪いとしても)供給されるので、いずれ解消される不満である。
ワクチン統制経済の弊害
なりふり構わない政権の苛政(リーダーシップ)の結果として、様々なコロナ対策禍が生まれた。上記の「不足」問題は、実は供給が徐々に進めば解消され、ワクチン接種も希望者にはある程度は進むので、数か月の辛抱である。物資不足に起因する統制経済の問題を解消するには、大量の物量投入しかない。それよりも禍根を残したのは、以下の二つである。
第1に、行政として絶対に守らなければならない公平な配分という基準を崩壊させた。ワクチン接種希望者にとっては早期配分が重要であるが、総量が限られるならば公平な優先順位付けが不可欠である。しかし、接種回数・人数のノルマが肥大化し、順位付けはどこかに消し飛んだ。幸い、ワクチンは人々が血眼で争うほどの価値がなかったので、大混乱には至っていないが、行政のあり方として深刻な傷となった。
第2に、ワクチン蔓延が至上命題となったため、任意接種という大原則が失われ、ワクチン接種に向けた様々な圧力が発生した。政府の勧奨宣伝工作自体が、接種派には「錦の御旗」、忌避派には「踏み絵」として作用する。特に、職場・学校・医療介護現場のように、上下関係・集団関係が作用するときには、その同調圧力は大きい。蔓延率・蔓延速度や職域接種参加などで忖度・寵愛競争が作用するので、国からの自治体・事業者・学校への抑圧は、個々の住民・従業者・学生に抑圧移譲される。ワクチン・パスポートは同調圧力と差別を正当化する。こうして、ワクチン差別が深刻化する。
自治体は、行政の公平性を守り、ワクチン差別への対抗策を本来は採らなければならない。しかし、ミイラ化した現実の自治体は、公平性の崩壊に指をくわえ、自らも差別に加担して他地域から優先配分を受けようとし、各地で生じるワクチン差別への有効な対策を打てていない。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
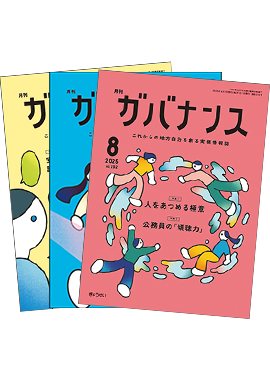
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫






















