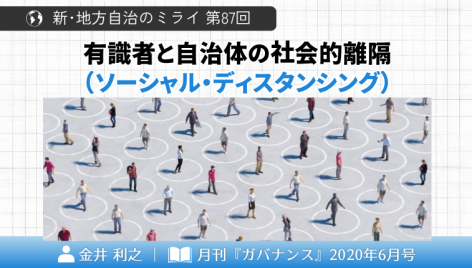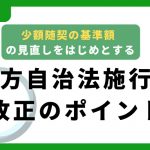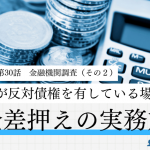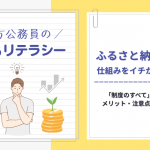新・地方自治のミライ
COVID-19緊急事態宣言のミライ|新・地方自治のミライ 第95回
地方自治
2025.08.18

出典書籍:『月刊ガバナンス』2021年2月号
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
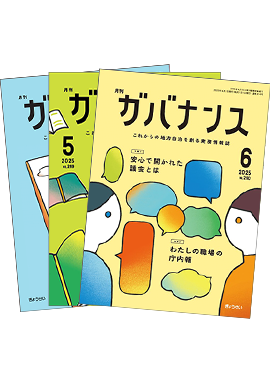
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2021年2月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

2011年3月11日から福島第一原子力発電所が苛酷事故を起こし、原子力災害対策特別措置法に基づき菅直人首相が原子力緊急事態宣言を発出した。同宣言が完全解除されていないなかで、COVID-19感染拡大第一波に関して、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)に基づき、第1次緊急事態宣言が2020年4月7日に発出された。一旦は全面解除となったが、秋以降の第三波の拡大が続いた。菅義偉首相は2021年1月7日に第2次緊急事態宣言を発出した(注1)。今回は、緊急事態宣言の炙り出す問題について、検討してみたい。
注1 2021年1月13日には7府県が追加された。
宣言発出の権限
当初、COVID-19緊急事態宣言では、官邸主導の国政が前のめりで発出するのではなかった。分権の観点からは重要である。
1都3県への発出は、2021年1月2日に、1都3県知事が要望したことが契機である(注2)。宣言発出の手続要件として、〈知事から首相への要請〉を加えることが、実態に即していよう。そもそも、首相が自治体と協議もせずに、一方的に宣言できる現行法制は、集権的で適切とは言えない(注3)。
注2 追加7府県のうち大阪府・京都府・兵庫県および愛知県・岐阜県・栃木県からも要請があった。
注3 要請のなかった福岡県も対象となったが、要請を行っていた熊本県は対象とならなかった。後手を批判されている国が自治体の要請に従うのではなく、独自に判断したことを演出するためとも考えられる。
区域限定の宣言ならば、当該区域の自治体に権限を授権すれば充分である。宣言の発出権限を、はじめから知事とする選択肢もあろう。しかし、知事に発出権限が付与された場合、宣言が濫発される恐れもあろう。首相と知事に相互了解を盛り込み、単独の意思では発出できないことが、適切かもしれない。
実際には、特措法と無関係に、首長は事実上の「緊急事態宣言」などを発出してきた。宣言に伴って、事実上とはいえ住民の行動変容を目指す以上、条例によって首長の権限を明確にしておくことも必要である。
特措法の緊急事態措置の限界

特措法は、①蔓延防止措置、②医療等提供体制確保措置、③国民生活経済安定措置を規定している。
ところが、特措法定の③の内容は貧弱である。一時的に市場経済が混乱したときの統制経済しか措置がない(注4)。統制経済が現実的には長続きするはずはない。つまり、特措法定の③では生活経済の安定を実現できない。
注4 災害救助法では現物給付を行うが、特措法は主に民間事業者任せである
実際、第1次緊急事態宣言時においても、各種の現金給付が不可欠であった(注5)。自粛経済では、市場経済が混乱して生活経済が成り立たないのではなく、民衆・事業者の資金不足が問題である。しかし、特措法は、現金給付を国・自治体の為政者に義務づけていない。
注5 「 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」(2020年4月7日閣議決定、同年4月20日変更)。
経済制限と義務・制裁化と現金給付
緊急事態措置の実効性を高めるために、義務づけ、過料・罰則、制裁的公表などが追加される動きがある。机上論の法治主義者は責任の所在の曖昧な要請を批判して、法的義務の明確化を支持するだろうが、実際には、自粛警察と密告に「錦の御旗」を与えるだけに終わる。
営業自粛を要請しても応じない理由は、経済生活のためである。就労第一社会では、生活保障を行政が支えることはなく、働く自助が前提になる。感染拡大防止という大義を示しても、休業・時間短縮には合利的な事業者は応じない。それゆえ、要請を実効的にするためには、要請に応じることが合利的であるよう現金給付をするしかない。例えば、第2次緊急事態宣言に伴う時間短縮要請に対しても、それに応じた事業者に月額180万円(日額6万円)の協力金給付を行うこととなった。
もっとも、飲食店への直接的な時間短縮要請に留まらず、①には、民衆の幅広い自粛経済が想定されている。市場経済は、多方面の網目状の相互取引と循環をしている。したがって、影響を受けるのは、直接的な制限対象事業者だけではない。経済循環を見込んで、現金給付を設計しなければならないが、その計算は至難である。
つまり、現行特措法定の③の統制経済は論外であるが、①と事実上の③を両立させようと、営業制限(自粛または規制)と現金給付をセットにするだけでは、充分とは言えない。結局、第1次緊急事態宣言のときと同様に、個々人と事業者に、営業・労働制限の状況とは無関係に、投網を掛ける幅広いセーフティネットを提供せざるを得ない。姑息の③である。但し、莫大な財源が必要だった。
感染拡大防止と生活保障の両立

机上の特措法では、①により②は可能になるし、その逆も成り立ち、法定の③が統制経済だけで済むならば、①②③は鼎立し得る。しかし、就労第一社会では、事実上の③とは経済活動の回復による稼得(=就労自立)であり、統制経済では足りない。これが「経済と感染拡大防止の両立」という政策目標となった。
経済活動の回復に依存する生活安定は、結局、人間の外出・往来・接触を拡大させ、①と矛盾する。①ができなければ必然的に②も破綻するので、政策目標としての①②③は鼎立しない。第2次緊急事態宣言の発出により、仮に①②が達成できたとしても、事実上の③が深刻な打撃を受けるのは必至である。
したがって、短期的には、姑息の③として、再び大規模な現金給付をせざるを得ない。しかし、それと同時に重要なことは、就労第一社会から脱却し、1年から2年程度は働かなくても国民生活が保障される経済体制の構築である。年金での所得保障がされている高齢者は①②に傾注できる。しかし、就労自立以外に所得保障がない中年・若者・苦学生などは、事実上の③のために、経済活動を再開せざるを得ない。
特別定額給付金を恒常化させる構想も、就労第一社会のままでは、就労へ狩り立てる必要が残る以上、現行福祉給付を切り下げるだけに終わる。自己積立と所得シェアとを組み合わせた厄災失職保険を整備し、働かないでも生活保障ができる社会にすべきである。統制経済と就労自立しかない現行の③を、規範上の③に組み替える必要がある。
自治体による生活保障体制
知事が緊急事態宣言に前向きで、国政が後ろ向きだったのは、自治体が②を主に担い、国が事実上の③を担っているからである。自治体は、病床・人員確保と保健当局による入院調整とを担うので、②の逼迫に脆弱である。法定の③はほぼ存在しない(注6)。それゆえ、①を通じた②を目指す。国は、逆に医療崩壊に直面しないので、観光・飲食事業者などに配慮する傾向が強い。そして、非正規労働者や生活困窮者の声を受け留める行政はほとんどない。
注6 現行特措法には存在しないともいえるが、②のために医療経済統制が強化される可能性はある。もっとも、自由診療制に固執する日本医師会(=開業医の利益集団)はそれに抵抗するだろう。治療や入院の優先順位を、自治体(保健当局)が判断・指示することは、入院調整の域を超える水準に入る。
知事を初めとする自治体が、①②③の政策目標をバランスよく衡量できるためには、第1に、自治体が③による全住民への生活保障の責任を負うことである。上記の厄災失職保険など、全世代所得保障が全国一律制度となるならば、自治体の政策偏向は避けられない。
第2に、①に依存しない②の構築である。COVID-19のような感染症は、ある程度の蔓延拡大は不可避であって、①がなくても②ができるように、医療供給を常備するしかない。欧洲諸国に比して、人口比病床数・医師数が多く患者数が少ない日本が医療崩壊に瀕していることは、医療管理を行う都道府県の失政と言わざるを得ない(注7)。
注7 日本医師会(=開業医の利益集団)が声高に①を主張するのは、②の強化のための(公立)病院への医療資源の集約を怖れているためであろう。
おわりに
COVID-19は、現代日本行政のミイラ化した体質を抉り出した。非難合戦によって第2次緊急事態宣言を発出させ、知事たちは国政への責任転嫁に当面は成功したが、早晩、②と事実上の③の破綻に直面する。しかも、国は、事実上の③として、旧来型のGoToに加えて、デジタル化とグリーン化による経済第一しか、思いつかない。結局、新たな就労がなければ、感染症蔓延を初めとする今後の厄災に対して、事実上の③は破綻し続ける。規範上の③として、自治体による生活保障体制の構築が必要である。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
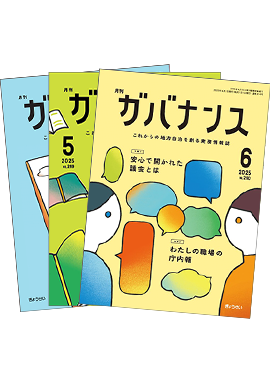
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫