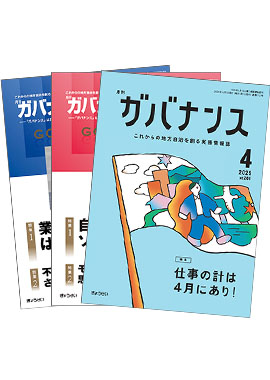自治体の防災マネジメント
被災者を支援する民(みん)の力 ~平成28年熊本地震と令和2年7月豪雨に学ぶ~|自治体の防災マネジメント[105]
地方自治
2025.07.09

出典書籍:『月刊ガバナンス』2024年12月号
★「自治体の防災マネジメント」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!
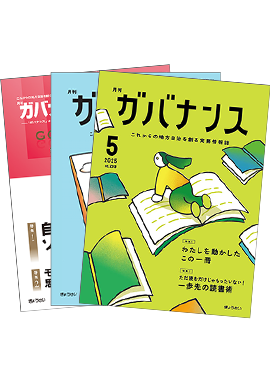
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
※写真はイメージであり、実際の土地とは関係ありません。
本記事は、『月刊ガバナンス』2024年12月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
ぼうさいこくたい2024
ぼうさいこくたいは防災活動を実践する多くの団体が一堂に会し、その取り組みや知見を発信し共有する日本最大級の防災イベントです。内閣府主催で2016年に始まり、今年は熊本で第9回が開催されました。さまざまなセッションや来場者が楽しく学べる体験型ワークショップ、屋外展示等を実施しています。
私は第1回から参加していますが、年々参加者が増え、内容も充実していると実感しています。今年は過去最高の約1万8000人の来場があったそうです。熊本県は、2016年4月の熊本地震と20年7月の豪雨で大きな被害を受けました。現在は復興の途上ではありますが、今年のぼうさいこくたいを機に一層の飛躍を期しています。
熊本県主催セッション
10月19日14時半~16時、「被災者を支援する民(みん)の力」をテーマに熊本県主催のセッションが行われました。地震と豪雨災害発生当時に「共助・自主避難所」「医療」「報道」「福祉」で活躍された4人のパネリストが登壇し、私が座長を務めました。本番前に、なんと木村敬熊本県知事に激励をいただきました(写真1)。
写真1

左から木村敬熊本県知事、吉村靜代さん、武田真一さん、石本淳也さん、皆吉秀太さん、筆者。(提供:熊本県)
初めに開催趣旨について、私から「近年の災害では地域住民はもとより、被災地外からライフライン企業、医療、福祉、ボランティアなど多くの民の力が活躍しています。今後の災害でも、間違いなく民の力が必要とされます。その望ましいあり方はどのようなものになるか、一緒に考えていきましょう」と話しました。
楽しい避難所生活
まず吉村靜代さん(NPO法人益城だいすきプロジェクト・きままに代表)から「主役はわたしたち~避難所からのコミュニティ形成~」と題して報告をいただきました。吉村さんは熊本地震で自宅が全壊し、中央小学校の避難所で4か月間、その後、仮設住宅で3年間を過ごしました。
「避難所の状況は昔も今も変わりません。まず、避難所の通路で区画を整理し、できるだけ日常に近い生活を送れるように心がけました。そうすると高齢者が元気になっていきます。行政やボランティアに頼ると、被災者が元気をなくすので、自主運営が大事。被災者の得意分野で動いてもらって、不審者を入れない工夫をする。できる人ができること、できたし(できた分だけ)でやっていきました」。驚いたことに「楽しい避難所生活だった」というのです。
「住民が仲良くなったので、仮設住宅も同じところに入って孤立化を予防しました。仮設住宅では内外の人と人がつながって、湖が見える広場づくり、みんなで集まる夏祭りなども、役所ではなく自分たちで企画し実施しました。熊本豪雨水害でも民間のボランティアセンターを立ち上げて支援活動を行い、被災者同士でつながりをつくりました」。
鳴りやまぬ心配の電話
次に話されたのは皆吉秀太さんです。今は医療法人社団の法人事務局長を務めておられますが、20年の豪雨災害当時は八代市坂本地区にある医院に介護福祉士として勤務し、施設長でした。「豪雨災害により医院等が被災したので、入院患者の搬送などを行いました。被災直後から医師その他スタッフとともに被災地での医療を提供しています。
大雨が降っていても『正常化の偏見』で甘く見ていました。停電しエレベーターが使えない中、医院の1階にいた17人を3人で3階に上げるのが大変でした。多くの知人から電話が来て、鳴りっぱなし。連絡することができないので、もう1台ケータイを持ったほうがいいです。患者を自衛隊ヘリで救急搬送する難しさや、少ない人数で残った患者の世話をするのが大変でした」。ほかにもたくさんの教訓を話していただきました。
ことばと情報で命を守る
3番目はフリーアナウンサーの武田真一さんです。2023年にNHKを退職され、現在、日本テレビ系「DayDay.」でMCを務めていらっしゃいます。
「1993年7月12日22時17分に発生した北海道南西沖地震では、5分後の22分に奥尻島に津波の第1波が到達しました。しかし、気象庁が大津波警報を出したのが22分、NHKが大津波警報を伝えたのが24分でした。間に合わなかった、という反省から、気象庁は現在、地震発生後2~3分で発表し、報道各社へも同時に配信できる体制になりました。
また、起きてしまった被害を伝える報道から、被害が起きないように伝える報道が重要だとしてアナウンサーの訓練を重ねました。その結果、有名な『東日本大震災を思い出してください。命を守るため、一刻も早く逃げてください…』という放送がされました。冷静に情報だけを伝えるインフォメーションにとどまらず、人々に行動を促すコミュニケーションに力点を置いています。また、備えることの大切さ、特に情報を理解することの大切さを伝えています」
最後に話された、熊本地震の際の、NHKスペシャルでの武田さんのことばが胸を打ちます。「熊本県は私のふるさとです…多くの方々が絶え間なく続く地震に脅えながら、また灯りのない夜を迎えることを思うと胸が締め付けられます。…不安だと思いますがこの夜を乗り越えましょう、この災害を乗り越えましょう」。
福祉コーディネーションの大切さ
最後は、熊本県介護福祉士会会長の石本淳也さんです。介護職・相談員・介護支援専門員などを経て、現在は熊本市内の社会福祉法人リデルライトホームの施設長を務められています。
「熊本地震でなかなか介護職の支援が来なかったので、当時はあまり使われていなかったSNSで呼びかけたところ、問い合わせが殺到し、SNSってすごいと思いました。
熊本地震をきっかけに介護福祉士の養成カリキュラムに災害支援が入り、良かったです。20年の豪雨時はコロナ禍で、県内でボランティアを集めなくてはならず苦慮しました。県内には福祉支援団体がDWATとDCATがあるので、得意分野で活動してもらいました。コーディネートした中には、弁当やホテルが用意されていないと怒って帰るなど、難しいボランティアもいました。避難所では、自宅では何とか自立していた方が、要支援、要介護になる事例が見られたので、医療や保健と同時に福祉関係者が入ることが重要です」。
熊本地震の時、福祉避難所を立ち上げましょう、と筆者から福祉関係者に呼びかけたことがあり、そこに石本さんも来られていたそうです。その時の様子が(写真2)です。
写真2

益城町社会福祉協議会会議室での福祉避難所打合せ。(提供:石巻包括ケアセンター所長 長純一先生撮影(2016年5月4日))
民の力を生かすために
この後パネルディスカッションも行いましたが、紙幅の関係で省略します。まとめとして、私が述べたいのは次の2点です。1点目は、被災者支援は民のほうが上手であること。例えば、役所の備蓄食料はアルファ米やビスケットなど主食に偏っていますが、民は「きっと野菜や肉が足りないだろう」と考えて炊き出しをします。もう1点は、支援したいと考える民の力を被災者支援に上手につなげる調整機能が重要だということです。
なお、本セッションはぼうさいこくたいHPでアーカイブが見られます。ぜひご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=nUVW_KwIxOQ&t=208s

著者プロフィール
跡見学園女子大学教授
鍵屋 一(かぎや・はじめ)
1956年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、東京・板橋区役所入区。法政大学大学院政治学専攻修士課程修了、京都大学博士(情報学)。防災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長、危機管理担当部長、議会事務局長などを歴任し、2015年4月から現職。災害時要援護者の避難支援に関する検討会委員、(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事、(一社)防災教育普及協会理事なども務める。著書に『図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ』(学陽書房、19年6月改訂)など。
★「自治体の防災マネジメント」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!
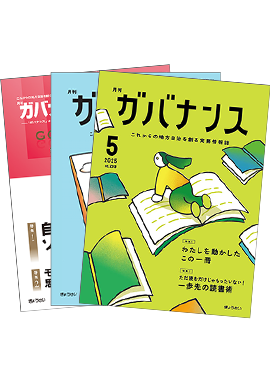
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫