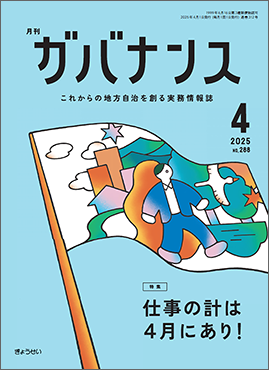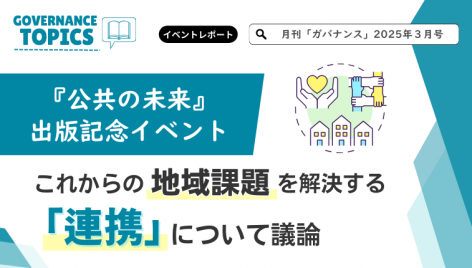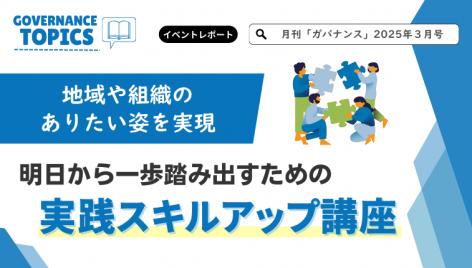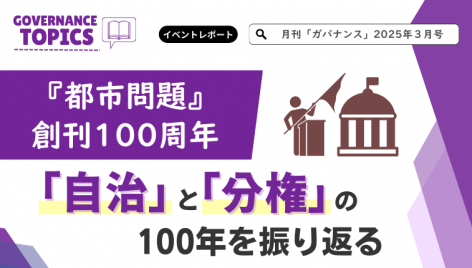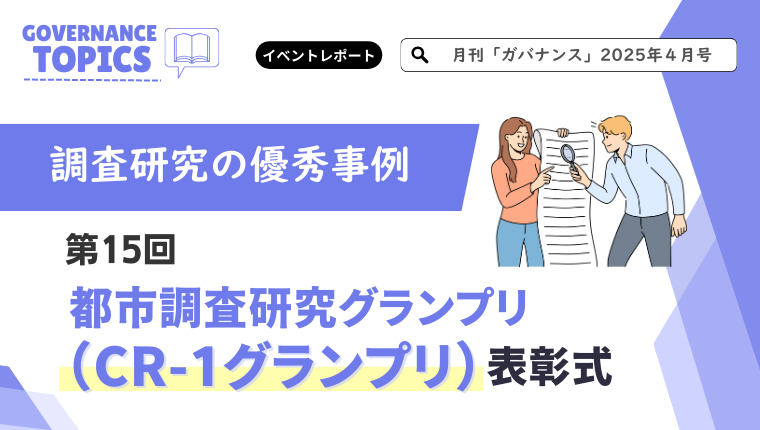
ガバナンスTOPICS【イベントレポート】
【調査研究の優秀事例】第15回都市調査研究グランプリ(CR-1グランプリ)表彰式/イベントレポート
地方自治
2025.04.25
(『月刊ガバナンス』2025年4月号)
【連載一覧はこちら】
【ガバナンス・トピックス】
地域の実情に即した調査研究を表彰
──第15回都市調査研究グランプリ(CR-1グランプリ)表彰式
(公財)日本都市センターは2月28日に第15回都市調査研究グランプリ(CR-1グランプリ)表彰式を都内で行った。全国の都市自治体や自治体職員による調査研究の優秀な事例を表彰した。

日頃の研究成果が評価。受賞者らは喜びとともに研究協力者らにも感謝を述べた。
具体的な施策につながる調査研究を評価
全国の都市自治体や職員が行った調査研究を募集し、優秀な事例を表彰する本グランプリは、2010年度から実施。今回で15回目を迎えました。

今回は過去最多の32件(政策基礎部門20件、政策応用部門7件、実務部門5件)が応募。(公財)日本都市センターによる第一次審査、そして第二次審査および最終審査は都市自治体の経営に関する学識経験者4人による審査委員会(座長/横道清孝・政策研究大学院大学名誉教授・客員教授)によって行われた。最終的に、最優秀賞1件、優秀賞2件、奨励賞2件が入賞作品として決定した。
横道座長は、全体講評として「いずれも地域の実情に即し、課題解決に向けた具体的な施策につながるもの。調査で得たエビデンスに基づき、丁寧かつ詳細な分析が試みられており、調査研究の水準向上と研究熱意を感じ取ることができる」と述べた。
5つの研究成果を表彰
最優秀賞
豊中市の子どもの学びと育ちに関する総合的な調査研究
(豊中市都市経営部とよなか都市創造研究所)
最優秀賞には、豊中市都市経営部 とよなか都市創造研究所による「豊中市の子どもの学びと育ちに関する総合的な調査研究」が選ばれた。
この研究は、「すべての子どもたちの可能性・チャンスの最大化」を目的に、同市が保有する子どもに関連する教育・福祉・保健分野などの複数部局にまたがる情報を収集・接合しながら、子どもの学びと育ちをめぐる格差の実態把握と、その克服に向けた調査研究を実施(2023年度~2025年度)。研究所がハブ的役割を担い、同市の保有する子どもに関する行政データを収集。行政データと独自アンケートを3年間にわたり個人単位・経年で接続し、パネルデータの構築・分析をした。
審査委員会による講評では、「子どもに関する多岐にわたる分野の膨大なデータを統合、データベースを作成しており、総合行政主体である都市自治体だからこそ可能な、部局を横断した画期的な取組みだ。独立したデータでは把握できない詳細な状況を、子どもパネルデータを作成することにより的確に把握し、モニタリングする仕組みが構築できている」と評価。同研究所の比嘉康則研究員は、「本調査研究は2025年度まで続く3年間のプロジェクト。今回の受賞は1年目の結果に対するもので、最終年度に向け内容をさらに深化・拡張していきたい」と、喜びと今後の抱負を語った。
優秀賞
コロナ禍における生活習慣と意識の変化に関する研究プロジェクト
((公財)荒川区自治総合研究所)
優秀賞には2団体が選ばれた。(公財)荒川区自治総合研究所の「コロナ禍における生活習慣と意識の変化に関する研究プロジェクト」(政策基礎部門)は、区民の生活習慣と意識がコロナ禍前後でどのように変化し、どのような影響を及ぼしたのかを調査、その影響により生じた区民の不幸や不安につながりかねない要素や今後の課題を明らかにすることを目的とした。
21、22年度に実施した荒川区民総幸福度(GAH)に関する区民アンケート調査を中心に、幸福実感度や、区政で重要視している「健康・福祉」、「子育て・教育」などの各指標の実感度の変化やその要因を区所管部署への聞き取りも交え分析し、求められる施策の方向性を提言した。
講評では、「幸福実感調査の弱点は回答者の主観性が強く反映されること。本調査研究ではGAHのみに依拠することなく、他の先行研究や調査結果を適切に参照している点も評価できる」とし、「コロナ禍で低下幅の大きかった指標については、コロナ禍から日常が回復することで指標が元に戻るのかどうか精査し、今後の政策提案に繋げてほしい」と付け加えた。
計量テキスト分析を用いた災害時における自治体産業保健対応マニュアル案の構築
(熊本市都市政策研究所)
もう一団体は、熊本市都市政策研究所による「計量テキスト分析を用いた災害時における自治体産業保健対応マニュアル案の構築」(実務部門)。2016年の熊本地震発災後、熊本市の産業保健部門は、明確な指針がないまま手探りで産業保健対応を行った。それらの対応を検証した上で、今後に生かせる大規模災害等発生時を想定した産業保健対応マニュアル熊本市版(案)を実際に作成することを目的として行われた研究。職員アンケートを実施し、災害時の熊本市役所内産業保健活動マニュアルに「災害発生時の産業保健対応ロードマップ」を作成、発災時の産業保健部門の対応指針として位置付けた。
講評では、「自治体の産業保健対応に関する調査研究自体が多いとは言えず、そこに着目し分析・課題把握・マニュアル作成まで繋げたことは学術的・実務的に意義深い」とされた。同市の産業医でもある藤井可併任研究員(医療主幹)は、「熊本地震の際、職員への産業保健活動を手探りで行った経験を体系的に考察し、今後の災害時の自治体産業保健に活かし、備えたいという産業医の気持ちが発端の研究。他自治体の災害時産業保健の参考になるのであれば幸いだ」とコメントした。
奨励賞
奨励賞には、主観的評価を重視する「ウェルビーイング」の概念を政策や行政計画に取り入れる意義や具体的な手法等について研究を行った(公財)福岡アジア都市研究所「ウェルビーイング(新たな都市の評価に関する研究Ⅱ)」(政策応用部門)と、自治体の政策で採用可能なナッジ案を提言した彩の国さいたま人づくり広域連合「ナッジ理論を活用した政策づくり」(政策基礎部門)が選ばれた。
各受賞者による研究内容の発表に続き、受賞者と横道座長も交えて、意見交換。受賞を喜ぶとともに、新たな研究の手法や視点を持ち帰った。

横道座長らも交え、研究について意見交換。研究過程での苦労話なども話された。
(本誌/浦谷 收)