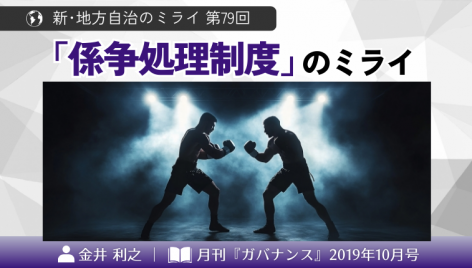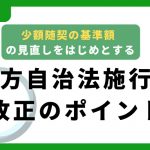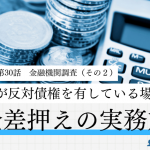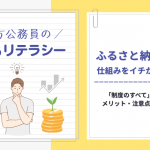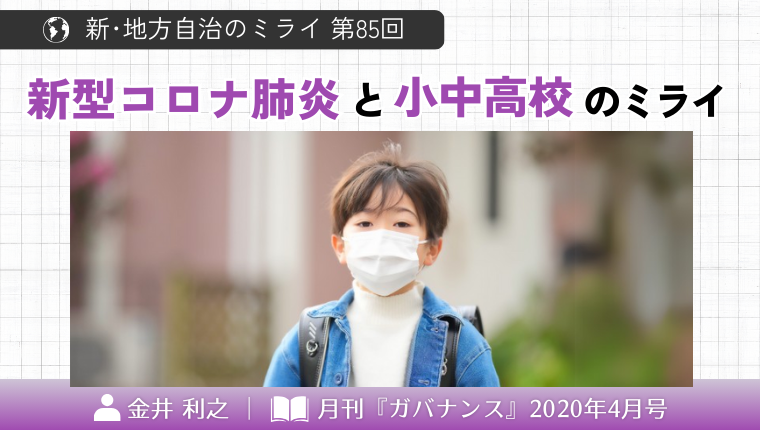
新・地方自治のミライ
新型コロナ肺炎と小中高校のミライ|新・地方自治のミライ 第85回
地方自治
2025.05.29

出典書籍:『月刊ガバナンス』2020年4月号
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
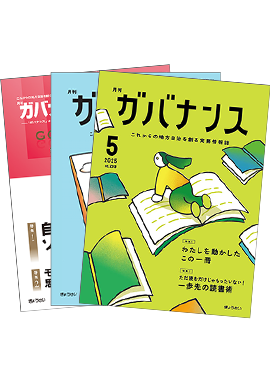
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2020年4月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに
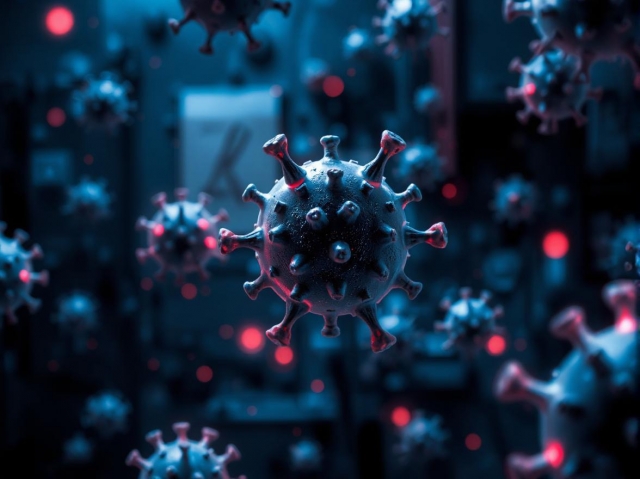
2019年12月頃より中国で発生した新型コロナ肺炎は、世界的大流行(パンデミック)となってしまった。もっとも、新型=「未知」ゆえの過剰反応かもしれない。逆に、予防原則からすれば、現時点ではやむを得ない対応かもしれない。しかし、「未知」の事態への対応として執った行動によって、様々な悪影響が現実化されることも懸念される。
安倍首相は2020年2月27日18時半頃に、新型コロナウイルス感染症対策本部会議の席上で、突如、3月2日からの全国一律の小中高校の一斉臨時休校を要請した(注1)。また、一斉要請がなくても、学級閉鎖・休校は、自治体の選択肢としては充分に有り得る(注2)。小中高校は基本的には公立だから、自治体にとって難しい問題である。
注1 毎日新聞デジタル版2020年2月28日20時01分配信。
注2 例えば、北海道は、道知事が2月25日に一斉休校の方針を示し、翌26日に北海道教育委員会が27日からの一斉休校を各市町村に要請した。TBS NEWS 2020年2月26日11時31分。また、千葉県市川市は2月28日から市立小中学校の一斉臨時休校を、27日に決定・公表した。時事ドットコムニュース2020年2月27日11時44分配信。市立幼稚園、放課後子ども教室、放課後保育クラブ、高齢者施設、集会施設、スポーツ施設、図書館・博物館、文化・観光施設、公園なども同様に休館・休園とした。保育園は「共働き家庭などの事情があり、現時点では休園を考えていない」とした。東京新聞ウェッブ版2020年2月28日付。
小中高校の不要不急性
感染を抑えるために、閉鎖空間・至近距離・一定時間以上に接するような機会を避けることが必要であると、2020年3月3日現在では考えられていた(注3)。その意味では、学校・教室はその一つである。もっとも、およそ世の中で閉鎖空間・至近距離・一定時間以上(・会話)の空間は沢山ある。全てを止めて自宅・自室待機になっては、社会生活は成り立たない。ライフラインは維持すべきである(注4)。会社・役所の活動も完全には止められない。結果として、感染症拡大は不要不急の活動をえぐりだす。
注3 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の見解」。その後、密閉空間・高密度・近距離会話の3要件と整理されている(3月19日段階)。
注4 感染症への抵抗力は衛生状態と栄養状態に規定されるならば、経済活動を維持することが最大の対策かもしれない。
小中高校の一斉休校とは、要するに、小中高校での教育活動は不要不急であるとした政策判断である。感染リスクは、初等中等就学齢に限られないから、高齢者などの集まる施設、例えば、老人病院(介護療養型医療施設)、老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービス施設などを休止・閉園にする必要があるかもしれない。しかし、これらの施設を閉鎖すれば、高齢者のケアをどう確保するのか、という大問題が発生しよう。それゆえに、高齢者ケア施設に閉鎖を一律に要請できない。
子ども世代であっても事情は同じである。そのため、保育所・幼稚園・学童保育などの閉鎖を、首相は要請しなかった。保育所・学童保育は、基本的には保護者が子どものケアをできないから、必要不断なのである。これらが閉鎖すれば、保護者がケアをするしかなく、保護者の社会活動が停止してしまう。幼稚園は、名目的には教育施設であるが、実態的には、保育所と同じく児童ケア施設である。
児童ケア施設としての学校

学校は教育施設であれば、少なくとも不急可断である。実際、学校には夏冬春季という長期休業が元々ある。その意味では、「一斉休校」も「春休みの前倒し」である(注5)。春休みが長くなるだけならば、大して問題はない、ように見えるかもしれない。しかし、こうした教育の建前が弊害を生むのである。
注5 チェルノブイリ原発事故のときには「夏休みの前倒し」の措置が執られた。東日本大震災・福島第一原発事故では災害によって学校どころでなくなった。
なぜならば、小中高校は実態としては、児童ケア施設の面を持っているからである。保育所・学童保育を閉鎖できないのと同じである。小学校を休校にした場合、特に低学年の場合には、結局、保護者が自宅でケアをするしかない(注6)。会社に子どもを連れて行けば、満員電車やオフィスで感染リスクに晒す。こうなれば、大人の社会生活に深刻な制約要因になる(注7)。
注6 なお、長期休業でも同じ問題があるはずなので、「前倒しの春休み」ならば、保護者は対応できるはずという見方もあろう。しかし、長期休業は予見可能性があるので、保護者としては対策を打っておくことができる。唐突な休校では対策が打てない。ごく短期であれば無理も利くだろうが、「前倒しの春休み」がいつまで続くかも予見できないので、保護者の対応の見通しが立たない。
注7 例えば、神奈川県鎌倉市役所は、3月3日から300人程度の職員が出勤できず、業務縮小を迫られた。
それゆえ、小学生でも学童保育で預かるしかない。ところが、学校は教育施設であるという建前のもと、広大な空き教室や建物があるにもかかわらず、学童保育の物的環境は狭隘である。また、教員定数は確保されているが、学童保育者は充分に確保されていない。結局、学童保育を、学校教室を利用し、学校教員の手を借りて、行うことになる。これならば、結局、学校を不断開校しているのと同じである。それゆえ、休校しないまま、自宅待機・不登校を奨励する方がよいかもしれない。
つまり、実態として、小中高校が児童ケア施設として機能してきたのである。むしろ、教育の建前のもとで、学校に長期休業があること自体が問題なのであろう。もちろん、児童ケア施設としての色彩は、中学・高校と年齢が上昇すると減っていく側面はあろう。とはいえ、エネルギーの余っている中高生を徘徊させると、「青少年健全育成」の観点から問題であるとして、学校に大量収容しているのであろう。
教育施設という建前の迷走

第1に、小中高校は教育施設としては、不急ではあるが、必要であるという建前を維持すると、厄介な問題が起きる。端的に言えば、長期休校でできなかった教科指導を、後で「取り戻す」という話にならざるを得ない。仮に休校期間が2週間であれば、その分を取り戻すだけで済む。しかし、感染蔓延の状況によって、休校はさらに延長されることとなった。そうなれば、しわ寄せは益々大きくなる。再開後の学校はさらに大きな負担を強いられる。
第2に、教育にこだわるのであれば、学校に登校させて集団的に教育するのではなく、「個別最適(みのたけ)」化として、自宅学習で代替する方向に行かざるを得ない。仕事でテレワークが推奨されるように、「宿題(homework=自宅仕事)」に切り替えることになろう。それは、(予備校のような)映像・動画授業かもしれないし、タブレット端末・学習用ソフトウェアによるICTを活用したデジタル教材かもしれない。実際、Soceiety5.0や「未来の教室」やGIGAスクール構想やEdTechとして、教育にデジタル技術を動員することは打ち出されており、中長期的には教育は脱施設化するだろう。
そもそも、教育・学習は学校だけで行われるのではなく、個人・家庭環境の影響が強い。しかし、自宅学習ができるのは、自宅学習できる家庭環境という文化資本が必須であり、その文化資本を個人が相続する限りである。それゆえ、自宅学習できる環境を整備するという児童ケア方策なくして、こうした「個別最適(みのたけ)」化は、普通教育の崩壊と教育格差の拡大を招く。教育へのこだわりが、結果として普通教育の破壊を招くのは皮肉である。
さらにいえば、教育・学習は、孤立した個人による自習や個別指導だけではなく、人間関係内の相互作用の自生的作用によるのであって、脱施設化=「個別最適(みのたけ)」化だけでは、教育機能を維持できないだろう。教師が教えなくても、子どもを集めるだけで、自然と教育・学習は進む(注8)。個別化は教育機能を弱める。
注8 例えば、教師が教科課程として授業しないでも、デジタルネイティブ世代は自然にデジタル技法を学習しているし、そもそも、平均的な教師のデジタル能力を凌駕していよう。
第3に、小中高校が教育施設ではなく児童ケア施設という観点からすれば、「個別最適(みのたけ)」化によって、教育機能が崩壊していくこと自体は、大した問題ではない。より重要なのは、教育施設の建前のもとで、実質的に実現している児童ケア機能が、脱施設化によって失われることである。小中高校の一斉休校で学童保育のニーズが高まったように、学校が教育にこだわればこだわるほど、本当に必要不断の機能としての、児童ケアが浮上するだろう。
おわりに
新型コロナ肺炎は、当面は、不要不急の活動を炙り出す圧力となる。それによって、慣習や日常で見過ごされてきた不要不急を整理する機会にはなる。学校での授業は、教育機能としてみれば不要不急の最たるものに見えたのだろう。逆に、児童ケア機能としては必要不断の活動であることを確認する機会になる。
同時に、「不要不急」の活動を、政治的または煽情的に狙い撃ちすることは、大きな副作用も生むだろう。例えば、観光・テーマパーク・イベント・飲み会などは「不要不急」の最たるものかもしれず、国外国内ともに大幅な落ち込みが起きている。確かに、学校教育も「不要不急」であろう。しかし、社会生活は、「不要不急」に見える活動の編み目で成り立っている。「非常事態」「瀬戸際」で「よく分からない敵との闘い」に「総動員」と称する方針は、結果的には、社会生活を抑圧し得る(注9)。自治体が「非常事態」や「自粛」を煽らず、冷静に「無用の用」を許容することも重要であろう。
注9 令和2年2月29日安倍内閣総理大臣記者会見。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
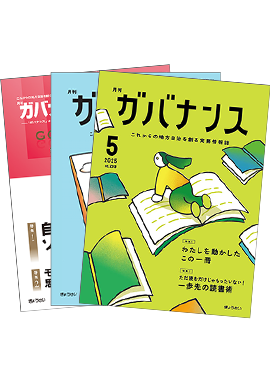
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫