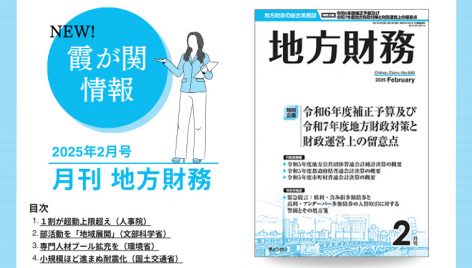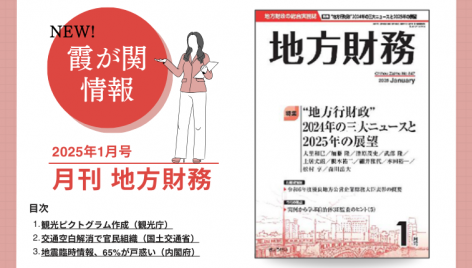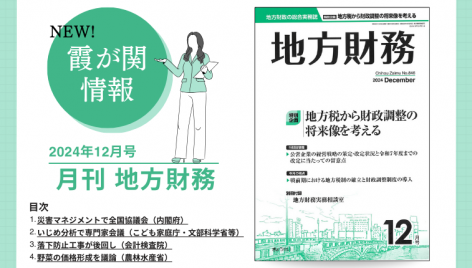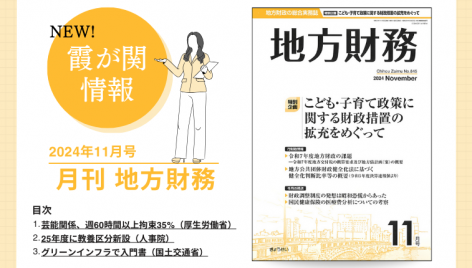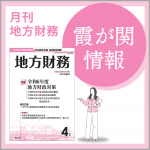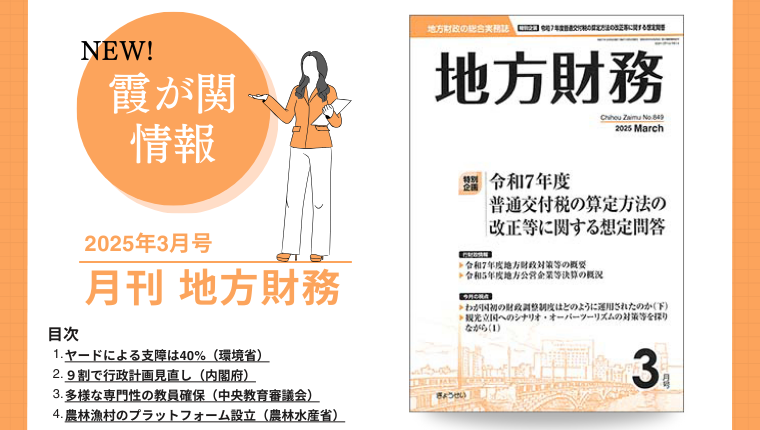
霞が関情報
霞が関情報「地方財務」2025年3月号(ぎょうせい)
時事ニュース
2025.04.02
※2025年2月時点の内容です。
霞が関情報
(『月刊 地方財務』2025年3月号)
ヤードによる支障は40%(環境省)
環境省は、金属くずや廃プラスチックを再生資源物として保管している場所である「ヤード」の実態調査結果をまとめた。それによると、ヤードは全国に3260か所設けられており、地域別では関東地方が2019か所で最も多かった。火災や土壌・地下水汚染、騒音・振動など生活環境保全上の支障が発生していると答えた自治体の割合は40%に上っている。
調査は、生活環境保全への影響を把握するのを目的に、47都道府県と20政令市、62中核市の計129団体を対象に実施。2023年10月から1年間の状況について、24年10~11月に聞いた。回答率は100%だった。
調査結果によると、管内のヤード設置状況を把握しているのが82団体。内訳は、都道府県41団体、政令市・中核市41団体だった。このうち36団体が、過去5年間ほどで管内のヤード数が「増加している」と答えた。考えられるヤード数の増加要因には「外国籍の事業者の進出」や「スクラップ価格の高騰」が多く挙がった。
ヤードの規制について、再生資源物の保管に関する条例を制定していると回答したのは12団体だった。
9割で行政計画見直し(内閣府)
内閣府は、法令などに基づいて自治体が作成する行政分野の計画について、事務負担軽減に関する見直しの状況(2024年)をまとめた。全498計画のうち、これまでに見直しを実施したのは約9割の451計画だった。内閣府は、一定の成果がみられるとしており、引き続き各省庁に取り組みを促していく。
見直しは、2023年3月の「計画策定等における地方分権改革の推進について~効率的・効果的な計画行政に向けたナビゲーション・ガイド~」の閣議決定に基づく対応。24年12月末時点の状況を調べた。
具体的な見直しの内容として
▽関連する他の計画と一体的な形での策定
▽「努力義務」から「できる」規定への変更
▽国の認定や国との協議の手続の撤廃
▽国が保有しているデータの提供や手引きの充実
──などが挙げられる。
自治体にとって、増加する計画に関する業務への対応に多大な労力を要している面があったため、必要最低限にすべきだとして取り組みを続けている。
多様な専門性の教員確保(中央教育審議会)
中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)は教員養成部会で、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について議論を始めた。企業に在籍しながら教師として勤務する場合の任用形態や、大学の学部段階で教職課程を履修しなかった社会人等が大学院で教員免許を取ることができる仕組みなどを検討する。
阿部俊子文部科学相が2024年12月に中央教育審議会に諮問したのを受けた。26年には答申をまとめる見込みだ。
公立の小中高校、特別支援学校の採用者数全体に占める民間企業などの勤務経験者の割合(22年度)は約4%程度にとどまっている。
こうした状況を踏まえ、中央教育審議会は同年12月、学校組織が多様な専門性や背景を持つ人材との関わりを常に持ち続け、人材を積極的に取り込んでいく重要性を示した答申を出した。
農林漁村のプラットフォーム設立(農林水産省)
農林水産省は、農山漁村での地方創生の機運醸成を目的とした「〝農山漁村〟経済・生活環境創生プラットフォーム」を設立した。地域と企業のマッチングなど関係者間の連携について議論を進める。テーマごとに専門部会を設けて検討し、夏前までに取りまとめを出す見通しだ。
プラットフォームには、関係省庁や自治体、企業、金融機関、教育機関などが参画。人口減少が深刻化する農村の活性化に向けた事業を後押しするため、官民のマッチングの在り方などを探る。農山漁村での「お困りごと」を、気軽に会員に相談できるような場として位置付けている。
具体的には
▽通いによる農林水産業への参画・コミュニティ維持(地元企業などとの連携)
▽農山漁村を支える官民の副業促進
▽市街地と農山漁村間の物流網の維持・確保(郵便局や物流事業者などとの連携)
▽外部企業との案件形成に向けた民間資金・人材の確保
の4テーマについて、専門部会で情報や意見の交換をする。