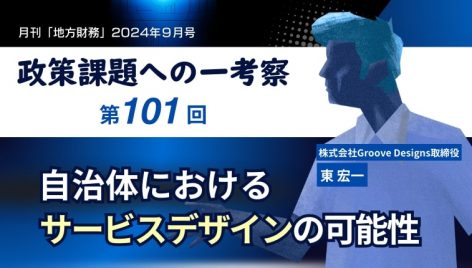新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第35回 「生涯活躍のまち」のミライ
時事ニュース
2023.08.24
本記事は、月刊『ガバナンス』2016年2月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
はじめに
2015年6月4日の日本創成会議・首都圏問題検討分科会『東京圏高齢化危機回避戦略 一都三県連携し、高齢化問題に対応せよ』については、本連載第28回「東京圏高齢化のミライ」(15年7月号)として採り上げたところである。
その前から「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(14年12月27日閣議決定)に基づき、日本版CCRC構想有識者会議(座長:増田寛也氏)が地方創生担当相のもとに設置され、15年2月25日には第1回会合が開催されている。同有識者会議は、6月1日の第5回会合で「日本版CCRC構想(素案)」を取りまとめた。7月22日には、「日本版CCRC構想に関する地方自治体との意見交換会」も開催されている。
8月25日の第8回会合には「『生涯活躍のまち』構想中間報告」となり、12月11日の第10回会合で「『生涯活躍のまち』構想最終報告」として取りまとめられた。そこで、今回は最終報告を検討することにしよう。
アメリカの「CCRC」と「生涯活躍のまち」の溝

有識者会議第1回資料1「日本版CCRC有識者検討会議の開催について」によれば、「日本版CCRC」とは、「希望する高齢者が健康時から移住し、自立した社会生活を営める」ものだそうである。そもそも「CCRC」とは、アメリカで見られる「continuing care retirement community」だそうで、「継続ケア付き高齢者共同体」などとも翻訳される。一般に、定年退職後等という意味で「リタイア」は理解されているから、「隠居」「老後」「残日」(注1)「シルバー」となる。
注1 藤沢周平『三屋清左衛門残日録』文春文庫、1992年。
しかし、そのような「引き籠り」観が満載では、為政者は元気が乏しく困るのであろう。「シルバー」のような「燻し銀」では「錆び」なので「活力あるというイメージ」がなくて困るということで、民間でも「プラチナ社会」などという用語もあるくらいである(注2)。
注2 三菱総合研究所(理事長:小宮山宏氏)「プラチナ構想」における「プラチナ社会」http://platinum.mri.co.jp/platinum-society/preface/index。2016年1月5日閲覧(2023年5月リンク切れ)。そのほか、楡周平『プラチナタウン』祥伝社、2008年。なお、この小説は2015年にテレビ化されている。楡周平『和僑』祥伝社、2015年は、「プラチナタウン」のその後を描く。
有識者会議及び政府は、若者・中年を海外の戦地でも「活躍」させるべく国会で議論している15年の真夏の最中に、老人にも「活躍」してもらうことを検討していたようで、「CCRC」は「生涯活躍のまち」と翻訳された。その後、女性の「活躍」=「shine」(注3)と合体され、15年10月には「一億総活躍社会」となった。
注3 「シネ」とローマ字読みしてはいけない。
「総活躍」の方向のなかでは、「リタイア」せずに「自立した社会生活」を営んでもらいたいということである。アメリカ版CCRCが持っていた「豊かな老後の生活」というイメージは、「生涯活躍のまち」からは「消滅」してしまった。
高齢者の地方移住希望?

最終報告によれば、「生涯活躍のまち」構想の意義は、高齢者の地方移住希望の実現にあるという。生産年齢世代を中心とすべき東京圏の「活躍障害」となっている高齢者を、東京圏から地方圏へ移住させるのが、日本版CCRCを議論し始めた契機なのである。「姥捨」て的な思惑が見え隠れするが、それが高齢者自身の「希望」として正当化されている(注4)。
注4 もっとも、単に東京圏から地方圏への老人移住では、「地方消滅」を促進して、地方圏の中枢的都市への「選択と集中」を進めることができない。したがって、僻地・辺地や限界集落から「まちなか」に移住することも、「生涯活躍のまち」にとっては必要である。そのため、最終報告では、「生涯活躍のまち」構想は、単に大都市圏からの地方圏への老人移住だけではなく、「東京圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地方や『まちなか』に移り住み、多世代と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医療・介護を受けることができるような地域づくり」とされた。とはいえ、東京圏からの地方圏への老人移住が、構想の大きな柱である。
しかし、最終報告で興味深いのは、むしろ、東京在住者の意向調査の結果である。実は、10代から30代では地方移住希望にほとんど性差はない。ところが、40代から男性が高く女性が低いという傾向が見られ、50代になるとその乖離は非常に大きくなる。男性の地方移住希望は50.8%であるのに対して、女性は34.2%である。そして、女性の地方移住希望は、10代から60代にかけて一貫して低下している。また、男性も60代になると、急速に地方移住希望は減少し、36.7%にまで下がり、女性60代(28.3%)との性差は減少する。
つまり、「高齢者の地方移住の希望実現」という最終報告の自己正当化に無理がある。実態は、「退役予備軍の男性中高年の希望実現」ということになる。
したがって、「生涯活躍のまち」構想が、本当に高齢者男女の希望を実現するのであれば、「熟年離婚のすゝめ」ということである。しかし、依然として老々家族介護に期待しているのであれば、「生涯活躍のまち」は困ったことになる。とはいえ、「生涯活躍のまち」でケアが継続されるのであれば、予め高齢夫婦を解体し、「生涯活躍のまち」に男性を「入営」する方が適切と為政者は考えているのかもしれない。
退役予備軍の男性の地方移住希望?

仮に地方移住希望を実現したいのであれば、本来、最終報告は50代男性について、キチンと分析すべきなのである。しかし、最終報告は、予め勝手に決めている高齢者の地方移住という為政者政策目的を、単に正当化したいだけのようである。したがって、こうした分析をすることは、為政者的には意味はない。しかし、敢えて最終報告のお題目の建前を額面通り受け取って、移住希望を実現することは有意味だろうか。
50代男性とは、均等法世代より若干上の世代であり、「女性活躍」には依然として抵抗のある世代である。企業勤務で定年を迎えることが──労働規制破壊によるリストラの横行のなかで実現できるかどうかはともかくとして──理想のキャリアイメージである。が、仮に実現したとしても、10年後の60代にはキャリア消滅が視界に入ってくる。
少し上の世代であれば、「関連会社出向」「天下り」による「再就職」という「理想の第二の人生キャリアイメージ」が存在したが、もはやそのような希望は抱けない。かといって、会社人間なので、地域に特にネットワークはない。今さら、地域デビューをするのは困難である。というか、企業で「活躍」した男性高齢者が地域で活動すると、地域の人々の「活躍障害」となりがちであり、地域からも望まれない。
中高年女性は、専業主婦・有職者を問わず、既婚者・未婚者を問わず、いわゆる「女縁」を持っている傾向が強いので、加齢による地域ネットワークの喪失の危機感は、中高年男性よりは乏しい(注5)。しかし、中高年男性は、会社から放り出されると、「社縁」は乏しくなる。
注5 上野千鶴子『「女縁」を生きた女たち』岩波学術文庫、2008年。
中高年男性には、加齢が脅威なのである。逆に、現に居住している東京圏に柵がないので、地方移住によって失われる地縁は少ない。女性の場合には、地方移住によって失われる縁が大きいため、当然ながら地方移住希望は、加齢とともに下がる。しかし、社縁が有期であることを自覚する中高年男性は、地方移住にかすかな希望を抱く。
もちろん、地方移住によって、中高年男性が新たな縁やキャリアを形成できるとは限らない。したがって、現実を直視するようになる60代となると、急速に地方移住希望は萎むのである。いわば、最終報告が拠り所とする中高年男性の地方移住希望は、単なる10年先が見えた世代の10年後の現実を直視しない幻想なのである。したがって、最終報告や政府が、こうした幻想を政策対象としないことは、妥当であろう。
おわりに
結局のところ、「生涯活躍のまち」とは、男性女性どの世代の真の希望とも無関係であり、単に為政者の希望の吐露である。日本創成会議や最終報告が心配しているのは、大量の高齢者が東京圏に滞留しつづけ、東京圏の「活躍障害」となることである。そのため、男性を中心とした退役高齢者を地方圏に移住させたいのであり(注6)、そのための収容施設の開拓が必要なのである。
注6 女性高齢者は「女縁」があるので、東京圏に滞留し続けても、それほど「活躍障害」にはならない。
しかし、単に収容されるだけでは費用がかさむ。そこで、「自立した社会生活」を宿営して「生涯活躍」(注7)してもらいたいわけである。「生涯活躍のまち」は、男性高齢者の入営者を中心に組織された、運営推進法人が管理する、近未来版「屯田兵」であろう。
注7 「生涯活躍」とは、「365日24時間死ぬまで働け」(とある企業『理念集』)ということである。
「生涯活躍のまち」を受け入れる自治体がどうなるか、また、入営した男性等高齢者がどのような宿営生活を送るのかを検討するには、先例を繙く必要があろう。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)など。