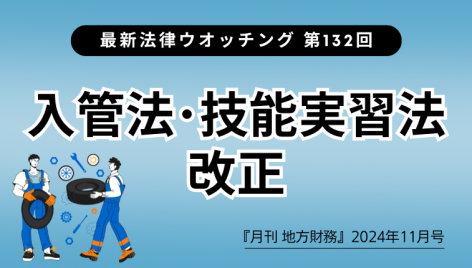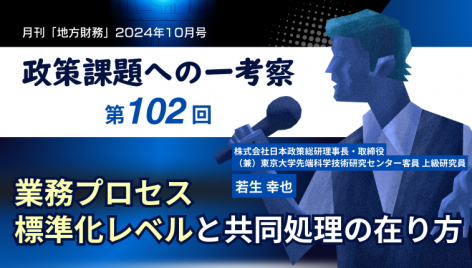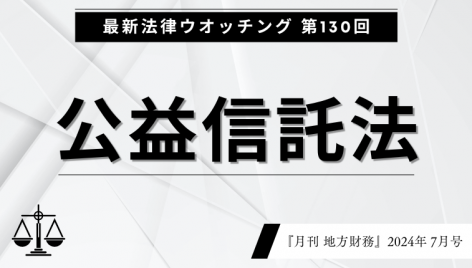新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第13回 水俣病認定業務のミライと自治体
時事ニュース
2023.01.17
本記事は、月刊『ガバナンス』2014年4月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
はじめに
水俣病が公式に確認されてから半世紀以上が過ぎているものの、依然として水俣病は解決していない。国・企業は水俣病の発生をなるべく認めようとせず、また、「認定」するとしても限定して運用しようとし、そのたびに、裁判が起こされて、行政側の「認定」が覆されるという事態が続いている。水俣病が自治体に投げかける問題は過去のものではない。
さらに、福島第一原子力発電所のレベル7事故が、晩発性の放射線障害を引き起こすことになると、国・自治体の行政の体質が変わらなければ、同じような遅延と闘争が繰り返されかねない。もちろん、予防原則から、敢えて帰還困難区域・居住制限区域指定などの「強権措置」を取ることで、被害発生を防ぐ努力をしてはいる。しかし、ミライとしては常に踏まえるべき課題である。
水俣病認定と訴訟

「公害健康被害の補償等に関する法律」(公健法)にもとづき、知事・政令指定都市長は公害健康被害認定審査会の意見を聞いて、認定処分を行う。知事等が行う水俣病の認定処分に対して不服のある者は、知事等に異議申立ができ、さらに、異議申立に対して知事等のした決定に対して不服のある者は、国の公害健康被害補償不服審査会(環境大臣の所轄)に審査請求ができる。しかし、納得の得られる「認定」がなされない場合には、訴訟が提起される。
認定申請者の死亡後に、「判断資料不足」を理由に棄却した熊本県の処分が違法であるとして、棄却処分の取消と認定処分を求める訴訟が、2001年に熊本地裁に提起された。最終的に最高裁まで争われ、13年4月16日最高裁判決で県側が敗訴した。そこで、熊本県は認定申請者を水俣病と「認定」した。
また、水俣病の認定基準が間違えているとして、熊本県が行った棄却処分および国の公害健康補償不服審査会の行った棄却裁決の取消と認定処分とを求める訴訟が、09年に大阪地裁に提起された。そして、13年4月16日に、最高裁は大阪高裁判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。実質的な熊本県側の敗訴である。そこで、県は同年5月7日に控訴を取り下げ、原告を水俣病と「認定」したのである。
最高裁判所の判決に行政が従って行動を改めるのは、当然である。熊本県の「認定」は極めて常識的である。さらに、国の公害健康被害補償不服審査会も、13年10月に、4月の上記最高裁判決に沿って、県の棄却処分を取り消して、「認定相当」と裁決した。熊本県は職権で「認定」を行った。
ところが、環境省は、裁決の拘束力はのちの処分には及ばない、個別事案であり参考事例に過ぎない、などとして、判決や裁決を軽んじる姿勢を示したのである。この点に関して、熊本県側は、13年12月には、水俣病の認定基準の在り方を検討している環境省に対して、納得のいく方針を示さない限り、認定業務の返上の覚悟で物を申していくとしたのである。最高裁判決を踏まえた認定基準を環境省が示さなければ、県は認定業務ができない。法定受託事務である以上、県は国(環境省)の基準に縛られる。しかし、その基準が最高裁判決を満たしていなければ、当然に裁判で覆される。裁判で覆されるような「違法」な処分を、法定受託事務として国の基準により強制されるのでは、責任ある仕事をやれない、ということである。
「違法」な処分を強制される自治体の対応策

熊本県側は国に、①公害健康被害補償不服審査会と環境省の間で異なる考え方を整理し、②最高裁判決を踏まえた認定基準を策定するとともに、③臨時水俣病認定審査会の再開を求めた。
①は、環境省の基準に従って「認定」したら、国の公害健康被害補償不服審査会で逆転裁決される、というのでは、県としては困るからである。要は、2人の「上司」から、矛盾する指示を出されては困るということである。統一した運用を欲するのは、「部下」としては、当然のように見える。しかし、こうした熊本県の発想はかなり疑問がある。なぜならば、個別処分に関しては、同不服審査会が「上司」であって、環境省は「上司」ではない。したがって、本来、県は環境省の基準に従う筋合いはない。最終決定者の判断を忖度して、中間決定者は行動すべきなのである。そもそも、環境省と同審査会が事前に摺り合わせをしては、独立した審査庁が存在する意味がない。
②は、法律に基づく行政の観点から言えば、極めてもっともな要望のようにみえる。基準作成者の環境省も、認定権者である県も、不服審査者である同不服審査会も、いずれも行政の一員だからである。しかし、分権社会の観点からは、このように、国(環境省)に基準策定を自治体の側から求めていくのは、適切ではなかった。むしろ、国(環境省)が策定する政省令・基準の規律密度を弱め、県が最高裁判決を踏まえた認定基準を策定できる余地を拡大することを求めるべきであった。
その理由は簡単である。分権とは、国が作る基準と自治体が作る基準が、どちらが国民・住民にとって適切な基準を作れるかというと、自治体が作る方が適切であると推定する「国のかたち」のイメージである。つまり、環境省に任せて、最高裁判決を踏まえた、被害者救済を適切にできる新基準ができないだろう、ということである。
③は、ある意味で、そうしたことを前提にした要望である。つまり、環境省には最高裁判決を踏まえた適切な新基準を作る能力はない、と県側は考えている。したがって、そのような新基準を法定受託事務として強制されるのは、県としては不本意である。ならば、裁判所で覆されるような「認定」をするのであれば、国が自ら直接に行うべきだ、というものである。一種の事務返上論である。「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」に基づき、県の公害健康被害認定審査会とは別個に、国に臨時水俣病認定審査会(臨水審)が設置され、認定審査業務を並行するのである。
なお、申請者本人の同意が必要である。これは当然であり、県に比べて、不適切な基準に従うかもしれない国の審査会に事案を移すのであるから、不利益を被るかもしれない申請者本人の同意が不可欠である。しかし、県よりも厳しい審査が予想される臨水審に応じる申請者は少ないのもまた、当然に予想されている。したがって、③の方策は、ほとんど問題の解決になっていない。
機関委任事務体制下のミイラ

環境省は、単独症状でも認定可能とする新指針を、14年3月7日に通知した。新指針は、従来の認定基準の「補足」とされる。当然ながら、環境省としては、新指針は最高裁判決を踏まえたもの、という立場である。しかし、被害者団体には、最高裁判決を踏まえたものではないという声もあり、今後も、対立が継続する懸念は消えていない。そして、臨水審に応じる申請者が少なければ、結局、県は国の新指針に沿った「認定」をすることになり、県としては不本意な行政不服審査や訴訟に直面し続けるかもしれない。
このような事態を避けるには、最高裁判決を踏まえて、自治体は自らが納得できる行政運用の基準を自ら作るしかない。それによって、結果として争訟が起きるとすれば、それは自ら対応すべきである。しかし、意に沿わない国の策定する基準に従い、意に沿わない「不認定」を行い、意に沿わない争訟を戦い、意に沿わない敗北裁決・判決を受けて、「認定」を職権で個別にする、というのは生産的とはいえない。これは法定受託事務であっても、「地域における事務」である以上、自治事務となんら違いはない。通達という基準を求めるという機関委任事務体制下のミイラがいまだに根強く存在しているのである。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)など。