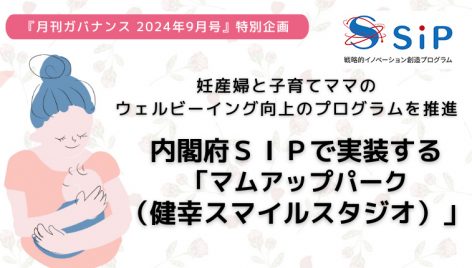新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第7回 子ども・子育て(支援)政策のミライ
時事ニュース
2022.11.30
本記事は、月刊『ガバナンス』2013年10月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
社会保障制度の持続可能性

2013年8月6日に、社会保障制度改革国民会議は報告書を取りまとめた。「確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋」という副題が示すように、報告書は社会保障制度の持続可能性に関心がある。そのため、社会保障4分野の一つとして、「少子化対策分野」が大きく取り上げられているのが、従来の社会保障制度の見方からの大きな転換である(報告書第2部Ⅰ)。そして、「子育て」を含む社会保障の多くが自治体を通じて国民に提供されていることから、報告書でも「国と地方が共同して支える社会保障制度改革」が謳われており(第1部3(7))、この報告書は自治体にとっても極めて重要な方向性を提案したものである。そこで、今回は、同報告書をもとに、自治体における子ども・子育て(支援)政策のミライを検討したい。
次世代への「負担の先送り」

報告書では、1990年の「1.57ショック」を受けて、子ども・子育て政策を1990年代から縷々行ってきたことは述べられている。しかし、それが充分に展開されていたとは言えない。もちろん、それがゆえに、少子化が進んだという性急な結論を出すつもりはない。しかし、事実として少子化には歯止めがかかっていない。そこで、報告書は、子ども・子育て政策への拡充を正当化するために、《子ども・子育て政策=少子化対策》という図式を提唱したと考えることができる。
裏返して言えば、子ども・子育て政策を、「子どものため」の政策であるという内在的観点では正当化ができなかったのである。子ども・子育て政策は、少子化に歯止めをかけ、社会保障の将来の担い手を作りだし、同時に経済成長にも寄与することによって、社会保障の持続可能性をもたらし、高齢者世代や現役世代にメリットがあるということで、正当化を試みる。要は、将来に負担をさせるために次世代を作るのだから、消費税増税による財源を子ども・子育て政策に回せるわけである。負担を次世代に転嫁するために、次世代を作ろうというのであるから、やはり、「負担の先送り」の一種なのであろう。現代日本に住む合利的な人々は、骨の髄まで「負担の先送り」的思考に縛られている。
報告書では、赤字国債に依存した社会保障制度は、次世代への負担の先送りであり、望ましくはないという判断に立っている。しかし、現時点で全世代を通じて社会保障が存立し得ても、少子高齢化の持続的進行を前提とすれば、将来時点、特に、団塊の世代が後期高齢者となる中長期的展望では、社会保障は存続し得ない。そのためには、次世代を増やしたいという気持ちになるのは、当然であろう。しかし、そのような合利的な提言は、合利的な人々によって自己崩壊しかねない。ミイラ取りはミイラになる。
合利性のしっぺ返し
合利的な現役世代は、自身の将来の社会保障の確保のために、次世代を育成したいという思いを持つだろう。これを、家レベルで行えば、家督を継がせ、隠居した自分たちの老後の扶養をさせるために、跡取りを作ろうという発想である。もちろん、跡取りも合利的であろうから、タダでは隠居の面倒は見ない。ということで、家督と扶養との取引となる。個人レベルでも同様に、老後の面倒を看てもらうために子育てをする、ということである。しかし、そもそも、法定の相続制度は扶養(生活監護)とは取引という制度になっていない。また、子ども世代も合利的である。したがって、子どもを育てたからといって、老後の面倒を看てもらえる保障は全くない。
個々の家や親・家庭での子育てと老後の面倒との取引が成立しないので、それを社会化(共同化)しようというのが、社会保障制度であるとも言えよう。しかし、この取引も、各世代の合利性を踏まえれば、魔法のようにはいかない。社会保障制度の将来の担い手にさせようとして次世代育成をしても、いざ、育成された次世代が、将来において担い手になる保障は全くない。むしろ、この段階で、さらに自助努力的発想を深め、社会保障制度を削減するかもしれないのである。というか、合利的な次世代は、将来の社会保障を止めるのが合利的である。
世代間の合利性からの解脱

実は、報告書も、「世代間の損得計算」を超えて、「全世代型の社会保障」を目指すことを提言している。なぜならば、世代間の合利性を前面に出す限り、様々な観点での再分配を内包する社会保障制度は、脆弱なものにならざるを得ない。それゆえにこそ、あえて損得勘定の合利性から解脱する必要があるはずである。しかし、報告書はその決断が仕切れず、《子ども・子育て政策=少子化対策=将来の社会保障の担い手育成による現役世代へのメリット》、という損得勘定(感情)にも訴えかけてしまった。これでは、社会保障制度の脆弱性は直せない。
報告書が目指す「全世代型の社会保障」を言うのであれば、子ども世代に対する社会保障サービスは、それ自体として保障されなければならない。高齢者世代に介護・医療などを保障するのは、それ自体として必要なことだからである。同様に、子ども世代に様々な保育・教育・医療・発達支援・保健などを保障するのは、それ自体として必要なことだからである。《社会保障=老人のためのサービス》、という「1970年代モデル」を超えて、《社会保障=全員のためのサービス》、という「2025年モデル」をもっと前面に打ち出すべきだったのであろう。
これは、実は社会保障制度の強靭性とつながる。しばしば、「真に必要な人に福祉を限定するべき」という重点化の議論はある。これは一見すると福祉を重視しているような装いを持つが、実は、福祉を切り下げる。というのは、《社会保障=貧困層のためのサービス》という「選別主義モデル」にしてしまい、階層間の損得勘定(感情)を喚起して、「負担」する側の富裕・中間階層の政治的抵抗を強化し、結果的に社会保障制度を脆弱なものにする。
強靭な社会保障のためには、《社会保障=全階層のためのサービス》という「普遍主義モデル」にする必要があった。同様に、世代別で見れば、強靭化のためには、《社会保障=全世代のためのサービス》という普遍性が必要なのである。
自治体現場での正当化
以上のような、社会保障制度の持続性あるいは強靭性は、国レベルで正当性を構築すればよい、という考えもあろう。しかし、現実はそうではない。国民を日々説得し、社会保障サービスの正当性を獲得し、強靭な社会保障制度を安定的に回転させて再生産するには、自治体現場レベルの正当化力が重要なのである。
自治体現場では、損得勘定(感情)に基づく苦情や通報が横行している。このようななかで、心ある合理的な職員といえども、日常業務で苦悩しつつ、膨大な業務に忙殺されて、サービスと職務に対する充分な正当化ができていない。自治体によっては、そのようなチクリを奨励するという、「地域主権」ぶりを発揮している。あるいは、民主党政権下での「子ども手当」や「高校無償化」にも、損得勘定に基づく様々な非難が寄せられ、結局のところ、合利的な国民には充分には受け入れられなかった。
こうした事態を乗り越えるためには、自治体現場レベルでも正当化力が必要である。自治体が取り組むべき子ども・子育て政策は、そうした強靭化への試金石になる。子育てを社会化・共同化・地域化することで、子ども世代に対する社会保障サービスを「保障」できるか、自治体の努力が試されているのである。これまでも、「エンゼルプラン」(1994年)「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」(2007年)など、子育て支援は提唱されながら、実態は伴っていなかった。こうしたミイラ化した子ども・子育て政策に、今度こそ、生気を吹き込めるか、大きな岐路に立っている。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)など。