
新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第1回 分権改革と政局
時事ニュース
2022.09.05
本記事は、月刊『ガバナンス』2013年4月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
アジェンダから消滅?

2012年12月の総選挙で、自民党は地滑り的大勝を収め、この10年来の友党である公明党とあわせて、特別多数を占める安定政権を作り出した。日本維新の会やみんなの党など「第三極」と連立を組む必要もなくなった。衆議院で再可決が可能な特別多数を占めたことで、実質的な「ねじれ国会」は解消された。そのような情勢であれば、参議院の野党勢力の切り崩し工作も容易である。
こうして成立した第2次安倍政権は、デフレ脱却と経済再生を優先事項に掲げて、「アベノミクス」と呼ばれる景気対策を矢継ぎ早に打ち出した。一定の市場の好感とともに、世論の理解も得て、順調な滑り出しを見せている。民主党政権が掲げた「地域主権」が否定されるのは当然としても、93年の国会決議以来の「地方分権」も、アジェンダから消滅したようである。「三位一体改革」時の政府与党合意(2005年11月30日)をまとめたときに、「分権改革に終わりはない」というフレーズを使い、第1次政権時には地方分権改革推進法を制定させて第3次分権改革(注1)を開始させた安倍氏であるが、少なくとも、現時点までは、地域主権戦略会議を廃止して地方分権推進本部を置いたくらいで、ほとんど「地方分権」を掲げることはない。では、第2次安倍政権では「分権改革」はどうなるのであろうか。
注1 筆者の独自の用語である。2006年から2011年ごろまでの動きを指す。
大いなる誤解

政権が、安定的な長期政権を築くことは分権改革に寄与するであろうか。省庁官僚制や与党族議員の抵抗が、分権改革を阻害しているという見方からすれば、政権すなわち首相官邸が強力な体制を構築すれば、分権改革が進展するように思われる。物事の実現には、意思と能力が必要である以上、分権改革への意思と、それを実現するだけの政治力が必要だと思われがちである。
しかし、そのような発想は、大いなる誤解と言ってよいだろう。
まず第1に、首相官邸と族議員とが対立しているという前提があるが、細かく見れば、そのような要素があるとしても、大局的には当てはまらない。族議員から構成される与党議員が、与党総裁を首相として指名して、内閣が構成されている。議院内閣制という憲法制度は、それなりに重いのである。自民党一党政権があまりに長く続いたため、首相官邸あるいは政府と、与党・族議員との対立が目立ったが、総じて言えば、内閣は与党に支えられているのである。政権と与党が内紛をすれば自滅するのは、民主党政権の末路を見れば明らかである。
第2に、強力な政権に、分権改革を推進する意思が本当にありうるのか、という疑問である。仮に、理念的に分権が望ましいとしても、政治は理念だけで動くものではない。政権は、自らの目指す政策を強力に進めようとすれば、権力を握って離さない。それどころか、独立機関にせよ、自治的主体にせよ、強力にコントロールを及ぼそうとする。現に、第2次安倍政権では、「アベノミクス」という金融緩和・インフレ政策のために、日本銀行の独立性は風前の灯である。政治家が人気取りのために中央銀行に金融緩和の圧力をかけて通貨価値が下落するという教科書通りの推移である。こうして考えれば、自治体に対しても集権的な態度で臨むのが自然である。
つまり、強力な政権が分権改革を掲げても、分権改革は進展しない。
では、その裏は……
強力な政権が分権改革を掲げない場合にはどうなるであろうか。当然、分権改革を掲げていないのであるから、分権改革は進展しない。弱体な政権が分権改革を掲げるとどうなるか。弱体な政権は官僚制の抵抗を排除できないので、分権改革はできない。弱体な政権が分権改革を掲げない場合はどうか。これは、そもそも、問題にならない。こうしてみると、政局的には、どのような場合であれ、基本的には分権改革は実現しないのである。
このような構造的な困難性を踏まえると、2000年の第1次分権改革は、針の穴に糸を通すように、奇跡的であったと言えるだろう。逆に言えば、このような奇跡的事実を当たり前のように感じて、その後も、さらなる分権改革が有り得るかのごとき蜃気楼を装ったのが、森喜朗政権以降の「分権改革」のアジェンダであったと言えよう。
分権改革では、法律制定のような国政政権の強力な政治力を必要とする。しかし、法律制定のような制度改革を要しないのであれば、自治体と国の事実上の力関係の問題となる。そうであるならば、制度運用によって分権方向に実態が動くかどうかは、自治体と国との政権を構成する勢力間のバランス・オブ・パワーによる。国と自治体の関係は、このようなゼロ・サム関係ではないという側面もあろうが、実態としては、ゼロ・サム的な力関係の側面もある。国が攻勢になれば、自治体は守勢になる。自治体が守勢になれば、国は攻勢になる。政局とはそういうものである。
守勢から攻勢へ、そして守勢へ?
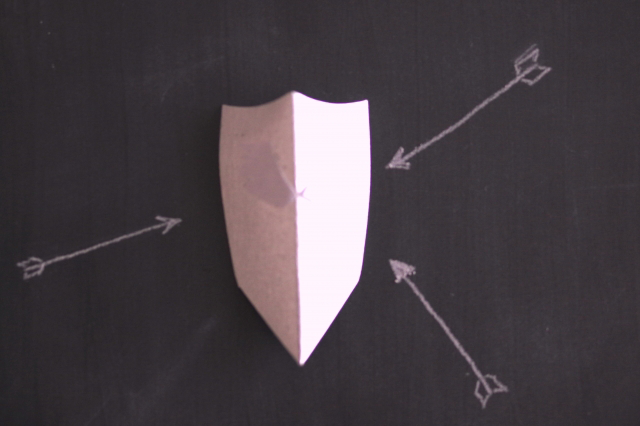
森政権は不人気のため弱体化の兆しが見えており、その意味で、分権的運用も展望し得る状態であった。しかし、その後、小泉政権に切り替わり、官邸主導の強力な政権運営に転換した。当然ながら、小泉政権は国民の支持を背景に、各種の既得権益集団に攻勢をかけた。その最大の標的となったのが郵政事業であるが、自治体も例外ではない。三位一体改革での地方財政削減や、平成の大合併の国策的推進により、自治体は徹底的に守勢に立たされた。自治体側は反転攻勢のために、分権改革の再始動を要請し、それを受けたのが第1次安倍政権である。
当初、安定・長期政権が見込まれた第1次安倍政権なので、政局的に言えば、分権改革を掲げたとしても、その結果は集権的なものになるはずであった。しかし、たまたま、07年の参議院選挙で敗北して退陣に追い込まれたため、額面通りの分権指向が残された。第1次安倍政権、小(しょう)福田政権(注2)、麻生政権、小(しょう)鳩山政権(注3)、菅政権、野田政権と、ほぼ1年しか持たない弱体政権が続いた。結果として、国は自治体に圧力をかけることが困難となり、自治体は攻勢に立ち、国は守勢に立った。
注2、3 福田赳夫政権や鳩山一郎政権と区別するために、「小」と命名している。
もちろん、自治体が攻勢に立ったとしても、自治体が国法制定をできるわけではないので、地方分権あるいは地域主権という制度改革が進展するわけではない。しかし、制度運用の面では、相当の自由度が許されることになる。それが政策面で発揮されればよかったのであるが、阿久根問題のような暴走現象として現れてしまい、自治体は好機を失ってしまった。それでも、「大阪都構想」を掲げる大阪府市の意向を忖度して、特別区移行法という法律が国政で制定されたのは、守勢に立つ国政の象徴であった。
しかし、状況は変わりつつある。第2次安倍政権が安定政権を構築すれば、一転して自治体は守勢に立たされることとなろう。参議院で与党が大勝すれば、さらに、その情況は強まる。自治体は厳しい時代に入り、まさに真価が試されよう。
*
第2次安倍政権の将来は不明である。しかし、仮に政権が強力であり続けるのであれば、分権的な制度改革も進展しないし、分権的な制度運用も困難である。ならば、自治体はその魂を守るために、必要に応じて長い眠りについて、時機の到来を待つ方策もあろう。いよいよ、自治体は「ミイラ化」への施術が必要な時期なのかもしれない。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)など。























