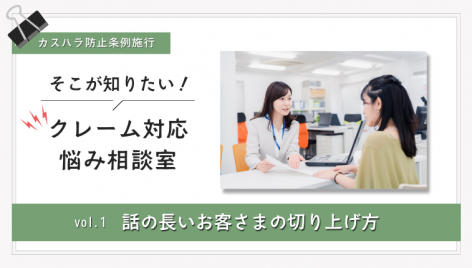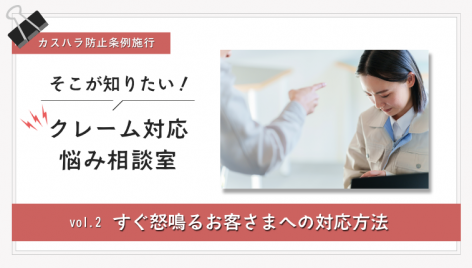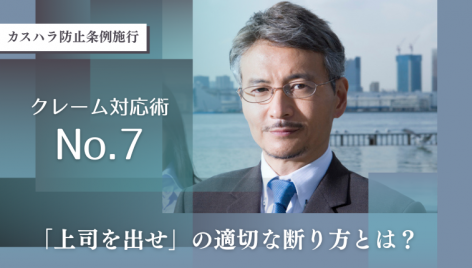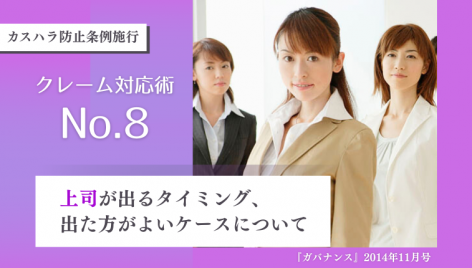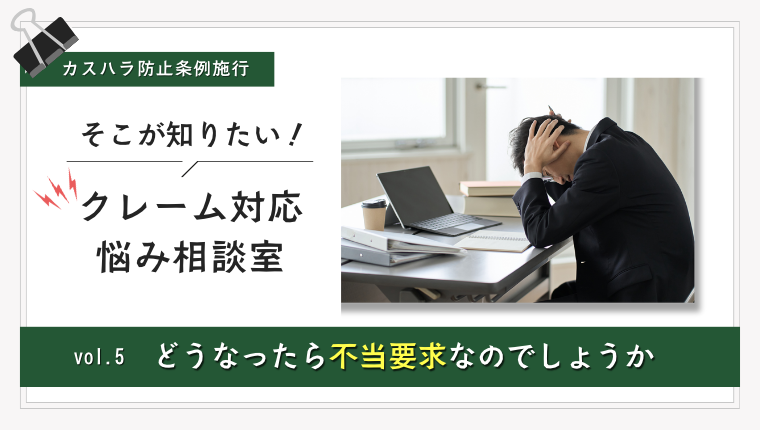
そこが知りたい!クレーム対応悩み相談室
【カスハラ対策】どうなったら“不当要求”なのか|クレーム対応悩み相談室5
キャリア
2025.05.09

この記事は5分くらいで読めます。

出典書籍:月刊「ガバナンス」創刊20周年記念別冊付録『そこが知りたい!クレーム対応悩み相談室』
※本書は月刊「ガバナンス」2019 年4月号〜2020 年4月号までに掲載した連載をまとめたものです(一部加筆・修正)。
Chapter5 どうなったら不当要求なのでしょうか
2025年4月1日、東京都などで「カスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例」が施行されました。
これにより、企業や自治体にも適切な対応策の整備が求められています。
本連載では、月刊『ガバナンス』の連載をまとめた別冊付録『そこが知りたい!クレーム対応悩み相談室』の内容を引用して掲載。
人材教育コンサルタントの関根健夫さんが自治体でのクレーム対応術を解説しています。
今回は不当要求の具体例と対応策ついて解説します。
カスハラ・クレーム対応の参考としてチェックしてください!
この記事で分かること
・お客さまが不当要求をする背景
・不当要求の具体例と対応策
前項に続きDさんの相談です。不当なことを言っただけで不当要求と言えないことはわかりましたが、実際にどうなったら不当要求なのでしょうか。

人材教育
コンサルタント
関根さん

① 不当要求の前に迷惑行為を意識する ② 迷惑行為には、やめてほしいことを繰り返し述べる
非常識な発言の「背景」
D 前回で、不当な要求をすることと、不当な手段をつかって要求することの違いが分かりました。
関根 解決策のないこと、非常識な言い分でも、要求しただけでは不当要求とはいえません。
D 私たち公務員は、相手方の言っていることがどのようなことであっても、まずはよく聞かないといけないのですね。
関根 非常識な言い分は、その背景にきっと何かあるのです。例えば、間違った情報や古い情報が通用すると思ってそのような発言になったり。また、人の常識は経験から作られますから、何か特異な経験があって思い込んでいるケースも考えられますね。
D そうかもしれませんね。
関根 ですから不当なことを言われたら、すぐに気分を害していやな顔をするのではなく、まずは聞いて“きっと何かあるのだろう”と考えてみることです。これが“寄り添う”とか“思いやる”ということなのではないでしょうか。
D でも、内容が正しくても、言い方が不当なら不当要求ですよね。
関根 例えば、机を叩くという行為は暴力行為です。原則的にはあってはならないことです。でも自分の思いが通じず、興奮して思わず机を叩いてしまったなどということがないとは言い切れませんよね。だから程度問題なのです。
D あまりにもひどい場合は、と前回うかがいました。具体的には、どういうことでしょうか。
関根 行為があまりにひどいかどうかは、状況によっても違います。例えば、相当な恐怖を感じるほどの状況とか、精神的に相当な圧力がかかった状態であれば、不当と言えます。判断するポイントは「やめてください」と言うことです。例えば机を叩かれたら、「机を叩くのはやめてください」と言ってください。相手が「悪かった。もうしない」と言うのなら、許してあげてもいいのではないでしょうか。しかし、こちらの制止を無視してやり続ければ、不当要求行為と判断できます。
不当要求の前の「迷惑行為」
D 不当要求は、犯罪ですよね。
関根 確かにそうですが、そうも言えない現実がありますね。
D どういうことですか。
関根 本人に悪気がないのにこちらがいきなり犯罪だと主張すると角が立ちます。私は、不当要求の手前に「迷惑行為」という概念があると思います。犯罪は理屈ですが、迷惑はこちらの気持ちです。実際に口には出しませんが、迷惑ですという気持ちで「やめてください」と言いましょう。
D 「迷惑です」とは言わないほうがいいのでしょうか。
関根 言ってもいいですが、多くのお客さまはこちらに迷惑をかける意図がないでしょうから、いきなり言わないほうがいいと思います。もちろん結果的には迷惑になっているのですから、あまりにひどい場合やすでに何度も警告を発しているのにその行為をやめていただけない場合は「迷惑です」「暴力です」「犯罪です」と言ってもかまいません。けれども、それは相当に険悪な状況になることを覚悟の上で、事務的な対応をするということでしょう。
D もっと、ひどい暴力だったらどうしますか。
関根 もちろん本当に殴られたり何かを壊されたりしたら「やめてください」というレベルではありません。すぐに職員が駆け寄って制止し、警察に通報するべきです。
D 脅迫行為の場合はどうですか。
関根 同じ考え方です。脅迫はこちらの判断で「それは脅迫です」と主張してもいいですが、発言がたった一言では悪質とは言い切れません。迷惑だという前提で「そのような発言はやめてください」と繰り返し、程度を越えたら「やめていただけないのであれば、これ以上対応できません」と言うことですね。
D 最近は、メールでそういう書き込みをされることもあります。
関根 基本は同じです。メールや手紙の場合は証拠が残りますから、第三者に迷惑行為を説明しやすいかもしれませんね。また、前回もお話しした、長く居座り続ける人も、こちらが正当な理由で「帰ってください」と言っているのに、正当な理由なく居続けたら、居座り行為、不退去です。こちらが迷惑だと思っていても「帰ってください」と言わずに、ニコニコ話を続けていてはそれを問えません。
D 正当な理由とは何ですか。
関根 基本的には、第三者が常識的に正当と判断できる理由であればいいのです。具体的には「すでに同じお話を5回、十分に聞きましたので……」とか「この後、○時から会議がありますので……」といった具体的な理由を述べましょう。「何かと忙しいので……」といったあいまいな言い方では理由として弱いし、相手方も感情的に不快な気分になるでしょう。
D なるほど、よく分かりました。
【関根先生の著書はこちら】
月刊『ガバナンス』で好評を博した連載「クレーム対応駆け込み寺」を加筆修正、再構成し単行本化
クレーム対応のさまざまな悩みを解決!
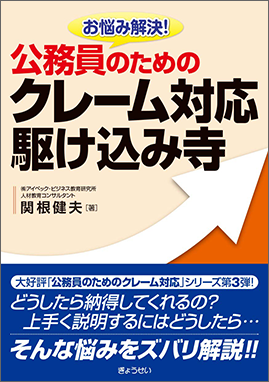
お悩み解決!
公務員のためのクレーム対応駆け込み寺 編著者名:関根健夫/著
販売価格:2,420 円(税込み)
試し読みはこちら ≫
【こちらもおすすめ】
カスハラをはじめとする不当要求行為等について、実際の事例から対応を学ぶ!

自治体職員のための
不当要求行為対応ブック
-事例からわかるトラブル回避策- 編著者名:宇都木法律事務所(代表弁護士 宇都木 寧)
販売価格:3,080 円(税込み)
試し読みはこちら ≫