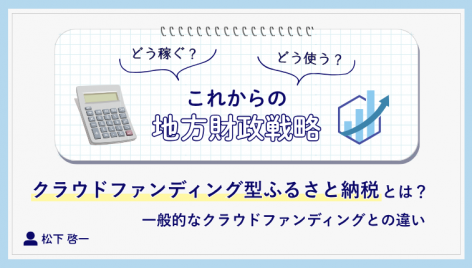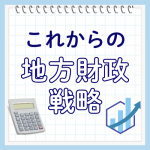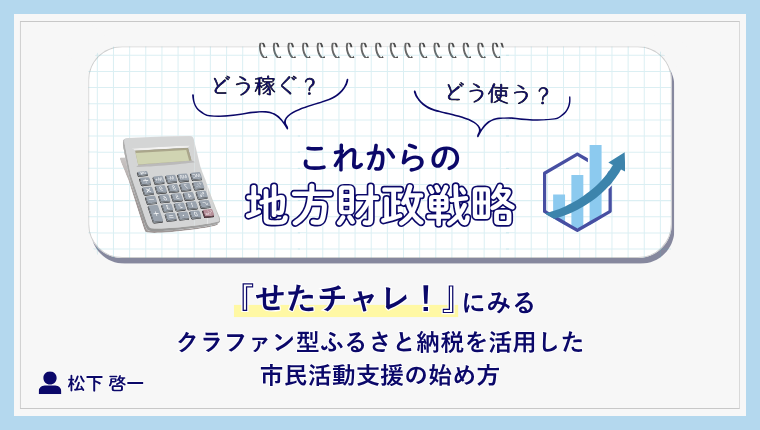
どう稼ぐ?どう使う?これからの地方財政戦略
せたチャレ!- クラファン型ふるさと納税を活用した市民活動支援の始め方|どう稼ぐ?どう使う?これからの地方財政戦略
地方自治
2025.10.28

出典書籍:月刊『地方財務』2025年10月号
★本記事は「月刊 地方財務」で連載中の内容の引用です。本誌はこちらからチェック!

月刊 地方財務 2025年10月号
特集:2026年度省庁別重点施策をよむ
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,870 円(税込み)
詳細はこちら ≫
どう稼ぐ?どう使う?これからの地方財政戦略
CF型ふるさと納税事業の最前線②―せたチャレ!にみる市民活動支援の始め方
松下啓一
最近の自治体では、ふるさと納税を組み込んだ新しい支援事業が試みられるようになった。
世田谷区は、これまで「提案型協働事業」として、地域活動団体等からの提案を受けて、その団体の専門性や先駆性を活かしながら、公共サービスの充実や地域の課題解決を図る市民活動支援事業を行っていた。しかし、その活動の原資となるのは自治体の予算であり、補助金額の上限や限定された補助期間等の制約から、大きなインパクトを残せる事業の実施・継続が難しいという課題を抱えていた。
この状況を改善するため、世田谷区は2025年度より「提案型協働事業」について、ふるさと納税を活用した市民活動支援事業である「せたがやクラファン!チャレンジ(以下「せたチャレ!」という)」として生まれ変わらせた。この事業は、市民からのふるさと納税(寄付)を活動の原資とすることから、寄付額に応じて補助を行うことができ、大きなインパクトが残せる事業展開も可能になる。また、クラウドファンディングを通して支援の輪を広げることで、団体が財源確保のノウハウを学ぶことができ、事業継続につなげることもできる。
スタートしたばかりということで、制度実施にあたって考えたこと、悩んだことも鮮明に記憶しているのではないか。また、市民からのふるさと納税(寄付)を活動の原資とすることから、従来の自治体のやり方とは違って戸惑ったこともあるのではないか。その苦労話や知恵を絞ったことを聞けば、後に続く自治体の参考になるのではないか。そんな趣旨から、この事業の担当である世田谷区市民活動推進課の伊藤課長に、この制度の開始にあたって考えたことなどを聞いた。
1 せたチャレ!
せたチャレ!とは
松下 こんにちは。よろしくお願いします。まずは、伊藤さんの自己紹介からお願いします。
伊藤 こんにちは、伊藤です。世田谷区には1992年に入庁し、2020年度より担当課長として、政策経営部(行革担当)、保育部を経て、2024年度より生活文化政策部市民活動推進長に着任しています。また、2016年ごろより、プライベートで区内の地域活動に関わり、一緒に活動しています。
松下 仕事とは別に地域活動を実践しているのですね。それでは、「せたチャレ!」の概要を紹介してください。
伊藤 団体や企業等が行う地域課題や社会的課題の解決を目的とした「課題解決事業」の提案を募集し、採択された事業について「ふるさと納税を活用したクラウドファンディング」の機会を提供する制度です。この機会を通じて、寄付者は共感する事業を指定して応援し、また団体は自主財源の確保策を身につけ事業規模を拡大し、世田谷区における新たな人材の交流や地域の活性化を目指すものです。
導入の経緯
松下 どうして、この制度を導入しようと考えたのでしょうか。
伊藤 10年ほど前に佐賀県が「佐賀未来創造基金」の設立とともに始めたこの種の取り組みを知っていました。墨田区や渋谷区でも同様に導入されている中、世田谷区でも機会があれば導入できないかと思っていました。
松下 協働提案事業はもう20年以上の歴史がありますが、課題も多いですね。
伊藤 世田谷区の「提案型協働事業」は、姿かたちを変えながら、NPOのスタートアップなどを目的として20年間続けてきた事業です。区との協働事業を行うためのインセンティブとして、最大50万円を最長4年間受け取ることができる補助事業でした。一方で、補助終了後に活動を継続している団体は少なく、50万円を前提とした計画が多いこともあって、大きなインパクトを出すのが難しいと感じていました。
松下 これは協働提案事業のあるあるですね。金の切れ目が事業の切れ目で、この制度が抱える大きな課題の1つです。
伊藤 そこで、より多くの資金を調達し長く活動を続けられるようになるには、クラウドファンディングが有効ではないかと考えました。さらに、ふるさと納税の仕組みが活用できれば、寄付者の負担は2000円となります。これは一般のクラウドファンディングと比べて非常に有利な条件で、公開審査を経ることで納得感も得られやすいと考えました。
松下 たしかに、ふるさと納税ならば、全国からの寄付も期待できますし、返礼品を取り入れると大きなインセンティブになりますね。
伊藤 世田谷区をより良くしたいという人々が応募し、それを応援する人々がつながることで支援の輪が広がり、資金調達力や活動の持続性が強化されるのではないか。そのような期待を込めて、「せたチャレ!」を導入することを提案しました。
2 制度設計で考えたこと
制度趣旨・対象事業の変化
松下 次に、制度設計にあたって、考えたことなどを伺いたいと思います。財源が予算からふるさと納税の寄付に変わることで、事業の性質や内容、手続きなどさまざまなところが変わりそうです。ふるさと納税の強みを活かそうと考えれば、協働提案事業の制度趣旨そのものも変化してきますね。
伊藤 大きな変化では、新設した「課題解決事業」は区所管課との協働を提案要件としていない点があげられます。しかし、地域課題・社会的課題の解決という目的に変化はありません。
松下 市民の寄付が活動の原資となることで、これまでの協働事業にはない事業もあがってきますね。
伊藤 「補助対象経費が100万円以上の事業であること」という要件を設けているため、より大きなインパクトを社会に残せるような事業提案が可能になりました。また、クラウドファンディングの実施から、より共感を得られるような事業があがってくると思います。
新たな団体が応募する可能性
松下 応募できる団体・事業の推進主体も、これまでのところとは違う団体が声を上げる可能性がありますね。
伊藤 新設した「課題解決事業」では必ずしも区所管課との協働は求めていません。そのため、より自由な発想を持った団体からの応募が考えられます。また、募集にあたっては「企業」や区内において計画的かつ継続的に活動している「区外事業者」も応募の対象にしており、さまざまな団体が応募可能です。
松下 ずいぶんと違いますね。
経費の範囲・広報・PRの変化
松下 募集要項をみると、今回の補助金では、これまで使えなかった用途にも、使えるようになっていますね。これも市民の寄付が原資ということが影響しているのですか。
伊藤 クラウドファンディングで、団体自らが集めた資金という側面が強いため、これまでよりも使える範囲が広がっています。
松下 市民の寄付を意識すると、広報やPRの内容、方法もこれまでの協働事業とは大きく変わりますね。いわば内輪のPRから、開放的・積極的なPRといった変化です。
伊藤 昨年度までは、50万円の補助金額が決まっていたため、各事業の活動を成果報告会で発表するにとどまっていました。ただ、今年度はクラウドファンディングで活動資金を獲得するため、より積極的なPRが必要になります。そのため、事業の魅力を発信するPRイベントを企画しています。この場を通して、より多くの方に各事業の存在を知っていただき、団体への支援へつながるような機会を提供します。
予定どおりの寄付が集まらなかったとき
松下 クラウドファンディング型なので、予定どおりの寄付が集まらないというケースも考えられます。その場合は、どうなりますか。
伊藤 その場合は、不足分を団体の自己資金で補う、または事業の規模を縮小することで、必ず実施していただきます。寄付が集まらなかった場合への対応については、事業の選定における評価項目の1つになります。
寄付金の歳入・歳出
松下 財務処理も違ってきますね。歳入予算としては、どのように処理するのですか。
伊藤 寄付金はすべて基金に入ります。年度末までの団体補助金額に対して基金より繰入処理(充当)を行います。
松下 では、歳出の処理はどうでしょうか。
伊藤 当初予算である程度の団体補助金額を計上しています。寄付確定額にあわせて団体へ補助します。
松下 寄付が思いのほか集まって、団体への補助金額の合計が当初予算額を超えた場合、反対に集まらなかった場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。
伊藤 各事業の獲得寄付金額の合計が当初予算を超える場合は、補正予算を組んで対応します。逆に集まらなかった場合は、執行残になります。
新たな事務負担・財政負担
松下 新しい事業なので、新しく生まれる事務負担もあるでしょう。どんな事務が増えてきますか。
伊藤 新たに実施するPRイベントへの対応やGCF®に関する事務などがあります。
松下 この事務の増加に対して、どのように対応していますか。
伊藤 選定事務やPRイベントに関して、運営補助委託を行いました。
松下 委託費用など、新たな経費も出てきますね。ただ計画通りにいけば、事業費用は寄付で賄えることになるのでしょうか。
伊藤 新たな経費として、運営補助委託にかかる経費があげられますが、昨年度まで外郭団体の中間支援組織に対して運営支援のため補助金を支出しており、今回の委託経費はその金額以下で抑えることができました。また、補助事業がクラウドファンディングを実施した際に、一定の金額を超える部分については、事務手数料として基金への歳入になります。その結果次第では、補助事業へ支出する定額補助額を賄える可能性もあります。なお、運営補助委託は一般財源で対応しています。
3 自治体として特に心すること
★本記事は「月刊 地方財務」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 地方財務 2025年10月号
特集:2026年度省庁別重点施策をよむ
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,870 円(税込み)
詳細はこちら ≫