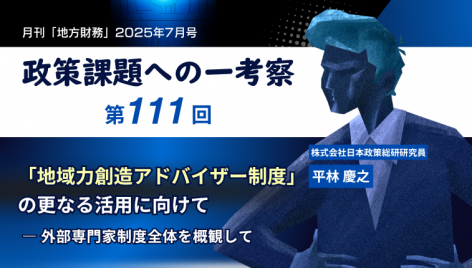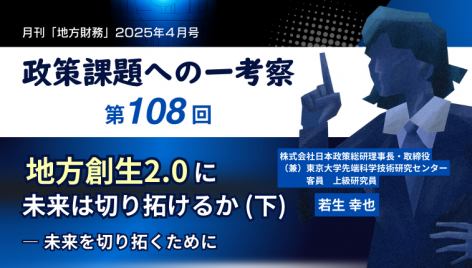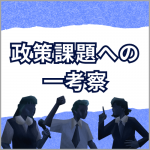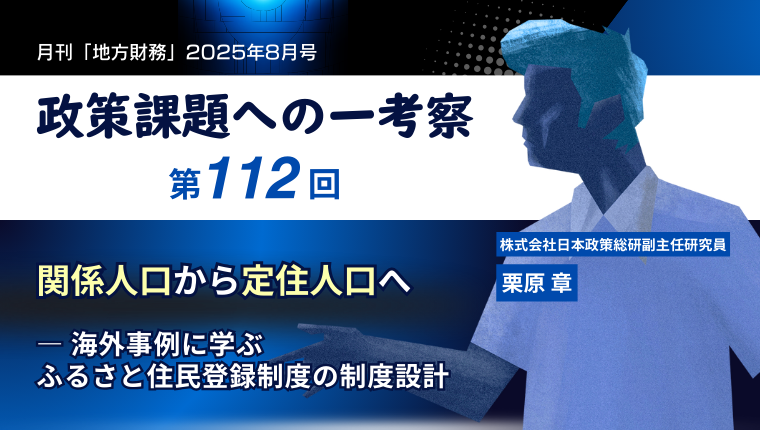
政策課題への一考察
関係人口から定住人口へ ― 海外事例に学ぶふるさと住民登録制度の制度設計|政策課題への一考察 第112回
地方自治
2025.09.10

出典書籍:『月刊 地方財務』2025年8月号
★「政策課題への一考察」は「月刊 地方財務」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 地方財務 2025年8月号
特別企画:「骨太の方針2025」と地方創生・地方行財政
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:3,960 円(税込み)
詳細はこちら ≫
【政策課題への一考察 第112回】
関係人口から定住人口へ ― 海外事例に学ぶふるさと住民登録制度の制度設計
株式会社日本政策総研副主任研究員
栗原 章
※2025年7月時点の内容です。
1 はじめに
総務省が2025年中の制度化決定を目指して構想しているふるさと住民登録制度は、関係人口が地域の新たな担い手として地方の持続可能性を支えるための制度的な枠組みを構築することが目的である。また本制度は観光客、二地域居住者、リモートワーカー及びボランティア希望者など、登録者と地域との多様な関わり方を前提にしている。さらに、この前提には将来的な定住人口の移行へとつながる関係人口の基盤づくりが制度の目的に含意されていると理解できる。
本稿では、ふるさと住民登録制度が単なる関係人口の可視化にとどまらず将来的な定住人口への移行を見据えた制度設計であるべきとの立場から、財源確保、制度への参加促進、実施体制及び運用といった制度設計における主要論点に沿った示唆を導出するべく、諸外国の先行事例を調査し制度設計上の論点に照らして分析・考察する。
2 諸外国の類似事例にみる制度的示唆
(1)非居住者との公平な負担関係の構築
非居住者に対して単に税の優遇を与えるのではなく適正な金銭的負担を求め、それに対して地域サービスの利用権や参加特典を付与する仕組みとすることが望ましい。これにより自治体財政を持続可能なものにするとともに、非居住者も公平感を持って地域に関与することができる。
例えばフランスでは、2019年から段階的に居住税の改革(1)を進め、2023年以降は住宅税を完全廃止した一方、別荘など(セカンドホーム)に対しては課税を維持した。また、住宅不足が深刻な都市部では自治体の裁量でセカンドホームに対して最大60%の付加税を課し、非居住者にもインフラ維持費を負担させ、その税収を自治体サービスの財源に充てている。
〔注〕
(1)フランス上院広報機関(Service-Public.fr)のプレスリリース(2022年7月25日)
https://www.publicsenat.fr/actualites/non-classe/pourquoi-la-taxe-dhabitation-sur-les-residences-secondaires-flambe-dans-de-2
日本では既にふるさと納税制度が非居住者による地域支援の仕組みとして機能している。また、2006年に同制度の創設を提案した福井県では二地域居住先の自治体での行政サービスに対する負担として現行制度とは別枠の納税上限額(所得割合の1割)を設定するほか、住宅ローン減税の二地域居住先に適用拡大する提案の動きがある(2)。さらに総務省でも複数の自治体に対して住民税を分割して納付できる分散納付に係る議論がなされる(3)など、国内にも関係人口の財政的貢献を制度的に下支えする示唆がみられる。
〔注〕
(2)福井県知事のSNS(X)投稿(2025年6月9日)
https://x.com/TatsujiS/status/1931975386658955383
(3)総務省「個人住民税における二地域居住の論点について」(2022年7月)
000834003.pdf
こうした国内外の制度的示唆を踏まえ、ふるさと住民登録制度においても、登録者が納税や寄付を含む一定の金銭的負担の対価として地域サービスの提供を受ける仕組みなど、税優遇等のインセンティブに依存しない対等な関係を構築することが自治体財政の持続可能性を高めることにつながる。なお、ふるさと納税制度との棲み分けについては今後議論を深めていく必要があり、将来的には制度の基軸をふるさと住民登録制度に段階的に移行させることも検討に値する。
(2)政策意思決定プロセスへの参加機会の確保
非居住者を政策意思決定のステークホルダーとして明確に位置付け、政策意思決定プロセスへの参加機会を制度的に確保することで、関係人口の当事者意識を高めることができる。自身の声を地域施策等に反映することができれば、地域課題に対する非居住者の主体的な貢献を促すことが期待できる。
例えばニュージーランドの地方選挙では、住民登録地とは別の自治体に不動産を所有し税金を納めている者を当該自治体の選挙人名簿に登録することで、居住地及び当該自治体双方で投票権を行使できる制度を設けている(4)。この制度は、非居住者に対して納税負担と政策決定プロセスへの参加資格の獲得を両立させる先進的な試みとして評価することができる。
〔注〕
(4)ニュージーランド地方選挙情報サイト「Vote 25」
Non-resident Ratepayer Roll - Vote 25 | Pōti 25
このほか、都市住民が地方に夏季専用の別荘を持ち長期休暇を過ごす文化が根付く北欧諸国での取り組みも参考になる(5)。例えばデンマークの国内最多の夏季別荘を抱えるオズヘアス市では、自治体主導の別荘所有者評議会(市議会に助言する諮問機関)を通じ、別荘滞在者と常住住民が意見を交わす場を設けている(6)。
〔注〕
(5)北欧研究機関Nordregioの公式プレスリリース(2019年2月13日)
Seasonal tourists and second homes boost local economies, but challenge local service planning | Nordregio
(6)オズヘアス・ランドリゲア議会(SOL)の公式Webサイト
Input:SOL - Sommerhusradet for Odsherreds Landliggere | Odsherred Kommune
ふるさと住民登録制度においても、登録者が地域の意思決定プロセスに参画できる枠組みを検討することが望ましい。具体的には、登録者向けのオンライン住民集会やアンケートを実施し、地域課題や計画案に対する意見を継続的に集める仕組みが挙げられる。また地方自治法の範囲内で、地域協議会にオブザーバーとして登録者が参加できる制度を設けることも考えられる。これらの仕組みにより登録者の声が自治体行政に届くことで地域の一員として責任を感じるようになり、支援の継続や将来的な移住にもつながると考えられる。
(3)体験型インセンティブによる定着誘導
現地での体験や所属意識といった非金銭的なインセンティブを提供することで、関係人口の満足度と参加意欲を高めることができる。地域文化や交流を通じて、登録した地域を応援する意欲を引き出し、ひいては定住人口につながり得る。
例えばドイツでは郷土カード制度(Heimatkarte(7))を導入し、地域在住者及び別荘所有者向けに「シュヴァルツヴァルト・プラス郷土カード」を年83ユーロ(約1万3000円)で販売している。購入したカードで美術館、スキー場及びゴルフ場などのアクティビティを1年間完全無料で楽しむことができる。税優遇や金銭のばらまきではなく現地での体験価値をインセンティブとして提示することで、関係人口の満足度と参加意欲を高めている。また提携施設側も利用者増で収益が生じるため官民双方にメリットが生じる。
〔注〕
(7)シュヴァルツヴァルト・プラス公式Webサイト
Schwarzwald Plus Heimatkarte für Einheimische
また、イタリアでは過疎地域の老朽化した空き家を1ユーロから売却(最終的な落札価格は1000~2万ユーロ程度が相場)し移住希望者を募るプロジェクトが実施されている。空き家の購入者に対しては、購入後数年以内の改修義務を課しているにもかかわらず海外を含む世界中から応募が殺到した。例えばシチリア州サンブーカ市では300軒以上の空き家が売却され、そこに北米を含む外国人が定着した事例(8)がある。
〔注〕
(8)地元紙『ラ・シチリア』(2025年4月30日)
Anche la tv svedese lancia un format sulle case a 1 euro a Sambuca di Sicilia : e il borgo e sempre piu ricco di stranieri - La Sicilia
ふるさと住民登録制度においても、ふるさと納税制度において用いられる主なインセンティブである税優遇や返礼品等の代替案として地域の公共施設利用権や地域イベント優先参加券など現地への訪問を前提にしたサービスを提供し、継続的な地域参加や将来的な定住につなげる制度設計が有用である。
(4)民間との連携による制度運営
民間の資金やノウハウを取り入れることで、自治体単独では困難な人材誘致や交流施策が可能になる。また、参加者に一定期間の地域関与を契約等により義務付けることで、一時的な関与ではなく継続的な地域貢献及び定着を促すことができる。
例えば米国オクラホマ州タルサ市の民間財団(George Kaiser Family Foundation (GKFF))の資金で運営しているリモートワーカー誘致プログラム(Tulsa Remote(9))では、審査を通過したリモートワーカーに対して1人当たり1万ドルの奨励金を支給し、最低1年間はタルサ市に居住する契約を締結している。これに対して、契約者は引越補助金、コワーキングペース利用権及び人的ネットワーキング支援などを享受する。なお、自治体は主に広報等の間接的な協力を担う。結果、2021年末までに約1200名のリモートワーカーがタルサ市に移住した。
〔注〕
(9)CREC(2022年4月)
Findings-on-Remote-Worker-Attraction-Programs-prepared-for-the-SEDE-Network-April-2022.pdf
日本においても、地域活性化や人材誘致において民間団体が果たす役割は徐々に拡大している。例えば、地域創生に取り組む企業や財団が地方自治体と連携して副業人材のマッチング支援やリモートワーカー向けの住居・仕事・交流機会の提供を行う事例が増えている。
特に、経済産業省が推進する「地域経済政策推進事業費補助金(映像・芸術文化を通じた関係人口創出事業)」では、民間企業が地域との接点を持つ人材を育成・派遣する仕組みが制度化されており、自治体との協働による制度運営の可能性が示されている。
ふるさと住民登録制度においても、民間財団や企業が制度の一部を担うことで自治体の財政的・人的負担を軽減しつつ、柔軟で持続可能な制度運営が可能となる。例えば、登録者へのインセンティブや地域滞在支援、オンライン交流の場などの設計を民間が担い、自治体は制度の認証・広報・地域調整に注力する分担モデルが考えられる。このような分担モデルは民間(財団や企業)にとって、地域貢献を通じた企業価値の向上(CSR・ESG)、社員の経験値向上、新規市場開拓及び地域資源を活用した商品開発など様々なメリットが想定され、持続的なパートナーシップの構築が期待できる。
(5)デジタル技術の活用及び自治体業務効率化
デジタル技術の利点を活かし、地理的距離や国境を越えた人々を関係人口に取り込むことが可能である。オンラインで登録・参加できる仕組みを整備し、在外邦人及び外国人にも門戸を開くことでグローバルなネットワークが地域経済を下支えする原動力となり得る。
また新制度の導入に際しては、自治体職員の業務負担を最小限に抑える工夫が不可欠である。デジタル化や標準化により手作業を削減するほか、広域連携や民間委託などで効率化を図るべきである。
例えばエストニアはデジタル技術で非居住の人材や企業を誘致し国家の利益に直結させた先進事例として有名である。同国では2014年に外国人に対して誠意府発行のデジタルIDカードを付与し、非居住であってもエストニア国内での会社設立や銀行口座開設を実施できるe-Residency制度を運用開始した(10) 。この制度により2020年までに累計7万人弱が住民登録者となり、1万6000社超のエストニア国籍企業が設立された。
〔注〕
(10)エストニア内務省プレスリリース(2022年10月22日)
E-Residency of Estonia is expanding | Siseministeerium
また、先に挙げたニュージーランドの事例では当初、非居住納税者が選挙投票をするには紙申請が必要であったものの、2025年の地方選挙に向けてオンライン投票フォームが各自治体サイトに整備され始めている。これにより、複数自治体に関係する住民でも利便性高く権利を行使できるようになった。またデジタル化した受付・管理処理により自治体側の事務負担が軽減するとともに、情報の一元化も可能となる。
さらに、フランスのセカンドホームへの課税では、非居住者自身が毎年税務ポータルで受託の住居状況を申告することが義務付けられている。虚偽申告や申告漏れには罰金を科すことで申告情報の正確性を確保するよう努めている。これにより、自治体職員が個別に別荘の実態を現地調査する手間を軽減することができる。
ふるさと住民登録制度の運用においても、マイナンバーカード等を活用したオンライン登録・手続きプラットフォームを構築し、在外日本人や外国人も含めて関係人口にアプローチすることが有用である。例えば、多言語対応のポータルサイトを設けることで、登録、寄付及び意見投稿などの一連の手続きをワンストップで受け付けることができる。さらにSNSやビデオ会議で地域情報発信・交流イベントを実施することで、国外を含む遠隔の登録者も地域貢献し参加できる環境が整う。これにより、登録者へのサービス向上と自治体職員の負担を最小限にとどめることの両立が可能となる。
3 結論
本稿では、ふるさと住民登録制度が将来的な定住人口への移行につながる制度設計に資するべく、諸外国の先行事例をもとに日本の制度設計に向けた示唆を導出し以下のとおり整理した。
財源確保
非居住者にも適正な負担を求めつつ、地域サービスの利用権や参加特典を付与することで、財政的持続可能性と制度参加の公平性を両立できる。さらに、二地域居住先への分散納付制度の導入などにより関係人口の財政的関与を制度化し、将来的にふるさと納税制度の基軸を本制度に段階的に移行させることも検討に値する。
制度参加促進
金銭的インセンティブに依存せず、地域体験や交流を通じた関係の深化によって、関係人口から定住人口への移行を促すことができる。公共施設の利用権やイベント参加権など、現地訪問を前提とした仕組みが鍵となる。また、非居住者を地域の意思決定プロセスに制度的に組み込むことで、当事者意識と継続的な関与を引き出すことができる。オンラインでの住民集会や協議会へのオブザーバー参加など、参加枠の制度的な確保が求められる。
実施体制
自治体単独ではなく、民間団体や地域財団との連携によって、柔軟かつ持続的な制度運営を可能にする。特に都市部の企業や副業人材との接点を活かした誘致モデルが有用である。このモデルは民間視点でも地域貢献を通じた企業価値の向上など様々なメリットが想定され、持続的なパートナーシップの構築が期待できる。
運用
マイナンバーカードや多言語対応ポータルを活用し、遠隔地からの登録・参加・意見提出を可能にすることで、在外邦人や外国人も含めた関係人口の裾野を広げるとともに、自治体職員の業務負荷を最小限にとどめることができる。
これらの示唆を制度設計に反映することで、ふるさと住民登録制度は非居住者を地域の担い手として位置付け、関係人口から定住人口への移行を促すとともに、地域社会の持続可能性を支える制度的な枠組みとして展開することができる。
*政策コンテンツ交流フォーラムは、株式会社日本政策総研、神戸シティ法律事務所が連携ハブとなり、国・地方自治体・民間企業のメンバーを架橋し、政策的課題を多面的に検討するネットワークです。本コラムを通じて、フォーラムにおける課題認識、政策創造の視点等をご紹介します。
本記事に関するお問い合わせ・ご相談は以下よりお願いいたします。
株式会社日本政策総研 会社概要
コンサルティング・取材等に関するお問合せ先
https://www.j-pri.co.jp/about.html
★「政策課題への一考察」は「月刊 地方財務」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 地方財務 2025年8月号
特別企画:「骨太の方針2025」と地方創生・地方行財政
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:3,960 円(税込み)
詳細はこちら ≫