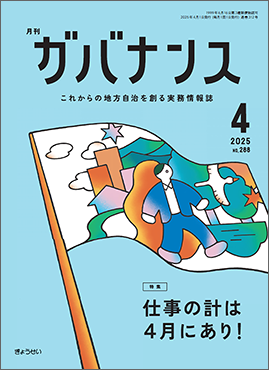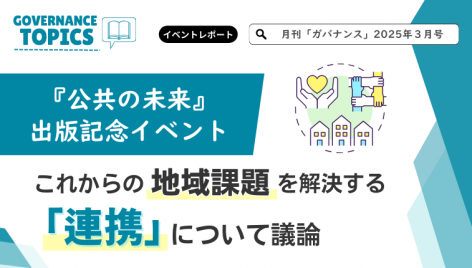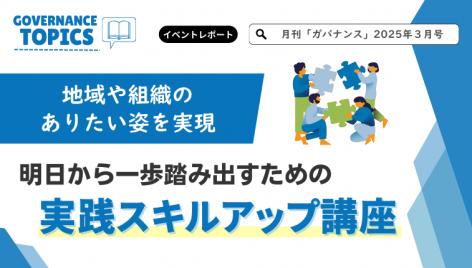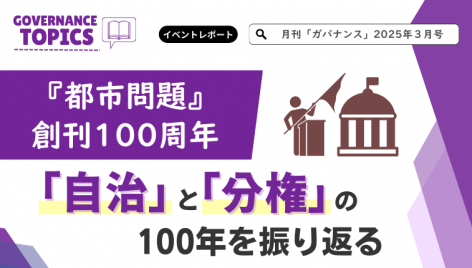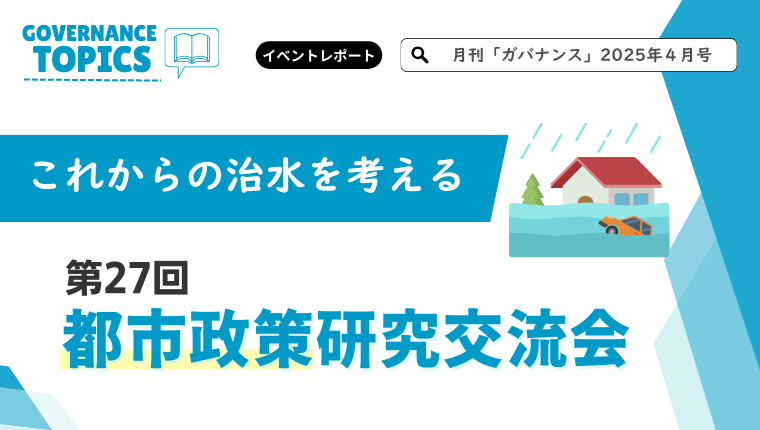
ガバナンスTOPICS【イベントレポート】
【これからの治水を考える】第27回都市政策研究交流会/イベントレポート
地方自治
2025.05.01
(『月刊ガバナンス』2025年4月号)
【連載一覧はこちら】
【ガバナンス・トピックス】
複数分野の連携で、これからの治水を考える
──第27回都市政策研究交流会
(公財)日本都市センターは2月21日に「水害多発時代の流域治水」と題し、都市政策研究交流会を開催した。同センターの研究会の成果を取りまとめ、24年10月に第一法規㈱から出版された書籍『水害多発時代の流域治水──自治体における組織・法制・条例・土地利用・合意形成』(以下、本書)の内容をより深く検討する会で、オンラインでの実施となった。
多角的な視点で流域治水を考える
今回のテーマは、日本の喫緊の課題である流域治水。複数の分野が横断的に連携し、解決していくことが求められるテーマだ。
本書の刊行の背景となった日本都市センターの研究会では、「国民の生命を守るため、自治体に何ができるのか」を模索し、治水の具体方策を土木工学、都市計画学、行政学など多角的な視点から議論してきました。

本会は、その議論をさらに深めつつ、得られた知見を共有する場である。
プログラムは、米田順彦氏(日本都市センター理事)の開会の挨拶からスタート。「これまでの治水対策では、主要な河川を管理している国土交通省や都道府県が先頭に立っていた。しかし流域治水では、土地利用・都市計画について幅広い権限を持つ自治体の役割が非常に大きくなってくる。本会が、自治体職員や流域の住民の方々にとって考えを深めるきっかけになれば」と話した。

多くの有識者が集まり、流域治水を考える場となった。
パラダイムシフトを迎えた治水の「理念」を紹介
次に、執筆陣による各章紹介が行われた。本書は全8章で、1、2章が【理念編】、3~8章が【実務編】として構成されている。
第1章 水害多発時代の流域治水の原理
まず【理念編】、第1章「水害多発時代の流域治水の原理」について、中村晋一郎・名古屋大学大学院工学研究科准教授が解説。本章で伝えたいこととして、
①流域治水は明治以降、史上3番目の大転換
②どの土地にもその土地固有の浸水リスクがある
③土地固有の浸水リスクに応じた治水への転換を
の3点をあげた。
このうち①について、1979年ごろから始まった総合治水(*)が都市部に限定されていたことに触れ、「2010年代に入ると、気候変動などの影響による歴史的水害が多発した。これを契機として、21年には『特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改善する法律』が施行。貯水、ダム、河道、土地、水防を一体的に管理していく流域治水が、全国的に推進されるようになった」と地域への広がりを説明した。
* 河道やダム貯水池といったハード面の整備のみではなく、保水・遊水機能(調整池、雨水タンク、透水性舗装等)、土地利用規制などの対策も組み合わせた総合的な治水。
第2章 自治体における流域治水政策
次に、第2章「自治体における流域治水政策」について、瀧健太郎・滋賀県立大学環境科学部教授が滋賀県の流域治水制度を軸に解説した。
その中では、氾濫後の対応強化のため、法制度的に氾濫原の管理が難しい立場にある河川管理者とは別に「氾濫原管理者」を設置する工夫や、住民の暮らしに即したリスク(地先の安全度)評価の実施、高リスク地における建築規制や土地利用規制をめぐるリスクコミュニケーションの重要性など、住民に寄り添った形での流域治水の方策が紹介された。
これら1、2章の解説を踏まえ、加藤孝明・東京大学生産技術研究所教授が、土木・河川工学ではなく、都市計画やまちづくり、防災を専門とする立場から、次のようにコメントした。
市民を含め、河川工学に対する知識・関心は薄く、災害リスクを読み解くリテラシーは不足している。治水のパラダイムシフトを迎え、肝となるのは流域全体でのリスクと努力のシェア、そして、残余リスクの受容と、残余リスク低減のための社会システムの構築だろう。社会全体で取り組んでいく必要がある。
また、OKY(お前・こっち来て・やってみろ)というワードを紹介。「理念は素晴らしくても、現場に落とし込んだ際にOKYとなることは多い。そうならないためにも、各地の実践を共有できる場や、現場からのフィードバックを生かせる体制を整えることが大切」と話した。
「実務」に即した知識を共有
第3章 流域治水政策における自治体の位置づけと主体間の連携
次に【実務編】として、第3章「流域治水政策における自治体の位置づけと主体間の連携」を、高野裕作・(一財)交通経済研究所研究員が解説した。
高野氏は、自治体に関係する流域治水の関連法を、「河川・治水行政」「都市計画・土地利用」の2つに整理。これらの法や制度で対応しきれない部分を、条例でカバーしていく必要があると論じた。また、主体間連携の枠組みとして流域治水協議会、流域水害対策協議会の2層を紹介。これら協議の場を通じた、市町村間の活発な協働に期待を寄せた。
第4章 流域治水に対応する組織・人員体制のあり方
続く第4章「流域治水に対応する組織・人員体制のあり方」を、大谷基道・獨協大学法学部教授が解説。論点として、
①どのような組織体制が必要か
②人材をどのように確保するか
の2点をあげた。
このうち②では、
■仕事の専門性よりも地元での就職を重視する若手へのさらなるアプローチ ■市町村単独ではなく、より集客力のある県とタッグを組んでの採用試験 など、新たな対応策の提案も行われた。
第5章 流域治水条例の傾向と総合性・合理性
第5章「流域治水条例の傾向と総合性・合理性」については、内海麻利・駒澤大学法学部教授が解説。各地の流域治水条例を分析し、その内容を
A.理念・責務等
B.計画等
C.施設整備・管理
D.環境等保全
E.行為規制
F.協議会等
G.支援・教育
H.情報整備
I.避難対策等
の9つに分類した。このうちどの要素を含むかにより、自治体の流域治水条例は「総合型」と「行為規制型」に大別できるという。創意工夫がこらされた流域治水条例のもと、協議会や計画間の調整も行いながら、各地域で総合性、合理性が確保されていると説明した。

駒澤大学の内海教授は各地の流域治水条例を検討し、その総合性と合理性について論を展開した。
第6章 水害多発時代における都市計画制度上の論点(市街地編)
土地利用に焦点をあてた第6章「水害多発時代における都市計画制度上の論点(市街地編)」、および第7章「都市計画制限による流域治水の実践と取組み(農村部編)」は、松川寿也・長岡技術科学大学環境社会基盤系准教授が解説。
6章の市街地編では、立地適正化計画における水害リスク対応に着目し、リスクの低い土地が居住誘導区域として積極利用されるという利点を取り上げた。一方、既存のインフラ設備等の面から、高リスクであっても市街地評価が高くなる「居住誘導浸水想定区域」が存在することにも言及。立地適正化計画内で設ける防災指針の重要性を強調した。
第7章 都市計画制限による流域治水の実践と取組み(農村部編)
また7章の農村部編では、市街化調整区域の開発規制にフォーカス。想定浸水深や安全対策如何では開発が可能となる現状に問いを投げかけ、「ハザードありきではなく、土地利用計画の本来の趣旨を踏まえたうえで、リスクに応じた規制と誘導を行うべきだ」と考えを示した。
第8章 流域治水におけるまちづくりと合意形成
第8章の「流域治水におけるまちづくりと合意形成」は、田中尚人・熊本大学大学院先端科学研究部准教授が解説。地域の文化的景観に取り組んできた立場から、多様な主体の連携による、風土に根差した“かわまちづくり”を提案。その地に根づいた実践知を丁寧に読み解きながら進めていくことが大切だと話した。
その後、【実務編】の各章について知花武佳・政策研究大学院大学教授、松井望・東京都立大学都市環境学部教授からコメントや質問が寄せられ、執筆担当がそれに答える形で、議論をさらに深めた。
水害多発時代に重要性を増す治水について、さまざまな角度からとらえ直す機会となった。
(本誌/森田愛望)