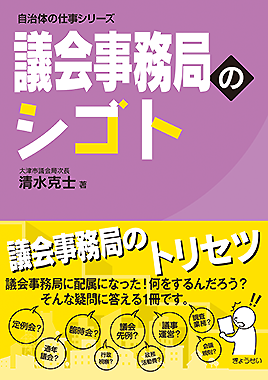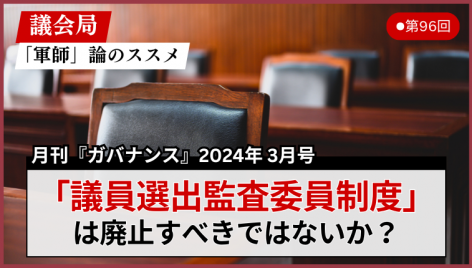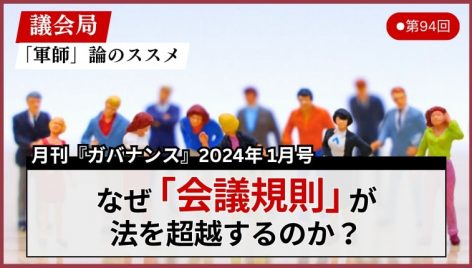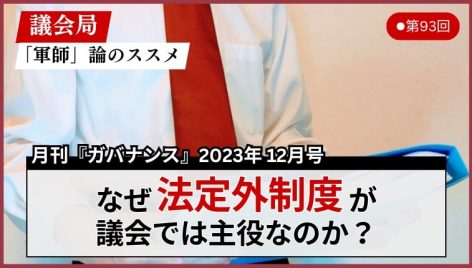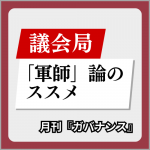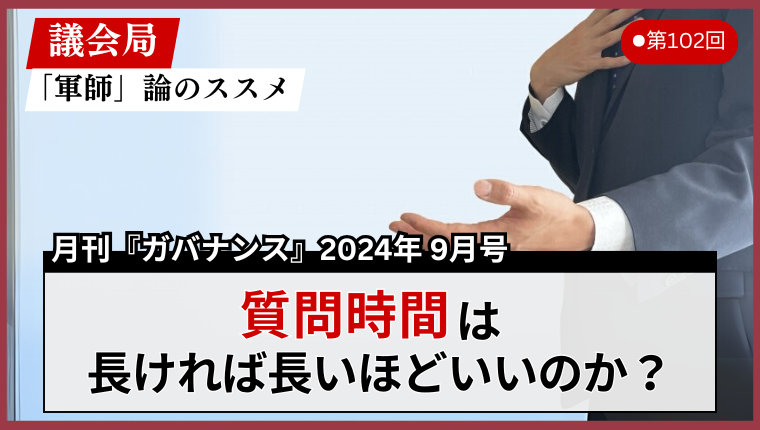
議会局「軍師」論のススメ
議会局「軍師」論のススメ 第102回 質問時間は長ければ長いほどいいのか?
地方自治
2025.04.17
本記事は、月刊『ガバナンス』2024年9月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
先日、ある議員研修会に講師として招かれた際に、事前質問で「質疑時間の制限の是非」を問うものがあった。今号では、当日の答えに補足して、あらためて考えを述べたい。
■誰のための質問か?
事前質問の背景には、発言者数が増加傾向にあり、審議時間も長時間化してきたため、会派ごとの発言時間が短縮されたことがあるようであった。
もとより質疑については、再質問回数や総時間などの違いはあっても、全く無制限という議会のほうが少ないだろう。もちろん、質問する議員個人の立場からは、質問時間は長ければ長いほど良いと考えるのも理解できる。だが、1年365日、1日24時間の時間的制約が万人に適用される以上、全く無制限とすることは、限られた小規模議会以外では現実的ではないのも事実である。
また、一般質問にも共通するが、議会対行政の関係性でしか捉えていないと、質問時間が長ければ長いほど議会としての機能発揮をしていると考えられがちである。だが議会の現場で質疑応答するのは、プロである議員と行政関係者であろうが、公開の場で行われる意義は、その議論自体がアマチュアである一般市民のためのものであるからではないのか。その観点からは、現状の質問が市民フレンドリーなものと言えるのか、再度検証する必要性はないだろうか。
具体的には、行政の専門家ではない大多数の一般市民に議論を積極的に聴いてもらおうとするなら、必然的に行政課題を端的に指摘し、疑問点をコンパクトに質すことが大前提となるのではないか。一般市民に議会の印象を尋ねると、残念ながら「議員の話は無駄に長い」というものが少なくない。そこに両者の根本的な意識のズレはないだろうか。
■立場による体感時間の違い
その必要性を感じるのは、現職時代に議会広報改革に取り組んでいた時の経験にある。それは、大津市議会と交流があった高校生に「若者にも読んでもらえるよう、議会だよりもいろんな工夫をしているんだが、どうしたら君たちに議会に興味を持ってもらえそうかな」と聞いてみた。答えは「議会だよりなんか読んだこともないし、興味をそそるとしたら動画ですね。それも長いのはダメですよ。3分以内なら見てみるかも」であった。興味のない話に付き合うのは3分間が限界なのだと感じさせられたのである。
一方で、筆者は主に議会関係者を対象とした3分間のプレゼンテーションに何度かトライしたことがあり、短時間で的確に伝える難しさも実感している。その時は正直なところ、いわば玄人集団へのプレゼンであったが、それでも3分間ではパフォーマンスの場としてはともかく、核心部分を聴衆に伝えるのには無理な時間設定だとも感じていた。
この二つの経験から感じたのは、玄人集団に伝えようとするには不足を感じる短時間であっても、業界外の素人集団に伝えるには長すぎると感じられてしまう、「時間の二面性」である。つまり、誰に伝えたいと思うかによって、また、聴くのが誰かによって、適正時間の相場感は大きく異なるということである。
もちろん、議会の質問時間も3分間が適正だとは思わないが、議論の当事者である議員や行政関係者の視点ではなく、議論を聴く市民の視点で質問時間の妥当性を考えてみることが必要ではないだろうか。
第103回 議会BCPがお守りでいいのか? は2025年5月15日(木)公開予定です。
Profile
元早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員・元大津市議会局長
清水 克士 しみず・かつし
1963年生まれ。同志社大学法学部卒業後、85年大津市役所入庁。企業局総務課総務係長、産業政策課副参事、議会総務課長、次長、局長などを歴任し、2023年3月に定年退職。著書に『議会事務局のシゴト』(ぎょうせい)。