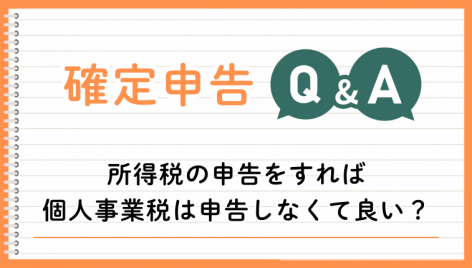
【確定申告Q&A】所得税の申告をすれば個人事業税は申告しなくて良い?
NEW地方自治
2026.01.30
最新記事より
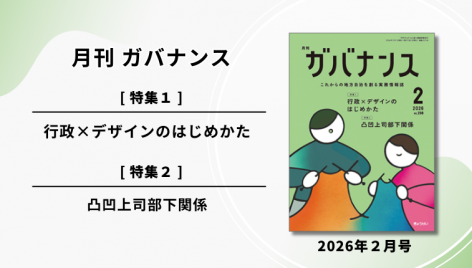
地方自治
2026.01.28

地方自治
2026.01.28
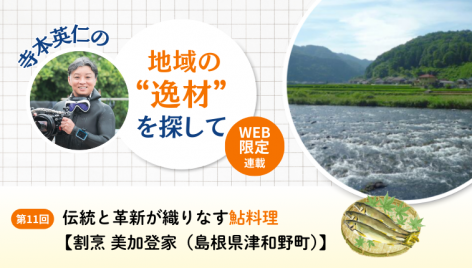
地方自治
2026.02.02
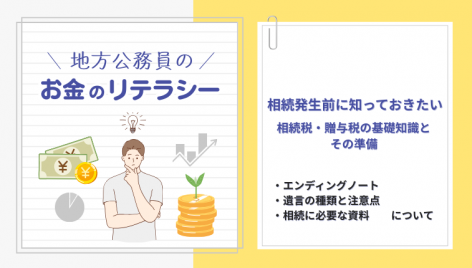
地方自治
2025.12.17
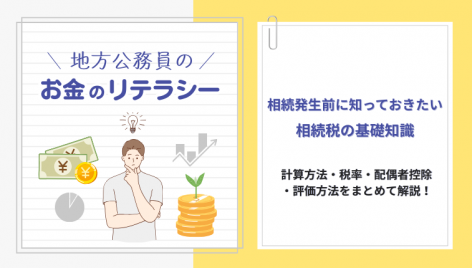
地方自治
2025.12.25
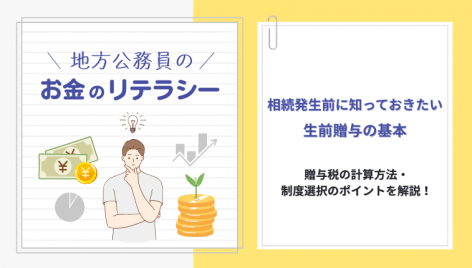
地方自治
2026.01.13
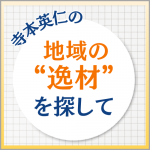
寺本英仁

ガバナンス編集部
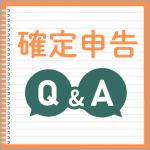
月刊「税」

ガバナンス編集部
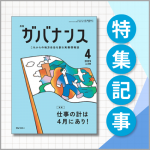
ガバナンス編集部

金井利之
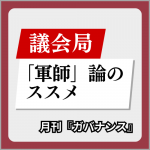
清水 克士

鍵屋 一

ガバナンス編集部
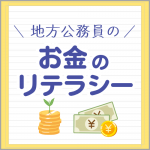
鈴木 豊、林 賢是

ガバナンス編集部

月刊「地方財務」
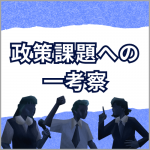
月刊「地方財務」
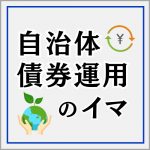
月刊「地方財務」
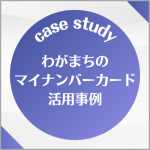
J-LIS編集部

月刊「地方財務」
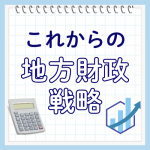
松下 啓一

J-LIS編集部

J-LIS編集部

鷲巣研二

関根健夫

古橋香織
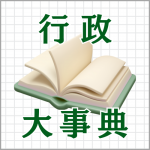
ぎょうせい

関根健夫
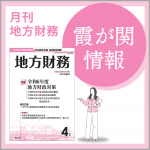
月刊「地方財務」
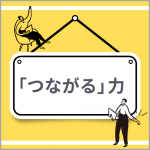
月刊「ガバナンス」

若生 幸也

葛西 優香

塩見 政幸
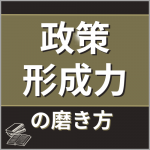
塩見 政幸
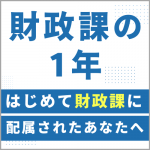
林 誠
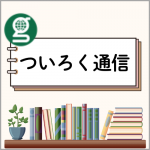
ぎょうせい

塩見 政幸
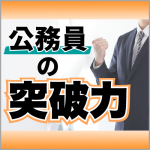
安部浩成

小松 俊也

千葉大右・多田 功・山形巧哉・今村 寛

ぎょうせいオンライン編集部

塩見 政幸
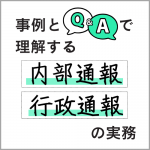
日野 勝吾
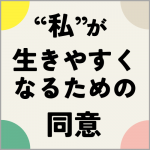
遠藤 研一郎
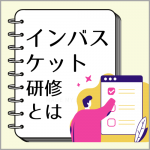
鳥原 隆志

市川 博之

福島 弘行
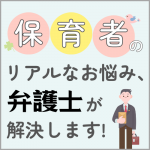
吉永公平

ガバナンス編集部
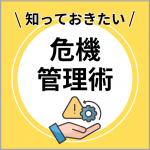
酒井明

笹谷秀光
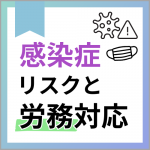
弁護士法人淀屋橋・山上合同
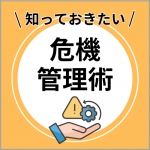
木村栄宏
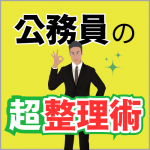
本山毅
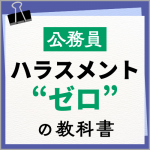
高嶋直人

野田遊

山村武彦
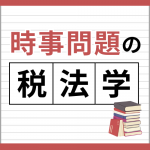
林仲宣

ぎょうせいシステム事業部

稲継裕昭
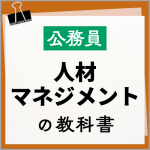
高嶋直人
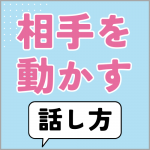
八幡紕芦史

八幡 紕芦史

山口 利恵
ランキング

【確定申告Q&A】合計所得金額と総所得金額等はどう違う?

【確定申告Q&A】住民税の申告が必要な人・不要な人を解説

【カスハラ対策】「上司を出せ」の適切な断り方とは?|クレーム対応術 7

公職選挙法とは|最新行政大事典【用語集】

【カスハラ対策】お客さまを出禁にする手順を解説

第三波を迎えた「大阪都構想」のミライ|新・地方自治のミライ 第93回

【103万円の壁→配偶者123万/大学生世代150万に】令和7年改正で配偶者控除・扶養控除はどう変わる?|地方公務員のお金のリテラシー

詫びと謝罪の違いとは?|クレーム対応術6【カスハラ対策】

【カスハラ対策】不当要求とは?具体例と判断のポイント|クレーム対応術11

【確定申告Q&A】住民税申告書の提出先・提出期限は?