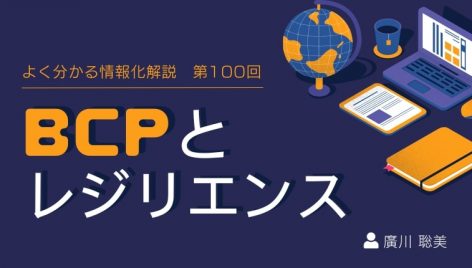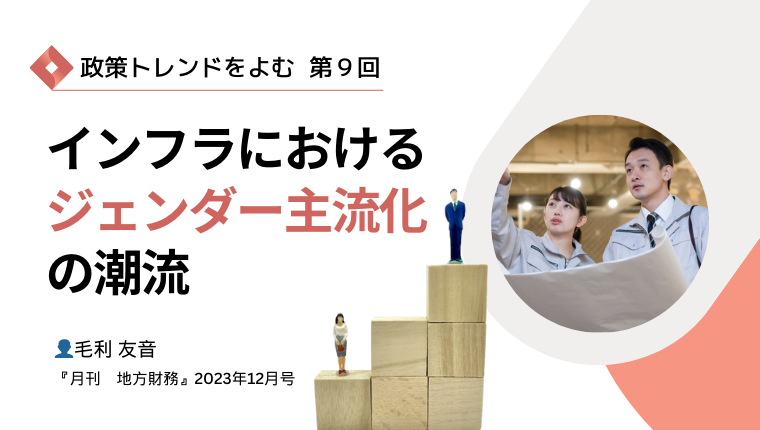
政策トレンドをよむ
インフラにおけるジェンダー主流化の潮流|政策トレンドをよむ 第9回
地方自治
2024.01.05
目次
※2023年11月時点の内容です。
政策トレンドをよむ 第9回 インフラにおけるジェンダー主流化の潮流
EY新日本有限責任監査法人 CCaSS事業部
毛利 友音
(『月刊 地方財務』2023年12月号)
【連載一覧はこちら】

2023年6月、世界経済フォーラムが2023年度版「ジェンダーギャップ指数」を発表した。報告書によると、世界全体の総合スコアは68.1%から68.4%に向上した一方で、日本のジェンダー指数の順位は146か国中125位であり過去最低の結果であった。指数は教育、健康、政治参画、経済の4つの分野ごとに評価されており、日本は教育(47位)と健康(59位)においては高い順位を維持している一方、政治参画(138位)と経済(123位)の分野においては順位が低く、日本におけるジェンダー平等の実現は、他国に比べ大きく後れをとっていることが明らかとなった。(1)
〔注〕
(1)World Economic Forum(2023) “Global Gender Gap Report 2023”
近年、あらゆる取り組みにおいて常にジェンダーの視点を施策に反映する「ジェンダー主流化」が世界で進んでおり、(2)国際会議や多国間協議等においても、ジェンダー視点が取り入れられている。日本でも、地方創生のための男女平等や女性の活躍推進に関する取り組みが進みつつある。(3)
〔注〕
(2)外務省「ジェンダー平等と女性のエンパワーメント」(2023年10月13日アクセス)
(3)内閣府男女共同参画局(2023)「男女共同参画白書令和5年版」
本稿では、ジェンダー主流化の重要性について交通インフラを取り上げて紹介する。一般的には、交通インフラ整備はすべての人に裨益するため、性別を考慮すべき領域とは考えられにくい。しかしながら、交通インフラは、長期にわたり男女問わず多くの人々に利用されるものであり、交通インフラ整備からジェンダー視点を排除するということは、ジェンダー不平等が深刻化することを意味している。既存の交通インフラにおいては、ジェンダー視点が欠けた設備・サービスになっていることも危惧されるため、見直し・改善が求められる。(4)交通インフラ整備にジェンダー主流化を取り込むことは、地域におけるジェンダー不平等を是正し、社会包摂を実現するために重要なのである。
〔注〕
(4)The World Bank Group “All too often in transport, women are an afterthought”(2023年10月13日アクセス)

交通インフラ整備におけるジェンダー主流化を加速させるためのポイントはさまざまであるが、本号では主に2つ紹介する。1つはインフラ整備を実施する組織内におけるジェンダー主流化である。社内におけるジェンダー主流化が促進されることで、事業においてもジェンダー視点が組み込まれることが期待される。グローバルでは、「Women's Empowerment Principles(WEPs)」と呼ばれる女性の経済的エンパワーメントを推進する原則が活用されている(5)(詳細については内閣府男女共同参画局HP等を参照)。
〔注〕
(5)内閣府男女共同参画局「女性のエンパワーメント原則(WEPs)」(2023年10月13日アクセス)
その他、日本国内においても、「女性活躍推進法」等の法整備などが行われている。
交通インフラ整備におけるジェンダー主流化の第2のポイントは、事業を実施する際、ジェンダー視点を通して事業がどのような影響を及ぼすのかを事前に評価し、計画を立てることである。具体的には、構内や車内だけではなく、駅やバス停にたどり着くまでのルートの安全性が確保されているか、料金体系が公平性の高いものになっているかなどが挙げられる。料金体系については、毎日通勤などで同じルートを行き来する人に比べて、家事や買い物のため毎回の利用で違う場所に行き来する人々は、定期券などの利用ができないため、交通機関を頻繁に利用する同士の中でも格差が生まれてしまう。公平性の高い利用環境を実現するためには、ジェンダー視点を入れた事業の評価、計画の見直しが求められる。
加えて、交通インフラ整備は、地域の産業を活性化し、新しい雇用の創出にもつながることも指摘されている(6)。事業がもたらす影響を評価する際、交通インフラ導入に伴う経済効果についてジェンダー視点を入れて調査することで、地域の女性が活躍できるような機会を特定することができる。例えば、長距離の電車であれば、車内販売用の商品を地域女性経営者から買い付けるなど、事業のサプライチェーンに女性を組み込むことが可能である。加えて、地域で活動する女性起業家や関連するネットワークやコミュニティと連携すれば、新しい雇用機会創出も期待できる。また、働き手の確保という観点から、地域の教育機関と連携し、女性を対象としたエンジニア育成プログラムなどといった取り組みも考えられる。
〔注〕
(6)Australian Government Partnerships for Infrastructure “Transport in frastructure:trends, challenges and opportunities in a post-COVID world”(2023年10月13日アクセス)
上記で述べたように、事業においてジェンダー主流化を行うことは、ジェンダー不平等を是正するだけでなく、地域における経済効果も見込まれ、社会包摂の実現につながるものであるといえる。日本においても今後、ジェンダー主流化が進んでいくことが望ましいのではないか。
本記事に関するお問い合わせ・ご相談は以下よりお願いいたします。
持続可能な社会のための科学技術・イノベーション | EY Japan
多様な人材の活躍推進(DEI、外国人材の受け入れ・共生、新たな学び方・働き方) | EY Japan