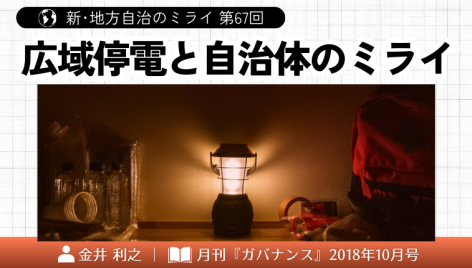自治体の防災マネジメント
自治体の防災マネジメント[32]福祉避難所を考える(上) ──活用されない福祉避難所制度
地方自治
2020.10.07
自治体の防災マネジメント―地域の魅力増進と防災力向上の両立をめざして
[32]福祉避難所を考える(上)──活用されない福祉避難所制度
鍵屋 一(かぎや・はじめ)
(月刊『ガバナンス』2018年11月号)
福祉避難所については、阪神・淡路大震災における取り組みを総括した「災害救助研究会」(旧厚生省、1995年)が、「大規模災害における応急救助のあり方」において「福祉避難所の指定」を初めて報告した。それ以降、必要性は認識されているものの、事前指定への取り組みは地域でバラつきがあり、平成19(2007)年能登半島地震、中越沖地震において、福祉避難所が一定の機能を実現し、災害時要配慮者支援に貢献した例もあったものの、全体として十分な成果が得られないまま、東日本大震災が発生した。その後、内閣府が福祉避難所ガイドラインを制定するなどしているが、熊本地震以降の災害でも十分な効果を発揮しているとはいいがたい。
一方で、わが国の65歳以上の高齢者人口は、1950年には総人口の5%に満たなかったが、1970年に7%を超え、さらに、1994年には14%を超えた。高齢化率はその後も上昇を続け、2018年10月時点で27.3%に達している。すなわち、1995年の阪神・淡路大震災時に比べて、ほぼ2倍の高齢者がいるのである。
このためか、高齢者の災害関連死が目立っている。東日本大震災においては3676人(2018年3月31日現在、復興庁)、熊本地震においては、直接死が50人であるのに対し、関連死が219人(2018年9月28日現在、熊本県)と4倍を超えている。東日本大震災では少なくとも90%以上、熊本地震でも80%が高齢者とみられている。それは、一言で言えば、高齢者にとって避難生活が非常に厳しいからである。
これまで近隣のさりげない見守りや生活支援、福祉事業者による定期的な支援に支えられてきた高齢者が、近隣者や福祉関係者も被災することにより、一挙に困難な状況に陥るのである。福祉避難所ならば、支援の手が行き届くが、在宅になると、その状況がほとんど見えなくなる。
今後、75歳以上人口は団塊世代が順次加わることにより、2018年の約1691万人から、2025年には2180万人とわずか7年で500万人も増加する見込みだ。災害時の避難生活が困難な人もそれだけ増えていく。したがって、福祉避難所の果たす役割はますます大きくなる。今月から3回にわたって、福祉避難所のあり方を考えたい。
低調な福祉避難所利用
「平成30年7月豪雨災害(西日本豪雨災害)」では、福祉避難所の開設が遅れ、利用できない避難者が多かった。
「被害が大きい岡山県倉敷市、広島市、愛媛県宇和島市では約2900人が避難生活。福祉避難所の利用は14日時点で約20人にとどまる。過去に一般避難者が殺到した事例があり、存在を積極的に知らせていないことが、妨げの一因となっている」(産経WEST、7月14日)
「岡山、広島、愛媛の3県では災害弱者向けの『福祉避難所』は46カ所で開設され、計253人が利用。(中略)相当数の災害弱者が孤立している可能性がある」(毎日新聞、7月22日)
福祉避難所の利用者は災害救助法で「高齢者、障害者の他、妊産婦、乳幼児、病弱者等避難所での生活に支障をきたすため、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者、及びその家族まで含めて差し支えない」となっている。だとすれば、福祉避難所を利用すべき要配慮者が、2900人の避難者の1%以下の20人にとどまって良いはずがない。
福祉避難所は二次避難所か
福祉避難所の開設が遅れる理由について、私が聞き取った限りでは、「急いで開設する必要はないと思った」「市町村職員が福祉避難所を運営することになっていたが、人手が足りなかった」「福祉避難所の運営方法がわからなかった」などがある。
福祉避難所の確保・運営ガイドライン(内閣府(防災担当)2016年4月、P29)では、「市町村は、災害が発生し又は発生のおそれがある場合で、一般の避難所に避難してきた者で福祉避難所の対象となる者がおり、福祉避難所の開設が必要と判断する場合は、福祉避難所の施設管理者に開設を要請する」となっている。
文字通りに解釈すれば、要配慮者は最初に一般避難所に行き、福祉避難所の対象となる者と認められてから、福祉避難所が開設され、そこに行くことになる。まさに二次的な避難所であり、それゆえ、災害応急対策の中で位置づけが低くなっている可能性がある。実際に東京都は、地域防災計画で二次避難所(福祉避難所)と表記している。ガイドラインは、要配慮者が最初から福祉避難所を利用することや、福祉避難所の指定を受けていた福祉施設が自主的に開設することを禁止しているわけではないが、誤解を生みやすい表現になっている。
要配慮者の立場から考えるとどうだろうか。災害後に自宅に住めなくなってから、一度、一般避難所まで避難物資を持って移動し、福祉避難所が開設されるのを待って、そこから再度、移動することになる。一般の避難所は福祉避難所よりも環境が悪いのが一般的だから、体調が悪化する可能性がより高い。本来は体調が悪化しないように避難生活を送ることが最も大事なはずだ。
市町村職員から見ると、一言で「移送」というが、避難所を移るためには本人の希望、親族や支援者の考え、福祉避難所の受け入れ態勢の確認、受け入れ同意の確保、移送日時や方法の打ち合わせ、荷物を含めた移送業務と多くの調整作業が発生することになる。多忙な時期に、さらに大きな負荷を加えてしまう。
だとすれば、要配慮者の体調悪化や市町村職員の業務量増大を避けるためにも、一般避難所での生活が難しい要配慮者と家族は、最初から福祉避難所に向かい、利用するべきである。
福祉避難所は覚悟が必要
熊本地震では、福祉避難所に指定されていた福祉施設に多くの一般避難者が押し寄せ、災害時要配慮者への支援が手薄にならざるを得なかった。近年の災害対応で、福祉避難所の開設を積極的にPRしない事例が出てきているが、このような事情を参酌したものと思われる。だが、混乱を避けることを優先するがゆえに、支援を必要とする要配慮者を見過ごしてはいないだろうか。
熊本地震で実際に福祉避難所を運営した職員は次のように述べている。 「テレビで90歳のおばあちゃんが車中泊をしているのを見て、ここに来てもらえればいいのに、と思ったこともあります。福祉避難所を知らない人もいたので『災害時はここに福祉避難所ができるので来てくださいね』とお知らせするのが大事です。行っていいのか迷った人もいたようです。福祉避難所といっても地域の方だけではありません。デイや居宅の利用者、職員の家族、その他色々なツテを使って集まってきます。ライフラインが復旧するまでは、選別できないほど多くの方が来られるので、覚悟が必要です」

Profile
跡見学園女子大学教授
鍵屋 一(かぎや・はじめ)
1956年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、東京・板橋区役所入区。法政大学大学院政治学専攻修士課程修了、京都大学博士(情報学)。防災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長、危機管理担当部長、議会事務局長などを歴任し、2015年4月から現職。避難所役割検討委員会(座長)、(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事、(一社)防災教育普及協会理事 なども務める。 著書に『図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ』 (学陽書房、19年6月改訂)など。