
新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第52回 テロ等準備のミライ
地方自治
2024.04.24
本記事は、月刊『ガバナンス』2017年7月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
はじめに
政府与党がテロ等準備という罪を犯すことに関する法律を制定した(注1)。「共謀罪」とも呼ばれることもあるが、首相による「印象操作」との指摘を勘案して、「テロ等準備罪」とも呼ばれる。どのような用語を採用するのかは、「印象操作」にも関わるので難しい問題もあるが、本稿では政府与党及び一部メディアの「印象操作」論に準拠して、「テロ等準備罪」という表記を採用する。ただし、本当は、組織犯罪処罰法改正である(注2)。
注1 正確に言えば、法律を制定するのは国会ではあるが、実質的には国会両院の絶対多数を押さえているのは政府与党であり、特に内閣提出法に関しては、実質的に法律を制定するのは政府与党であるので、このように表記する。
注2 正式には「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」であり、「テロ等準備法」ではない。
このような刑事法に関する法律は、通常は自治体には縁遠い。自治体に影響するのは、一般的には地方自治法・地方税法を初めとする総務省関係のものが中心であり、また、介護保険法など、自治体の事務に係る個別政策分野に関する各府省庁関係のものが多い。刑事法に関するものは、基本的には、法務省・検察庁および警察の業務である。
もちろん、警察の実働部隊は警視庁・道府県警察本部であり、自治体の組織ではある。しかし、地方警務官制度のもとで、上層部は国家公務員であり、実働の現場警察職員はその指揮監督下にある。また、警察は公安委員会の管理の下にあり、知事部局とは別である。その意味で、実質的には、都道府県の一般行政からは別世界だと思われている。ましてや、市区町村からすれば、そもそも組織的にも無縁の世界である。個別法には様々な処罰規定が盛り込まれることもあり、また、自治体は条例で罰則規定を盛り込むことも可能である。しかし、運用においては、自治体からすれば、あくまで刑事事件として告発できるだけで、それでは一般人と違いはない。
つまり、刑事法の執行に関して、自治体は一般人と何ら違いはないのである。そこで、今回は、自治業界の雑誌には似つかわしくないかもしれないが、テロ等準備罪に関して検討してみよう。
テロの価値とテロ対策
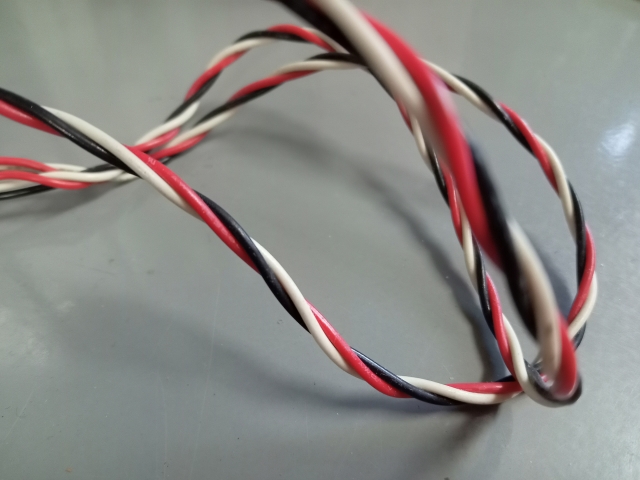
テロとは、アルカイダの9・11同時多発テロやIS(「イスラム国」)の爆破事件など、多くの人々を殺傷することがイメージされる。もっとも、ランサムウェアによるサイバー・テロなどのように、情報システムを破壊することで、多くの人々の生活を困らせ、場合によっては、命に関わるような事態を起こす。
日本でも、1995年3月20日にオウム真理教が起こした「地下鉄サリン事件」があった。こうした犯罪が人々を不安にさせるのは当然であり、テロ等準備罪(共謀罪)によって、テロが阻止できるのであれば、人々の自由が制限される側面はあるにせよ、やむを得ないという気にもなるだろう。
しかし、「テロ(Terror,terror‒ism)」とは「恐怖(terror)」に由来するように、テロの本質は、大量殺傷・大規模犯罪それ自体にあるのではなく、むしろ、人々に恐怖感を与えることにある。テロを起こす目的は、犯罪犠牲者本人に被害を与えることだけではなく、犯罪を見聞・体験して生き残っている人に恐怖を与えて、その人たちの思考・行動を萎縮・変容させることにある。「テロに屈しない」などと主張することはできるが、テロを恐怖した段階で、すでに「テロに屈したこと」そのものなのである。そのように、人々がテロに怯えれば怯えるほど、テロの価値が上がり、テロを誘発・促進することになる。日本政府は、テロ等準備罪の必要性を流布することによって、テロの価値を高めることに国際貢献した。
テロ対策では、犯罪被害に過剰に恐怖しないことである。もちろん、多くの人は犯罪被害に遭いたくない。犯罪が起きれば速やかに犯人を検挙して処罰して欲しいし、できれば、犯罪が起きない環境を作ることが期待される。犯罪予防・対策は必要であるが、恐怖を過剰にしないのが、最大のテロ対策である。
例えば、地下鉄サリン事件は許し難い。と同時に、東京圏民は、事件後も、「平常心」で地下鉄を使い続けている。自治体としての東京都庁も、テロに恐怖したわけではない。都民も、およそ、危機管理には適切とは思えない青島幸男を、直後の4月9日の選挙で都知事に選出している。青島都知事は、世界都市博を中止にしたが、もちろん、多数の一般人が集まるソフトターゲットである都市博の警備が不安だから中止にしたのではない。少なくとも、1990年代までの日本では、「平常心」というテロ対策がなされていた。
政治テロル

古典的には、政治的・経済的な有力者を対象とする「暗殺事件」こそが、テロルとされてきた。戦前日本は、こうした政治テロル大国であり、原敬・浜口雄幸・犬養毅という政党内閣の首相は、いずれもテロルに斃れている。五・一五事件、二・二六事件は、昭和維新の名の下に日本の政党内閣を死滅させたテロル事件である。
戦後体制において民主政治が定着したのは、全体として政治テロルが低調になったことと、相関していよう。野党第一党党首であった浅沼稲次郎への白昼暗殺テロル(1960年10月12日)はあったが、少なくとも、首相・知事が暗殺されたことはない。もちろん、政治家・有力者に対する殺傷・暴行事件が消えたわけではなく、例えば、伊藤一長・長崎市長暗殺事件(2007年4月17日)、本島等・長崎市長狙撃事件(1990年1月18日)、柳川喜郎・岐阜県御嵩町長襲撃事件(1996年10月30日)が起きたりしている。
政治家対象ではなくとも、地下鉄サリン事件直後の國松孝次・警察庁長官狙撃事件(1995年3月30日)や、青島都知事宛の小包爆発物により都庁職員が重傷を負った事件(同年5月16日)も起きている。そもそも、自治体現場では、行政職員対象暴力は頻発している。
重要なことは、こうした政治テロルに対して、世間が「犯人の心情は理解できる」などという反応を全く示してこなかったことである。そして、政治家も、政治テロルに怯んで信条・政策を歪めては来なかったし、政治家への成り手がなくなる事態も発生していない。もちろん、必要な警備・警護はすべきである。とはいえ、覚悟のない為政者は、政治テロルに怯え、テロに屈して、過剰な警備・警護、さらには、予防的捜査や拘束・取調を期待して、法規制を整備するのであろうが、少なくとも、今までの日本の自治体の為政者には、そのような「腰抜け」はいなかったのである(注3)。
注3 ちなみに、狙撃された國松警察庁長官はその後も堂々としていたが、警察庁刑事局長は、庁舎内のトイレに行くにも護衛を付けたという。
おわりに

以上のように検討していくと、自治体・住民が維持すべきことは、テロ等準備罪と無縁のスタンスそのものである。政府与党および「癒(ゆ)党」維新の会は、「テロ等準備罪」という名称によって、国民にテロへの恐怖感を流布させ、テロリズム集団を利してしまった。
また、野党や反対派市民運動は、「共謀罪」の問題性を指摘したが、その結果、「誰でも警察当局の恣意で内心を含めて犯罪捜査される」という恐怖感を煽ってしまった。確かに、法案の中身が曖昧であることを審議では指摘しなければならないし、その立法・解釈・運用は厳格化すべきである。しかし、理由はともあれ、政府与党が「テロ等準備罪」と命名していたためテロへの国民の恐怖感が流布された。国民は、本物のテロに怯え、加えて、テロ等準備罪の適用に怯える、二重の恐怖を煽情された。
こうしてみると、「テロ等準備罪」が生まれたこと自体が、現代日本の「テロへの屈服」であった。その意味で、筆者が今回のテーマに採り上げたことは、まさに政府与党が言うところのテロの思惑に乗ってしまった失態である。
逆に、今後とも、自治体・住民は「テロを恐怖せず」という姿勢を持ち続けることが大事であろう。例えば、東京マラソンにせよ、オリンピック・パラリンピックにせよ、コンサートにせよ、テーマパークにせよ、警備は重要である。しかし、それをごく「平常心」で行うことが肝要なのであろう。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)など。






















