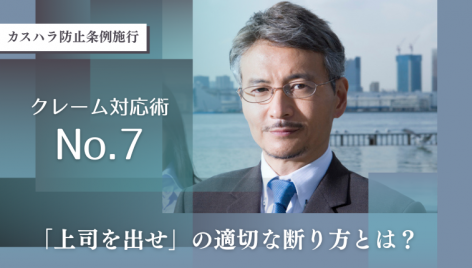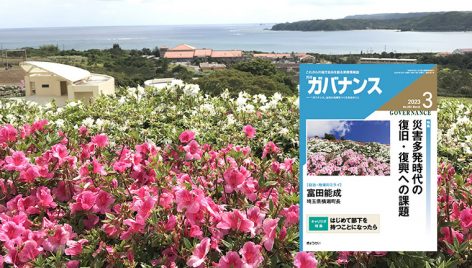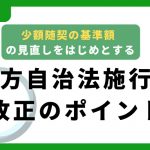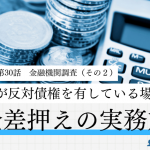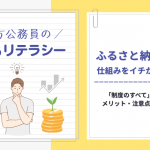新・地方自治のミライ
宴のミライ|新・地方自治のミライ 第102回
地方自治
2025.10.10

出典書籍:『月刊ガバナンス』2021年9月号
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
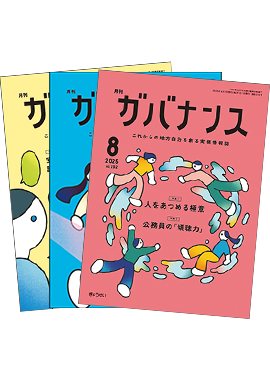
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2021年9月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

第三次東京オリンピックが、7月23日から8月8日にわたって、開催された。新国立競技場の設計紛糾、エンブレムの盗作疑惑、招致活動汚職疑惑、森喜朗・組織委員会会長の女性差別発言・辞任、開会式演出関係者の虐待・差別言動など、ありとあらゆる禍事(まがごと)を引き寄せたかの感がある。極めつけは、COVID-19である。
こうしてみると、不幸に塗(まみ)れているようにも見える。とはいえ、東京だけは台風直撃を免れ、適度な波浪のおかげでサーフィン競技ができた。また、東京39℃の酷暑も大会閉幕後の8月10日であった。何より、「無観客」になって、多数の熱中症患者の発生を避けられた。「塞翁が馬」であろう。
イベント行政の麻薬効果

古来より、為政者はお祭り(イベント)が大好きである。「政」は、「まつりごと」であり、政治・行政と祭事・催事は不可分である。イベントは政治利用されやすい。
一方では、イベント開催により、深刻な課題から民衆の目を逸らせて、様々な不満を紛らわすことで、為政者の安泰を図る。麻薬効果である。イベントによって、いろいろな高揚感や満足・感動が得られれば、他で様々な不満や課題があるとしても、一時的に忘れられる。為政者が最終的に東京オリンピックに期待したのは、アスリートの活躍や「国威発揚(メダルラッシュ)」によって、「空気が変わる」ことであっただろう。
もちろん、イベントが終了したときに、以前から存在する課題は消えてはいない。むしろ、イベント開催によって、課題が放置されたゆえに、あるいは、課題をイベント自体が悪化させたがゆえに、さらに深刻になっていることもあろう。とはいえ、イベント終了後も、興奮から醒めるまでの時間が長ければ、麻薬効果は持続する。さらに、次のイベントが予定されれば、それに向かって誘導できる。イベントの「つるべ打ち」によって、幻惑し続ければよい。イベント依存症である。
イベント行政の転嫁効果
他方では、イベントを抑圧すること自体が、深刻な課題の解決に向けて、真摯に取り組んでいるかのごとき為政を演出する。転嫁効果である。古来から、為政者は歌舞音曲を抑圧し、風俗・文芸の取締に勤しむことは多い。イベントに課題発生の責任を転嫁し、イベント抑制が課題解決策であるかのように、為政者は民衆を誘導する。民衆も「自粛警察」で呼応する。
抑圧対象はイベントに限らない。芸能、演劇、コンサート、ライブ、スポーツ大会、披露宴、歓送迎会、お盆帰省、飲酒・会食なども同じである。実際、1940年開催予定だった第一次東京オリンピックは、軍部の圧力によって返上を余儀なくされた。今回でも、1年延期から始まって、感染症専門家・一部マスコミ・野党などの再延期論・中止論・無観客論など、イベント抑圧それ自体が、重要な課題であるかのような政策論争の空間が形成された。
イベント行政の課題抑圧効果
イベント開催自体が、課題解決に効果を持つことはほとんど期待できない。逆に、イベント抑圧自体も、課題解決に効果を持つことはほとんど期待できない。例えば、オリンピックを開催すれば、シングルマザーの貧困問題が解消するわけでもなければ、オリンピックを中止にすれば、この問題が解消するわけでもない。恐らく、COVID-19に関しても同様であろう。要するに、イベントの是非は、課題解決には、どうでもよいのである。
重要なことは、イベント開催の是非が大きな争点となることによって、より重要な課題が浮上できなくなることである。イベント行政には、課題抑圧効果がある。麻薬派と転嫁派の是非論議が、擬似的な政策論争空間を占有し、より重要な課題の浮上を抑圧する。この課題抑圧効果が顕著に可視化したのは、後述するイベントの経済効果が雲散霧消したからである。
イベント行政の経済効果論

現代の為政者は、通常はイベント開催において、麻薬効果と転嫁効果を前面に打ち出すことは少ない。むしろ、イベントにより、様々な建設・広告需要や、観光・インバウンド需要が発生する経済効果を喧伝することが普通である。イベント開催費用捻出には、最終的には公金を投入し得るので、費用負担をはるかに上回る経済効果が、行政的弁明のためには、不可欠である。
イベント行政は、通常、経済政策としての費用対効果が、中心的な論争課題となる。イベントの内容や感動などの麻薬効果は副次的である。理屈上は、公金を投入すれば、必ず官公需は発生するので、建設・広告などの受注業界には「経済効果」がある。イベント自体の地元・国内への経済効果がゼロでも、受注業界などにとっては問題はない。これで困るのは、公金費用負担を転嫁される一般社会である。この場合には、受注業界と一般社会でゼロサムの分配問題が発生する。
経済効果論とは、費用負担をする一般社会にもメリットがあると主張する言説である。しかし、経済効果は、しばしば「捕らぬ狸の皮算用」である。受注業界はイベント開催前に官公需受注を先に確保するので、経済効果が蜃気楼であっても、問題はない。宴の後に一般社会に残されるのは、雲散霧消した経済効果と、膨大な開催費用負担である。
イベント行政の経済効果霧散の効果
第三次東京オリンピックは、「無(有料)観客開催」となった。入場料収入は蒸発した。インバウンド観光客を当て込んだ需要も破裂した。まさに、経済効果が無く、費用負担のみが残る構造となった。最も悲劇的なイベント行政における経済(無)効果である。テレビ放映収入を確保した国際オリンピック委員会(IOC)は、「経済効果」を確保した。しかし、現実の人流によって経済効果を期待する地元東京や日本国内にとって、経済効果はない。単に開催負担のババを引かされた。
このことは、IOCや海外テレビ局などに比べて、日本の関係者が愚昧であったことを明らかにする。言うまでもなく、このようなババは、外国勢力に押し付けられたのではない。頼まれもしないのに、立候補する都市・東京都が存在し、それを後援する国政為政者が存在したからである。さらに言えば、オリンピック自国・地元開催を期待する経済界・報道界・スポーツ界などの関係者や、それを支持する一般民衆がいたからである。
費用がゼロならば、イベント開催は遊興効果があろう。イベント自体の収益で費用を回収できる、という「旨い儲け話」に引っ掛かる体質から、「進んで自ら」ババを引かされる。「飛んで火に入る夏の虫」とは、「世界都市」・東京のことである。招致活動を推進する勢力は、開催に伴う官公需受注という「経済効果」は確保できているので、ババを引く側ではなく引かす側である。
おわりに
第三次東京オリンピックは、多くの東京都民や日本国民が、「行徳の俎(まないた)」であることを実証するカモネギ宣伝効果を持った。IOCなど国内外のイベント推進の関係者は、しっかりと「経済効果」を確保している。「行徳の俎(まないた)」なのは、受注業界等からのトリクルダウンを受けられない我々一般民衆である。
戦後日本では、各地の自治体は、こうしたイベント招致に奔走してきた。そして、しばしば、大きな地元負担を背負った。しかし、そのような負担経験にもかかわらず、あるいは、それゆえに、見果てぬ経済効果を夢見て、何度もババを引く。カジノと同じである。イベント推進の為政者にとっては、イベントは、「経済効果」・麻薬効果・課題抑圧効果が期待できるので、おいしい話であろう。こうして、地元一般民衆はミイラのように干からびていく。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
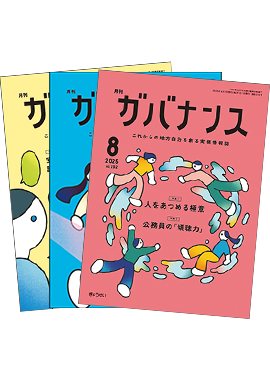
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫