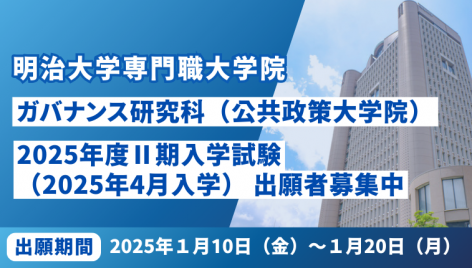新・地方自治のミライ
ワクチン接種証明のミライ|新・地方自治のミライ 第103回
地方自治
2025.11.17

出典書籍:『月刊ガバナンス』2021年10月号
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
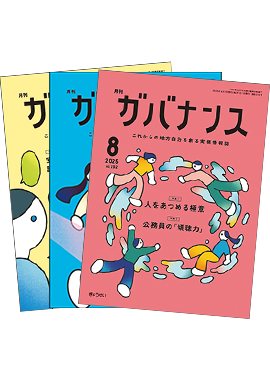
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2021年10月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

去る9月9日に、政府新型コロナウイルス感染症対策本部は「ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方」をとりまとめた。飲食、イベント、人の移動、学校において、「ワクチン・検査パッケージ」を活用して、行動制限を緩和する基本的方向性を打ち出した。
この時期に打ち出されたのは、自民党総裁選や、来るべき総選挙において、政界関係者が全国的に移動(遊説)するから、それに伴って感染拡大をしたと批判されることへの「政治的ワクチン」に過ぎない。
ワクチン・パスポート
「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」が、いわゆる「ワクチン・パスポート」である(注1)。2021年7月26日から、各市区町村で受付が始まった。海外の渡航先への入国時に、相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用されるよう、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明する文書を交付するものである。
注1 詳しくは厚生労働省HPを参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
相手国がどのような取扱をするかは、実は相手国の勝手なのであるが、相手国が望む証明書を持参すると便宜を取り計らってもらえるならば、日本政府として日本国民などに、発行するのは当然と言えよう。もっとも、こうした証明書が国際的に乱立することは、不合理な障壁になりかねない(注2)。
注2 ワクチンにもスプートニクⅤ、シノバックス、シノファームなど各種あるし、この他、陰性証明や抗体証明などもありうる。
甲殻類型国家
上記接種証明書は、国内向けに発行=発効するものではない。「ワクチン・検査パッケージ」で想定されているものとは異なる。そもそも、国内的には、接種を受けた本人には、接種時に発行される「接種済証」や「接種記録書」がある。
近代国家の大原則は、国境管理を国家が掌握し、国内通行管理(「関所」)の設営を国家が排除することである。これを甲殻類型国家という(注3)。「ワクチン・パスポート」は国境をまたぐときにのみ通用する、というのは極めて自然である。
注3 ジョン・トーピー(藤川隆男訳)『パスポートの発明─監視・シティズンシップ・国家』法政大学出版局、2008年。
もっとも、そのようなパスポート類似の書類を、市区町村が発行するのは、いささか事務責任としては筋違いである。本来は、上記の「接種済証」などをもとに、旅券事務の一環として処理すべきであろう。
国内移動の自由を縛る証明書

明治体制は、良くも悪くも中央集権化による近代領域国家を形成した。国内的な移動は自由になった。従って、江戸時代の通行手形は消滅した。現代まで、特定の証明書を持つがゆえに移動可能であり、持たないがゆえに移動できない、という仕組を採ってきていない。
もちろん、本当の意味で国内移動が、自由(本人の意のまま)であるとは限らない。実際、カネがなければ移動は困難である。また、運転免許証を持たなければ、自動車運転はできない。しかし、乗客として自動車に乗った移動は可能である。通常、鉄道・バス・タクシーなどの公共交通機関を利用するときに、本人証明書類は求められない(注4)。
注4 旅客船では氏名、年齢区分、性別、住所を記載した旅客名簿(乗船名簿)が義務づけられているが、基本は海難事故用である。
「ワクチン・パスポート」は、本人証明にとどまらず、本人が何をしたのかの証明を提示させて、国内移動の自由を縛り得る。これは、近代日本の国内的一体性を二重の意味で制約する。第1に、実質的に国内において関所的な地域間の分断を復活させる。第2に、特定の人間行為に応じて扱いを異にするのであり、人々の間の分断を作り出す。
自治体の潜在的分断指向性
近代国家における地方自治は、人々が自治体間を移動することを統制できない。このことは、自治体にとっては、様々な困難をもたらしてきた。例えば、地方圏の過疎化・少子高齢化が生じたのは、若い世代が大都市圏に流出したからであり、地方圏自治体は流出を阻止できない。自治体は人流に悩まされてきた。それゆえに、住み続けられるよう、選ばれるように、施策への努力をする動機付けも存在した。
とはいえ、自治体為政者は、潜在的には人流を統制しようとする。特に、貧困層などの施策にとって「重荷」になる人間を排除しようという誘因を持つ。そして、新型コロナウイルス感染症では、まさに感染者または感染のおそれのある他県民の流入を忌避するという動きが生じた。「県境をまたぐ往来の制限」である。もちろん、法的権限によって県境に検問所が設けられたわけでもなければ、物理的に壁が建設されたわけではない。しかし、県外ナンバー狩り、県境検温、県境間往来自粛要請、帰省自粛要請などが展開されて来た。対外排除・閉鎖主義という自治体の悪癖は、何かの拍子に表面化する危険を持っている。
ワクチン接種証明の危険性

政府が提唱する「ワクチン・検査パッケージ」なるものが、どのようになるのかは流動的である。ともあれ、ワクチン接種証明により行動制限が緩和され、ワクチン接種証明がなければ行動制限が課されるのであれば、人々の間に様々な分断と差別・排除と同調圧力が生じるのは避けがたい。そのような悪しき行動を事業者や一般民衆が行うだけならばまだしも、行政がその後押しをすることになる。行政は本来、民間で生じ得る分断・差別・排除・同調圧力を抑えるように行動しなければならない。しかし、分断対策の最前線に立つべき自治体は、分断指向性を持っているのである。
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種は、本人が自らよく考えて判断すべきとされている。確率的に「科学的有効性」が認められ、行政は推進しているにもかかわらず、本人の任意判断に委ねるのは、矛盾するようにも見える。「ワクチンを接種しないのは、科学的合理性を理解できない無知蒙昧な人間だ」となりがちである。だから、「行政・専門家はもっとわかりやすく啓蒙・説明・宣伝すべきだ」となる。さらには、行動経済学に基づいて人々を接種に仕向ける「ナッヂ(捺智)」を利用する実践もあろう。
しかし、統計的確率的有効性は、大量の事象群を扱う行政・専門家には当てはまっても、唯一の事象しか存在しない個人の選択には当てはまらない。それゆえに任意接種なのである。しかし、「ワクチン・検査パッケージ」が、行動制限の緩和/維持/強化と結合するとき、任意の判断はあり得なくなる。行動制限緩和という利益誘導を受け、行動制限という不利益を被り、個人の意思決定は歪む。そして、あとになって問題が生じても、行政や専門家は、「自分の判断だから自己責任だ」と責任回避する。自治体は、こうした活動のパシリ役にさせられ、あるいは、率先してお先棒を担ぐ。
おわりに
ワクチンは重症化を防ぐなどの効果が期待される、とされている。従って、ワクチンが行き渡れば、一般的に行動制限を緩和できる。接種者・非接種者(注5)が飲食店・イベント・旅行・学校に混在しても、リスクを回避したい人はすでに接種済みである。非接種の人間が重症化しようと、それは自分の判断である。非接種者も感染を避けたいならば、様々な感染予防策を採るであろう。接種者は、非接種者が感染した所為では重症化しない。感染者の絶対数が増えたとしても、重症者・死亡者数は抑えられ、医療体制も持続できる。ワクチン接種証明は、ワクチンに本当に効果があるならば、全く不要である。
注5 希望者に広く行き渡った時点では、「未接種者」ではない。
ワクチン接種の効果は完全ではなく、特に、重症化を抑えたとしても、感染・発症・伝染自体を大きく防ぐとは限らない、とも言われる。それゆえ、接種者が自らは重症化しないから安全だと放埒になり、感染拡大の原因になる可能性はある。さらには、ワクチンの効果は絶対ではないので、接種者にも感染対策を引き続き求めざるを得ない。こうして、ワクチン接種証明だけに頼ることもできない。ワクチン接種証明の国内利用は、様々な分断と差別を生みつつ、恣意的な制限/緩和の組み合わせである「ワクチン・検査パッケージ」による閉塞状況は続く。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
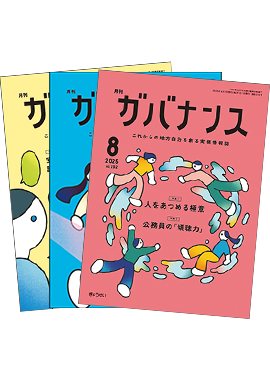
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫