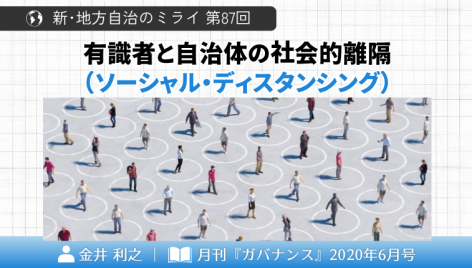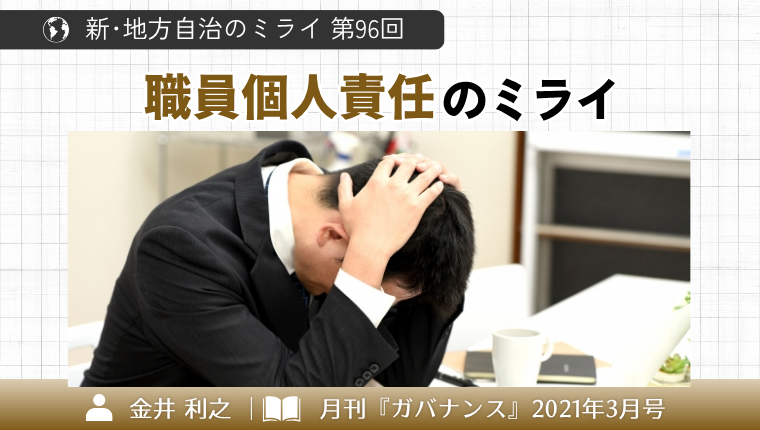
新・地方自治のミライ
職員個人責任のミライ|新・地方自治のミライ 第96回
地方自治
2025.08.25

出典書籍:『月刊ガバナンス』2021年3月号
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
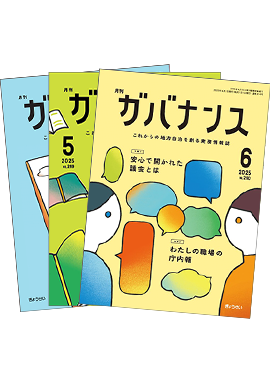
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2021年3月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

兵庫県庁において、2019年10月初めに庁舎貯水槽で排水弁の閉め忘れをしたため、1か月にわたって給水が続き、約600万円の水道代が余計にかかった事件があった。業者に委託して年に1回の点検を行うが、立ち会った職員が、自分で後のチェックをするとして業者を先に帰しながら、排水弁を閉め忘れていた。神戸市水道局から、水道代が異常に跳ね上がっているとの連絡があり、1か月後に気付いたという。
県は職員の責任は重いと判断して、2020年11月に職員を訓告処分にするとともに、裁判例などをもとに県が半額について職員個人に賠償を請求して、当該職員は支払をしたという(注1)。
注1 FNNプライムオンライン2021年2月8日16:00配信。
本件の処理に関して、兵庫県庁内でどのような意思決定過程があったのかは、詳らかではない。したがって、本件それ自体ではなく、一般的・構造的な現象として、自治体の管理運営と職員の仕事のミライを論じてみたい。
監査報告書
本件は、2020年11月の県監査報告に記載されている。県庁各部局に対する99の指摘事項が羅列されている。例えば、収入未済額が多額である、特定財源の収入が予算より減少したため事業に関係のない収入証紙収入を充当していた、契約保証金を徴収していない、埠頭用地の利用率が低調である、工事請負費が過大支出だった、などである。本件はわずか3行、「4 庁舎管理について(管財課)(改行) 県庁西館の受水槽の排水弁を閉め忘れたまま、給水したため、水道料金・下水道使用料約600万円(前年同時期との比較による試算額)が不経済な支出となっていた」と書いてある。
監査上の問題にも軽重がある。監査報告では、「主な指摘事項」を要約しているが、そこに本件は掲記されていない。さらに、「留意・改善・要望事項」にも、明示的な言及はない。要するに、本件はその程度というのが、監査委員の判断である。
組織と個人責任
組織として仕事をしているときに、個々の職務遂行によって損失や損害が生じることはあるが、その損失や損害を職員個人が負担をするのは異例である。仕事にある程度のミスが生じるのは避けがたい。こうした過誤は一定確率で存在するので、たまたまミスを犯した職員のみが集中的に負担すべきではない。組織とは、多数職員が共同作業することで、個々人の職務遂行によって生じるもしれない損害を、当該職員個人ではなく、職員共同で分散する機能を持っている。
そのような組織の機能を踏まえれば、損害補塡を職員個人に負わせることは、組織としての体を為していないことを意味する。こうした取扱を、管理職、監査当局、首長等理事者層、職員個人、職員組合などが、当然として提案または受容するのは、組織のミイラ化の徴候である。
組織改善

組織自体としては、ミスは少ない方が良い。組織の管理運営・指揮監督の役割は、ミスの確率を下げるように、仕事のあり方を常に見直し、様々な体制を作ることにある。そもそも、監査の役割は、組織として改善を促すことである。
例えば、チェックは職員2人で行うなど、改善策は単純かもしれない。業者側も、排水弁を閉めるところも含めて受託業務である以上、仮に職員が「先に帰っていい」と言っても、両者で確実に立ち会うべきだろう。
改善策を構造的に作り出すことが、上司や組織の役割である。場合によっては、人事上の処分もあり得る。しかし、それは損害の弁償ではない。損害に関しては、組織として処理するのが当然であろう。
職員個人の支払の可能性
確かに、職員個人が弁償責任を常に負わない、とは言い切れない。例えば、職員が犯罪として公金流用すれば、弁済させるのが自然である。また、故意ではないとしても、限りなく重大な過失の場合には、支払責任を負う場合もあろう。
アメリカの納税者訴訟をモデルとした住民監査請求・住民訴訟の場合にも、違法な職務によって、団体としての自治体に財務会計的な損害を与えたときには、理事者、職員、相手方に求償を求め、団体としての自治体の損害を回復する法制になっている。
しかし、実際の住民訴訟は、自治体の違法な政策決定・業務処理を裁判所によって確定し、自治体の政策・業務を改善することが、真の機能である。納税者ではなく、住民としての立場で自治体運営の適正化・適法化を裁判所に求める。納税者としての損害を取り戻すのではなく、住民の立場で自治体を統制する。財務会計的な求償は、訴訟技術上の口実にすぎない。
自治体が、不注意に水道代を高く支払うのは妥当ではない。しかし、それは組織としての問題である。個々の職員に支払わせ、自治体の損害がなくなっても、問題が消えるわけではない。むしろ、職員に負担を負わせて組織改善をしなければ、管理運営の懈怠を積み重ねることになる。
自業自得という納得

組織が職員個人に支払を求め、職員がそれに納得して支払い、住民がそれをやむを得ないと受容する社会構造が、本件のような取扱を生んだ。職員の負担金額は大きすぎるという反応はあっても、ある程度の個人負担はやむを得ないという見解もある。兵庫県庁によれば、都立高校で同種の事案について、半額を職員側に負担させた先例や裁判例を参考にし(注2)、また弁護士の見解も受けたという。裁判所・法律家の見解や、他の自治体の発想も、今回の取扱の背景にある。
注2 なお、半額を職員が負担した点は同じだとしても、都立高校の案件では、教職員は複数だったこと、個人負担は10万円程度であったことなど、本件の先例にならないという見方もある。仮に、個人負担額の金額を先例にするならば、300万円ではあり得ない。
その社会構造は、第1に、職員バッシングである。住民が行政のあり方に厳しい目を向けるのは、民主的統制の観点からは当然ではある。しかし、組織の管理運営を担う首長・幹部職員も、部下である職員への管理監督責任を負うのではなく、住民と一緒になって職員を責めるポピュリズムである。
第2に、歴代国政指導者が煽動してきた自己責任・自助の論調である。有力者ではない住民や一般職員は、組織・社会・政策あるいは環境に起因した困難に直面しても、自らが負うべき責任や負担として納得するという規律付けである。住民や一般職員は直接の被害に加えて、自業自得という非難を受けて、二重に被害を受ける(被害者バッシング)。
第3に、非正規化・個人事業主化である。自治体の仕事も、立場の弱い非正規労働者が多くを担っている。ミスをすると、契約解除・打ち切りになったりする。それゆえ、泣き寝入り的に自己負担を甘受させられる。この論理は、結局、正規職員についても個人責任の追及につながる。いわば、形式的には組織の正規被用者でも、実体的には、組織と個別取引をしている個人事業主という負担転嫁に変質している。
おわりに
昭和後期の自治体であれば、ぬるま湯の職場であって、身内をかばい合い、ミスを隠蔽し、ミスを改善せず、漫然と無駄遣いをしていた。また、仮に行政の無駄遣いが判明しても、官尊民卑のなかで、受注業者側に責任を負わせて、表面上は済ませていた。本件で言えば、水道の栓の閉め忘れを業者の所為にして、業者に600万円を支払わせる。もちろん、それでは業者いじめになるので、長期多角決済的に埋め合わせる。指名や談合により、発注機会を回すとか、発注金額を高くするとかである。もちろん、こうした昭和後期の悪しき慣行は是認されるものではない。
しかし、責任追及は、住民が自治体という組織を統制するものであって、トカゲの尻尾切りを許容するものではない。弱者に負担を押しつける構造は、住民・受給者・利用者・受苦者、受注業者、非正規職員・正規職員などに対して、健全な結果を生まない。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
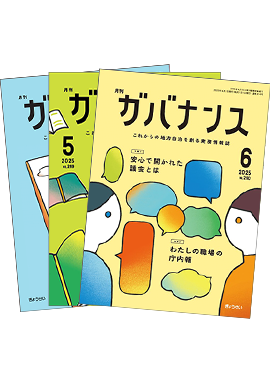
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫