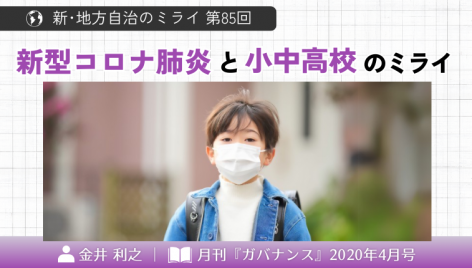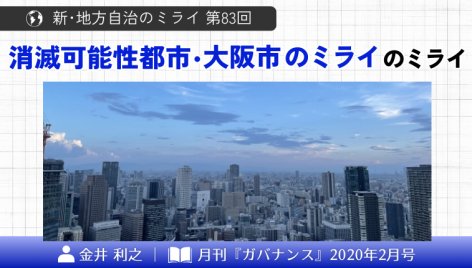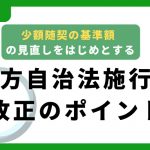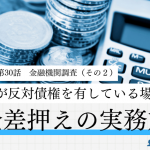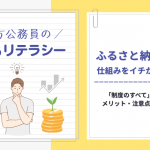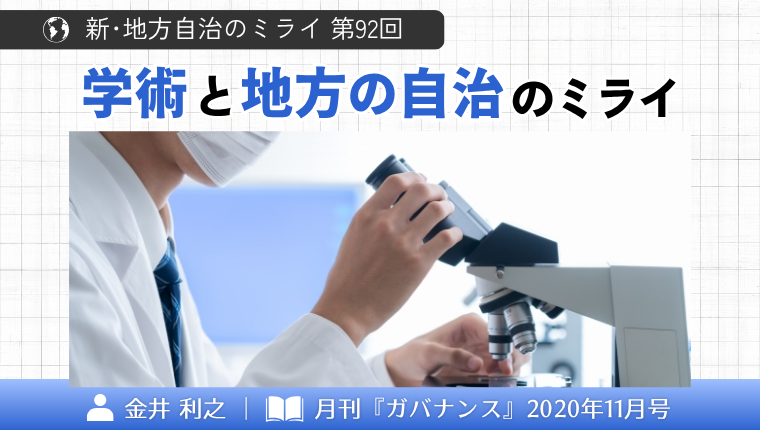
新・地方自治のミライ
学術と地方の自治のミライ|新・地方自治のミライ 第92回
地方自治
2025.07.21

出典書籍:『月刊ガバナンス』2020年11月号
★「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
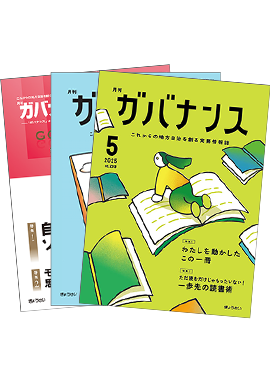
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読)
編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2020年11月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

日本学術会議の新会員について、8月31日に同会議から推薦された105名のうち、6名の任命拒否を菅首相が行ったことが、10月1日に明らかになった。日本学術会議は、「科学者の内外に対する代表機関」(日本学術会議法第2条)として、政府からの独立性が必要である(同第3条)。1984年までは選挙制であったが、現在は推薦に基づく任命制になっている(同法第7条②)。とはいえ、独立性の観点から、形式的任命という国会答弁もあり、推薦候補の拒否は原則ではなかった。
しかし、第2次安倍政権のもとで、補充の際に推薦候補の任命を拒否する、推薦に対する拒否は可能と内閣法制局に解釈させる、定員以上の多数の候補者を出させる、日本学術会議と事前調整する、などの介入をしてきたことも明らかになった。独立性を有すべき団体・組織・機関の人事の自律性の問題は(注1)、自治体にとっても他人事ではなく、今回はこの問題を考えよう。
注1 学問の独立性という観点からは、日本学術会議に劣らず、学内投票・学長選考会議選考・法人申出・文科大臣任命制の国立大学学長の人事の自律性も深刻である。
公選制と人事の自律性
団体・組織・機関が独立性を保持しようとすれば、人事の自律性は重要な要素である。自治体の首長・議員が有権者からの直接選挙によることは、国や他団体からの介入を否定して自治体の自治を保障する。
戦前の府県知事は官選であり、内務省が内務官僚を任用した。また、1888年市制では、市会は有権者(制限選挙権)の公選制であったが、市長は、市会が候補者3名を推薦し、内務大臣が天皇に上奏裁可を求めて決めた(注2)。
注2 上奏制とは、内務大臣が推薦して、天皇が決定するものである。内務大臣の推薦(上奏)通りに天皇が追認する慣行ができれば、人事権は内務大臣にある。さらに言えば、内務大臣の上奏の内容を、内務省高官あるいは内務省地方局が実質的に決定し、内務大臣はその上申を追認するだけならば、人事権は内務省高官または地方局にあることになる。
1952年地方自治法改正は特別区の自治権を制限し、都の内部団体と位置づけたため、区長公選制も廃止されて、区長は区議会が都知事の同意を得て選任する区長選任同意制が導入された。区長直接公選制の復活は1974年である(注3)。
注3 戦前の北海道二級町村制においては、町村長を北海道長官が任命する官選制であった。また、二級町村制さえ施行されない区域もあった。
推薦制と限界

候補者を複数推薦し、そのなかから他者が選抜するならば、当該他者が人事権者となる。推薦も何もなく、他者が任用する単純任用制が最も強い介入であり、官選知事はこの形態である。それに比べれば、1888年市制での市長に対する人事権は、絶対的に内務大臣が握るわけではない。候補にない人物を市長に据えられないからである。とはいえ、3名いれば、市会の優先1位の人物を否定して、より自分に好ましい人物を据えられる。推薦が1名であれば、選択権を弱められる。
もっとも、推薦は何名でも大差はないともいえる。3名であれ1名であれ、内務大臣は気に入らない人物を市長に据えない。市長が空席で困るのは市であるならば、市会は、内務大臣が納得する候補者を選定せざるを得ない。あるいは、過剰に自制するしかない。または、了解を得られるかの当たりをつける内々の事前協議をせざるを得ない。推薦制の人事では自律性は危うい。
地方財政審議会と団体推薦制
地方財政審議会は、国の審議会(8条委員会)であり、総務大臣が委員への任命権を有する。ただし、審議会(自治体でいえば附属機関)委員の人事権(依嘱権)を行政側が握ることは、自由任用・政治任用を意味するとは限らない。同審議会委員の場合には、
①識見
②両議院同意
③団体推薦(5名中最低3名)
という条件が付されている(注4)。
注4 中央労働委員会は団体推薦制である。使用者委員は使用者団体の推薦、労働者委員は労働組合の推薦、に基づき、首相が任命する。労働戦線の分裂の問題もあり、必ずしも労働組合が推薦した人物が委員として任命されるとは限らない。
本論としては③が興味深い。全国知事会と全国都道府県議会議長会、全国市長会と全国市議会議長会、全国町村会と全国町村議会議長会、の共同推薦が1名ずつである。総務大臣が共同推薦された人物を任命しないことは制度上はあり得る。
しかし、現実にはそうしたことはまず起きない。なぜならば、団体推薦制とは、推薦する団体の意思を尊重する制度精神だからである。実態は、総務大臣の背景にある国政与党と、地方六団体の背景にある地方政治勢力との権力関係次第である。ただし、戦後日本の場合には、国・地方を通じて通常は自民党一党支配なので、対立は表面化しにくい。
国と地方の協議の場と団体代表制

民主党政権時代に発足した国と地方の協議の場は、任命制も推薦制も採らない。地方側は、地方六団体を「代表する者」各1名合計6名である。議長・議長代行は、国側構成員から首相が指定する。副議長は、地方側構成員が互選する。
これに対して、地方制度調査会の委員は、国会議員、自治体議員、自治体首長、自治体職員、地方制度学識経験者のうちから、首相が任命する。自治体議員・首長が委員になるため、地方六団体関係者が任命されることもあるが、制度上は団体推薦制でもない。団体推薦制の地方財政審議会は、地方制度調査会よりは自律性は高い。しかし、国と地方の協議の場は、団体推薦制でもなく、団体代表制であり、最も自律性が高い。有権者から選挙される自治体首長・議員が、全国的連合組織(団体)を構成し、その代表を互選・輪番または選挙する。
国会同意制と限界
自治体の場合、最終的に自らが選挙制で構成できるので、自治体代表を間接選挙で選出することは可能である。もっとも、これは国政の政府与党・官僚制にとっては掣肘であり、なるべく、任命制や推薦制にとどめようとする。国と地方の協議の場で、団体代表制を導入できたのは異例といえる。
しかし、選挙によらない団体・組織・機関の場合、人事の自律性、特に、政府与党からの人事の自律性を確保することは容易ではない。
最高裁判所の場合には、長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命し、判事は内閣が任命する。三権分立として政府から最も独立性が確保されるべき裁判所は、実は人事の自律性を持たない。国民審査に付されるので、それが一種の事後信任の投票制として機能するともいえるが、極めて脆弱である。それゆえ、弁護士、裁判官、検察官、外交官、行政官、学者、女性などという「枠」を前提に、団体推薦制的な要素も加味されてはいるが、極めて脆弱である。政権幹部の自由任用に限りなく近い。法曹資格も必須ではない。
会計検査院・人事院や独立行政委員会も、政府からの職務遂行の自律性が求められる。しかし、通常、人事は政府が掌握している。例えば、会計検査院の検査官は、両議院の同意を経て内閣が任命する。辛うじての歯止めは国会同意制であり、人事院、地方財政審議会、国家公安委員会などの行政委員会、さらには、地方分権推進委員会・国地方係争処理委員会などでも採用されている。しかし、国会両院多数派と政府が同一党派であれば、国会同意制だけでは、自律性は達成しにくい。
おわりに
団体・組織・機関の独立性・自律性を保持することは容易ではない。自動制・選挙制でなければ、誰か他者が人事権を持つ任命制になりやすく、任命権者に従属しやすい。それゆえに、任命権者の判断を制約すべく、任命権者が左右できない条件を課すことが重要である。推薦制は制約条件の一つではあるが、それだけでは必ずしも充分ではない。
行政職員の資格任用制は、公務員試験成績や専門資格による条件であるが、合格者・有資格者が採用人数より何倍も大きければ、実質的には任命権者の裁量は大きくなる。
推薦制も任命制も、団体・組織・機関の独立性・自律性の必要性に応じて運用されなければならず、それは、法令では規律を書き切ることは難しく、実例や不文律として形成されるべきものである。法文文理解釈や、前例踏襲の是非判断ではなく、制度総体として、どの程度の独立性・自律性が確保されるべきかという問題である。推薦制において、定数分だけ推薦して全員承認という形式的任命制の不文律は、独立性を保障する一つの工夫である。日本学術会議の会員任命を巡る政府の介入は、自治体にとっても他山の石として内省すべき事件である。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
★「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
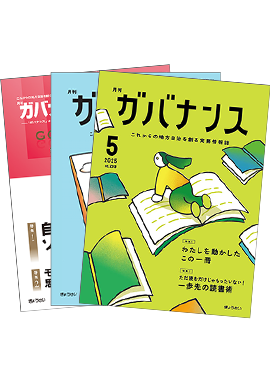
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読)
編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫