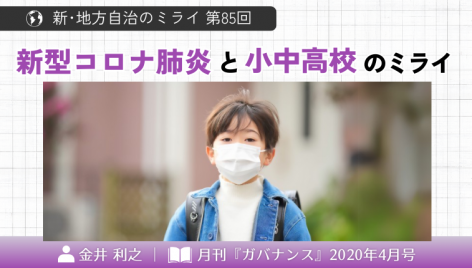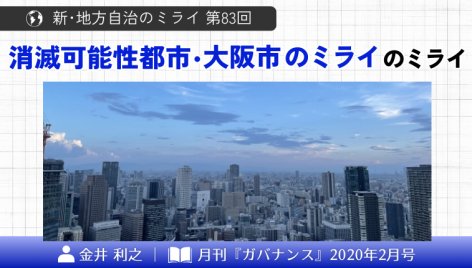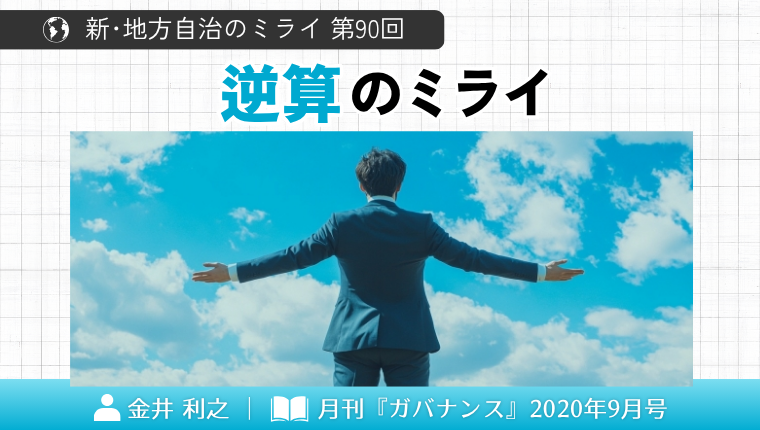
新・地方自治のミライ
逆算のミライ|新・地方自治のミライ 第90回
地方自治
2025.07.07

出典書籍:『月刊ガバナンス』2020年9月号
★「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
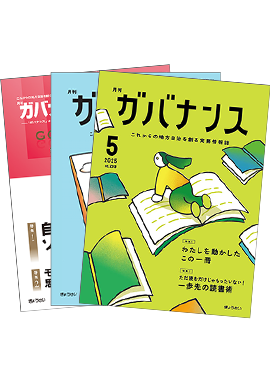
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2020年9月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

2020年6月26日に、第32次地方制度調査会(以下、地制調)は「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申」(以下、答申)を安倍晋三首相に提出した。
「過去からの延長線ではなく、2040年頃を展望して見えてくる変化・課題とその課題を克服する姿を想定した上で、現時点から取り組むべき方策を整理する視点」(答申1頁)は、極めて野心的である。そこで、今回は答申を取り上げることにしよう(注1)。
注1 拙論「巻頭言」『地方議会人』2020年9月号も併せて参照されたい。
「地方消滅」論と逆算方式
自治制度官庁は、いわゆる「2040構想研究会」(注2)の頃から、高齢者人口がピークを迎える2040年頃から逆算する、いわゆる「バックキャスティング」の思考方法に基づき調査研究を行ってきた。しかし、この当時、政府は全体としては「まち・ひと・しごと創生」(「地方創生」)を政策に掲げていた。
注2 正式には「自治体戦略2040構想研究会」、2017年10月設置。第一次報告(2018年4月)、第二次報告(2018年7月)。
2014年のいわゆる増田氏第一レポート(注3)は、2040年の地域人口(20~39歳女性人口)の未来予測に基づいて、多くの市町村の「消滅可能性」を指摘した。さらに、東京圏の繁栄は、地方圏からの若者の人口流入で成り立っていることを論じた。地方圏の市町村で子どもが産出されないことは、東京圏に流入すべき原資が枯渇することであり、東京圏の経済も成り立たない。そのような未来予測に基づき、現時点としての対策を逆算すると、地方圏での人口再生産を進めるしかない。こうして、「地方創生」は、市町村ごとの人口維持・拡大方策としての「地方人口ビジョン」「総合戦略」に帰着した。 注3 日本創成会議・人口減少問題検討分科会提言「ストップ少子化・地方元気戦略」(2014年5月)。
避けるべき未来予測に立って、そこから、逆算して現時点で対策を打つと、政府の建前としては、未来予測は「外れるはず」となる。つまり、地方は消滅しない。それゆえ、逆算は意味がなくなる。逆算方式に基づき現時点で対策を確立することは、未来予測の可能性を有り得なくする自家撞着を引き起こす。
「地域の未来予測」の逆算方式

「地方創生」によって、冷静な未来予測は不可能になるかに見えた。そのようななかで、「2040構想研究会」は、再度、2040年を標的にして未来予測を試みた。「地方創生」を進める限り、人口減少の地域社会の将来を直視しない。それでは、2040年の未来に向けて現時点から対策を採れず、手遅れになる。それを避けるために、バックキャスティングを行った。
「2040年を展望して見えてくる変化・課題」は、未来予測として与件とされる。人口減少の予測のなかで人口減少を避けるのが「地方創生」であるならば、「2040構想」は、人口減少を前提として「克服する姿」を設定することで、自家撞着を避ける。額面上は「地方創生」に邁進している一部自治体からは、「梯子を外された」という批判を受ける。しかし、多くの自治体は人口減少を与件にしている。そこで、一定の説得力を持つであろう。
現時点の延長線上での逆算
「過去からの延長線ではなく、2040年頃を展望」することを、現時点の人間ができるのか、という根本的な問いがある。20年先のあるべき姿を展望することは確かに可能ではあるが、過去から現在に至る趨勢から離れる方法があるのか不明である。少なくとも、2040構想研究会も地制調も、特段の方法論を提示していない。結局、現時点の人間が、過去から現在への趨勢をもとに、あとは適当に思念する。つまり、過去からの延長線上なのである。
過去からの趨勢を現時点の人間が言及した2040年の未来の姿をもとに、そこから逆算して現時点の行動を決めることは、過去からの趨勢の延長線上で現時点の政策を構想することと同じである。
2040年に投影して「客観的与件」のように仕立てて、それに拘束される形で現在の行動を正当化する。しかし、それは過去からの延長線から現時点で考える人間たちの自己言及である。〈現在こう思うから、現在こうする〉では身も蓋もないので、〈現在こう思うから、将来こうなるので、現在こうする〉という。しかし、本質は同じである。
現時点の限界

答申は過去からの延長線上にあり、至って「月並み」な中身であり、すなわち、地方行政のデジタル化、公共私の連携、地方公共団体の広域連携、である(注4)。いずれも、ありふれた政策提言である。
注4 地方議会に至っては、2040年への展望からの課題提起すらなく、ただ、直近の問題を提示しているだけである。
地方行政の機械化・電算化・デジタル化は、20世紀後半以来の一貫した延長線であり、近年でも、住民基本台帳ネットワーク、個人共通番号(マイナンバー)など、ありふれた方向性である。公共私の連携は、戦時中の町内会・部落会の動員に始まって、コミュニティ施策、公民協働、地域協議会など、これまた百年河清のごとき懐メロである。自治体の広域連携は、昭和・平成の大合併、道州制論、各種の広域行政手法の考案など、食傷気味である。つまり、なにひとつ、2040年から逆算するまでもない。
しかも、CIVID-19の想定外の登場によって、1年先ですら予測できないことを露呈した。世界史は疫病で動くといえるくらい、感染症は重要な駆動力である(注5)。しかし、2040年の感染症から逆算するどころではない。過去の延長線で、SARSや新型インフルエンザなどの感染症を検討するような関心もなかった。結局、〈現在こう思う〉デジタル化の議論に回収され、過去の延長線の呪縛を内省する機会としても生かせなかった。
注5 ウィリアム・H・マクニール『疫病と世界史(上)(下)』中公文庫、2007年、佐々木昭雄訳、ジャレド・ダイアモンド『銃・病原菌・鉄(上)(下)』草思社文庫、2012年、倉骨彰訳。
「未来予測」は一つか
政策提言であるから、〈現在こう思うから、現在こうする〉で充分なところ、逆算方式によって〈現在こう思うから、将来こうなるので、現在こうする〉と自己言及するのは、不要にも見える。しかし、逆算方式は、あたかも未来予測が一つであるかのごとき鏡像(自画像)を見せることで、〈現在こうする〉ことを唯一無二にする手法である。
しかし、デジタル化も公共私の連携も広域連携も、過去の延長線から現在まで存在する有力な潮流の一つではあるが、唯一ではない。むしろ、実態は、デジタル化への懐疑・批判、公共私の連携への疲労、広域連携への抵抗など、少なくとも別の延長線が存在し、それらのせめぎあいのなかで、累次の政策選択は為されてきた。それゆえ、デジタル化・公共私連携・広域連携の推進派から見れば、遅々としており、将来に向けて間に合わないという焦燥感が生じる。そして、対処を妨害するのが、デジタル化・公共私連携・広域連携の懐疑派である。
懐疑派から見た〈現在こう思うから、現在こうする〉と、推進派から見た〈現在こう思うから、現在こうする〉は一致しない。それゆえ、推進派から見た〈将来こうなる〉に話を逸らし、〈現在こうする〉。〈現在こう思うから、現在こうする〉という路線を強行する仕掛である。
おわりに
公正な逆算方式であれば、〈現在こう思うから、将来こうなるので、現在こうする〉について、少なくとも二つの未来予測(シナリオ)が必要である。できれば、鍵となる駆動力(キー・ドライビング・フォース)に応じて、4種程度の未来予想が提示されるべきだった。少し考えるだけでも、地球温暖化の危機的進行、自然災害の多発、環境汚染、米中覇権闘争、疫病の拡散、周期的な経済恐慌と経済格差・貧困、食糧難・水不足、ポピュリズム的民主主義と安全重視による国家の強権支配、情報産業(プラットフォーマー)の支配または情報産業と政府の結合による情報統制社会と個人的不自由、AI化の進行による人間疎外(シンギュラリティ)など、様々な延長線が存在する。逆算方式で未来を論じるならば、思考の呪縛からの解放が必要である。さもなければ、現在の思体(おもいたい)を保存したミイラを見せるだけになるだろう。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
★「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
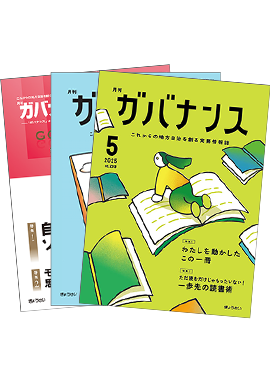
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫