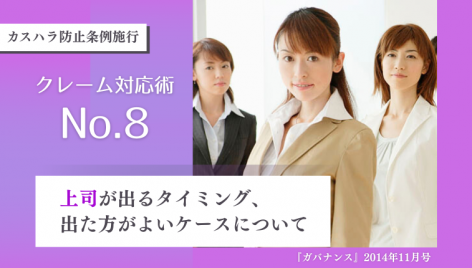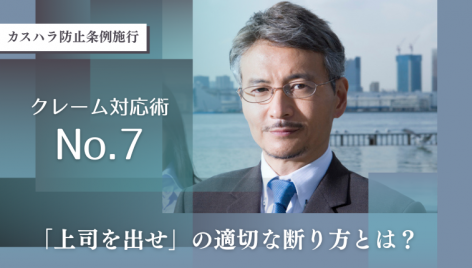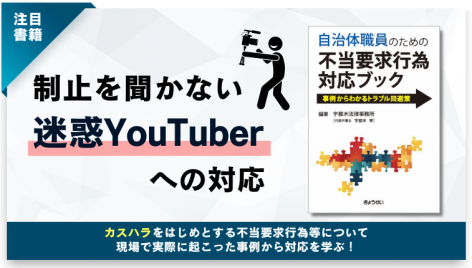そこが知りたい!クレーム対応悩み相談室
クレーム対応における説明・説得の技術【カスハラ対策】|クレーム対応悩み相談室3
キャリア
2025.04.30

この記事は5分くらいで読めます。

出典書籍:月刊「ガバナンス」創刊20周年記念別冊付録『そこが知りたい!クレーム対応悩み相談室』
※本書は月刊「ガバナンス」2019 年4月号〜2020 年4月号までに掲載した連載をまとめたものです(一部加筆・修正)。
Chapter3 こちらの説明を、なかなか理解していただけません
2025年4月1日、東京都などで「カスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例」が施行されました。
これにより、企業や自治体にも適切な対応策の整備が求められています。
本連載では、月刊『ガバナンス』の連載をまとめた別冊付録『そこが知りたい!クレーム対応悩み相談室』の内容を引用して掲載。
人材教育コンサルタントの関根健夫さんが自治体でのクレーム対応術を解説しています。
今回は説明を理解していただけないときの伝え方をご紹介します。
カスハラ・クレーム対応の参考としてチェックしてください!
この記事で分かること
・理解を得られない理由
・結論が変えられない時の対応
・お客様に伝わりやすい「言い方」の工夫
Cさんはなかなか市民に話を理解してもらえずに悩んでいるようです。

人材教育
コンサルタント
関根さん

① 結論を変えられないなら、言い方を変える ② 言い方を工夫することが、クレーム対応における説明、説得の技術
主義主張の手前の問題
C お客さまの中には、こちらの説明をなかなか理解していただけない人がいます。
関根 役所は、社会のすべての人に対応するので、いろいろな人がいて大変でしょうね。それはどのようなときのことですか。
C 手続きの仕方や決まりごとの根拠、趣旨を説明するときなどですが、一概にはいえません。
関根 確かにさまざまな状況がありそうですね。
C そういったときにどのように考えればいいのでしょうか。
関根 こちらが法や決まりにしたがって、常識的に正しいことを一所懸命に話したとしても、相手方にこちらを理解しようという気持ちがないと、現実には理解を得られないでしょうね。
C それは、主義主張が違うからということですか。
関根 基本的な考え方が違っていると、こちらの主張をなかなか受け入れてもらえないことはあるでしょう。ただ、申し上げたいのは手前にある問題です。その場では忙しくゆっくり聞いていられないとか、難しい話は聞く気がしないとか、そういうことも含みます。
C 確かに、手続きの仕方などの説明は、主義主張とはあまり関係がないですよね。
関根 例えばこちらが専門用語などのなじみのない言葉を使うと、それに意識が引っぱられてしまい “この話は自分には難しい” “聞いても分からないだろう” などと、話を理解しようとする気持ちが失せてしまうこともありますね。
C 確かに、そういうケースもあるかもしれません。
関根 そのうえ考え方がずれていると、複合して “偉そうに” “不親切だ” “だから役所は嫌いだ” など本題とは違ったマイナスの感情を増幅する可能性もあります。
C なるほど。だから、専門用語は使わないほうがいいのですね。
関根 使わないほうがいいというより、注意が必要でしょうね。専門用語は正確な意味を持つ言葉ですから本来はそれを使うべきです。要するに、相手方が抵抗なく意味を受け取れればいいわけです。
言い方を考えることが大切
C では、こちらの言い分を分かってもらうためには、どんな言い方をしたらいいのでしょうか。
関根 大切なのは、言い方を考えるということです。役所のクレーム対応は、多くの場合、結論が決まっています。無理を引き受けるわけにはいかないし、かといって単純に「できません」「無理です」「ダメなものはダメ」などと言えば角が立ちます。
役所に限らず、組織で仕事をしている以上、組織の決まりがあり、許される範囲、許されない範囲があります。結論が決まっている以上、結論を変えるわけにはいきません。であれば、言い方を変えるしかないでしょう。私は、それこそがクレーム対応における説明、説得の技術だと思っています。
C そういうものですか。
関根 コミュニケーションは、人と人とが自分の持っている情報やそれに関する考えをお互いに伝え合うことです。情報そのものは、見たり聞いたりした自分が知り得た事実ですから、それを曲げてしまっては不誠実になります。時には虚偽を申告したとして不当な行為になる可能性すらあるのです。
C 確かにそうですね。
関根 また、自分の考えが相手方ににわかに受け入れられないからといって、考えや結論をいちいち変えてしまっては、主体性がなくなります。そのようなコミュニケーションを続けていると、やがて信頼は失われ、人間関係にヒビが入ることになりかねません。
C では、どのような言い方をすればいいのでしょうか。
関根 そこが難しいところです。人は皆違う人格を持っています。同じ話をしても、人によって同じ反応が返ってくる保証はありません。こちらが伝えたい結論を先に伝えて、その後に結論に至る理由を話すほうが理解しやすいと思う人もいるでしょうが、意に反する結論を言うと、逆上して話し合いにならなくなってしまう人もいるでしょう。あることをお願いする場合でも「○○をしてください」と端的に言ったほうがいいケースもありますが、一般的には「恐れ入りますが」「お手数ですが」などとへりくだったほうが抵抗感は少ないでしょうね。
C 相手の顔色を見て、ということですかね。
関根 そう言ってしまうと切ないですが、万能な話し方はないのですから、言い方をいろいろと考え、その場で工夫することです。
結論が変わらないのですから、こちらは相手が理解していただくまで、何度でも説明することになります。でも、同じ言い方を繰り返したのではくどいだけで、相手も聞いてくれないでしょう。手を替え品を替えいろいろな言い方で何度も説明することで、相手が熱意を感じ「なるほど」と思う瞬間があるのです。
C 分かりました。言い方を考えて工夫してみます。
【関根先生の著書はこちら】
月刊『ガバナンス』で好評を博した連載「クレーム対応駆け込み寺」を加筆修正、再構成し単行本化
クレーム対応のさまざまな悩みを解決!
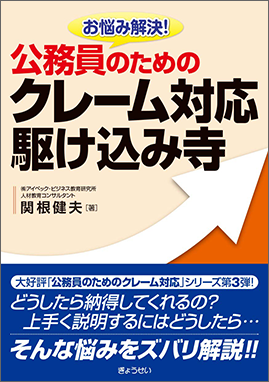
お悩み解決!
公務員のためのクレーム対応駆け込み寺 編著者名:関根健夫/著
販売価格:2,420 円(税込み)
試し読みはこちら ≫
【こちらもおすすめ】
カスハラをはじめとする不当要求行為等について、実際の事例から対応を学ぶ!

自治体職員のための
不当要求行為対応ブック
-事例からわかるトラブル回避策- 編著者名:宇都木法律事務所(代表弁護士 宇都木 寧)
販売価格:3,080 円(税込み)
試し読みはこちら ≫