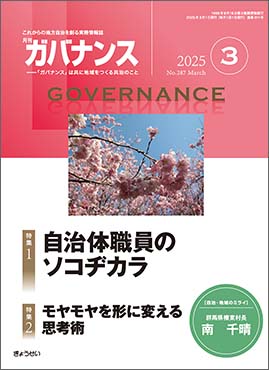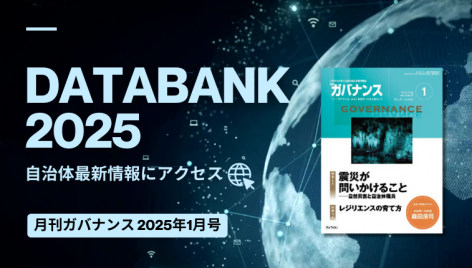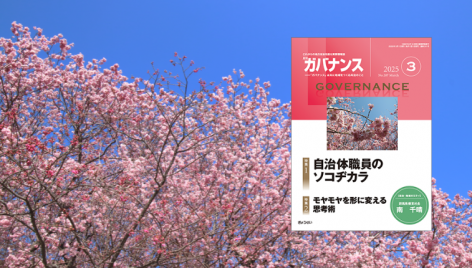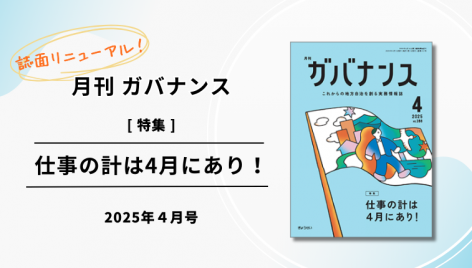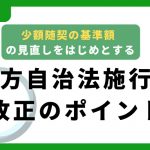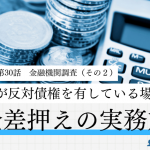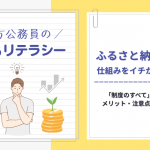自治体最新情報にアクセス DATABANK
自治体最新情報にアクセス|DATABANK2025 月刊「ガバナンス」2025年3月号
地方自治
2025.04.04
目次
●「住民協議会」の設置を条例化
奈良県田原本町(3万1600人)は、「田原本町つながりと助け合い推進条例」を制定し、24年12月19日に施行した。町民等と町がまちづくりについて共に考える場として「住民協議会」を設置することなどを定めた条例で、町民等一人一人がまちづくりを「自分ごと」として捉えることを進め、つながりと助け合いのまちづくりを推進するのが目的。全6条で、基本理念を明記した上で、住民協議会や、情報の共有及び意見等の聴取などについて規定している。
住民ニーズの多様化・複雑化や行政職員の減少、地縁的なつながりの希薄化に伴って行政のみによるまちづくりに限界がみえている中、町実施のアンケートで「行政への住民参加」の項目の重要度が最低値となっていた。そこで、「自助・共助」の促進に向け、地域のつながりを深め、町民等のまちづくりの自分ごと化による自主的活動を尊重し、多様な主体による助け合いの推進を目指して条例を制定した。住民協議会は、行政への参加を通じて具体的な課題解決を「自分ごと」として考えてもらう場であり、町では22年度と23年度に開催した。今後も必要に応じて、無作為抽出による熟議プロセスとして開催するとしている。
(月刊「ガバナンス」2025年3月号・DATA BANK 2025より抜粋)
●衛星画像と生成AIを活用して固定資産税業務を効率化
香川県善通寺市(3万300人)は、衛星画像と生成AIを活用して土地用途の現況を確認し、固定資産税の算定業務の効率化を図る取組みを進めている。
固定資産税は、土地や家屋の適正な評価を行い、課税年の1月1日の状況によって評価額を決定して賦課している。その評価のための土地の利用方法や家屋の建築状況は、①市内全域パトロールによる現況の目視確認、②航空写真での前回撮影時との違いの発見で把握しているが、①は時間と手間がかかり、②は航空写真撮影が高額なため近隣4市4町と合同で3~5年に一度行っており、現況とのタイムラグで正確な情報がつかめないという課題があった。
そこで、航空写真より比較的安価な衛星画像を毎年1月1日に近いタイミングで購入し、画像解析を行えるAIを利用して写真上で前年との違いを抽出する仕組みを検討。衛星画像と汎用ソフトを購入して税務課職員のチームが民間システム会社の協力を得ながら基本システムを開発し、試験運用を重ねて汎用性の高いシステムの構築を図っている。具体的には、新旧の衛星画像を地理情報に特化したGISソフトウエアのQGISに読み込ませ、土地や家屋ごとに前年との違いを生成AI(ChatGTP4o)で画像判定して抽出。抽出したデータをエクセルで一覧化し、それを基に職員が衛星画像で確認して前年と違う物件を絞り込んで、現地調査を行う取組みを試験的に進めている。同様のシステムを外注で開発すると非常に高額になると予想されるが、税務課職員がフリーや安価なソフトで作成したことにより費用は約120万円で済んだという。市は民間企業と協力の上、画像判定精度や操作性を向上させ、付随機能も追加して独自のシステムを構築し、25年度以降にパッケージ化して他自治体から引き合いがあれば提供することも検討している。
(月刊「ガバナンス」2025年3月号・DATA BANK 2025より抜粋)
●部活動地域移行に向けて「プレ地域クラブ活動」を実施
愛知県大府市(9万3000人)は、中学校部活動の地域移行に向けて、1月18日から2月15日まで、市内中学校の部活動と連携した「プレ地域クラブ活動」を実施した。
市は、8月から土日の学校部活動を行わず、活動を希望する中学生は新たに設置する「おおぶ地域クラブ」でスポーツや文化活動を行うという方針を定め、検討を進めている。部活動は学校教育の一環であるのに対し、「おおぶ地域クラブ」は、生涯学習の一環として地域団体が運営管理する。子どもたちが地域で運動・文化活動を楽しむことができることを目指し、土日の活動から順次開始する計画。
今回の「プレ地域クラブ活動」は、「おおぶ地域クラブ」の開始を前に、活動管理アプリの使用(スケジュール管理、出欠管理、活動報告)、現場管理体制の整備(クラブ活動巡回、平日部活動連携)といった運営管理に関する実証を行うもの。実証の対象部活動は、大府中学校の卓球部・バスケットボール部(男女)、大府南中学校の卓球部・バスケットボール部(男)。
25年度から「おおぶ地域クラブ」の運営管理を担う予定のNPO法人TRILL(トゥリル)に委託して実施した。
(月刊「ガバナンス」2025年3月号・DATA BANK 2025より抜粋)
●デジタルアーカイブ「かわさき環境100年史」を開設
川崎市(152万9100人)は、市制100周年記念事業として川崎市デジタルアーカイブ「かわさき環境100年史」を開設している。
溝口エリアが脱炭素先行地域に選定されるなど2050年の脱炭素社会の実現に向けて先進的な取組みを進めている同市は、宿場町から工業都市へと発展する中で公害やごみ焼却施設逼迫などの環境問題に直面し、解決を図ってきた。その過程で蓄積した資料を次世代に継承し、市民と川崎の環境の歴史を振り返って、川崎の環境に対する誇り(環境シビックプライド)を育むとともに、市民一人ひとりが環境課題を自分事として捉え、脱炭素社会のさらなる実現に向けたきっかけづくりにするのがアーカイブ開設のねらい。
同アーカイブでは、環境に関する「市政だより」掲載の1954年以降のスクラップ記事や、市民ミュージアムや環境総合研究所が所蔵する写真、約1200点を掲載。1959年以前から2000年以降までの年代別や、カテゴリー別(「大気」「水質」「下水」「廃棄物」「みどり」など)に検索できる。掲載写真は著作権法上認められた「私的使用のための複製」や「引用」などの場合に限り、二次利用を可能としている。また、川崎市の「環境課題への取組のあゆみ」を「明治・大正」「昭和」「平成・令和」「未来に向けて」に分けて紹介している。環境をテーマにしたデジタルアーカイブは全国初とみられる。
川崎市デジタルアーカイブ
https://www.digital-archive-env.city.kawasaki.jp


(月刊「ガバナンス」2025年3月号・DATA BANK 2025より抜粋)
●タブレットアプリを活用して児童虐待対応業務の精度を向上
北九州市(92万1200人)は、産業技術総合研究所発のスタートアップである㈱AiCAN(本社:川崎市)と連携し、同社が開発したタブレットアプリを活用して児童虐待対応における判断の質の向上や業務効率化などを図るための実証実験を行っている。
具体的には、虐待が疑われる家庭や学校を訪問した職員がAiCANのアプリを導入したタブレットを持参し、
①タブレットアプリで現場と職場(児童相談所)をつなぎ、現場の情報(調査内容や画像等)をリアルタイムで共有
②調査(聴取)するポイントのリスト化
③訪問先での音声入力やOCR機能等を活用した記録の作成
――を行っている。①によって職場の所長や課長等が現場にいる職員と直接やり取りを行うことで、精度の高い判断と対応が可能になる効果が期待される。また、②は経験の浅い職員のサポートがねらいで、調査(聴取)ポイントを平準化することによって職員間の経験の差を埋める効果を期待。③は記録作成の時間短縮等による業務効率化がねらいで、それに伴って担当職員が直接こどもや家庭に関わる時間を増加させて、より丁寧で適切な対応につなげる効果が期待されている。このような児童虐待対応業務の取組みは九州初の試みだという。
市は24年度から、市内スタートアップに特化した成長支援と、スタートアップによる行政課題の解決や市内企業との協業に対する支援を行う「企業変革・スタートアップ・グロースサポート事業」を創設。AiCANは同事業のイノベーション支援プログラム「行政課題解決」枠の1社として採択された。年間最大400万円の支援を受けて市設定の課題解決に資する実証に取り組んでいる。24年度中は22台のタブレットにアプリを導入して進めており、25年度は導入拡大も検討し、26年3月末まで行う予定。
(月刊「ガバナンス」2025年3月号・DATA BANK 2025より抜粋)
●「緊急一時支援全国ネットワーク」を設立
宿泊を伴う支援を必要とする人たちのための緊急受け入れ団体の代表者らが集い、2月6日、「緊急一時支援全国ネットワーク設立シンポジウム」が開催された。主催は「『属性を問わない緊急一時支援』の全国波及のための調査研究及び実践ガイドの作成、セミナー開催、ネットワーク構築事業委員会」、事務局は仙台市を拠点とする「特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター」。オンライン形式で約450人が参加した。
同事業は赤い羽根福祉基金の助成事業で、22年度は自治体や緊急受け入れ団体へのアンケート・ヒアリング等を通じた実態の把握と整理、23年度は事例集・実践ガイドの作成・配付、シンポジウムの開催、24年度は全国キャラバンの開催、WEB広報紙の発行等に取り組んできた。今回の「緊急一時支援全国ネットワーク」の設立は、これらの調査研究や実践の集大成とも呼べるもの。
設立に当たり、「緊急一時支援」とは、「既存制度では対応しにくい課題、複合課題を持つ人を、いつでも(緊急も含めて)、一時(一定期間)受入れ、安心して日常生活を送れるよう支援する」ことと整理。障害、認知症、虐待、DV、生活困窮、外国にルーツを持つなどの事情により、既存制度の中では支援が十分に受けられない人々。調査研究の中で、こうした人々を受け入れる緊急一時支援施設(NPO法人等が運営)が各地にあるが、地域を越えた横のつながりがないことが浮き彫りになった。そこで、各施設の代表者や職員が自由に交流できる場としてネットワークを設立することにした。
代表世話人は、横田能洋氏(茨城NPOセンター・コモンズ代表理事)ら3人。ネットワークでは今後、各市町村との連携・協働を図りながら、各施設の取組みの共有や意見交換などを行うことにしている。
(月刊「ガバナンス」2025年3月号・DATA BANK 2025より抜粋)