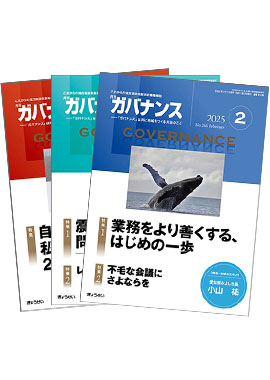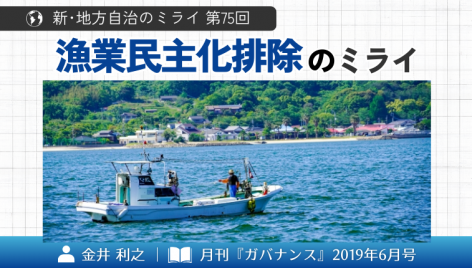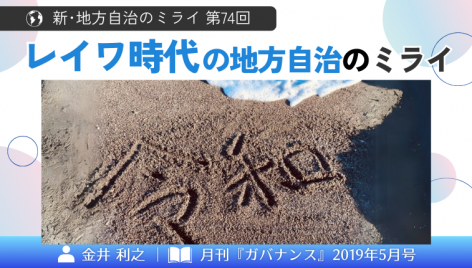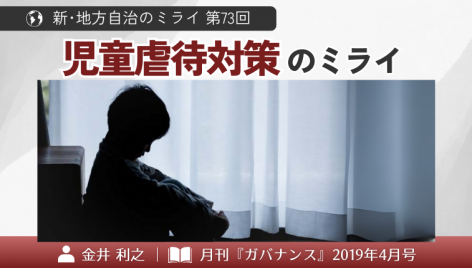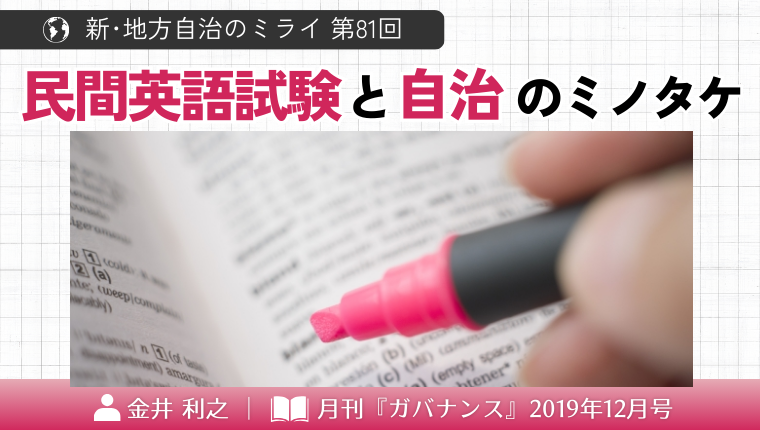
新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第81回 民間英語試験と自治のミノタケ
地方自治
2025.04.07
本記事は、月刊『ガバナンス』2019年12月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに
2021年度大学入学者選抜(2020年度実施)に導入が予定されていた、大学入学試験への英語民間試験の導入が、2019年11月1日に「延期」された。高校生からの反対署名も集まり、高校関係者からの懸念もあり、さらに国会でも追及を受けていた。要するに、国・民間事業者の執行能力という「身の丈」(荻生田光一文科相)に合わない、教育再生実行会議などの机上のプランは、無能なゆえに実現できない。
通常は、教育政策として考えられて、自治体からは対岸の火事のように受け取られているかもしれない。しかし、本論ではこの問題を自治の観点から論じてみたい。
全国画一執行の難しさ

大学入学試験は、本来は各大学が個別に行えばよいものであるが、仮に全国的に共通して導入しようとすると、執行において大変な困難に直面する。試験は公平・平等であるべきだから、同一試験問題というだけではなく、同日同時間の一斉実施、画一的採点が不可欠である。
より広く公平性を考えれば、例えば、全国の受験生にとって、現実的に受験可能なエリアに試験会場がなければならない。また、受験料も本来は無料であるべきだが、仮に受験料を取るにせよ、あまりに過度な金額になる場合には、経済階層の点から公平性を保てない。さらに、当日の悪天候や交通機関の乱れなどでも、実質的な有利不利が発生することもある。当日、試験を実施できない場合もあり、その場合には追試が用意されなければならないが、公平な追試とはなかなか難しい問題である。加えて、視覚障害や身体障害や病気など、様々な配慮を要する状況があり、公平性を満たしながら、個別の合理的配慮を導入することは、大変なことである。
50万人を超える試験を公正に行うために、大学入試センター試験として、作題・採点は中央で行っているが、全国津々浦々の大学施設等を利用して一斉に実施されている。このノウハウと努力は並大抵のものではない。というか、様々な不公平と失敗を重ねて、どうにか彫琢してきた前世紀の遺産である。
もちろん、これは、大学入試センター側だけの努力ではできない。画一行動に慣れ親しみ、同調的行動を厭わない、自発性も疑問も持たないような、従順な高校生などを生み出してきた戦後学校教育の「成果」でもある。また、そのように忖度して自らを規律してきた高校生などの、「自己陶冶」の帰結である。北朝鮮でマスゲームができることと同様に、日本で大学入試センターができることは、決して自明ではない。
官でできない=民でできる?

このような画一性を要求する業務において、記述式や音声問答を導入することは、極めて困難である。各大学の個別入試で記述式や音声問答(面接・討議など)を導入することはあるが、あくまで、それは受験生の数が限定されるから、執行可能なのである。記述式採点は、それなりのノウハウを持った採点者が、画一的に答案を見る必要がある。同一人物が全答案を見て公平性が保てる。あるいは、詳細な採点基準があって、誰が採点しても同じように評点できるくらいでなければならない。
英語入試で、「読む、聞く、書く、話す」の導入という目的自体が妥当だとしても、記述式解答や音声問答を、50万人を超える同一試験で導入することは、ほとんど不可能である。
そのため、ノウハウの蓄積のある大学入試センターでもできないことを、民間企業でできると考えること自体が、愚昧な政策決定と言わざるを得ない。行政や大学が無能であるのは事実であるが、それは、民間事業者が有能であることを意味しない。民間事業者は、「適当」な資格試験・模擬試験などは行っている。しかし、本当に大学入学者選抜に使える試験を執行することとの間には、天と地ほどの差がある。「行政でできないならば民間にやらせればよい」という近年にありがちな発想が、このような愚行を招いた。
民間事業者の本質的無能力
これまでも、自治体は国の政策を、全国画一的に執行することに動員されてきた。戸籍、住民基本台帳、個人番号、国政選挙、統計調査、保育、学校教育、環境規制、生活保護、介護、健康保険、運転免許など、様々な業務が押し付けられている。
しかし、執行責任を担う自治体は、国が立案した政策が画一的かつ公平に執行できないと認めるときには、執行上の問題を提起するだろう。もし、記述式・音声問答を導入する試験を自治体が執行せよといわれれば、確実に異論を提起したはずである。少なくとも、自治体には、執行不能・困難なときには、それを異議申立する責任があるし、実際、多くの場合ではしてきた。
しかし、民間事業者は、全国画一的に執行できないときにも、できないと異議申立できない。自己の無能力を認識・表明する能力がない。民間事業者とは本質的に無能力である。その理由は以下の通りである。
第1に、民間事業者は、「できない」と表明したら、仕事を受注できない(注1)。民間事業者は、無理と分かりながらも、「できる」と強弁しなければならない。
注1 123万人の受験が見込まれるので、123億円利権といわれている。ベネッセのGTECは年間100万人が受験している。電子版NEWSポストセブン2018年11月11日07:00配信。
第2に、民間事業者は、50万人を超えるサービスを、同日同時間帯に一斉にする発想が、そもそもない。模擬試験や資格試験のように、適当な回数に、適当な時期に、適当な判定をする仕事のイメージでしかない。要するに、仕事の精度に関する発想が異なる。
第3に、民間事業者は、できるだけ「手抜き」をした方が、利益になる構造がある。公平性を確保するには、様々な費用がかかる。しかし、例えば、能力のある採点者を大量に短期に雇うよりは、適当にアルバイトを雇った方がよい(注2)。
注2 センター試験の記述式の導入は、執行の観点から懸念されているが、ベネッセ子会社に外注化しており、英語民間試験と同じ構造がある。
実は「高邁(こうまん)」な目的?

もっとも、英語民間試験の導入は、1点刻みの公平性ではなく、もっと適当(おおらか)な入試を目指す、「高邁」な理想を掲げていたのかもしれない。公平性や機会の平等に目くじらを立てず、様々な不平等・不公平を受容して、運命と「身の丈」に合わせる、富裕層、二世三世に都合のよい社会を「取り戻す」のである。
英語試験で「読む・聞く・書く・話す」の能力を問うのではなく、要するに能力などは適当(かけみたい)なものであるから、大学入試も運命に委ねる、という発想である。「不公平で適当」(アンフェア)な試験ならば、そもそもやらないのがいいかもしれない。しかし、能力検査を完全に止めるのではなく、1点に拘っても仕方がない程度の粗雑な能力検査なので、民間事業者でも実行できる、というものである。
しかし、能力は適当(かけみたい)だ、進学は偶然だ、努力は無駄だ、公平はない、ということを受験生は納得していない。仮に、このような「高邁」または高慢な政策を導入したければ、小中学校レベルから、教育方針を変えないとならない。もちろん、「身の丈」論者が期待するように、現在の学校現場では、所詮は家庭の経済環境や家柄で格差は決まる、努力しても無駄だ、貧困の連鎖は不可避だ、などという諦観は行き渡りつつある。しかし、幸か不幸か、まだ悟りが足りない大学受験層は、あるいは、学校における立身出世の能力主義を従順に内面化しすぎたがゆえ、依然として、「努力すれば何とかなる、公平な評価はある」などという発想を抱いている。
おわりに
自治体は公立高校を持っていながら、ほとんど、この問題に声を上げることはなかった(注3)。学力向上や大学進学率に、自治体為政者は、しばしば大きな価値を置いていながら、漫然と日々を過ごしていた。上記の通り、英語統一試験を自治体が実施することになっていれば、もう少し真面目に執行準備の対応をしていたかもしれない。高校生や学校現場は声を上げたにもかかわらず、高校生の尻を叩いて学力向上を煽るだけが、自治体為政者の「身の丈」であった。
注3 例えば、文部科学省は2019年8月27日に、自治体に対して民間英語試験の会場確保への協力を求めていた。要するに、自治体は全く主体性と当時者意識を欠いていた。日本経済新聞電子版2019年8月27日18:06配信。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。