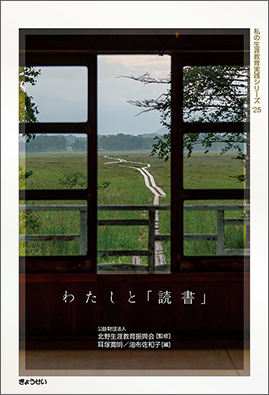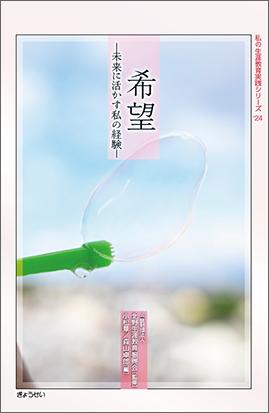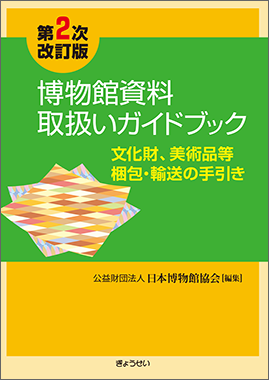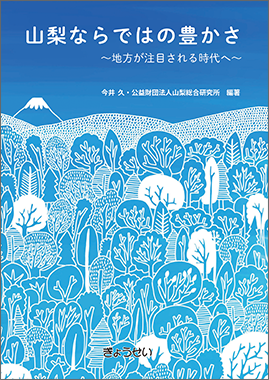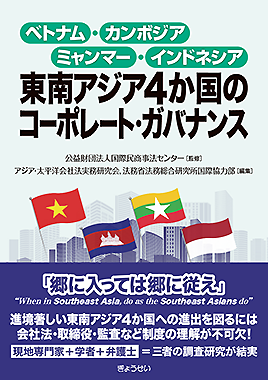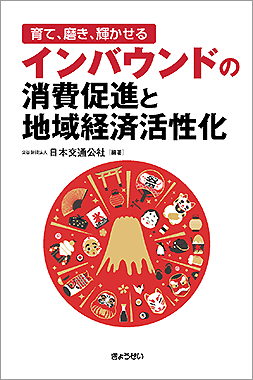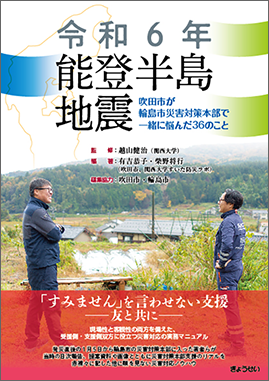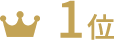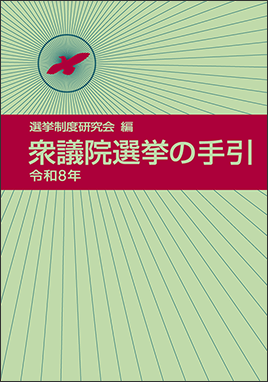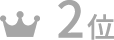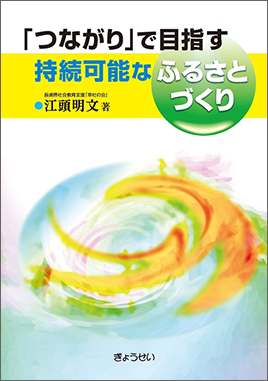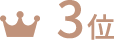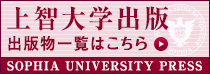公益財団法人北野生涯教育振興会が毎年行っている「自身の経験を通じた小論文・エッセー」において、入選作品を中心に編集したもの。令和7年度は「わたしと読書」がテーマ。
【本書「まえがき」より抜粋】
応募された作品を読んでみて、とくに感じたことがあります。それは、「読書は遺伝する、読み聞かせを通じて」ということです。もちろん、読書行動が遺伝子を媒介として生物学的に遺伝するわけではありません。家族の子どもへの読み聞かせというすぐれて文化的な営みを通じて、子どもに遺伝するのです。読書はこの意味で、文化的相続の性質が強い営みです。
親が子どもに物語るという行為によって、そして子がそれを聞き、物語られた世界を自ら想像して世界観を作り上げるという相互行為によって、読書という営みは次の世代に継承されていくのです。
この本に収録された作品の中に登場する読み聞かせが、なんと多いことか。読者もすぐに気づくことでしょう。
学力の社会学的研究の領域を概観してみると、国際的にも共通した知見を見いだすことができます。その一つは、幼少期における親の子どもに対する読み聞かせは、子どもの学業成績を高める影響があるという知見です。とすれば、読み聞かせが伝達するのは、読書習慣のみならず、学力の基盤を含んでいて、さらには世界観や人生の方法論にまで及ぶことは、想像に難くありません。
目次
序章 読書論(耳塚 寛明/お茶の水女子大学名誉教授)
1 ある受験参考書との出会い 受験と読書
2 読書の危機 デジタル環境に蝕まれる知性
3 みんなを幸福にするためにどうしたらよいのかが知りたくて読んできた
第一章 導きと気づき
○エレナからの教え
○ページの羅針盤
○まほうのほん
○心で見る読書
○本が差しのべてくれた手
第二章 派生していく物語
○つながる読書 つなげる読書
○読み聞かせてもらった私
○本の要塞と門番
○僕と家族の本棚
○本が母子を繋ぐ
第三章 様々にみせる真骨頂
○音楽会という老後の楽しみ
○読書の境界
○潜る度深くなる海
○デジタル時代に『三四郎』を読む
第四章 欺くして受け継がれる
○私と父のあいだにあるもの
○回り道
○世界一のばかとポエマー
○育休を百冊の本とともに
○語り継ぐ思いを明日へ
終章 人は本を選び、本は人をつくる(油布 佐和子/早稲田大学教育・総合科学学術院名誉教授)
はじめに
1 本との付き合い
2 読書とジェンダー
3 言葉と表現をめぐって
おわりに
入賞論文執筆者一覧
あとがき
公益財団法人北野生涯教育振興会概要