
新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第42回 「改憲」論議と地方自治のミライ
時事ニュース
2023.10.18
本記事は、月刊『ガバナンス』2016年9月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
はじめに
2016年7月の参議院選挙の結果、いわゆる「改憲勢力」が国会の衆参両院の3分の2を占めるようになった。このため、第2次安倍政権のもとで、「改憲」論議が進められるものと想定されている。もっとも、与党の一角である公明党は「改憲勢力」と呼ばれることを忌避しているし、参議院選挙でも具体的に「改憲」が争点となったわけでもない。また、仮に野党第一党の民進党を含めての「改憲」論議が必要ということであるならば、以前から、民主党=民進党を含めれば国会の3分の2以上の議席はあった。
とはいえ、与党・自民党は「自主憲法」制定を党是として、「改憲」草案まで取りまとめているし、安倍首相も「改憲」には前向きである。また、自治体関係者のなかにも、国民代表制と「一票の価値の平等」の原理のもと、参議院の「合区」が迫られ、都道府県単位の地域代表制の習律が崩壊に瀕している現在、「改憲」によって、自治体などの都道府県単位の地域代表制の確立を期待する向きもあろう。さらに言えば、連邦制的な道州制・分権改革や「地域主権」改革も、「改憲」を要するという観点から、「改憲」に夢を求める自治体関係者もいるかもしれない。そこで、今回は今後の「改憲」論議を見据えて、自治体として留意すべき点を検討してみよう。
「改憲」による分権化は有り得ない

非常に重要なことであるが、「改憲」によって、自治体にとって有利な分権化は有り得ないことは、肝に銘じておくべきことである。それは「改憲」手続から明らかである。よく知られているように、「改憲」には、①国会両院の3分の2以上の合意による発議と、②国民投票による過半数の賛成が必要である。
①とは、政権成立に必要な衆議院の単純過半数、安定政権の運営に必要な両院単純過半数を超えて、両院で3分の2という圧倒的な権力が成立していることを意味する。このような盤石の権力を得た国政が、「改憲」の発議において、自治体に対して権力を付与し、国政の権力を抑制する分権化を進めるはずがない。有り得るのは、「改憲」によって、盤石な国政政権が崩壊しても、自治体を国が支配できる〈憲法〉を、自治体に「押し付ける」だけに終わるのである。つまり、日本国憲法の改正手続に拠る限り、「改憲」によって分権化が進むことは有り得ない。
②とは、国民多数派が少数派に「押し付ける」内容が、国民投票によって承認されやすいことを意味する。地方自治に関係する国民の少数派/多数派の分布とは、端的に言えば、地方圏/大都市圏の分布に他ならない。つまり、国民投票で可決されるような「改憲」とは、大都市圏を優遇するような内容でしか有り得ない。したがって、地方圏切り捨て的な「改憲」は有り得ても、地方圏の地域代表制を確保するような「改憲」は、有り得ない。歴史的には、地方圏は自民党の支持基盤であったとしても、自民党が「改憲」を本気で考えれば、地方圏を切り捨てるような内容にならざるを得ない。自民党系の地方圏自治体の期待は裏切られることになるのが、「改憲」の論理である。
権力分立制と「改憲」論議
自治体としては、地方自治に関わらない「改憲」論議には、取り敢えず、無関心であるかもしれない。しかし、憲法とは、人権保障と権力分立制に関わるものであり、統治機構である自治体としては、無関係ではいられない。端的に言えば、地方自治制度とは、権力分立の一種である。国政の立法・行政・司法の三権分立を「水平的権力分立」と呼ぶのに対して、国と自治体の権力分立は、「垂直的権力分立」とも呼ばれるものである。
憲法制定において、全体として権力分立が進むのであれば、自治体への分権も進み、全体として権力集中が進むのであれば、自治体への分権は後退する。しかし、上述の通り、「改憲」は国政の超巨大統治勢力への権力集中を前提とするものであるから、「改憲」がされる以上、為政者への権力集中が固定化されるのであって、自治体への分権は進まない。「改憲」は、常に自治体にとっては、「押し付け憲法」になる。
憲法と「押し付け」
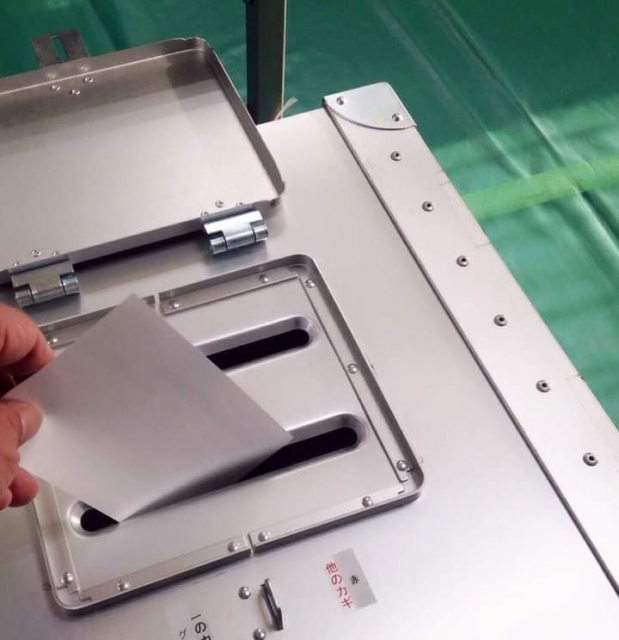
近代的意味での憲法とは、本来、為政者にとっては常に「押し付け」である。主権者である国民が、人権保障をすることを目的に、為政者を束縛するために憲法を制定するからである。「押し付け憲法」とは論理的に必然である。憲法が「押し付け」に感じられるとすれば、その人が、為政者であるか、為政者とメンタリティが一致しているか、のどちらかである。そのような憲法は、むしろ正常に機能している。
とはいえ、為政者は、国民を統治・支配することにやりがいを感じている人々であるから、国民に別の意味の〈憲法〉を「押し付け」ようと考える。いわば、為政者が守るべきものではなく、国民が守るべきものとして、為政者が国民に守らせるものとして、〈憲法〉を考える。〈憲法〉とは、為政者が国民に「押し付け」るものとなる。為政者が発議する「改憲」は、国民に対する人権制限・義務付加という「押し付け」の色彩を帯びがちである。こうした「改憲」が国民投票で支持されるとするならば、国民は為政者とメンタリティが同じであることが実証される。自由な権利を保障されてきた国民は、その時点では、自由に自虐できる。
自治体は為政者側か国民側か
このような「改憲」過程において、自治体は微妙な立場にある。自治体為政者は、国政より小なりとはいえ、支配者側の一部である。自治体為政者は、国民・住民に〈憲法〉を「押し付け」たいという感性を、国政為政者と共有しうる側面がある。例えば、国政への野心を持った自治体為政者の場合、そうした同調は強いだろう。また、国政への野望を持たず、自治体レベルの権力で満足している為政者も、住民に義務を「押し付け」たほうが、治政が楽だと思うであろう。このような自治体為政者は、住民の権利保障を放棄して、「改憲」論議に乗ることになる。
他方、自治体為政者は、為政者とは言いながらも、国からは統治・支配・統制される側にある。その意味では、国政からの「押し付け」に常に苦しめられる立場にある。また、住民の権利保障のために存在する権力分立制の一種として、国政に対する防波堤の役割が期待される。このような観点に立つ場合には、自治体の自治権の保障自体が重要である。国からの〈憲法〉の「押し付け」に対して、自治体は忌避感を示すことが自然になる。つまり、自治体為政者は、人権制限的な〈憲法〉の「押し付け」に繋がる「改憲」論議に乗りにくくなる。
自治体為政者が、国政為政者の「出先」として振る舞うか、住民の代表として振る舞うかは、自治体為政者の人格・識見によりけりである。そして、どのような自治体為政者を、自治体の住民が選出するか、次第である。
おわりに
「自主憲法」制定という「改憲」論議は、何をどう改正したいかを含んでいないので、議論のしようもない。実体内容の問題ではなく、制定・改正の主体・手続の問題だからである。しかし、為政者が憲法を「押し付け」られたこと自体を不満に思う感性から「改憲」論議を出発するならば、つまり、国政為政者が制定主体であるという発想であるならば、「改憲」論議から生じる改正案の内容は、常に、〈憲法〉を国民・住民・自治体に「押し付け」るものにならざるを得ない。
このような「改憲」論議では、住民の利益を第一に考える自治体為政者は、深刻に苦悩するだろう。逆に、国政為政者の「出先」として権力に与かろうと考える自治体為政者は、為政者と同じメンタリティで欣快に活躍するだろう。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)など。























