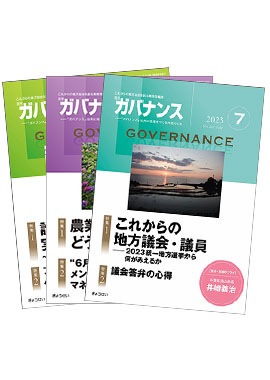新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第36回 ミイラ化する国地方係争処理制度
時事ニュース
2023.09.05
本記事は、月刊『ガバナンス』2016年3月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
はじめに
2000年第1次分権改革は、機関委任事務制度を廃止して、国からの関与に法的根拠を求める「法化」を行った。そして、そのような国の権力的介入が法的に妥当であるか、権力的関与を受ける自治体側の「権利」救済のために、裁判所による事後審査が必要となる。
その前段階の行政的な勧告機関として、国地方係争処理委員会が、総務省(01年中央省庁等改革前は総理府)に設置された。したがって、2000年改革が「初期」(所期)の機能をその後に果たしているのかは、国地方係争処理制度がいかに運用されているかにかかっている。
係争処理制度の運用状況

実際の国地方係争処理制度の運用状況は、表面的には芳しいものではない(注1)。例えば、横浜市場外馬券税問題では、国の不同意に対して横浜市が審査を申し出て、係争処理委員会による再協議の勧告は出された(01年7月24日)(注2)。しかし、再協議では総務大臣の同意は得られない(注3)。結局、横浜市政における政権交代を経て、横浜市側が場外馬券税条例を廃止する(04年2月)ことで、係争事態が消滅した。いわば、国側の引き延ばしによって、自治体の意向は実現しなかった。
注1 http://www.soumu.go.jp/main_content/000364654.pdf。2016年2月7日閲覧。
注2 http://www.soumu.go.jp/main_content/000025092.pdf。2016年2月7日閲覧。「勝馬投票券発売税」と表記されている。
注3 建築確認申請に対して建築主事が建築確認を与えず、半永久的に宅地開発指導要綱に基づく「行政指導」を継続させるようなものである。
また、新潟県は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対する国の北陸新幹線工事実施計画の認可について、審査を申し出た。しかし、国交大臣による新潟県知事への意見聴取は関与に該当しないとして、係争処理委員会は却下の決定を行い(09年12月24日)、新潟県側は高等裁判所への提訴を断念した。
なお、都道府県と市区町村の間の係争処理に係る自治紛争処理制度も同様である。手賀沼干拓事業に係る我孫子市の農用地利用計画の変更に関する千葉県知事の不同意について、我孫子市は審査を申し出た。これに対して、自治紛争処理委員は、同意基準がないことを違法と捉え、不同意取消、同意基準の設定・公表、協議の再開を勧告した(10年5月18日)。千葉県は同意基準を設定・公表し、協議を再開し、そのうえで改めて不同意にしたため、我孫子市が再度の審査申出を行った(11年7月26日)。今度は自治紛争処理委員は、千葉県知事の不同意は違法でも不当でもないとした(10月21日)。結局、我孫子市は高裁への提訴を断念した。この事案でも、基礎的自治体の意向は実現しなかった(注4)。
注4 詳しくは、http://www.soumu.go.jp/main_content/000141017.pdf。2016年2月7日閲覧。
制度の潜在的機能?

以上のように、表面的には、自治体側または「下級」団体側への分権の防塁としては、係争処理制度は機能しているように見えない。しかし、制度は顕在的機能だけではなく、潜在的機能も有り得る。係争処理制度が国または「上級」団体側の権力関与を抑止していれば、無用の長物とは言い切れない。
もっとも、こうした潜在的機能の分析は極めて困難である。事案として表面化しないからである。例えば、住民基本台帳ネットワークへの不接続では、明らかに国の介入がなされ、一部自治体側の抵抗が発生していた。しかし、この問題は、係争処理制度によって解決されることはなかった。このときに、同制度が分権的機能を果たしたのかは、分かりにくいところがある。
また、いわゆる八重山教科書問題では(注5)、国は竹富町教育委員会に対して是正要求(14年3月14日)を発出したが、同教育委員会は是正要求に応じなかった。国側は違法確認を求める係争処理の申出をする可能性はあったが、結果的にはこれをしなかった。このような文部科学省の決定に関して、国地方係争処理制度がどのように機能したのかを鑑別することは容易ではない。
注5 詳しくは本連載第8回「教育集権のミイラ復活」(2013年11月号)、第9回「教育集権抑制への『大人の知恵』」(同年12月号)を参照されたい。
すなわち、①国が法解釈としての「敗北」を予期して審査の申出をしなかったのであれば、係争処理制度の潜在的機能は発揮されたと言える。しかし、②係争処理での法解釈上の「勝利」を国側は確信していたとしても、違法確認を得てもそれ以上の手段がないから無意味だと判断したのかもしれない。その場合には、係争処理制度自体というより、当該事務に代執行や間接強制を規定しない事務配分が最後に効いてくる。その意味では、自治制度は潜在的機能を持っている。もっとも、これは、2000年改革以前から、代執行が可能であるのは機関委任事務だけであった。③しかも、国側は、仮に手段がないと判断すれば、いつでも法改正をすることは可能である(注6)。実際、教科書無償法改正によって、紛争自体を終結させた。立法権を持つ国は、「万能」に近い。
注6 自治制度上の危険性は、「違法確認が係争処理制度で確定しても、自治事務では自治体が従わない場合には、国側に強制手段がない」という理屈で、全ての事務に係争処理での確定判断を自治体側に強制させる一般制度が創設されることである。もっとも、そこまで強制させる必要のある事務は、個別的に個別法で規定すべき、あるいは、そもそも法定受託事務とすべき、ということになろう。とはいえ、法定受託事務が増えれば集権化であるし、強制付自治事務では事実上は法定受託事務と同じであり、これも集権化である。
係争処理制度というSLAPP

①のように、係争処理で「勝利」を竹富町側が予期するのであれば、竹富町側から審査の申出をするはずであるし、その予期を国が共有していたのであれば、係争処理を導くような権力的関与(是正要求)を国はしなかったはずである。その意味では、①の仮説のように係争処理制度の潜在的機能が作用したとは言えない。
そもそも、仮に竹富町側が法的「勝利」を予期していたとしても、係争などの裁判的手続をあえて求めるかどうかは疑問である。
強者が、法的に「敗北」が確実であっても、相手方に負担や損傷を与えるために、あえて提訴に踏み切るということもある。こうした訴訟類型がSLAPP(strategic lawsuit against public participation)である。一般には、政府や大企業が市民・消費者などの参加を威圧するための恫喝的訴訟である。これは、権力的に強い者が訴訟手段を使って権力的に弱い者に圧力をかけるものであり、国と自治体の関係にも応用できる。一般に、訴訟は弱者の権利救済の手段と考えられているが、実際の訴訟には精神的・肉体的・経済的・社会的・政治的な(機会)費用が掛かるので、綺麗ごとでは済まない。
係争処理制度も、所期の制度設計では自治体側の権利防御に役立つと考えられたかも知れないが、実際には審査に付されるだけで自治体側は大きな負担である。だからこそ、初期の2000年改革では、国側からの審査申出の可能性を否定していた。しかし、12年の地方自治法改正によって、国からの違法確認訴訟制度が導入され、係争処理制度のSLAPP化が進んだ(注7)。
注7 http://www.soumu.go.jp/main_content/000190900.pdf。2016年2月7日閲覧。
紛争の潜伏化と表面化
係争処理制度が潜在的に機能する場合、国・自治体間の紛争は二段階で潜伏化する。一つには、政治的紛争としては表面化したとしても、係争処理制度という法的紛争にまでは持ち込まない。二つには、政治的紛争としてさえ表面化させずに、内々に自制することで処理される。
係争処理に持ち込んだときに結論において、「敗北」が予想される側は、審査の申出をしない。さらに、そのような結論を予想する場合には、政治的紛争として表面化させたとしても、「勝利」を予期する相手側は政治的交渉を真摯に行うことはありえない。
国の「勝利」と自治体の「敗北」が予期される場合には、自治体側から係争処理の審査の申出はなされない。国の「敗北」と自治体の「勝利」が予測される場合には、国は権力的関与をそもそもしないし、その前に自分に都合がよいように法制定・改廃すればよい。
係争処理が表面化されるのは、国と自治体の間で「勝敗」の予期が齟齬を来たして、偶発的紛争が起きる場合か、「勝敗」を度外視して、紛争の存在自体を公表することを目的とするか、のどちらかである。
おわりに
以上のように、2000年分権改革で大きな期待をもって導入された国地方係争処理制度は、必ずしも分権的な効果を持っているようには見えない。沖縄県の辺野古埋立に関する問題の却下(15年12月24日)も同様である。そもそも、肉体の永遠を確保すると称して作成されたミイラは、所詮は干物を作るだけであった。分権改革の成果を確保するために設置された国地方係争処理制度も、ミイラ化しつつある。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)など。