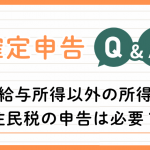新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第17回 個別的自治権と集団的自治権
時事ニュース
2023.02.24
本記事は、月刊『ガバナンス』2014年8月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
はじめに

第2次安倍政権は、2014年7月1日に、集団的自衛権の行使は憲法上禁じられているという従来の政府の憲法解釈を転換し、一定の要件のもとに集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈を閣議決定した。
従来の憲法解釈は、国会審議における野党の質問と、それに対する政府答弁、なかんずく、内閣法制局長官答弁という、質疑応答のもとに形成されてきた。しかし、閣議決定という、首相自身が任命した閣僚と首相が合意する手法での方針転換には、法の支配から見て、大きな懸念があるところである。
このような「潜在的脅威」である「大国」をまえに、弱小な自治体は、どのように自治権を守るのかは、極めて難しい課題である。
個別的自治権

自治体にとって、最も自治権を侵害する可能性の高い存在は、国(中央政府)である。もちろん、国は自治制度を保障しなければならない。そのため、国と自治体は敵対関係にあるとは限らず、むしろ、対等・協力という友好関係に立つべきことが、本来の姿である。とはいえ、制度としての地方自治を保障しても、個別自治体の存立や活動の自治を保障するとは限らない。そのため、個別自治体にとっては、国が自治権を侵害する可能は充分にある。
こうした観点から構築されたのが、2000年分権改革による国地方係争処理制度である。国は潜在的には個別自治体の自治権を侵害する可能性があるため、侵害された自治体は係争処理手続きに則って、対抗できるようにした。個別的自治権の法制化である。
もっとも、係争処理制度の運用状況を見る限り、必ずも個別的自治権の保障には効果的に機能していないようである。その理解は容易である。政権党の下にある各省が立案したものを政権党が多数を占める国会が法律として制定し、その法律に基づいて係争処理される。法令解釈も国の各省は行うことができ、本来は法令上許されないことでも、法令上可能であると解釈して関与しうる。そもそも、離島など全国に散在する遠隔地の自治体にとって、霞が関にある国地方係争処理委員会に出かけること自体、大変である。
結局、個別的自治権とは、法制外の政治力の行使である。個別的自治権とは、いわば、法制上は「大国」の軛(くびき)に喘ぐ弱小自治体が、政治力・実力を行使することが基底的な意味で、法的にも正統だと承認することを意味する。自治体は国に法令上認められた限定された権限だけを行使するのではなく、当該自治体に関わることに関して、潜在的かつ本源的に、法令上の明示的権限の有無とは無関係に、広範な権力を行使できる、という発想である。個別的自治権の考え方は、実は、戦後日本の自治制度においては、「総合性」として広く承認されてきた。
集団的自治権の模索

個別自治体は、個別的自治権をもっているとはしても、「大国」から見れば微力である。したがって、「大国」から簡単に自治権の侵害を受け得る。このときに他の個別自治体と協力して、自他の自治権を守ろうというのが集団的自治権である。古代中国で言えば、西方「大国」秦に対抗して、他の六国が同盟する「合従」論である。
ごみ処理や消防、災害時の相互援助など、自治体は様々な形態で他の自治体と協力するが、ここで問題となるのは、国による自治権侵害に対する協力である。この柱となるのが、全国知事会をはじめとする地方六団体等である。
地方六団体等でまとまって国と交渉することは、各個別自治体が陳情するより強力なことが期待される。こうしたものを法制化したのが、民主党政権下での「国と地方の協議の場」である。
もともと、「国と地方の協議の場」は、小泉政権下の三位一体改革の際に活用された。しかし、地方六団体は、様々な国庫支出金の整理案を提案して国と協議したものの、結局は、国の各省や与党の協議によって決着し、それを飲まされた。しかも、地方財政計画の策定や地方交付税の決定には関与できず、大幅な地方財政削減、いわゆる「2004年地財ショック」を防げなかった。また、それゆえに、平成の町村合併を防ぐこともできなかった。税・社会保障一体改革でも地方側への配分は少なかった。今日まで、地方財政制度全般に対する集団的自治権は、ほとんど機能していない。
こうした地方六団体等は、個別自治体の集合体であり、利害は一枚岩ではない。そのため、「大国」からの侵害に対して、機動的かつ断固たる対応を取ることはできない。地方六団体等は多数の個別自治体の最大公約数を反映するしかない。地方六団体等が進めるのは、結局は、個別自治体の個別的自治権の行使の集計である。地方六団体等や「国と地方の協議の場」は、集団的自治権にまで成熟していないのである。
また、一部の個別自治体は、抜け駆け的に「大国」に与し、他の個別自治体への自治権侵害を容認ないしは促進することもある。これは、古代中国で言えば、「大国」秦と個別に結託して延命を図ろうとする「連衡」論の系統である。この場合には、そもそも、地方六団体等の隊列さえ維持できない。集団的自治権など、ほとんど画餅に近いのである。
集団的自治(自滅)権の行使の困難性
観念的には集団的自治権は存在するが、現実には行使できない。個別自治体にとって重要なのは、個別的自治体の自治権であり、他の個別自治体の自治権ではない。よほど、お節介で利他的な為政者ではない限り、他の自治体の問題には静観して関わらない。
他の個別自治体の問題に関わるとしたら、それが当該個別自治体にとって有利になるときだけである。しかし、そのような帝国主義的な自治体はまずない。「大国」から他のある個別自治体が自治権を侵害されても、そのような係争に介入して、自分まで「大国」から攻撃されては、かえって「集団的自滅権」になって藪蛇である。つまり、「大国」からの自治権侵害に関しては、通常は、他の個別自治体は傍観する。それが、怜悧な政治の現実である。
当該個別自治体が他自治体に関与するとすれば、むしろ、「大国」の同盟者として、他の個別自治体の自治権侵害を、国と協力して行う場合である。ただし、これは、集団的自治権ではないし、そもそも個別的自治権の行使でもない。
集団的自治権の他治的・侵害的な本質
個別自治体は、結局のところ、個別的自治権を行使していくしか、現実的な方策はない。集団的自治権は、机上においては機能し得るが、現実的には想定される利害状況自体はほとんどない。各地の紛争に首を突っ込みたい、という為政者の介入主義的な選好をもとにしない限り、集団的自治権は行使されない。また、そのような侵出的な「部外者」が介入してくると、介入された個別的自治の点からすると、かえって自治を阻害することになりやすい。
集団的自治権の本質は、所詮は、他の個別自治体に関する「他治権」でしかない。集団的自治権は、合理的な為政者であれば、他の個別自治体に対して、行使しない。また、合理的な為政者であれば、他の個別自治体からの集団的自衛権の行使という「援軍」に期待しない。他の個別自治体が「他治権」を行使することは、それに他の個別自治体が利益を見出していることであるから、「大国」からの自治権侵害と同様に、当該個別自治体にとっては、自治権侵害の危機でもあるからである。
もちろん、個別的自治権の行使も簡単ではない。しかし、「大国」からの侵害に際して、他の個別自治体が利他的に救援を差し伸べてくれるということは、考えにくい。とするならば、主体的かつ地道に、自治のミライを模索するしかない。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)など。