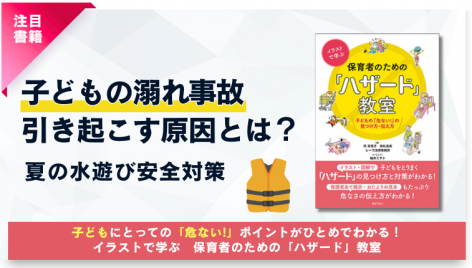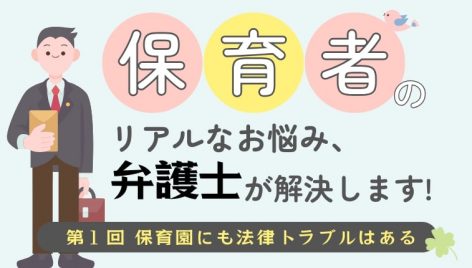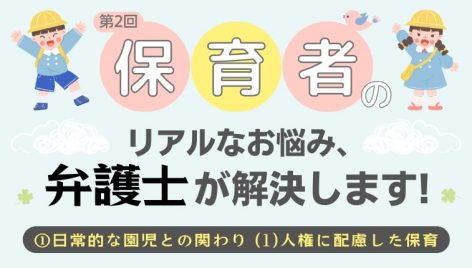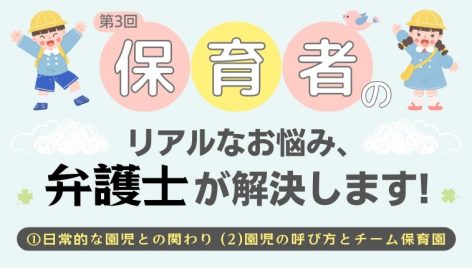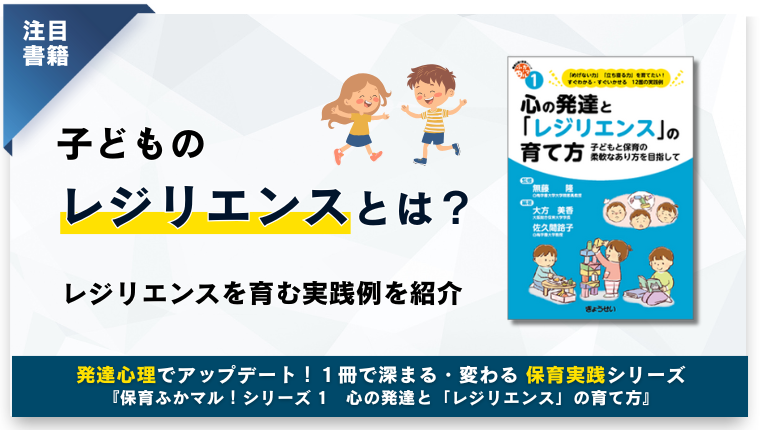
子どものレジリエンスとは?育み方の実践例とポイント
地方自治
2025.08.05
目次
心の発達や「レジリエンス」の知識、実践事例が保育のヒントに
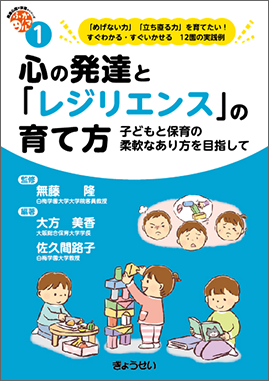
保育ふかマル!シリーズ1
心の発達と「レジリエンス」の育て方
- 子どもと保育の柔軟なあり方を目指して -
編著者名:無藤 隆(白梅学園大学大学院客員教授)/監修
大方 美香(大阪総合保育大学学長)
佐久間 路子(白梅学園大学教授)/編著
販売価格:2,530 円(税込み)
詳細はこちら ≫
『保育ふかマル!』は若手~中堅層の保育者向けに、発達心理学の視点から子ども理解と保育実践の手法をわかりやすく解説する全5巻のシリーズです。
1巻『心の発達と「レジリエンス」の育て方』では乳幼児の「めげない力、立ち直る力」(レジリエンス)の育み方を解説。本記事では、レジリエンスとは何かを説明している本書『はじめに』と、『レジリエンスを育む保育実践』を抜粋して紹介します。
この記事で分かること
・子どもの「レジリエンス」とは
・レジリエンスを育む保育実践例
・レジリエンスを育む保育のポイント
レジリエンスとは?(本書:「はじめに」)
「レジリエントである」(レジリエンス)とは、弾力性とか柔軟性とか回復力と訳されます。辛い目にあってもそこから立ち直れる力であり特性を指します。風邪を引いても休めば元気になることであり、それを心に広げることができます。近年はそれを家族や組織にも適用し、困難があっても、その組織として調整しながらやっていける力を指します。例えば、家族の一人が病気になり、当初は混乱しても、家族が分担し、外部の助けを借りながら、家族として支え合って機能していけることです。
本書はその概念を特に乳幼児を中心に幼い子どもたちとその子育てや保育へと広げて、研究の概要を整理するとともに、保育実践の事例をたくさん挙げて、特に保育の場面で保育者がどのようにして保育を柔軟に生き生きと進めていくかを論じています。
レジリエントであるとは、その事例にあるように子どもたちが難しさに出会い、保育者がどうしたらよいかと困るところでこそ発揮されます。そこでの工夫であり時間をかけての丁寧なかかわりであり、また保育の見なおしをしていくのです。
そこがよく分かるように、各事例にはそこにかかわりの深い方々にコラムとして解説を加えるようにして、理解が深まる工夫をしてあります。そのため、STEP3で論や実践的知見を整理して、保育者としての子どもへの向かい方をまとめました。子どもがレジリエントに育っていくには、保育者自身がレジリエントとなるよう心がけ、さらに保育者がチームとして園の同僚と運営をレジリエントにしていくことで可能になります。
レジリエントであることにより、生きていくことが楽しいことばかりでなく、困難や挑戦に満ちていて、でもそれを超えていく工夫をすることで必要な力が身についていくのです。本書からぜひそのための実践的な知恵と工夫を読み解いてください。
2025年夏
無藤 隆
【事例紹介】友達とかかわる楽しさを体験して人間関係を築く
1. 行事に参加することが苦手なH夫とY夫
H夫とY夫は双子のきょうだいです。2歳児の頃から、2人とも活発でよく戦いごっこをして遊んでいました。しかし、園の行事である「お楽しみ会」に関心を持ちつつも、人前に立って表現することを恥ずかしがって嫌がり、なかなか参加しようとしません。この保育園の「お楽しみ会」には、毎年お面や舞台背景を子どもたちが製作し、舞台で役を演じる劇の発表があります。保育者は、お楽しみ会の準備に2人をすぐに参加させようとせずに、長い目で見守りながらも、少しずつY夫の意思や成長するプロセスを尊重しながら、行事への参加を促していきました。

3歳児になった時には、「何だったら楽しくできそう?」と問いかけながら、継続的に2人と相談しながら行事に参加できそうなやり方を一緒に考えて取り組みましたが、お楽しみ会の当日は参加することはできませんでした。
4歳児の時には、お面や小道具づくりに参加することができました。しかし、当日は舞台袖で作ったお面をかぶって音を鳴らすことが精いっぱい。でも少しずつ苦手を克服しているように見えます。
そして、5歳児になった頃には、友達とのかかわりが深まってきたこともあり、クラスの友達と一緒に行事の準備に参加し、当日は舞台に上って演じることができました。ここに至るまでのプロセスを振り返っていきます。
H夫とY夫は絆が強く、いつも2人でのかかわりのなかで遊びが完結し、なかなか他の友達とのかかわりが広がりませんでした。2人で一緒にいる時には、ブロック等で剣を作り、ヒーローになりきって戦いごっこで表現を楽しんでいますが、お楽しみ会で行う劇には全く興味を示さず、行事の参加を誘うとキレるような様子で怒り、保育室を出て行ってしまう姿がありました。
3歳児の時はいつも2人だけで遊び、他の友達とのかかわりが広がりませんでした。2人とも遊びの中でヒーローになりきって遊ぶなど表現遊びは好きですが、人前に立って他人から見られることには苦手意識があるようでした。また、自由遊びは好きでよく遊べていますが、ゲーム遊びなど集団での遊びにはなかなか参加しませんでした。
2. 友達と遊ぶ楽しさを自分で見つける援助
保育者は、2人の関係を大切にしつつ、他の友達とのかかわりを広げていけるように援助しました。また、様々な友達と一緒に遊ぶ楽しさを経験しながら、様々なことへの興味・関心や意欲につなげていけるように援助しました。また、「お楽しみ会」などの行事にどう参加するかを保育者と一緒に考えながら自分で決めて参加できるように援助をしました。
(1)集団遊びに参加できる援助(3歳時)
3歳児クラスの時から、しっぽとりゲームなど、クラスでのゲーム遊びを日中の活動に取り入れて、大勢の子どもと一緒に遊ぶ時間を作るようにしました。また、異年齢で楽しめる活動を計画し、それぞれが異年齢の異なるグループで遊ぶことで、他の友達とのかかわりがもてるようにしました。その際には、H夫・Y夫と相談しながらできそうな方法を探り、「これならやってみたい」「これなら頑張れそう」と思える活動を自分で選んで参加できるようにしました。

(2)「自分で考えたことをやっていい!」という気づきへ
4歳児になると、行事の準備や練習をするときには、舞台に上がって表現することにこだわらないように心がけ、行事に必要なお面や舞台背景の制作も、行事への取組みと位置づけて、H夫・Y夫なりの表現や行事への取組み方を模索しながら楽しめるようにしました。また、2人には、「すぐに怒るのではなくてどうしたいのかをお話ししてほしい」と伝えました。しかし、保育者が手伝おうとすると「ダメだってすぐに言うでしょ!」と強い口調で言います。このような時には、保育者も気持ちが昂りますが、同僚保育者にも事情を話し、H夫・Y夫から離れてクールダウンして気持ちを落ち着かせるようにしました。
このような、保育者が行事への取組みを柔軟に捉えることや、H夫・Y夫に寄り添いながら一緒に方法を考えることを重ねていくことで、H夫とY夫はいつしか「自分で考えたことをやっていい」ということに気づいたのではないかと思います。2人とも戦いごっこが好きなことから、4歳児の時の劇の発表では、悪者と戦う役になりました。そして、気分が乗った時には劇の練習に参加できるようになりましたが、当日はお面をかぶって舞台裏で音を鳴らすという参加の仕方をしました。

(3)クラスの友達と一緒に取り組む楽しさを実感
5歳児になると、H夫が同じクラスの他児と仲良くなり、Y夫と離れて遊ぶ姿が見られるようになりました。そのうち、H夫と他児とのかかわりの中にY夫も加わり一緒に遊ぶようになりました。友達とのかかわりが少しずつ広がり、一緒におままごとに参加する姿も見られるようになりました。また、集団ゲームをしている他児の姿に興味を持って少しずつ参加できるようになりました。
こうして、同じクラスの友達との関係が広がっていくと、お楽しみ会の劇の練習でも、友達と一緒に取り組む楽しさを実感して、活動に一緒に参加する姿が見られるようになり、自分で考えたセリフや小道具を取り入れながら参加することができるようになりました。

3. 困ったことを自分の言葉で発信する経験
子どもの「やってみたい」「面白そう」という気持ちを尊重して、焦らずに、子どものペースでじっくり取り組めるような状況を作りました。行事は保育者主導で進めていきがちですが、保育者と相談しながら自分で考えて自分で決めて取り組むことで満足感や達成感が得られるように援助しました。また、他の友達との関係づくりを援助することで、子どもに友達と協力する楽しさを経験できるようにしました。
そして、幼児期には、保育者に対して、困っていることを自分の言葉で発信していける力を身につけられるように援助できるとよいと思います。これは小学校に入学してからも同じで、環境が変わって困ることがありますが、困っていることがあったら自分で先生に話をするように、子どもたちに伝えています。
(保育士 松本春菜/東京家政学院大学教授 中田範子)
▼『保育ふかマル!シリーズ1 心の発達と「レジリエンス」の育て方』では
他にも次のような内容を読むことができます。
幼児の発達と「レジリエンス」
・いま求められる力としての「レジリエンス」
・「レジリエンス」の捉え方と発達段階における課題
・「レジリエンス」を育む保育
レジリエンスを育む保育実践
・東京都品川区公立幼稚園
・文京区立お茶の水女子大学こども園
・とりやまこども園 ほか全12事例
「レジリエントな」子どもを育てる条件
・レジリエンスを育みたい子どもとの向き合い方
・レジリエンスを育むチーム保育のあり方・取組み方
・保護者との関係づくりとレジリエンス
・保育者自身のレジリエンスをどう高めるか
「我慢ができない」「落ち込んだら立ち直れない」子への関わり方、
「リカバリーできる力」の育て方をもっと知りたい保育者の方へ
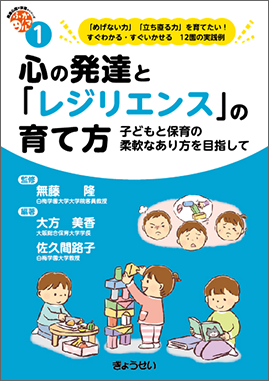
保育ふかマル!シリーズ1
心の発達と「レジリエンス」の育て方
- 子どもと保育の柔軟なあり方を目指して -
編著者名:無藤 隆(白梅学園大学大学院客員教授)/監修
大方 美香(大阪総合保育大学学長)
佐久間 路子(白梅学園大学教授)/編著
販売価格:2,530 円(税込み)
詳細はこちら ≫