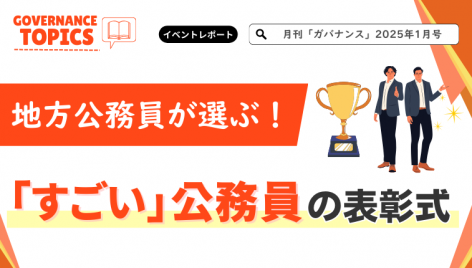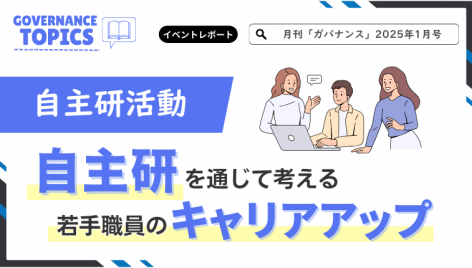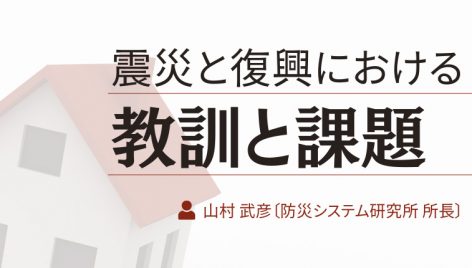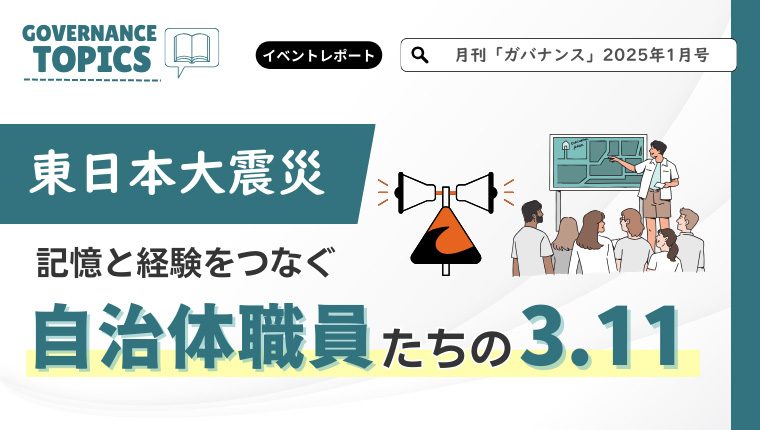
ガバナンスTOPICS【イベントレポート】
【東日本大震災】自治体職員たちの3.11/イベントレポート
地方自治
2025.02.06
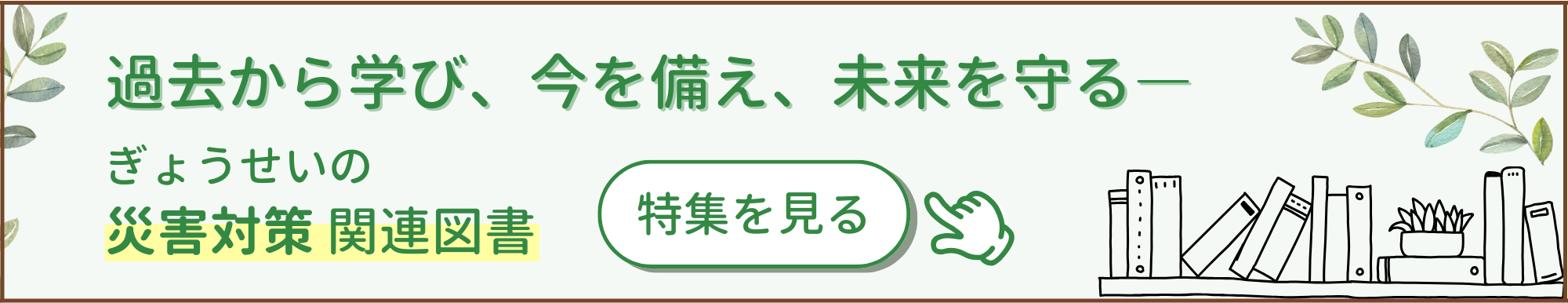
(『月刊ガバナンス』2025年1月号)
【連載一覧はこちら】
【ガバナンス・トピックス】
震災の記憶と経験をつないでいくイベントを開催
──東北OM15周年&あれスぺ10周年記念イベント「自治体職員たちの3.11」
東北地方のまちづくりや地域活性化に資する〝人財〟育成を目指し活動を行っている官民のネットワーク「東北まちづくりオフサイトミーティング(東北OM)」と東日本大震災での自治体職員の体験を語り継ぐイベント「あれからスペシャル(あれスぺ)」による共同イベント「自治体職員たちの3.11」(主催:東北OM、あれスぺ実行委員会、大学行政管理学会)が、2024年11月23日に仙台市で開催された。震災を経験した自治体職員らが当時の経験を共有し、将来に語り継ぐための場となった。

会場の東北学院大学ホーイ記念館。震災当時、この場所は東北大学のテニスコートで、緊急避難場所だった。
あの日の経験を語り継ぐために
イベントは、東北OM15周年と、仙台市役所職員の有志のグループTeam Sendaiが中心となり、東日本大震災の経験を記録し伝えるイベント「あれスぺ」10周年を記念し、仙台市の東北学院大学を会場に開催されました。

まず、東北OM運営委員の後藤好邦さん(山形市)が、「24年3月にNHKで放送された『語れなかったあの日 自治体職員たちの3.11』を観て、東北OMでも同じようなことができないかと思い立ち、あれスぺのみなさんと一緒に企画した」と企画趣旨を説明。
共同開催のあれスペ実行委員長の鈴木由美さん(仙台市)も挨拶。「あれスぺは、『風化に抗う』ことで始めた伝承イベント」と話し、東日本大震災の対応に従事した職員らへの聞き取りや、朗読や映像、専門家を招いてのワークショップなど、震災の記憶や経験を様々な形で伝え、未来に備える活動を紹介した。
「東日本大震災に対峙した学生と大学の災害ボランティアを考える」
最初のプログラムは、会場となった東北学院大学学務部の其田雅美さんが「東日本大震災に対峙した学生と大学の災害ボランティアを考える」と題し、講演をした。
東日本大震災から3週間後の3月29日に同大に設置された災害ボランティアステーションで中心的な役割を担ってきた其田さんは、その設置経緯や活動内容などを紹介した。宮城県内を中心に展開した学生ボランティア活動では「学生ボランティアがコミュニティ再生の『接着剤』としての役割を果たした」という。
其田さんは、「組織間の連携がなければ復興ボランティア活動はできなかった。組織と組織が平時から関係を構築していくことが大事だ」と経験からの学びを述べた。
震災体験の朗読
続いては、震災体験の朗読。「過去の震災の経験を継承し続ける組織文化を」(震災当時の宮城県総務部長の体験/朗読者:鈴鴨久善さん)と、「被災された方々にとって役所は最後のセーフティネットだ」(当時の仙台市宮城野区長の経験/朗読者:柴田恵美さん)の二つの話に会場が耳を傾けた。
それぞれのストーリー
「自治体職員たちの3.11」(聴き手:佐藤翔輔・東北大学災害科学国際研究所准教授)
このプログラムでは、2人の自治体職員が登壇した。
岩手県釡石市職員 宮本光さん
岩手県釡石市職員の宮本光さんは、東日本大震災当時は総務課に所属。1年後の12年6月から被災した中心市街地の再開発、用地交渉という本格的な復興事業に携わった。様々な事情や制約がある中、初めての用地交渉業務だったが必死に取得を進め、「やりがいもあったが消耗した1年だった」と振り返る。
翌13年になり、用地交渉2年目に入ると、代替地が不足し交渉が難航。それに加えて復興推進本部に異動し、復興事業リードも担うことなった。激務の中でも、「今頑張らなくていつ頑張るんだ」という思いで業務外の勉強会なども実施していた。しかし、心身ともに疲労もピークに達しダウン。病休そして異動となり、復興の最前線から離れてしまった。このことで宮本さんは、何年も後悔と葛藤を抱えてきたという。
それでも時間の経過とともに心情も徐々に変化。後悔は肯定や納得に変わった。今では、職員研修の講師など新たなチャレンジもしている。
この発表で初めて、自身の辛い経験を人前で打ち明けたという宮本さんは、「職員一人ひとりに震災からのストーリーがあり、それぞれの持ち場で踏ん張ってきた。復興は、見えない葛藤や陰の支えがあってこそだ」と話し、「長く続く復旧復興業務では、心身を自制することが難しい。発災後1年の復旧期は興奮状態でなんとか対応できるが、復興事業に着手する2年目以降は、難易度も上がり、疲労も重なる。大規模災害は長丁場になるからこそ、自分自身や仲間、つながりを大切にしてほしい」と、発災2年を迎える能登の自治体職員にも伝えたい、と話した。

自治体職員らは率直な経験を語った(左から宮本さん、福島さん、佐藤准教授)。
福島県南相馬市職員 福島勉さん
福島県南相馬市職員の福島勉さんは、震災時はまだ仙台で大学院生だった。春からの入庁予定が震災によって採用が遅れ、予定から1か月後の5月1日に入庁した。
震災対応に追われる市役所での辞令交付式はスーツではなく作業着で行われ、研修や歓迎会もないまま仮配属先に飛び込むように市役所生活が始まった。
その後、正式配属された企画経営課では、福島第一原発事故によって複雑に線引きをされる地域と向き合わなければならなくなった。地元では、様々な対立や矛盾が渦巻き、市民の分断を目の当たりにした。
それらに向き合う中で、福島さんには、「絶対的な価値観・正解はない」、そして、「震災で失ったものより、震災があったことで得られたものに目を向けよう」と軸が定まった。福島さんは「何かが起きた時にどうプラスの方向に捉えることができるかが大事なのでは」と語り、南相馬での様々な活動を紹介した。
元仙台市長の3.11
特別講演2――元仙台市長 奥山恵美子さん

震災時に仙台市長だった奥山恵美子さん。「とにかく復興のフェーズを上げることに努めた」と話した。
特別講演2では、東日本大震災時に仙台市長だった奥山恵美子さんが当時を振り返った。発災後いち早く応援に駆けつけてくれたのは、新潟市や神戸市の職員たち。中越地震や阪神・淡路大震災の経験を共有してもらった。「被災経験のある自治体は動きが早いことに驚いた」という。
発災から数日経ち、被害の状況が明らかになっていく中で、行政職員として長いキャリアを持っていた奥山さんも「これだけの災害に対して自分の頭の中に、どう判断すべきかの地図がなかった」ことが不安だったという。
そうした中で奥山さんが〝希望〟と感じたのは、過去の災害対応の前例だった。資料をかき集め、読み込んだという。そこには、これから自分が判断することになるであろうことがたくさん書かれてあり、「進むべき道が見えた」そうだ。
奥山さんは「震災は市長になって1年10か月ほどで起きた。復興では合意形成が一番難しいこと。でも私には地域住民に対して政治力がなかった。私が前に出るのではなく、仙台市が政令指定都市として持っている組織力をより高いレベルで発揮させることが私の仕事だと考えた」と当時を振り返った。
講演の後には、「100年後に伝えつづけるためのワークショップ」(ファシリテーター:遠藤智栄さん(㈱ばとん))で、参加者らが対話。「人の口から人の心に伝える」ために、経験や学びの共有と、新たなネットワークの構築の場が広がった。
(本誌/浦谷 收)