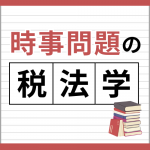時事問題の税法学
時事問題の税法学 第4回 夫婦別姓
地方税・財政
2019.06.24
時事問題の税法学 第4回
夫婦別姓
(『月刊 税』2016年2月号)
旧姓使用のハードル

大学の専任教員時代の話である。前年度に選考・採用され着任した女性教員が、新年度初日の辞令交付の際に提出した住民票記載の姓で騒ぎになった。応募書類から理事長による最終面接に至るまで、一貫して戸籍名ではなく旧姓(通称)で通していたのだ。学部長は、理事会から「いったい誰を採用したんだ」と嫌みを言われたようだ。
確かに女性研究者は、結婚により姓が変わると研究の継続性が損なわれるとして、結婚しても旧姓を使用する人は多い。大学では、旧姓使用を届ける必要があるが、役所や企業でも同様と思う。しかし教員公募に対して提出する履歴書には、戸籍名が記載されていると考えるのが自然である。研究業績書における姓名と異同があるなら両方を併記すれば足りるし、元来、教員人事では既婚・未婚は影響しない。
このとき驚いたのは、その女性教員が民法学者で、しかも家族法を専攻していたことだった。法令遵守などと大仰なことは言わないが、民法学者が民法という制度上の枠に拘らないのが面白かった。私自身、法令に対する批判はするが、結局、法令の枠からはみ出ることのできない強行法である税法の研究者としての悲哀も感じた。
夫婦別姓に関する民法改正

こんな夫婦別姓に関する解決が見出されるかと思われていたが、平成27年12月6日に最高裁大法廷は合憲判決を出した。今後は夫婦別姓の選択に係る民法改正が、国会審議に委ねられる。
夫婦別姓を主張する理由のひとつに姓が変わることでアイデンティティが失われるという見解がある。生家(実家)の姓を尊重し、維持することは、生家主義という新たな家制度かもしれない。
洋の東西を問わず、家の根幹は相続といえる。旧法における単独相続としての家督相続と異なり、現行では妻の法定相続分が定められている。これは内助の功を評価したものだろう。しかし高齢化社会の今日では、資産の維持・運用に関する内助の功は妻から同居している子や子の配偶者に移動している。また平等原則の見地から、資産管理に全く寄与していなくても、非嫡出子(婚外子)に対する相続分差別に対する違憲判決も出ている。家と付随する財産に係る相続にも新しい見方が必要になってきた。その意味で上述の生家主義の考え方も、新しい相続の形になる。
テレビで、「わが国では昔から女性は実家の姓を生涯使用していた。例えば、源頼朝の妻は、北条政子というでしょう」としたり顔で政治学者が解説していた。庶民に姓が許されたのは明治になってからであるから、これは説得力に欠ける。ただ選択制別姓については、実生活において混乱することもある。
判決前の報道では選択制を求める声が多く紹介されていた。そのなかで、事実婚の夫婦が病院等で親族でないことから、付き添いなどが認められないので、選択制になれば入籍できるというコメントが気になった。いまなら身分証などで同姓であるなら夫婦と推認される。選択制が導入されたとき、別姓であるが夫婦であると、手軽に立証する術が思い付かない。常に戸籍謄本や住民票を携行するのも不自然である。
ただ選択制導入により事実婚が解消されれば、明確化される税務手続もある。所得税の配偶者控除や寡婦控除、相続税における配偶者の税負担軽減、贈与税の配偶者控除などは、いわゆる法律婚又は法律婚の関係にあった者に適用される税務上の措置である。同棲している女性に、「事実婚?」と聞くと、「同棲しているだけ」と答えるケースが多い。「同棲」と「事実婚」の区別は、まさしく当事者(あるいは一方的に)の意思に関わる問題であり、形式的、客観的に婚姻関係が判然としない。相続税の手続ならともかく、通常の税務では、いちいち戸籍関係の資料を確認しないから、後日、家族関係に驚かされることもある。
もっとも今般の税制改正では先送りされたが、所得税の配偶者控除の見直しがすでに決まっている。課税対象を家、家族、世帯というグループから個人単位に移行する時代が来るだろうか。