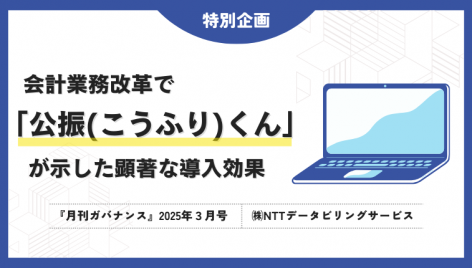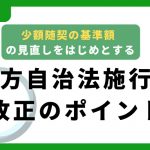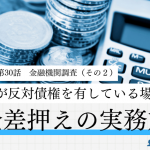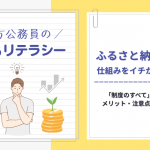自治体DXナビ
自治体DXナビ DXの「現場」(前編)─福島県磐梯町で見つけた、人とデジタルの交差点
地方自治
2025.11.19

この記事は4分くらいで読めます。

出典書籍:『月刊 J-LIS』2025年6月号
「自治体DXナビ」は「月刊 J-LIS」で連載中です。
本誌はこちらからチェック!

ご購読なら年間購読がお薦め!
月刊 J-LIS(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
この資料は、地方公共団体情報システム機構発行「月刊 J-LIS」2025年6月号に掲載された記事を使用しております。
なお、使用に当たっては、地方公共団体情報システム機構の承諾のもと使用しております。
自治体DXナビ
DXの「現場」(前編)
─福島県磐梯町で見つけた、人とデジタルの交差点
チーム愛媛DX推進支援センターセンター長 渡部 久美子
この記事は前・後編の「前編」です。「後編」の記事はこちらから!
自治体DXナビ DXの「現場」(後編)─愛媛県・市町協働事業「高度デジタル人材シェアリング業務」の現場から
はじめに
私自身が携わってきた自治体DXの「現場」は、大きく二つあります。
一つは、福島県磐梯町における地域プロジェクトマネージャーとしての業務。こちらは、住民の皆さんと直接向き合いながら進めた「対住民」の現場でした。
もう一つは、愛媛県の市町協働事業における高度デジタル人材シェアリング事業。こちらは、各市町の職員と伴走しながら、自治体の内側から変革を支える「対職員」の現場でした。
前編では、一つ目の現場、福島県磐梯町での取り組みについてご紹介します。
DXという言葉が先行しがちな今だからこそ、現場でどんな課題があり、どんな人との出会いがあり、何を目指して歩んできたのかを、私自身の体験をもとに丁寧にお伝えしたいと思います。
目的とビジョンを大切に
磐梯町は、人口約3,000人の自然豊かな小さな町です。この町で私が担当したのは、①地域通貨事業と、②高齢者向けスマホ教室の二つです。どちらの事業も表向きには「デジタル化の推進」と見られがちですが、私にとっての目的は全く別のところにありました。
大切にしていたのは、「デジタルを導入すること」ではなく、「町の未来をどう変えていきたいか」というビジョンです。私たちが目指したのは、技術導入のためのDXではなく、「自分たちの子や孫たちが暮らし続けたい魅力あるまちづくり」を実現するためのDXでした。
町長が掲げるこのビジョンに共感し、私たちのチームも、人と人とのつながりを支え、豊かな暮らしを後押しするための取り組みを進めてきました。
“導入すること”をゴールにしない
まず、地域通貨事業において、私たちは“導入すること”をゴールにはしませんでした。私が描いたのは、「町の経済が町の中で循環する仕組みをつくること」、そして「お金以外の資源―ヒト・モノ・コト・イミ・カチ―が交換される文化を育てること」でした。
1年目は、町民一人ひとりに寄り添い、対面で丁寧なサポートを行いました。デジタルに対して不安を持つ方が多い中、導入のハードルを一つずつ下げることを意識し、私たちのチームが直接町中を歩いて回り、一件一件の課題を一緒に解決していきました。こうして「点」と「点」が少しずつ「線」になっていったのです。
地域通貨事業の取り組みは、振り返ると三つのフェーズに分かれていたように思います。
1年目は、とにかく「点」を探すことから始まりました。町民一人ひとりの声に耳を傾け、どこにニーズがあり、どんな想いがあるのかを丁寧に拾い上げていきました。そして見つけた「点」には真正面から向き合い、安心してチャレンジできるよう寄り添いながら、その「点」を大きく育てていきました。
2年目になると、育った「点」と「点」をつなぐことを意識しました。
町内の異なる世代の利用者同士、利用者と加盟店として参画している事業者、事業者同士、さらには商工会と地元の商店といった関係者同士が、地域通貨を通じてつながり始めました。暮らす人、働く人、生きる人。それぞれが役割を超えて、町の中で自然に交わり合う関係が少しずつ育っていったのです。私は、対話の場を繰り返し重ねながら、使う人、支える人、届ける人、すべての立場の声を拾い、つながりを太くする支援を続けました。
そして3年目。私たちは、これまで町内で育んできた「線」と「線」を束ね、さらに「面」へと広げる挑戦に踏み出しました。町の中に留まらず、近隣市町村との連携や、磐梯町を訪れる観光客との交流にも地域通貨を介してつながりが生まれるようになりました。町を超えた広がりが、さらに地域への愛着や誇りを高め、町内外を巻き込んだ新たな「面」が形成されていったのです。
「点」が「線」になり、「線」が「面」になったとき。それは単なる事業推進ではなく、町の中に新しい文化や価値観を育む土壌ができた瞬間だったと、私は強く感じています。
「成長」「喜び」「感謝」を育む「ヒトのDX」
もう一つの取り組みが、高齢者向けのスマホ教室です。こちらも単なるデジタルデバイド対策ではありません。私が掲げたビジョンは、「ヒトのDX」でした。
「ヒトのDX」とは、デジタル技術を通じて、「できなかったことが、できるようになる」体験を提供し、その人の暮らしや人生に新しい可能性を届けることです。スマホの操作を教えることが目的ではなく、その先にある“新しいライフスタイル”や“彩りのある生活”こそが本質であると考えました。
教室では私自身が講師を務め、町内外のステークホルダーと連携しながら、一人ひとりの町民と対話を重ねました。私が伝えたかったのは、「いきなり使いこなす必要はありません。まずは“触ってみようかな?” という気持ちからで大丈夫です」ということでした。
デジタル変革はプロセスであり、目指すべきはその先にある「幸せな未来」です。だからこそ、教室では「使い方」ではなく、「スマホで何ができるのか」「それがどう自分の暮らしに役立つのか」といった“価値の部分”を丁寧にお伝えしました。
スマホ教室の中で、今でも忘れられない光景があります。参加者の皆さんがカメラアプリの練習をしていたとき、モデルになったのは、実は私の息子でした。彼は参加者の前に立ち、無邪気な笑顔を見せながらポーズをとってくれました。さらに別の日には、参加者の方にスマホの使い方を教えたり、抱っこされて嬉しそうに笑ったりしていました。
町の中で、世代を超えた交流が自然に生まれていく。その光景は、まさに私が目指していた「ヒトのDX」の一つの答えでした。

スマホ教室の様子
ある参加者の方とはLINEで友だちになり、週に一度、学校行事の応援や日常の励ましのメッセージを送ってくださいます。最初は短い文章だけでしたが、やがて絵文字が入り、スタンプも加わるようになりました。まるで、町民の方の“変化”と“成長”を、そっと見守らせてもらっているような感覚でした。
このスマホ教室を通して得られた最大の成果は、町民のデジタルスキルの向上ではありません。人と人とのつながりが太く、温かくなったこと。そして、デジタルがあってもなくても、人々が互いを支え合いながら、町の自治に向き合えるようになったことが、私にとって何よりの価値でした。
ヒトのDXとは、一人ひとりの人生という長いようで短い時間の中で、出会いをきっかけに「成長」や「喜び」や「感謝」を育むことだと考えています。毎日の暮らしの中で、ほんの少しでも誰かの人生に厚みや深みを与えられる、そんなきっかけをこれからも作っていきたいと思っています。
「現場」で汗をかきながら
最後に、私にとっての「現場」の定義をお伝えします。それは「対話が行われる場所」です。立場や役職、利害関係を超えて、人と人が真正面から向き合い、価値観を共有し、理解し合える場所。私は、そんな現場をつくることこそが、自治体DXの本質であると信じています。
変革とは、あくまでプロセス。その先にあるのは、誰かの人生が豊かになる未来です。福島県磐梯町で過ごした3年間は、私にとって「人と向き合うDXとは何か」を教えてくれた原点となりました。
これからも、現場で汗をかきながら、「誰かの幸せ」を見つめ続けていきたいと思っています。
Profile
渡部 久美子 わたなべ・くみこ
ソフトバンク株式会社にて業務改善プロジェクト等のマネジメントに従事。出産後に退社し、個人事業主を経て法人代表に就任。福島県磐梯町地域プロジェクトマネージャーに着任し、家族で移住。行政業務と並行し、愛媛県チーム愛媛DX推進支援センター長、真庭市共生DX技術責任者などを務める複業人材として活動。2024年よりニュージーランドへ拠点を移し、自治体関連業務をフルリモートで継続中。
「自治体DXナビ」は「月刊 J-LIS」で連載中です。
本誌はこちらからチェック!

ご購読なら年間購読がお薦め!
月刊 J-LIS(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫