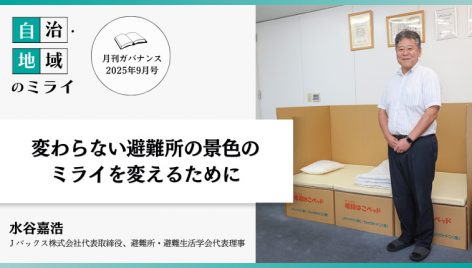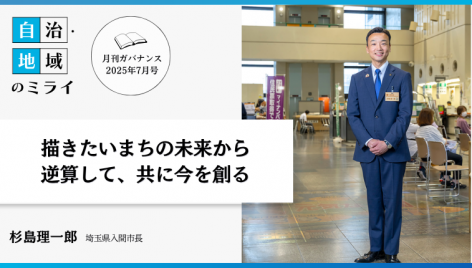自治・地域のミライ
自治・地域のミライ|解は現場にあり。地域の“シンクタンク”としての役所の力を発揮するために 前島根県浜田市長 久保田章市
地方自治
2025.10.29

出典書籍:月刊『ガバナンス』2025年11月号
★「自治・地域のミライ」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!
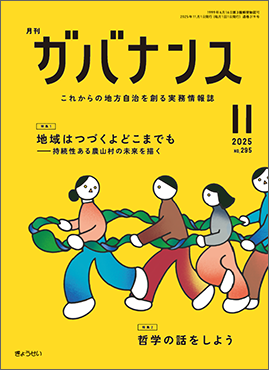
月刊 ガバナンス 2025年11月号
特集1:地域はつづくよどこまでも
──持続性ある農山村の未来を描く
特集2:哲学の話をしよう
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫
前島根県浜田市長
久保田 章市
2013年、故郷・島根県浜田市長となった久保田章市氏。長年、都市銀行に勤め、その後経営学者として大学で教鞭を執った経験を活かし、3期12年浜田市政を担ってきた。今年5月には身近な存在ながら、実はその実態をよく
知られていない自治体の「役所」を解剖する新著『役所のしくみ』を上梓した。2025 年10月の任期満了をもって、浜田市長の勇退を表明した久保田市長に、退任を前に経験や想いを聞いた。
*インタビューは退任前の2025年10月3日に行いました。

JR浜田駅前にあるからくり時計「どんちっち神楽時計」の前で。1時間ごとに上部のからくり時計が作動し、代表的な演目「大蛇(おろち)」を披露する。石見神楽は石見地方の代表的な伝統芸能で、2019年に日本遺産に認定された。「どんちっち」とは、子供たちがお囃子のリズムから「石見神楽」のことを「どんちっち」と呼ぶことにちなんだもの。「大蛇」にちなんだフォトスポットも今年設置された。
2005年10月1日に、浜田市、金城町、旭町、弥栄村、三隅町の5市町村が合併し、新「浜田市」が誕生。島根県西部、石見地方に位置し日本海を望む、山陰地方有数の水産都市。東は江津市、邑南町、西は益田市、南は広島県に隣接。面積690.64平方キロメートル。浜田川、周布川、三隅川等の主要河川が流れ、河川の下流域には平地を形成し、市街地や農地が広がる。2025年10月1日現在、人口4万7707人、12万4813世帯。2025年度の当初予算一般会計は433億598万円。
人口減少が進む中でも、人口を増やすような政策を決してギブアップしない
地元に活気を取り戻すために
――銀行勤務、大学教授を経て、地元・浜田市長を3期務めた。市長を志したきっかけは。
浜田市で生まれ育ち、大学入学を機に上京した。大学卒業後に都市銀行に勤務、その間には厚生省(当時)に出向し、社会保障を学ぶ機会に恵まれた。2006年から法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科客員教授(2008年からは教授)を務めた。同年4月からは市内にキャンパスがある島根県立大学の非常勤講師(現任)にも就任した。2007年に当時の宇津徹男市長からの依頼もあり、市の政策アドバイザーを務めることになり定期的に地元に帰ってくるようになった。
子どもの頃は水産都市として栄え、船の数も多かった。まちにもたくさんの人がいてにぎやかだった。しかし、帰ってくるたびに、まちが寂しくなっていく様子を目にしていた。「政策アドバイザーという立場から言うだけでなくやってみたらどうだ」と周りから推され、2013年の市長選に立候補し初当選した。
社会減が自然減を引き起こす
市の最大の課題は、人口減少。高齢化率は4割近くに達していた。「元気な浜田づくり」をキャッチフレーズにまちづくりを進めてきた。
特に力を入れたのが「産業振興、企業誘致による雇用の場の確保」「子育て支援、教育の充実」「高齢者が安心して暮らすことのできるまちづくり」の3つを重点目標として様々な施策に取り組んできた。しかし、いざ始めると目下の課題である人口減少、特に少子化が想定を上回るピッチで進み、人口も毎年約1000人程度減少している現実があった。雇用を支える事業所も廃業・撤退などで毎年減少していた。
このような状況から巻き返すためにも産業政策が重要と考え、企業誘致だけでなく、主要産業である水産業や農業などの地場産業、中国地方トップクラスの寄附額を誇るふるさと納税(当市では、「ふるさと寄附」と呼んでいる)の推進、日本遺産になった石見神楽などの地域資源を核とした観光振興に力を入れてきた。
また、若者の市外への流出による社会減も大きい。当市の高校3年生の18歳人口は現在おおよそ450人〜500人。8割は市外、そして県外へ進学や就職で転出して行き、多くは戻ってくることはない。その結果、産業や地域活動の担い手が不足するという状況に陥っている。なぜ帰ってこないかを考えると、進学した先で学んだことを活かせるような魅力のある仕事がないことが大きな理由だろう。これは当市に限らず地方都市の多くが直面している課題だ。若者の数が減ることで、結婚する人も減り、さらには出生数にも影響している。つまり、社会減が自然減を引き起こしてしまっている。
――2期目の途中からはコロナ禍に。人口減少に加えて地域や自治に何をもたらしたか。
振り返ってみると新型コロナ感染症は、まさに自然災害に匹敵する出来事だった。当市のような小さなまちだと、どこの誰が感染したらしいなどの噂が飛び交い、どうすれば感染拡大を防げるか、手探りで検討しながら対策を打っていかなければならなかった。
当時、新型コロナワクチン対策室を設置し、各部から10人の職員を招集し対応した。国の一人当たり10万円の給付に加え、市独自の子育て世帯への応援金の支給、プレミアム付き「はまだ応援チケット」の販売、市独自の事業者向け特別給付金事業、市内飲食店への感染防止パーテーション設置など様々な支援を行った。これらもその都度、各部から職員を招集し対応した。職員の皆さんの頑張りのおかげで何とか厳しいコロナ禍の時期を乗り越えることができた。
しかし、一番大変な時期を乗り越えたとはいえ、新型コロナの影響は続いていると感じている。特に出生数は大きく減少した。コロナ以前は毎年350〜400人くらいだったが、コロナ禍では300人を割り込み、昨年度は241人になった。今年度はさらに下回る見込みだ。
地域の行事もコロナ禍の3〜4年間はほとんどが中止となった。当時は行政側からも止めるような発信もした。しかし、コロナが落ち着いた今、以前のような開催や活動に戻っていない地域行事も多い。一度止めたことで、「たいぎいな」(浜田市など石見地方の方言で「めんどくさい」)となってしまった。行事というのは、毎年やっているからこそやり方が伝承されていく部分があるが、それが途切れてしまった。一度止めてしまうと復活させるのには非常にエネルギーが必要になってしまう。またやろう、というマインドが少なくなってしまったようにも感じている。
一方で、プラスの面としてはデジタル化が進む契機になった。WEB会議は普通となった。DX推進が当市の最重要施策の一つだ。本年4月にはDX推進室を設置。今後は、市役所に来なくても手続ができるなど環境が整っていくだろう。

くぼた・しょういち
1951年4月11日、島根県浜田市生まれ。東京大学卒業、法政大学大学院修士課程修了。横浜国立大学大学院博士課程単位取得満期退学。三和銀行・
UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)に30年間勤務し、支店長・部室長等を歴任。三菱UFJリサーチ&コンサルティング執行役員、法政大学経営大学院教授(専門は中小企業経営、後継経営者育成、地域経営など)を経て、2013年に浜田市長選に立候補し、当選。以後、3期市長を務めた。主な著書に『役所のしくみ』(日本経済新聞出版、2025年)、『小さな会社の経営革新、7つの成功法則』(角川SSC新書、2013年)、『二代目が潰す会社、伸ばす会社』(日本経済新聞出版、2013年)、『百年企業、生き残るヒント』(角川
SSC新書、2010年)などがある。
人を育てることが地域を育てる
――様々な施策で地域の課題解決を図ってきたことと併せて、職員や地域の人材育成にも力を入れてきた。
自治体は様々な課題を抱えている。人口減少、産業の低迷、空き家の増加、公共施設の老朽化、公共交通の維持──数え上げればキリがない。そしてこの課題に対応していくのは、最前線にいる自治体職員だ。
自治体の施策の発案には「国の好事例情報」「地方議員からの提案」「市民からの提案、要望」「職員の発案(ボトムアップ)」「首長の発案(トップダウン)」の5つのルートがある。
首長として嬉しいのは、「職員からの発案」だ。他の自治体でやっていることから学んだりしながら、知恵を絞る。これが増えれば、職員の施策立案能力が向上し、市役所内が活性化するだろう。
しかし、特に係長以下の職員が立案する施策には多くのハードルがある。施策の有効性や法的な問題はないか、事業費はどうするか、国の財政支援はあるのか──多くの詰めるべき点がある。せっかく施策を考えたとしても、部・課長からのストップや、ボツになることもある。これが続いてしまうと職員の「施策を考えよう」という意欲が低下し、ひいては自治体の施策立案能力の低下につながると感じた。
人材育成は、一義的には人事課が担当ではあるが、特に係長以下の職員が問題意識をもち、熱意をもって取り組んでいくためには、首長が積極的に人材育成に力を入れることが重要だろうと考えた。そこで、首長を交えた「施策ミーティング」を設けた。「生煮えの案でOK。どんどん施策を持ち込んでほしい」と市長室に長テーブルとホワイトボードを設置し、職員からの説明を聞きながら質疑・検討をして直接判断、指示を出すような仕組みにした。私が大学で教鞭を執っていたこともあってか、さながらゼミのような雰囲気だ。案件の都度の開催だったが、実質ほぼ毎週行ってきた。
職員発案で特筆すべきは「シングルペアレント介護人材育成事業」だ。2014年に日本創成会議のいわゆる「増田レポート」が発表され、当市も「消滅可能性都市」とされた。そこで女性職員らが「女性が増えるまち、住みやすいまちにするにはどうするか」を検討する勉強会を開催。特に母親のひとり親世帯に移住を促し、市内で不足している介護人材の担い手として働きながら、当市のコンパクトな地理的強みを生かしつつ職住近接で暮らしてもらうための取り組みを実施した。結果的に19世帯が移住をしてくれた。中には、お子さんが大きくなり一緒に市外へ転出してしまった方もいるが、現在もそのまま暮らしている世帯もある。この事業は注目され、行政視察も100件近くあった。その他にも「移動期日前投票車の導入」や「若い音楽家の誘致」など、全国的にも珍しい事業が「施策ミーティング」から生まれていった。
――金融業界、その後経営学の教員をしてきた。それまでのビジネスの世界と行政との違いは。
市長になった当初、予算編成の仕方に違いを感じた。民間企業の多くは中・長期の事業計画を策定し、投資計画を立てる。いかに経費を最小限にし、投資を抑えてパフォーマンスを上げ、収益を極大化させようとする。しかし、自治体の予算は基本的には単年度主義。3月に当初予算として策定された歳出予算は、4月から翌年3月末までに執行しなければならない。
私は、健全な財政を維持するためにはしっかりと中長期での財政計画を立てるべきと考え、2016年から10年間の財政計画を作成した。10年のタームで考えつつ、毎年12月にはローリングをする。そして毎年の予算で歳出と歳入をコントロールしながら財政運営を行っている。
また、予算承認後の施策の進捗管理についても、首長になってから疑問に思っていた。そこで、その施策のアイデアを実施するまでの課題を解決するために「ロードマップ会議」を設けた。担当職員と市長ほか幹部職員が一緒に進捗確認と課題共有、解決方法を毎月ほぼ2日間かけてじっくり議論する。民間企業でいうところのPDCA会議のようなイメージだ。この会議は、「施策ミーティング」同様、職員の育成にも役立っている。議論をすることでの施策立案力の向上、施策への責任感の醸成、そして達成した後のモチベーションアップにもつながったと感じている。

浜田市出身のスポーツ選手も多い。今年9月に開催された東京2025世界陸上男子3000m障害で8位入賞した三浦龍司選手もその一人だ。
中小企業のオヤジとして
――3期12年務め、今、自治・地域のミライをどのように考えているか。
「施策ミーティング」や「ロードマップ会議」などは、人口5万人くらいの規模で職員との距離が近いからできたとも感じている。人口が数十万人くらいの自治体になると首長が政策一本一本にしっかりコミットするのは難しくなるだろう。
私は経営学、特にも中小企業経営を専門にしてきた。当市くらいの規模の自治体の首長は、まさに“中小企業のオヤジ”だと思って自治体経営をしていくことが重要だと感じている。
人口減少は当市に限らず国全体としての大きな課題だ。賢く縮むこと(スマートシュリンク)もこれから大きな流れになるだろう。しかし、一方で首長としては人口増加、出生数増加のための政策をギブアップするべきではないと思っている。自転車がペダルを漕ぎ続けないと倒れてしまうように、あきらめずに続けることも重要だと感じている。
自治体が抱える様々な課題に対応するには、役所の役割は大きい。役所は「地域のシンクタンク」であり、実動部隊だ。予算を持ち、専門家が揃い、施策の基となるデータもある。民間と連携するにしても、役所が前面に立って地域を盛り立てていくことが重要になってくる。旗を振れる、活動できる「人材」をいかに育成することも重要だ。
地方の環境はこれからますます厳しくなるだろう。そのような状況だからこそ、役所に対する期待は一層高まってくる。そのような想いもあり、新著(『役所のしくみ』)を書いた。自治体は難しい課題も多くあるが、面白く、やりがいのある仕事だ。
私は「解は現場にあり」という言葉が好きだ。地方の課題解決のカギを握っているのは地方だろう。ぜひ、志ある人に役所で活躍してほしいし、議員になるという選択肢もあるだろう。でも、私の経験からすると究極は首長になって地域を変える!という想いをもつ人が一人でも出てきてくれると嬉しいと思っている。

久保田・前市長の新著
『役所のしくみ』(日経プレミアシリーズ)
出版社:日本経済新聞出版
新書判・定価990円(10%税込)
(取材・構成/本誌 浦谷收、写真/加藤智充)
★「自治・地域のミライ」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!
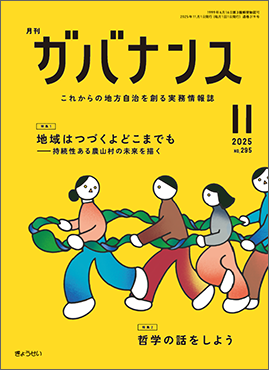
月刊 ガバナンス 2025年11月号
特集1:地域はつづくよどこまでも
──持続性ある農山村の未来を描く
特集2:哲学の話をしよう
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫