
新・地方自治のミライ
新しい資本主義と自治体のミライ|新・地方自治のミライ 第104回
地方自治
2025.11.24

出典書籍:『月刊ガバナンス』2021年11月号
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
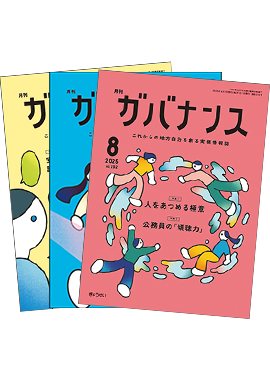
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2021年11月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

菅義偉前首相は、かねてより、説明力・発信力不足などを指摘されてきた。内閣支持率を低下させて、近々不可避的に生じる衆議院選挙において「選挙の顔」にならないとして、「菅(すが)下ろし」をされてしまった。つまり、自民党総裁選挙への立候補の断念に追い込まれた。
新型コロナウイルス感染症対策として為政者にできることは辞任である(注1)。それゆえ、前年の安倍晋三元首相と同じく、「正しい」選択である。政権与党の党利党略として、政局にとって効果的に辞任する。実際、自民党総裁選挙によってメディアの関心を集めた。岸田文雄新首相が選出された「ご祝儀」相場もあって、与党の支持率浮揚に寄与した。もちろん、首相辞任によって、パフォーマンスを繰り返す自治体首長を免責したことや、対策の検証を棚上げしたことは、国民に対する政策責任としては問題である。
注1 拙著『コロナ対策禍の国と自治体』ちくま新書、2021年、191頁。
岸田首相の所信表明

衆議院選挙直前の内閣は、制度的には「選挙管理内閣」である。総選挙後に国民の審判を得た本格的な政権を構成するのが、建前である。しかし、日本の場合、ロシアなどと同様、選挙前から与党「勝利」は、「自明」である。それゆえ、岸田内閣は、総選挙後も継続が「予定」されている。そこで、同首相の10月8日の所信表明を検討することは、自治体から見ても重要である。
所信表明によれば、「新しい経済社会のビジョン」を示して「新しい資本主義の実現」を目指すという。そのために、「信頼と共感を得られる政治が必要」とされ、「多様性が尊重される社会」を目指すという。「危機によって大きくなっている」「格差」「分断」に対して、「絆の力を呼び起こす」という。
そこで、政策を三つにまとめた。「第一の政策」は「新型コロナ対応」、「第二の政策」は「新しい資本主義の実現」、「第三の政策」は「国民を守り抜く、外交・安全保障」である。「新しい資本主義の実現」は、「成長戦略」と「分配戦略」からなる。冒頭では「大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長戦略の推進」と、アベノミクスと同趣旨を掲げているので、安倍元首相に対する「聞く力」は発揮された。また、「絆」は菅(すが)前首相の標語である。しかし、「新自由主義的な政策」の弊害を指摘し、「分配なくして次の成長なし」と、菅(かん)直人政権の「強い経済、強い財政、強い社会保障」にも「聞く力」を発揮した。
金銭勘定的には「強い財政」(増税)なくして「強い社会保障」があり得ないため、野田佳彦・民主党政権は社会保障・税一体改革に向かった。しかし、集票勘定的には、「強い財政」(増税)は「弱い政権」になるため、選挙目前にあり得ない(注2)。高市早苗・自民党政調会長を後見する安倍院政のもとの岸田首相も「経済あっての財政であり、順番を間違えてはなりません」と、「弱い財政」(赤字財政)による分配を目指している。財務事務次官から強い異論が出たのは、当然であろう(注3)。
注2 年収1億円以上で急激に実効税負担率を低下させている20%の金融所得分離課税の見直しでさえ、「当面触らない」としている。毎日新聞デジタル版2021年10月10日11時59分配信。
注3 文春オンライン2021年10月8日配信。「「このままでは国家財政は破綻する」矢野康治財務事務次官が“バラマキ政策”を徹底批判」。
自治と分権の不在

岸田首相の所信表明で特徴的なことは、「自治」と「分権」への言及が全くないことである。すでに第2次安倍政権から、実質的な集権逆流は進み、自治体は忖度と追従の水平的競争をさせられてきた。
岸田首相所信表明でも「菅前総理の大号令の下、他国に類を見ない速度でワクチン接種が進み、この闘いに勝つための大きな一歩を踏み出せました。前総理の御尽力に、心より敬意を表します」とある。〈ワクチン接種率の闇雲な上昇〉という単純なノルマ主義的案件の場合、垂直的官邸統制は、自治体間の水平的政治競争の寵愛・同調メカニズムを通じて、実効的に為される。
しかし、明確な政策方針が見えない案件に関しては、垂直的官邸統制は、硬直的な阻害要因となる。様々な組織からなる社会における波及効果を精密に計算できない官邸主導は、中央机上論に伴う様々な玉突き的なトラブルを招く。「新しい資本主義の実現」という社会経済のメカニズムの変更を目指すならば、自治体の現場における様々な自律的・主体的な調節が必須である。にもかかわらず、中央でビジョン策定する「新しい資本主義実現会議」のみが言及され、自治体現場への垂直的官邸統制を廃絶することを表明しないため、現場での大混乱と政策の竜頭蛇尾に陥りかねない。
地方への中央からの期待
「自治」と「分権」の不在に対して所信表明では、「地方」が登場する。言うまでもなく「地方」とは「中央」や「都市」に対置される用語である。中央大都市(首都=永田町・霞が関)における机上論の「新しい資本主義」に対応する「地方」なるものが、自治体や現場に期待される。所信表明では、まとめると3箇所で「地方」が言及されている。
第1に、成長戦略のなかの柱とはされず、前文的な位置づけで、「変革は、地方から起こ」る、とされる。「地方は、高齢化や過疎化などの社会課題に直面し、新たな技術を活用するニーズがあ」る。「例えば、自動走行による介護先への送迎サービスや、配達の自動化、リモート技術を活用した働き方、農業や観光産業でのデジタル技術の活用」である。内容的には、成長戦略の第一の柱の「科学技術立国」に近い。
第2に、成長戦略の第二の柱とされる「デジタル田園都市国家構想」である。「地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こ」す。「そのために、5Gや半導体、データセンターなど、デジタルインフラの整備を進め」て、「誰一人取り残さず、全ての方がデジタル化のメリットを享受できるように取り組」む。
第3は、分配戦略の柱とはされず、盲腸的な言及である。「これらに加え、地方活性化に向けた基盤づくりにも積極的に投資」する。
「地方」に期待されるのは、デジタル技術の活用と情報インフラ投資である。前菅(すが)政権のデジタルトランスフォーメーション(DX)以来の、あるいは、森喜朗内閣の「e-ジャパン構想」以来の、相変わらずのデジタル頼みの経済政策である。
しかし、日本の経済界にはデジタル化の技術革新をする能力がなく、ガラパゴス化して平成不況が生じた。デジタル化は世界の趨勢に合わせて進めるしかないだろう。が、経済界に革新能力はないので、経済政策や成長戦略にはならない。単に、世間並みに後衛の方から世界の技術変化についていくだけであろう。
このように、「新しい資本主義」の将来像が開けないデジタル化の先兵としてのみ、地方が期待される。地方は、自らは情報技術革新を生めない「好奇心」より「調和」を重視する日本的閉塞の下(注4)、国の方針(「令」)に「和」して踊り、病歴・生育歴・非行歴などの個人情報を供出する。「調和」より「好奇心」の外国で進む情報技術革新によってすぐに陳腐化するが、時代遅れの無駄なインフラ投資をさせられ、個人監視社会と財政破綻だけを招く。
注4 AERAdot. 2021年10月8日16時34分配信。ノーベル物理学賞の真鍋淑郎氏の日本に戻りたくない理由「核心をついている」。
おわりに
「新しい資本主義の実現」を目指すならば、本来は、自治体を分配戦略に位置づけるべきである。科学技術立国による成長という方針自体が、陳腐である上に実現可能性がなく、地方に最も適合しない。
地方圏は相対的に子育て・高齢者比率が高い。また、地方圏の経済循環を支える看護・介護・保育などの従事者の所得は、「公的価格」が鍵になる分配戦略の要である。
そして、大都市圏に人口比重が大きく傾いた現代日本では、池田勇人型の所得倍増・新産業都市でも、田中角栄型の「国土の均衡ある発展」でも、ましてや結果的に「新自由主義」への扉を開いた大平正芳型の「田園都市国家構想」でも、「新しい資本主義」は描けない。むしろ、看護・介護・保育などの公共サービスは、全国的に自治体を通じて、地域ごとに精妙に「調和」されるべき準市場である。そのために、自治体を分配戦略の中心に位置づけることが求められよう。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
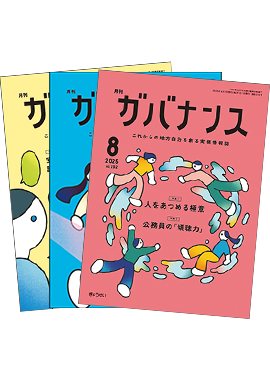
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫























