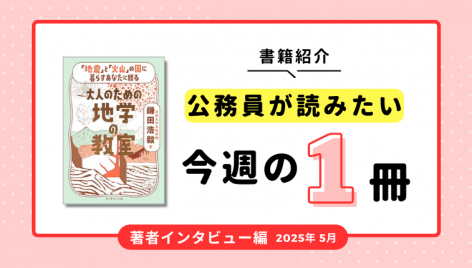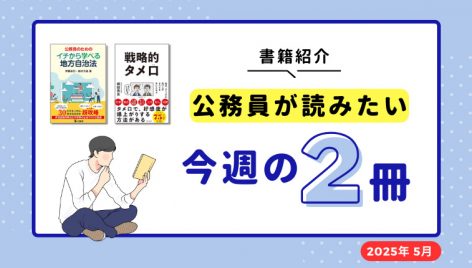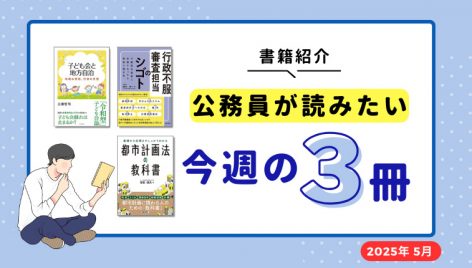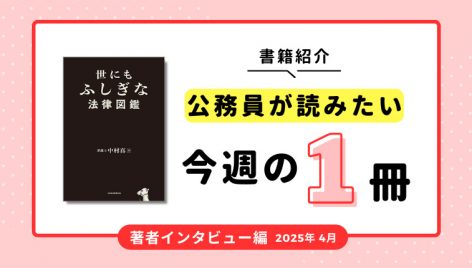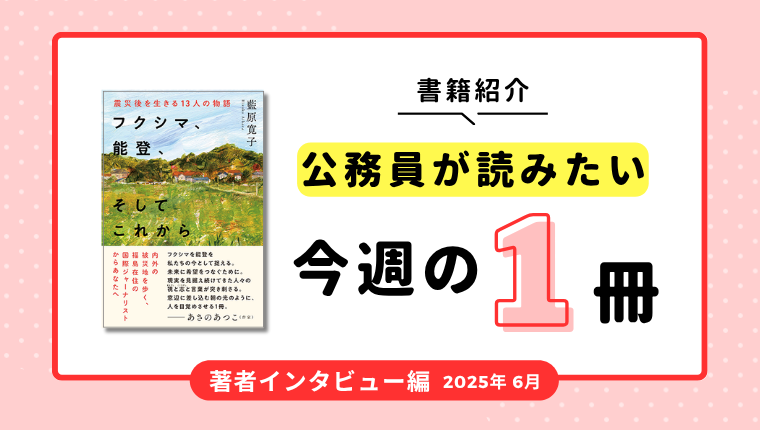
公務員が読みたい今週の3冊
公務員が読みたい今週の1冊【著者インタビュー編】フクシマ、能登、そしてこれから
雑誌から絞り込む
2025.07.07

この記事は2分くらいで読めます。

出典書籍:『月刊ガバナンス』2025年6月号
今週、何読む?
読書の習慣をつけたいと思いながら、まだ始められていない…。
日々読書を嗜んでいるが、そろそろネタ切れ…「次は何を読もうか」検討中。
そんな公務員の方はいませんか?
「公務員なら読んでおきたい」業務に役立つ必携図書や、「公務員の皆様が楽しく読める」おすすめ図書をガバナンス編集部がピックアップ。
「公務員が読みたい今週の3冊」では毎週2~3冊をご紹介。
特別編「公務員が読みたい今週の1冊」ではたっぷりの著者インタビューとともに、おすすめの1冊をじっくりとご紹介します。
「今週読みたい図書」の選定にぜひお役立てください。
【公務員が読みたい今週の3冊】バックナンバーはこちら
災害の個々の記憶を集合の記憶へ明日につなぐ「私たちの物語」
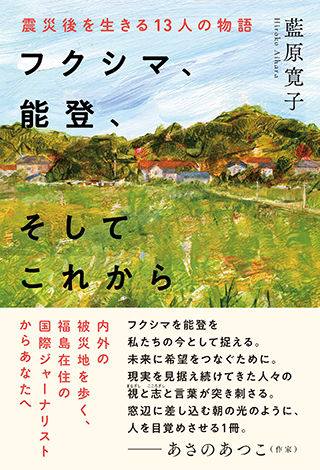
フクシマ、能登、そしてこれから
震災後を生きる13人の物語
藍原寛子・著
婦人之友社/1,500円+税
著者プロフィール

藍原寛子(あいはら・ひろこ)
ジャーナリスト。福島県生まれ。福島民友新聞記者を経てJapan Perspective Newsを設立、内外に発信している。阪神・淡路大震災、東日本大震災で支援・取材活動を重ね、能登半島地震では直後から被災地に通い、被災者の様子を伝える。2014年『婦人之友』に「福島のいま」、21年「10年後のフクシマ」、22年「コロナと医療」を連載。共著に『コロナと向き合う 私たちはどう生きるか』(婦人之友社)。2024年、被災地取材などにより日本外国特派員協会の報道の自由賞を受賞。福島在住。
フクシマ、能登、そしてこれから
── 著者インタビュー
「災害大国日本に暮らす、すべての人に読んでほしい」
そう願って、ジャーナリストの藍原寛子さんは初めての単著を上梓した。福島県で生まれ育ち、県紙『福島民友』の記者を経て独立。さまざまな被災地に赴き、取材や対話、支援活動を行ってきた。自らも東日本大震災の被災者の一人だ。奥付に示された第1刷発行日は、大震災発生から14年後の「3月11日」。「忘れられないこの日を、ここに刻んでおく」ことにしたという。
本書は、フクシマと能登の被災後を生きる人たちの言葉や思いを丹念に追った13篇からなる。うち9篇は、月刊『婦人之友』での2021年の連載「10年後のフクシマ」をもとに再取材。その後の出来事を盛り込むなど大幅な加筆修正を行った。4篇は、能登半島地震の被災者に取材した書き下ろしだ。
「ずっと、いろいろな方の物語をまとめたいと思ってきたが、震災後のフェーズは目まぐるしく変わった。私の中で、今まで耳を傾けてきた一人ひとりの体験が熟していく、まとまっていくのに必要な時間が、14年だったように感じる」
と藍原さんは振り返る。
市民が運営に参画する映画館「フォーラム福島」の総支配人、原発と対峙し続ける相馬市の元漁師、失われゆく故郷を言葉に遺す浪江町出身の歌人、大震災後数年間にわたり福島の子どもを迎え入れてきた石川県珠洲市の住職──。13の物語では、それぞれの主人公のほかにも、家族、友人、師や協力者、考えの異なる人など、さまざまな人たちの思いが織り込まれ、「歴史の共時性」「伝える責任」「議論の公共圏」など、ハッとさせられる言葉の数々に出会うことができる。生活と生業の再建は今なお途上であることも、切実に伝わってくる。こうした被災の記録を「痛みを伴う貴重な教訓」にしなければならないと藍原さんはいう。
「当事者の痛み。被災者を思っての痛み。何もできなかったという痛み。いろいろな痛みを分かち合うことが大切。ただ、作家の髙村薫さんが本書の私との対談で語っているように“個人の記憶を集めたら自動的に共同体の記憶になるわけではなく、語るべき者が『これが集合の物語だ』と語り下ろす必要がある。それができて初めて、個人の記憶が居場所を見つけられる”のだと思う」。
片仮名の「フクシマ」は世界にも伝えていくという使命感、「そしてこれから」には平和な明日への思いを込めた。カバー絵は、過酷な14年を経て、それでもなお美しい飯舘村の風景だ。
「伝えるべき記憶を皆さん一人ひとりが持っている。災害後、何を思いどう行動してきたか。本書を読むことで、この物語に参加してもらえたら嬉しい」。
物語は先へと続く。藍原さんはこれからも、各地に生きる人の声を聴き、伝えていくだろう。
月刊『ガバナンス』では、おすすめ書籍6冊を毎月まとめてご紹介!
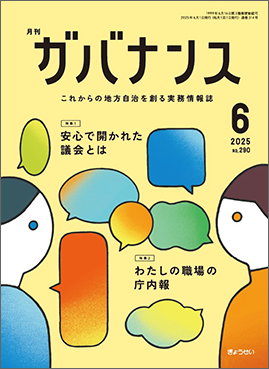
月刊 ガバナンス 2025年6月号
特集1:安心で開かれた議会とは
特集2:わたしの職場の庁内報 編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
ご購入はこちら ≫